artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
勝倉崚太「ニッポン小唄」

会期:2013/01/11~2013/02/28
フォト・ギャラリー・インターナショナル[東京都]
勝倉崚太の新作「ニッポン小唄」は、北海道・阿寒湖のアイヌ村から沖縄・石垣島の辺野古の海まで、日本各地を旅して撮影した労作である。日本人がその土地に刻みつけてきた「歴史」のありようを、写真を通じて探り出すというその意図は真っ当だし、6×7判カメラにカラーフィルムという、いまではやや古風になってしまった撮影のスタイルであるにもかかわらず、軽やかで楽しめるシリーズに仕上がっている。しかし、見ていて何か物足りなさを感じるのはなぜだろうか。それぞれの場所を撮影した写真から、一枚しか選ばれていないということもあるのかもしれない。次々に眼に入っては移り過ぎていくそれぞれのイメージが、あまり強く記憶に残っていかないのだ。
勝倉は2009年に同ギャラリーで開催された個展「おはよう日本」でも、すでに同じような趣向の作品を発表している。これだけ続けても作品としての厚みを実感できないのなら、そろそろ撮影の姿勢や方法論を考え直すべきではないだろうか。展示作品のなかで最もインパクトが強かったのは、東京タワーの前に金縁のフレームに入った古い写真(母親が5歳のときの踊りの発表会で撮影されたもの)を掲げた一枚だった。「日本人の歴史」といった大きな、だがやや漠然とした枠組みよりも、勝倉自身の家族の個人史を手がかりに、制作活動を再構築した方が、よりリアリティのあるシリーズに育っていきそうな気がする。それぞれの場面に対するこだわりを、もっと強く打ち出していってほしい。
2013/01/25(金)(飯沢耕太郎)
周縁からのフィールドワーク

会期:2013/01/18~2013/02/02
ギャルリ・オーブ[京都府]
写真家の小野規が2000年代にパリ近郊の郊外団地を撮影したシリーズ《周縁からのフィールドワーク》を起点に、周縁・境界を意識して自身の表現を模索する4作家(藤本由紀夫、小沢さかえ、中川トラヲ、山本基)を加えた展覧会。日本の公団住宅で育った筆者にとって、小野が捉えたフランスの郊外団地の情景はどこか懐かしく、20世紀モダニズムの普遍性を改めて実感した。一方、パリの郊外団地と言えば、1995年のフランス映画『憎しみ』に代表される、移民の巣窟で犯罪多発地帯という印象もある。小野の作品には映画のような荒廃した空気が感じられなかったが、実際はどうなのだろう。また、本展で筆者がもうひとり注目したのは、藤本由紀夫だった。作品は彼の定番と言うべき、オルゴールを用いたサウンドオブジェだったが、胴体部分を梱包用の段ボールで制作していたのだ。ガラスや金属を用いたこれまでの作例とはずいぶん違う印象で、見慣れた作品から新たな魅力を引き出したのは見事だった。
2013/01/24(木)(小吹隆文)
田尾沙織「ビルに泳ぐ」
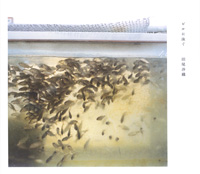
会期:2013/01/14~2013/01/27
Raum1F[東京都]
1980年生まれの田尾沙織は、2001年に第18回「写真ひとつぼ展」でグランプリを受賞した。たしかその時点で同展の最年少受賞者だったはずだ。それから10年以上が過ぎて、このときの受賞作『ビルに泳ぐ』がPLANCTONから写真集として刊行されることになった。それにあわせて同社のIFのスペースで開催されたのが本展である。
会場を巡ってやや拍子抜けしたのは、そこに展示されていた29点が、受賞時の写真そのものだったことだ。田尾はそれからプロ写真家になり、広告やエディトリアルを中心に活動の幅を広げ、ニューヨークにも長期滞在した。当然、その間の経験の蓄積が、何らかの形で展示に反映されているのではないかと期待していたのだが、そうではなかったのだ。
たしかに「ビルに泳ぐ」は、いま見ても新たな才能の出現を予感させる佳作だ。6×6判の画面の浮遊感とバランスのよさ、被写体に対するデタッチメントを基調とする距離感、当時若い写真家たちの心を捉えていたやや希薄なパステル調の色味──すべてが水準以上であり、的確な表現力が発揮されている。だが、それはあくまでも2001年当時の水準であり、いまそれを見せられても仕方がないと思う。むしろ、このシリーズをイントロダクションとするようなその後の作品の展開をしっかり見てみたいのだが、彼女にその用意はあるのだろうか。
2013/01/24(木)(飯沢耕太郎)
蔵真墨「イ・ケ・メ・ン」

会期:2013/01/18~2013/02/23
ツァイト・フォト・サロン[東京都]
蔵真墨の新作「イ・ケ・メ・ン」の展示を見ながら思い出したのは、アメリカの写真家ゲイリー・ウィノグランドのスナップショットの傑作『女は美しい』(Garry Winogrand, Women Are Beautiful, 1975)である。ヘテロセクシュアルな男性の眼から見た女性の魅力を、生命力あふれる写真群でぬけぬけと語り尽くした『女は美しい』とちょうど逆の方向から、『男は美しい』と言い切ってみせたのが今回の蔵の連作のように思えたからだ。だが、1960年代後半~70年代初頭の「ウィメンズ・リブ」や「カウンター・カルチャー」の時代を背景とした『女は美しい』とくらべると、時代状況と地域の違い(蔵の写真の主な舞台となっているのは東京と香港)もまた、明瞭に浮かび上がってくる。「イ・ケ・メ・ン」には、手放しの男性礼讃とはいい難い、やや鬱屈した翳りのような感情がうっすらと漂っているのだ。
今回の連作に使用されたのは、6×6判レンジファインダーカメラのニューマミヤ6である。同じフォーマットの一眼レフカメラの、画面の隅々までコントロールされたシャープな画像と比較すると、このカメラで撮影された写真にはどこか曖昧な領域が生じてくる。蔵自身「周囲に興味深い何かが写りこんでくる偶然」を期待してシャッターを切ったと語っているが、たしかに画面の周辺の部分のテンションは明らかに中心部よりも落ちているのだ。そのあたりにも、ウィノグランドの獲物を狙って仕留める狙撃手のような視点の取り方とは、違った感触があらわれてきているのではないだろうか。
2013/01/23(水)(飯沢耕太郎)
内藤正敏「神々の異界──修験道・マンダラ宇宙・生命の思想」

会期:2013/01/05~2013/02/02
東北芸術工科大学 本館7階ギャラリー[山形県]
内藤正敏は写真家・民俗学者として活動しながら、長く東北芸術工科大学大学院教授を務めてきた。今年定年退職ということで、その退官記念展として開催されたのが本展である。
大学本館の最上階のかなり広いギャラリースペースに、自ら企画・構成した77点の作品が並ぶ。1960~70年代の代表作である「即身仏」「婆バクハツ!」「遠野物語」から、近作の修験道の現場を取材した連作まで、その作品の選択が実に行き届いていて、バランスがとれている。内藤の著作を見てもよくわかるのだが、写真や文章を再構築していく編集者としての能力がとても高いということだろう。
ひと言で言えば、内藤が写真を通じてもくろんできたのは、「視える自然」の背後に隠されている「視えない自然」の所在を明るみに出すことである。それは現実世界の光学像を定着するという写真の基本原理を踏み越えようとする営みであり、本来は実現不可能なものだ。ところが、内藤の写真を見ていると、たしかに「視えない自然」がありありと写し出されているように思えてくることがある。たとえば富士山8合目の烏帽子岩で、諸国の飢饉に苦しむ人々への救いを求めて、31日間断食した果てに入定した身禄という行者に成り代わるようにして江戸(東京)を遠望した作品(「神々の異界」より「富士山」1992年)を見ると、時空を一瞬のうちに飛び越えてしまうような奇妙なトリップ状態に陥ってしまう。内藤にとって写真と修験道は、不可視の領域に肉迫するための呪具の役目を果たしていることが、今回の展示を見てあらためてよくわかった。
2013/01/22(火)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)