artscapeレビュー
2016年04月01日号のレビュー/プレビュー
ビアズリーと日本

会期:2016/02/06~2016/03/27
滋賀県立近代美術館[滋賀県]
19世紀英国のイラストレーター、オーブリー・ビアズリー(1872-1898)にまつわる展覧会。ビアズリーの名を広く世に知らしめたオスカー・ワイルドの戯曲『サロメ』英訳版が出版されたのは1894年、彼が亡くなるほんの数年前のことであった。夭折の天才、その短い活動が残した影響は驚くほど大きい。本展はビアズリーを軸に日英の美術の影響関係を、およそ270点のイラスト、版画、装丁本で紹介する。国内四カ所を巡回する。
切り落とされた預言者ヨカナーンの首に、サロメが口づけする場面を描いた《お前の口に口づけしたよ、ヨカナーン》はあまりにも印象的な作品だ。1893年に英国の美術雑誌『ステューディオ』に掲載されたこのイラストが出版社の目に留まり、ビアズリーは英国版の挿画に採用されたという。『サロメ』の挿画は、後の1910年に日本でも創刊間もない雑誌『白樺』に柳宗悦の紹介とともに掲載されて注目を集める。本展でみる、『サロメ』の挿画のためのドローイングは、大胆に空いた白い面の紙とくっきりと塗り分けられた黒い面のインクの質感のコントラストが美しい。そして、流れるような線、震えるような点描、細部の執拗な描き込みが、彼の幻想的でエロティックな作風を決定づけたように思う。もともとビアズリーはバーン=ジョーンズに私淑したというが、ビアズリーの作風とウィリアム・モリスらラファエル前派の作風のもっとも大きな違いもこのエロティックさにあるといってもいいだろう。ビアズリーはこの絶対的な個性によって賞賛を浴び、同時に、季刊誌『イエロー・ブック』や季刊誌『サヴォイ』など物議を醸した雑誌を次々と手がけることになったように思う。オスカー・ワイルドはビアズリーの描く『サロメ』のイラストに否定的だったというが、世紀末の英国に現われたこの二人の奇才の出会いこそが、あのイラストを生み出したのではないだろうか。[平光睦子]
2016/03/17(火)(SYNK)
イデビアン・クルー『ハウリング』

会期:2016/03/18~2016/03/20
世田谷パブリックシアター[東京都]
始まって早々「なるほど!」と思った。タイトルのことだ。草原に男が一人。歩く手に白い紙袋。「キーン」と耳鳴りのような不快音がし、立ち止まる。それで男は歩く進路を切り替える。また、少し歩くと不快音がする……こんな冒頭。「ハウリング」とは、マイクから出た音を同じマイクが拾うことでスピーカーからノイズが出る状況のこと。誰だってハウリングが嫌いだ。でも、誰だってハウリングを出してしまう、他人にとって不快な存在になりうる。なんとイデビアン・クルーにふさわしいタイトルだろうと思っているとサックス奏者5人組が登場。今作の白眉はなによりも音楽だった。ブラジル音楽ならばサウダーヂと呼びそうな多層の感情が重なるような音楽。でも、ジャズがベースなので、ブラジル音楽よりも乾いていて、もっとひっちゃかめっちゃかだ。拍子の異なるリズムとリズムが折り合わさる。その感じは、イデビアン・クルーのダンスにじつにピッタリ合う。60分のコンパクトな作品のテーマは、お見合いと結婚。二重の円を描いて向かい合う人と人。息を合わせているが、そうは簡単には合わない。気持ちを押しつけたり、気持ちに応えようとしたり、それで独りよがりになったり。そんな気持ちのズレやズレへの恐れやズレがどうでもよくなって衝動に任せるところなど、すべてがダンスの要素となる。むしろそれこそがダンスというものなのではないかとさえ思えてくる。けれども、同時にこんな気持ちも湧く。じつに井手茂太らしいダンスだと。もはやそれは一種の芸だ。井手が一代で築き上げた独自の芸能だ。その変わらぬクオリティを愛でつつ、笑ったり、ぐっときたりしているぼくは、多くの観客たちと同様、井手ダンスに魅了されているファンの一人に相違ない。でも同時に、このハイ・クオリティな舞台が透明な天井に突き当たっているようにも見える。結局、〈井手の思う/感じるところ〉にこの舞台は支配されている。〈井手の思う/感じるところ〉はじつに豊かだが、とはいえ、その豊かさには限界がある。そこには外部へと通じるほつれが意外と見当たらないのだ。ラストには、バブル期の結婚式のパロディか、ゴンドラ(?)から新婦(のみ)がスモークとともに降りてくる。彼女は文金高島田を頭に被り、しかし衣装は迷彩服。これが外部へのほつれを生むかと思いきや、戦争のモチーフは、文金高島田によるブーケトスへとズラされる。このズッコケはおかしいが、戦争にリアリティがもてない自分たちを露呈させはすれど、そこに留まる以外の道筋が描かれることはない。別に戦争を描けと言いたいわけではない。ウェルメイドな構成に、ピナ・バウシュのタンツテアターを連想させられたけれども、バウシュならば60分ではなく、その2倍かそれ以上のヴォリュームにしただろう。もしそうするならば、バウシュはどんな場面を付加しただろう。物質的な自然を用いた場面か? そんな想像をしながら、本作の外部に思いを寄せてしまう(だからといって、バウシュらしくせよ、などと思っているわけではない)。
2016/03/18(金)(木村覚)
春画展
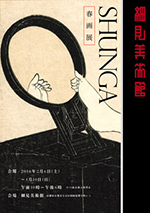
会期:2016/02/06~2016/04/10
細見美術館[京都府]
昨年開催された、日本初の「春画展」の巡回展。20カ所以上に断られつづけ、やっと開催にこぎつけたのが東京、永青文庫と、ここ、細見美術館だったという。東京展の観覧者は20万人を上回ったというが、本展も入館整理が必要なほどの連日の混雑ぶり。美術展には珍しいR18の年齢制限も人々の興味をさらにかき立てたのかもしれない。出品は狩野派や土佐派の肉筆画から名立たる浮世絵師の版画まで、大名家で代々密かに受け継がれてきたものから街中で庶民に貸し出されたものまで、およそ130点。なかでも、鈴木春信、鳥居清長、喜多川歌麿など美人画で知られた絵師たちによる春画には、美人画を手にした人々がその絵をとおして妄想したであろう、次なる場面を目の当たりにする思いがした。
春画は、しかし、基本的にただ猥褻なだけではない。春画には、性的なことがらと笑いが同居するのである。具体的には男女の目合ひの様子が描かれる。二人の肉体と、まといつく衣類、そして彼らをとりまく周囲の状況、どの絵もモチーフは驚くほど画一的だ。さらに、身体の一部が際立って強調されている点も共通する。その一部を描く執拗さが、不自然で、不調和で、滑稽なのである。[平光睦子]
2016/03/19(土)(SYNK)
プレビュー:森村泰昌:自画像の美術史 「私」と「わたし」が出会うとき

会期:2016/04/05~2016/06/19
国立国際美術館[大阪府]
大阪出身・在住ながら、地元の美術館で大規模個展を行なったことがなかった森村泰昌。待望の機会となる本展は、彼の「自画像シリーズ」の集大成と位置づけられており、ゴッホに扮した出世作から、レンブラント、ベラスケス、フリーダ・カーロ、シンディ・シャーマンといった過去の代表作と、今展のために制作された新作、未発表作品が一堂に会する。また、1985年に京都のギャラリー16で行なわれた伝説的展覧会「ラデカルな意志のスマイル」が再現され、上映時間60分以上の新作映像作品が発表されるなど、大変充実した内容となっている(作品総数134点)。そして、「森村泰昌アナザーミュージアム」と題した関連展覧会が名村造船所跡地(大阪市住之江区北加賀屋)で同時開催され、NPO法人ココルーム(大阪市西成区釜ヶ崎)でもイベントが行なわれるなど、美術館にとどまらない地域的な広がりを持っているのも見逃せないところだ。
2016/03/20(日)(小吹隆文)
プレビュー:林勇気 電源を切ると何もみえなくなる事

会期:2016/04/05~2016/05/22
京都芸術センター[京都府]
自身で撮影した画像、公募で第三者から提供された画像、インターネットから抽出した画像などをコンピューターに取り込み、切り抜きや重ね合わせを行なった後、複雑なレイヤーを施して映像作品化する林勇気。デジタル技術を駆使して記録や記憶の在り方を探ってきた彼が、これまでとは異なるタイプの新作を発表する。その肝は「電源」。展示室の映像機器の電源が1日に何度か落ちるようにセッティングし(1回当たり15分程度)、映像が見られない状態を観客に提示するのだ。これまでの作品があくまでも仮想世界の出来事だったのに対し、この新作ではリアルワールドの介入が大きなカギを握っている。それは、映像メディアの脆弱性を示すと共に、電源を切る行為によるメタ鑑賞体験や、バーチャルとリアルのあいだに立ち現れる何かを探る機会となるだろう。
2016/03/20(日)(小吹隆文)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)