artscapeレビュー
2017年10月15日号のレビュー/プレビュー
田代一倫「ウルルンド」

会期:2017/09/05~2017/09/24
photographers’ gallery/ KULA PHOTO GALLERY[東京都]
田代一倫は2013年に東日本大震災の被災地域を中心に撮影したポートレートの写真集『はまゆりの頃に 三陸・福島2011~2013年』(里山社)を刊行した。丁寧に向き合って撮影した「肖像写真453点と覚え書き」で構成されたこの写真集は、「震災後の写真」のあり方を模索した成果として高い評価を受けた。田代にとって、このシリーズの次のかたちを見出すことは簡単ではなかったのではないかと想像できる。その後photographers’ galleryで、韓国で撮影したポートレートの展覧会を3回ほど開催するなど、試行錯誤が続いていた。だが、今回の「ウルルンド」を見ると、少しずつその輪郭が定まりつつあるように見える。
「ウルルンド」=鬱陵島は竹島(独島)のすぐ西に位置する島で、日韓の領土問題にからめて言及されることが多い。だが、田代のアプローチはそのような政治的な文脈はひとまず括弧に入れ、『はまゆりの頃に』と同様に、被写体となる人物に正対し、「写される」ことを意識させてシャッターを切っている。結果的に、前作と同様に人物とその背景となる環境が絶妙のバランスで捉えられているのだが、シリーズ全体にそこはかとなく漂う緊張感が、これまでとは違った手触りを生じさせている。これから先は、より「人々の暮らしや立ち居振る舞い」に対する感覚を研ぎ澄まし、竹島(独島)や対岸の日本/韓国をよりくっきりと浮かび上がらせる工夫が必要になりそうだ。福岡出身の田代にとって、韓国との距離感はかなり近いものであるはずだ。そのあたりを意識して、もっと強く打ち出していってほしい。
2017/09/08(金)(飯沢耕太郎)
平敷兼七「沖縄、愛しき人よ、時よ」

会期:2017/09/04~2017/10/29
写大ギャラリー[東京都]
平敷兼七(へしき・けんしち)は1948年、沖縄県今帰仁村運天の生まれ。沖縄工業高校デザイン科卒業後、1967年に上京して東京写真大学(現・東京工芸大学)に入学するが、2年で中退する。東京綜合写真専門学校に入り直して、同校を72年に卒業している。その後、沖縄とそこに生きる人々を柔らかな温かみのある眼差しで撮り続けたが、その仕事がようやく評価されるようになるのは、亡くなる2年前、2008年に銀座ニコンサロンで個展「山羊の肺 沖縄1968─2005年」を開催し、第33回伊奈信男賞を受賞してからだった。だが、没後も展覧会や写真集の刊行が相次ぎ、あらためてその独自の作品世界に注目が集まっている。今回の写大ギャラリーの展覧会には、代表作の「山羊の肺」のシリーズから78点、ほかに沖縄出身者が入寮する東京都狛江市の南灯寮での日々をスナップした写真群から63点が展示されていた。
平敷の写真は一見、目の前にある被写体に何気なくカメラを向けた自然体のスナップショットに見える。だが、「山羊の肺」の「『職業婦人』たち」のパートにおさめられた写真の「前借金をいつ返せるか毎日計算する」、「客に灰皿をもって行く子ども」といったキャプションを読むと、彼が沖縄の現実と人々の生の条件を深く考察し、時には辛辣とさえ思える批評的な眼差しでシャッターを切っていることが見えてくる。亡くなる2日前の日記には「人生の結論は身近にあり、身近の人物達、身近の物達、それらを感じることができるかが問題なのだ」という記述があるという。あくまでも「身近」な被写体にこだわり続けながら、「感じる」ことを全身全霊で哲学的な省察にまで昇華させようとした写真家の軌跡を、もう一度きちんと辿り直してみたい。
2017/09/08(金)(飯沢耕太郎)
松本美枝子「ここがどこだか、知っている。」
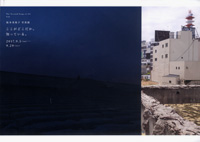
会期:2017/09/05~2017/09/29
ガーディアン・ガーデン[東京都]
松本美枝子は1974年、茨城県生まれ。1998年に実践女子大学文学部卒業後、写真家として活動し始める。写真集『生あたたかい言葉で』(新風舎、2005)、谷川俊太郎との共著『生きる』(ナナロク社、2008)など、日常を細やかに観察しつつ、思いがけない角度から描き出していくスタイルを確立していった。
今回のガーディアン・ガーデンでの個展でも、いかにも松本らしい思考と実践とを一体化した写真の展示を見ることができた。日付け入りの家族写真を再提示した「手のひらからこぼれる砂のように」(2017)、「古生代ゴンドワナ超大陸の海底あるいは高鈴山」、「震災による地盤沈下で消滅した砂浜あるいは河原子海水浴場」の2部から成る「海は移動する」(2017)、東海JCOの臨界事故をテーマにした「想起する」(2017)、日々のスナップ写真をアトランダムに上映する「このやり方なら、知っている。/ここがどこだか、知っている。」(2011~2016)、鳥取藝住祭で滞在制作した「船と船の間を歩く」(2014)、2面マルチのスライドショー「考えながら歩く」(2017)といった作品群は、一見バラバラだが、「時間と、それが流れる場所と、その中に生じる事象について、できるだけ考え続け観察する」という松本の一貫した姿勢を感じられるものになっていた。
特に興味深かったのは、会場の3分の1ほどのスペースを使ったスライドショー、「考えながら歩く」で、天気予報や歌などの日常の音と映像とが少しずつズレたりシンクロしたりしながら進行することで、観客の意識に揺さぶりをかけるつくりになっていた。われわれが「絶えず揺れ動く世界の際」にいることが、一見穏やかだが、微妙な裂け目を孕んだ映像の集積によって提示されている。展示を見ながら、そろそろ次の写真集もまとめてほしいと強く思った。
2017/09/13(水)(飯沢耕太郎)
港都KOBE芸術祭

会期:2017/09/16~2017/10/15
神戸港、神戸空港島[兵庫県]
神戸港の開港150年を記念した芸術祭。神戸という「場所の記憶」への言及として、古巻和芳と川村麻純の作品が秀逸だった。古巻和芳の《九つの詩片 海から神戸を見る》は、本芸術祭の目玉である「アート鑑賞船」に乗り、海上から鑑賞する作品の一つ。神戸の詩人たちが戦前、戦後、現代に綴った9つの詩が透明なアクリル板に記され、詩の言葉というフレームを通して、現在の神戸の風景を見るというものだ。伸びゆく線路と発展、都市の中の孤独、空襲、そして再び街が炎に包まれた震災……。紡がれた言葉は、場所の記憶への想起を誘う通路となるが、そのフレーミングは波に揺られるたびに不安定に揺れ動き、むしろ眼前の「現在」との時間的・空間的距離の中に「見えないもう一つの風景」が浮かび上がる。

古巻和芳《九つの詩片 海から神戸を見る》
川村麻純の《昨日は歴史》は、映像、写真、テクスト、音声から構成される複合的なインスタレーション。映像では、古い洋館の応接室のような室内が、ゆっくりと360度パンするカメラによって映し出され、淡々と物語る若い女性の声が重なる。明治42年に建てられた「ここ」は山の手の洋館であること、集う人々が口にする南国の果物の名前、「この町」にもあって故郷を思い出させる廟、農民の心情を歌った素朴な歌。「あの国」と「この国」の生徒が混じるも楽しかった学校の思い出、集団結婚式、言葉の通じない義母、結婚50年目に初めて帰郷できたこと。サンフランシスコ講和条約により、それまで「この国」の国民だった「彼女」は国籍を失い、自分は何者なのかという思いに苛まれる。具体的な地名や国名は一切示されないものの、被写体の洋館は台湾からの移民とその子孫が集う会館であり、「彼女」は戦前に台湾から神戸へ嫁いだ女性なのだろうと推察される。ここで秀逸かつトリッキーなのは、語りの視点の移動に伴い、「ここ」「この」「あの」という代名詞の指示内容が移り変わる点だ。「この港」(=神戸)は南米への移民を送り出し、ユダヤ人難民も「ここ」を通過したと声は語る。一方、亜熱帯としては珍しく、冬に雨の多い「ここ雨の港」は、神戸との連絡航路が結ばれた台湾の基隆(キールン)を暗示する。「この港」から「あの港」へ向かう船の中で、「彼女」はひどい船揺れのために目を覚まし、「一瞬、自分がどこにいるのか分からなくなる」。それは生理的な嘔吐感による一時の混乱であり、かつ「ここ」と「あそこ」のどちらにも定位できない移民のアイデンティティのあてどなさであり、さらには語りの視点の自在な移動がもたらす、時制と地理的な理解の混乱をもメタ的に指し示す。

川村麻純《昨日は歴史》
川村は、過去作品《鳥の歌》においても、日本と台湾の両方にまたがる女性の半生の記憶の聞き取りを元に、別の女性が語り直すことで、個人史と大文字の歴史が交錯する地点を虚実入り混じる手法で提示している(《鳥の歌》は、日本から台湾へ嫁いだ女性である点で、本作と対になる作品である)。とりわけ本作では、代名詞のトリッキーな仕掛けにより、移民のアイデンティティの浮遊性を示唆すると同時に、第三者の視点による小説風の文体を朗読する声が、「全てはフィクションではないか」という疑いを仄めかす。しかし、奥の通路に進むと、映像内で語られていた「歌」が、(おそらく記憶を語った高齢の女性自身の声で)聴こえてきた瞬間、そのエキゾティックだがどこか懐かしい旋律を奏でる声は、強く確かな実存性をもって響いてきた。それは、固有名詞を排した語りの匿名性の中に、故郷を喪失した無数の女性たちの生の記憶を共振させる可能性を開くと同時に、一筋の「声」への慈しみに満ちた敬意を手放さない態度である。
また、映像プロジェクションの背面には、写真作品5点が展示されている。室内から窓越しに見える風景を、窓のフレーミングと重ね合わせて切り取った写真だ。うち2点は、写真の上に水色の紐が水平に掛けられ、樹々の向こうに隠れた「水平線」の存在を暗示する。移民とその子孫が集う会館の室内から、窓越しに海の彼方の故郷へ想いを馳せる視線がトレースされる。一方、対峙する壁面には、19世紀アメリカの女性詩人、エミリー・ディキンソンの詩の一節が記されている。ディキンソンは後半生のほとんどを自宅から出ることなく過ごし、自室にこもって多くの詩を書いた。移住によって故郷から隔てられた女性たちが窓の外へ向ける眼差し。閉じた室内に留まったまま、詩という窓を通して、自らの内的世界への探求を鋭敏に研ぎ澄ませた女性の内なる眼差し。さまざまな時代、国籍、状況下に置かれた女性たちの幾重もの眼差しが、「窓」という装置を通して重なり合う。移民女性の歌うかそけき「歌」の背後に、幾層もの「歌」の残響が響きこだまするような、静謐にして濃密な展示空間だった。

左:川村麻純《昨日は歴史》 右:展示会場風景
公式サイト:http://www.kobe-artfes.jp/
関連レビュー
2017/09/15(金)(高嶋慈)
生誕120年 東郷青児展 抒情と美のひみつ

会期:2017/09/16~2017/11/12
東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館[東京都]
ぼくが初めて知った日本の画家は、たぶん東郷青児だと思う。幼いころ東横線沿線に住んでいたので、たまに父親が自由が丘のモンブランの洋菓子を買ってきてくれたのだが、その包装紙をデザインしていたのが東郷青児だったからだ。星空にのっぺりした女性の姿が描かれたもので、多少絵心のあった母親の口から「トーゴーセージ」という名を聞いたように思う。もっとも子どもにとっては包装紙より中身のほうがはるかに重要だったが。ともあれ東郷青児という画家は、ぼくのなかでは最初はとても甘美な思い出とともにインプットされていた。それが長じて美術に興味を持つようになると、その甘美すぎる絵柄とは裏腹の二科会のドンとして君臨する「帝王」の顔がかいま見えてきて、すっかり興ざめしてしまう。その彼が大正時代にキュビスムや未来派のスタイルをいち早く導入した前衛画家であることを知るのは、ずっとあとのこと。そんなわけで、東郷青児はぼくのなかでは浮沈の激しい画家なのだ(考えてみれば藤田嗣治も岡本太郎もぼくのなかでは浮沈が激しい)。
展示は、18歳で開いた個展の出品作《コントラバスを弾く》や、19歳で第3回二科展に初入選した《パラソルさせる女》など、初期の清新な絵画に始まり、7年間のパリ生活を経て帰国後《超現実派の散歩》などの傑作をものしつつ、デザインや壁画などにも手を染め、いわゆる東郷スタイルが固まっていく戦後までを振り返るもの。陰影をのっぺり描く東郷独自のスタイルは、すでにパリ時代から始まっているようだが、その後デザインを手がけるようになって加速していったように感じる。戦後になるともはや少女のイラストと変わりなく、陳腐としかいいようがない。この評価の低落はだれの目にも明らかで、同展の出品点数を見ても、絵画に絞ると戦前の30年間(1915-45)が41点なのに対し、戦後の32年間(1946-78)は17点しかない(60年代以降に絞るとわずか3点)。年とともにいかに作品が衰退していったかがわかる。逆に戦後、東郷は二科会の再建に尽くし、長く会長として君臨。ハデな前夜祭を繰り広げたりタレント画家の作品を入選させたり、戦前の前衛精神はどこへやら、世間受けしそうなパフォーマンスばかりが目立つようになる。
まあそんなことはどうでもよくて、この展覧会でハッと目が止まったのは藤田嗣治との関係だ。この10歳ほど年上の先輩とは20年代のパリで出会ったようで、その後二人は二科展内部に前衛的な傾向の画家たちが立ち上げた九室会の顧問を務めたり、 髙島屋から水着のデザインを依頼されたり、百貨店の壁画を競作したりと、戦前は緊密な関係を続けた。同展にはふたりの合作といわれる《海山の幸》も出ている。さてここで疑問。戦時中、藤田が戦争画にのめり込んだことは知られているが、東郷は戦争画を描かなかったのだろうか。戦後、藤田は戦争責任を問われて日本を去ることになったが、東郷は逆に二科展を舞台に影響力を強めていく。その違いは、単に戦争画を描いたか描かなかったかの違いなのか。
東郷は支那事変後、明らかに弥勒菩薩像を意識した伝統回帰的な《舞》を制作しているが、戦争画は描いた形跡がない。カタログの年譜を見ると、1943年「第2回大東亜戦争美術展・第九室に《出發》を招待出品」とあるが、どんな作品だったのかわからない。また戦後には飢えた母子を描いた《渇》と題する珍しい作品もあるが、基本的に戦前も戦後もほぼ一貫して洋風の女性像を描き続けたようで、戦争による大きな断絶はなさそうだ。考えられるのは、東郷は甘美な女性像を得意とする画家だったため軍からの依頼が来なかったのではないか。それに対して藤田も20年代は「乳白色の肌」で知られた画家だったが、30年代に入ると人気に陰りが見えてきたため、みずから進んで従軍し、戦争画の制作で起死回生を図ったのかもしれない。二科展の前夜祭などを見ると東郷も相当のお調子者だったことがうかがえるが、おそらく歴史に名を残そうとする野心と、ヌードの女性像も凄惨な戦争画も敬虔なフレスコ画も描き分けてしまう技量において、藤田にはおよばなかったに違いない。
2017/09/15(金)(村田真)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)