artscapeレビュー
2020年07月01日号のレビュー/プレビュー
写真とファッション 90年代以降の関係性を探る

会期:2020/06/02~2020/07/19(会期延長)
東京都写真美術館2階展示室[東京都]
かつて、ファッション写真がある種の権威を帯びて流通していた時代があった。アーヴィング・ペン、リチャード・アヴェドン、ピーター・リンドバーグといった写真家によって撮影され、『ヴォーグ』や『ハーパーズ・バザー』といった「ハイ・ファッション」誌に掲載された写真は、その時代の流行を左右するような力を発揮していたのだ。だが、1990年代以降になると、ファッションの震源地はハイ・ソサエティからストリートの若者たちに変わっていく。それに呼応してファッション写真のスタイルも、よりラフで日常的なものへと動いていった。
1980年代後半から、日本のファッション・シーンに深く関わってきた編集者の林央子が監修した本展では、90年代以降の写真とファッションのキーワードとして、「雑誌」「対話」「協働」「東京」「編集」「自由化」「ストリート」が挙げられている。これらのキーワードに沿うかたちで、「メゾン・マルタン・マルジェラ」のブランドイメージを作り上げたアンダース・エドストローム、ファッション誌『CUTiE』にカジュアルな日本人モデルのポートレートを発表して注目された髙橋恭司、90年代を代表するファッション・カルチャー誌『Purple』を創刊したエレン・フライスと現代美術家の前田征紀のコラボレーション、2014年に創設されたレーベル「PUGMENT」のファッションを身に纏った若者たちを、東京の路上で撮影したホンマタカシの写真がフィーチャーされていた。
東京都写真美術館がファッション写真を本格的に取り上げるのは、もしかすると本展が初めてかもしれない。期待して見に行ったのだが、1990年代のファッションそのものにスポットを当てるのではなく、むしろその余波を追う展示なので、観客にはやや拡散した、わかりにくい印象を与えたのではないだろうか。アンダース・エドストロームや髙橋恭司の仕事は、もう少しきちんと「写真」作品として展示してもよかったかもしれない。結局、90年代がファッション写真においてどんな時代だったのかということが、くっきりとしたイメージとしては立ち上がってこなかった。
2020/06/10(水)(飯沢耕太郎)
森山大道の東京 ongoing
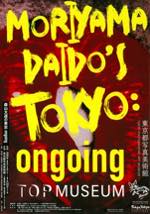
会期:2020/06/02~2020/09/22
東京都写真美術館3階展示室[東京都]
80歳を超えて、なおも「路上の写真家」としての活動を継続している森山大道の、近作を中心とした東京のスナップショット群の展示である。イントロダクションとして、森山の代名詞というべき大伸ばしの《三沢の犬》(1971)が掲げられ、カンヴァスにシルクスクリーンで印刷された『にっぽん劇場写真帖』(室町書房、1968)、『写真よさようなら』(写真評論社、1972)など1960〜70年代の写真が並ぶ。そのあとに続く『Pretty Woman』(Akio Nagasawa Publishing、2017)、『K』(月曜社、2017)、『東京ブギウギ』(SUPER LABO、2018)の3冊の写真集からピックアップされたモノクローム、カラーの写真150点あまりを壁一面にレイアウトしたのがメインの展示である。それらの写真から発するエネルギーの放射は、はまさに圧巻としかいいようがない。ほかに、1980年代の傑作「Tights」シリーズ(1987、2011にも再撮影)を、液晶モニターに投影して見せる小部屋もあった。
大阪の岩宮武二スタジオのアシスタントとして写真を撮り始めてから、「内外を問わずさまざまな都市の路上を歩きに歩き続けてきた。写真が表現であれ記録であれ何であれ、路上で歩く途上で出会った幾多の現象をとにかくほとんど直感のままに写し撮ってきた」と、森山は同展のカタログに寄せたテキスト「57年間のシンプルな日々」で書いている。だが、彼の写真を見ていると、単純な「直感」だけでは片づけることができない、ある特別なアンテナのようなものが備わっているとしか思えなくなってしまう。なぜ、まるで演出したとしか思えないような奇妙な出来事、どこからともなく姿をあらわす異形の人物、ありえない事物の組み合わせが、これほどの頻度で森山のカメラの前に出現してくるのか、そのあたりがどうしても納得できないのだ。
今回、写真を見ながら、森山がオブセッションのように繰り返し撮影している被写体があることに気づいた。「くちびる」と「ひかがみ」(膝の裏側)である。「くちびる」も「ひかがみ」も、意識(外)と無意識(内)とをつなぐ蝶番の役目を果たす身体の部位だ。森山は写真を通じて、見る者を謎めいた無意識の世界へと誘い込もうとしているのではないか──そんなことも考えた。
2020/06/10(水)(飯沢耕太郎)
オラファー・エリアソン ときに川は橋となる

会期:2020/06/09~2020/09/27
東京都現代美術館[東京都]
10年前に金沢で見たとき、よくできてるとは思うけど、それ以上特に感銘を受けなかったなあ。今回もやっぱり同じ。いや前回以上によくできてるだけに、なんの引っかかりもなく素通りしてしまう。もちろんエコロジーとかサステナビリティとか理論的裏付けはあるのだが、そうであればあるほどまるで優等生の解答を見ているようなある種の空しさを感じるのだ。あるいは、チームラボみたいにその場では十分に楽しめるのに、あとになにも残らないみたいな。それで十分といえば十分なんだけど、ぼくが期待するアートではない。
会場に入ると、最初に茫洋とした水彩画があるが、これは紙の上に置いたグリーンランドの氷河の氷が解けて顔料と混ざり合ってできたにじみだそうだ。その次の円形のドローイングは、作品を運ぶ際、二酸化炭素を多く排出する飛行機の輸送を避け、ベルリンから日本まで鉄道と船で運んだときの輸送中の揺れを記録したもの。どちらも環境汚染に対する警鐘ともとれるが、作品自体は偶然による産物にすぎない。
ガラスの多面体に光を当て周囲に反射させる《太陽の中心への探査》(2017)は、ソーラーエネルギーによって動かしているそうだ。とても美しい作品だけど、ソーラーエネルギーを使ってるとかいちいち弁解がましくも聞こえる。床に置かれたライトの前を通ると壁に虹色の影が映る《あなたに今起きていること、起きたこと、これから起きること》(2020)や、天井から吊った円形のガラス板に光を当て、重なり合う色の変化を楽しむ《おそれてる?》(2004)は、色彩のスペクトルを応用したライトアート。吹き抜けの大空間には、展覧会名にもなった新作《ときに川は橋となる》(2020)があり、円形の容器に張った水の揺らめく波紋を頭上のスクリーンに映し出している。
どれも実によくできているし、とても美しいのだが、原理的には光や色彩の性質を利用したライトアートだったり、偶然性を応用したオートマティスムだったりして、20世紀の前衛が試みてきた手法だ。もちろんそれを新たな装いの下に完成度を高め、環境問題への注意を喚起している点は評価もできるのだが、かえってそれがあざとさを感じさせるのも事実。
2020/06/11(木)(村田真)
中里和人写真展「光ノ漂着」

会期:2020/06/08~2020/06/27
巷房ギャラリー[東京都]
日本は海に囲まれた島国なので、日本海流、対馬海流、千島海流、リマン海流などが自然・社会・文化に大きな影響を与え続けてきた。中里和人は、このところ、そのことを写真で検証しようとする作品を制作・発表している。今回の「光ノ漂着」は、2018年に同じ会場で展示し、蒼穹舎から写真集を刊行した「Night in Earth」の続編にあたるシリーズで、海流に乗って日本各地の海岸に打ち上げられたさまざまな漂着物を題材にしている。
漂着物を撮影したり、それらを使ってオブジェ作品を作ったりすることは、それほど珍しくはない。だが中里は、おそらくこれまで誰も思いつかなかった方法で作品を制作した。海辺で拾い集めた漂流物を、古い幻燈機の中に入れ、近くの岸壁、土壁などに投影する。その画像をデジタルカメラで撮影するのである。つまりプリントに写っているのは、反射光によって浮かび上がるおぼろげな物体の像と、スクリーン代わりの壁のテクスチャーとの合体像ということになる。その幻影と現実のあいだに宙吊りになったイメージのたたずまいは、じつに魅力的で、まさに「モノとヒカリの窯変」としかいいようがない。会場には、実際に拾い集めた漂流物そのものも展示してあったが、その思いがけない変容には、写真家の思惑を超えた奇跡が呼び込まれているように感じる。
今回の展示は、北海道から沖縄まで50カ所あまりで撮影したという労作だが、この「海流シリーズ」はまだこの先もしばらく続きそうだ。次作も期待できるのではないだろうか。
関連レビュー
中里和人「Night in Earth」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年10月01日号)
中里和人「惑星 Night in Earth 」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年05月15日号)
中里和人『lux WATER TUNNEL LAND TUNNEL』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年11月15日号)
中里和人「光ノ気圏」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2014年03月15日号)
2020/06/12(金)(飯沢耕太郎)
東京2020 コロナの春 写真家が切り取る緊急事態宣言下の日本

会期:2020/06/11~2020/06/28
コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の解除を受け、ようやく休止していたギャラリー、美術館の展示も再開に向かいつつある。そんななかで、いち早く東京・目黒のコミュニケーションギャラリーふげん社で、写真家たちの作品とメッセージで「コロナの春」をふり返る企画展が開催された。参加者は、Area Park、大西みつぐ、オカダキサラ、蔵真墨、GOTO AKI、小林紀晴、佐藤信太郎、John Sypal、田口るり子、土田ヒロミ、田凱、中藤毅彦、新納翔、橋本とし子、普後均、藤岡亜弥、港千尋、元田敬三、山口聡一郎、Ryu Ikaの20名である。
同展は土田ヒロミを呼びかけ人として急遽決まった企画だが、非日常的な状況下で、写真家たちがどんなふうに行動したのかがとても興味深い。その対応は、外向きと内向きのどちらかに分かれているように見えた。街に出て、誰もいない街頭にカメラを向けたり、マスクの人物を写したりした写真はもちろんある。だが、逆に身の周りの情景や、家族、自分自身に意識を集中した写真がかなり多かったのはやや意外だった。大西みつぐは、自分の手とその影を撮影した写真に「個に徹することで、ひたすらその存在意義を絶えず自身に突きつける」とコメントを寄せている。田口るり子は自分の髪を切るセルフポートレート、小林紀晴はベランダに張ったテントからの眺めの写真を出品した。普後圴は餃子とソーメン、蔵真墨はソラマメと、身近なものを被写体としている。土田ヒロミは1979年に上野公園で撮影した「砂を数える」シリーズを、定点観測で再撮影した。このような自己確認の写真を梃子にして、新たな写真の方向性が見えてくることを期待したい。
「コロナの春」が写真の世界にどんな影響を及ぼしていくのかは、むろんまだわからない。だが、けっしてネガティヴなことだけではないはずだ。それぞれの写真家たちにとって、立ち止まり、息を継ぎ、さらに前に進むための、とてもいい機会となったのではないだろうか。
2020/06/13(土)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)