artscapeレビュー
福住廉のレビュー/プレビュー
ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人

会期:2010/11/13
シアター・イメージフォーラム[東京都]
90年代が「キュレイターの時代」だったとしたら、昨今は「コレクターの時代」らしい。日本に限ってみても、高橋龍太郎の「ネオテニー・ジャパン」(上野の森美術館ほか)や山本冬彦の「サラリーマンコレクター30年の軌跡」(佐藤美術館)、上田國昭・克子夫妻の「ゲンダイビジュツ『道(ドウ?)』」(練馬区立美術館)など、コレクションの傾向や作品の大小こそ異なるにせよ、これまで表舞台に上がることが少なかったコレクターにスポットライトが当てられるようになっている。これが、制作する美術作家を言説の面で牽引する美術批評や歴史的文脈に位置づけるキュレイションの弱体化と表裏一体の関係にあることは疑いないし、コレクターが前面化した背景にギャラリストが隠れていることもまちがいない。アート系の映画としては異例のロングランを続けている本作も、その意味では、現代アートの消費者の拡大と底上げを目論むギャラリストによる啓蒙映画として利用されている側面がないわけではないだろう。けれども、佐々木芽生監督が元郵便局員と図書館司書の夫妻のつつましくも豊かな暮らしに密着したこの映画は、そうした底の浅い「戦略」を打ち砕くほど、じつにまっとうなコレクターの真髄を浮き彫りにしている。それは、コレクションの前提には必ず「鑑賞」があるという厳然たる事実だ。ニューヨークの画廊界隈に頻繁に出没するハーブ&ドロシーの行動は、有望な作品を目ざとく買いあさってすぐさま転売して利益を得ようとする投機的なコレクターというより、むしろ銀座の画廊街に毎週出没する、一風変わった名物老人に近い。じっさい、この映画でもっとも印象的なのは、膨大なコレクションを文字どおり押し込んだ狭いアパートの一室より、この夫妻がオープニングに足しげく通いつめ、おしゃべりに興じながら批評的に鑑賞している姿だ。そう、鑑賞の先にコレクションや批評があるのであり、決してその逆ではないということを、ハーブ&ドロシーは身をもって体現しているのである。コマーシャルギャラリーの展覧会だけしか見ていないくせに現在のアートシーンを総括してしまうようなたちの悪い学芸員や美術評論家、売れそうな新人を一本釣りするために美大の卒展を徘徊する貪欲なギャラリスト、そのギャラリストの口説き文句を鵜呑みにして作品を買ってしまう低俗なコレクターが横行している昨今だからこそ、できるだけ多くの展覧会に足を運び、自分の眼で作品を批評的に鑑賞するという大原則を終始一貫させているハーブ&ドロシーの誠実な態度は際立っている。よきコレクターの映画というより、よき鑑賞者の映画である。
2011/01/01(土)(福住廉)
山口晃展 東京旅ノ介
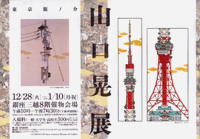
会期:2010/12/28~2011/01/10
銀座三越8階催物会場[東京都]
銀座三越で開催された山口晃の個展。すでに日本橋三越の広告を手掛けているので、いわばタニマチのご機嫌伺いという面も否めないところだが、そこは希代のアーティスト・山口のこと、過去作品を並べてお茶を濁すなどという無粋な真似だけはしなかったところがえらい。「東京」というお題のもと出品された大半は新作で、写真あり、立体造形もあり、超絶技巧の絵師というこれまでのイメージとは打って変わって、みずから新境地を開拓してみせた。なかでも秀逸だったのが、東京の下町の暮らしに照準をあわせて提案された「露電」。谷根千界隈の路地を縫うように走る路面電車で、二三人も乗ればたちまち満員になってしまうほど極小サイズの車体がいかにも下町の路地と風情に合致していて、「なるほど理にかなっている」と頷くことしきり。山口が描き出しているのは、あくまでも山口の頭のなかで膨張させた空想的想像力だが、それが他者にも伝わるほどおもしろいのは、その妄想がきわめて具体的な合理性にもとづいているからだろう。ピカピカの現代建築と古臭い日本家屋を掛け合わせた和洋折衷の建築風景は、山口がしばしば描き出すモチーフのひとつだが、これはたとえば東京国立博物館本館のような帝冠様式にたいするノスタルジックな眼差しの現われなのかと思っていたら、さにあらず。これは取り壊した日本家屋を高層ビルの頭頂部に再建するという、じつに合理的かつ現実的な提案だったのだ。そこにあった建物を木っ端微塵に破壊した上で建設される現代建築の傲慢さに対して投げかけられた現実的かつ批判的な提案なのだ。
2010/12/30(木)(福住廉)
いきるちから

会期:2010/12/02~2011/03/06
府中市美術館[東京都]
大巻伸嗣、木下晋、菱山裕子の3人を集めた企画展。「生きることのすばらしさに気づかせてくれる」ことが共通項として挙げられているようだが、なぜこの3人なのかはっきりと説明されていないので、企画展のテーマとしてはあって無きに等しいものだろう。大巻は回転する鏡面に光を乱反射させて壁面に虚像を映し出す大掛かりな空間インスタレーションを、菱山はアルミメッシュを針金とワイヤーで組み上げた人物像を、それぞれ発表した。突出していたのは、木下晋。鉛筆で描き出した老婆やハンセン病患者の肖像画は、いずれも観覧者の心を打つものばかり。それは、鉛筆によって描き分けられた深い皺と乾いた肌質が彼らの濃密な人生の軌跡を物語っていたことに由来するばかりか、極端にクローズアップした構図がモチーフにできるかぎり接近しようとした木下の態度を表わしていたことにも起因していたように思う。ジャーナリストにも通じる対象への肉迫。それを画面に前景化させるか、内側に隠しこむかは別として、木下のように世界にたいして誠実に対峙する姿勢こそ、いまもっとも学ぶべきことではないか。これを学ばずして、「生きることのすばらしさ」を知ったところで、たかが知れている。
2010/12/28(火)(福住廉)
吉村芳生 展──とがった鉛筆で日々をうつしつづける私

会期:2010/10/27~2010/12/12
山口県立美術館[山口県]
吉村芳生が大勝利を収めた。彼が現在制作の拠点としている山口県で催した大規模な個展は、70年代より継続しているこれまでの制作活動を振り返ると同時に、最新作によってこれからの展望も予感させる、すぐれて充実した展観だった。「六本木クロッシング2007」で大きな衝撃を与えたように、吉村芳生といえば、フェンスの網の目や自分の顔、新聞紙など、自分の眼に映る、きわめて凡庸な日常を、鉛筆や色鉛筆など、これまた凡庸な画材によって、ただ忠実に描き写す作風で知られているが、今回の個展では、その愚直な写生画の数々が披露されたのはもちろん、最新作ではその方向性が以前にも増して極限化していた。河原の草花を描いた《未知なる世界からの視点》は、横幅が10メートルにも及ぶ大作。草の緑と花の黄色が鮮やかな対比を構成しているが、川面に映るその光景も描き出しているので、上下で分けられたシンメトリックな構図が実像と虚像の関係を強調していた。ただし、注意深く見てみると、川面に見えたのは実像で、実像に見えたのは虚像であることに気づかされる。つまり吉村はこの作品を上下を反転させて展示していたのだった。吉村が、そして私たちが見ているのは、実像なのか、それともその反映にすぎない虚像なのか。そもそも双方はどのように峻別できるのか、実像が虚像でない根拠はどこにあるのか、すなわち私たちは何を見ているのか。吉村芳生の視線は、事物を眼に見えるままに描き出す写生画の方法論を踏襲しながらも、それよりもはるかに深いところに到達している。それを大勝利と呼ばずして、何と呼ぶというのか。
2010/12/11(土)(福住廉)
下平千夏─implosion point─
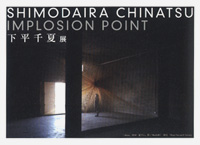
会期:2010/12/04~2010/12/25
INAXギャラリー[東京都]
緊張と弛緩。人間の身体がこの相反する二つの運動によって駆動しているように、下平の作品には運動の基本的な原型が垣間見える。大量の輪ゴムを連結した線を一本により集め、一方をきつく縛り上げる反面、もう一方を放射状に拡散させて空間の隅々で固定する。すると、線であることを失念するほど硬化したゴムの塊がおそるべき内向的な求心力を連想させるのたいし、四方八方に飛び散る無数の線が爆発的な外向性を体感させるのである。空間を両極に引き裂く力の狭間に私たちを追い込むところに、下平の作品の魅力がある。
2010/12/09(木)(福住廉)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)