artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
ロバート・フランク写真展 Part I 「Outside My Window」

会期:2011/06/02~2011/07/30
gallery bauhaus[東京都]
ロバート・フランクの写真集『私の手の詩』(1972)、『Flower is......』(1987)の発行元である邑元舍代表の元村和彦は、長年にわたるフランクとの交友の間に彼のプリントを多数所持するようになった。その一部を二部構成で紹介するのが今回の展示で、夏休みを挟んで9月3日~10月29日には Part II 「Flower Is」が開催される。
Part I 「Outside My Window」の展示は、1950年代初頭のパリやロンドンでのスナップショットから、1958年の写真集『アメリカ人(The Americans)』の時代を経て、1970年代以降の複数の写真をコラージュ的に構成する実験的な作品まで多岐にわたっている。だがそこには、あくまでも日常の事物に寄り添いながら、自らの生の流れに沿って写真を綴れ織りのように編み上げていこうとするフランクの志向をはっきりと見ることができる。1974年に愛娘、アンドレアの飛行機事故死を受けて制作したコラージュ作品には、「SKY」「ANDREA DIED DEC.28 th 1974」という書き込みがあり、鎮魂と作品制作の行為が切れ目なく融合していることが見てとれる。このような生と写真のアマルガムをめざすあり方は、1970年代以降、むしろアメリカの写真家たちよりは深瀬昌久、荒木経惟、鈴木清といった日本の「私写真」の写真家たちに受け継がれていったのではないだろうか。フランクは日本の現代写真家たちとの親密な交流で知られているが、それはその作品世界の基層が共通しているからではないかと思う。
会場に作家の埴谷雄高が『私の手の詩』に寄せた文章の一部を抜粋して掲げてあった。「事物も人間も、それを凝視すればするほど、見られるものと見るものとのあいだの内的なかかわりをあきらかにして、生と存在の端的な秘密を私達に示すのである」。たしかにフランクの写真を見ていると、そこから「生と存在の端的な秘密」が生々しい切り口で浮かび上がってくるように感じる。見慣れていたものが見慣れない異物に変貌する瞬間を、恐ろしく的確に捉える彼の特異な眼差しのあり方を、あらためて確認することができた。
2011/06/22(水)(飯沢耕太郎)
BankART AIR Program 2011 OPEN STUDIO

会期:2011/06/17~2011/06/26
BankART Studio NYK[神奈川県]
横浜のBankARTのアーティスト・イン・レジデンスのプログラムはかなり面白い。黙々とレース編みを続けているアーティスト(樋口昌美《ド イリ ー》)がいたり、漫画雑誌を「苗床」にしてカイワレ大根を育てていたり(河地貢士《まんが農業》)、ユニークな作品を楽しむことができる。この玉石混淆の雰囲気が、会場に活気をもたらしているように感じるし、50人(組)弱のアーティスト同士もいろいろ刺激を受けるのではないだろうか。
その会場の一角に、BankART Schoolの飯沢ゼミの有志が、「いまゆら(イマ・ユラギ・ツナイデ)」というスペースで参加している。毎週「ポートフォリオを作る」という授業を続けている最中に、「3・11」の大震災が起こったことは、彼らにとっても講師をつとめていた僕にとっても大きな出来事だった。だが、そのことが「反転した日常を写真とポートフォリオで検証する」というテーマの設定につながり、皆の力を集めてクオリティの高い展示を実現することができた。リーダーの若林ちひろさんをはじめとする13人の参加者にとっては得がたい経験だったのではないだろうか。6月18日には震災直後に宮城県太平洋沿岸に入って写真を撮影し、いち早く『hope/TOHOKU』というフォト・ブックをまとめた菱田雄介を迎えて、トークイベントが開催された。これから先、多くの写真家たちが復興の過程を長期戦で粘り強く記録していくと思うが、菱田の仕事はまさにそのスタートラインといえるだろう。
なお、『hope/TOHOKU』は僕の文章とあわせて再編集し、8月に『アフターマス 震災後の写真』(NTT出版)というタイトルで刊行する予定だ。いまその編集作業を進めているのだが、そこでは震災によって見えてきた写真を撮り続けることの意味を、あらためて問い直していきたい。
2011/06/18(土)(飯沢耕太郎)
劉敏史「-270.42℃, My Cold Field」
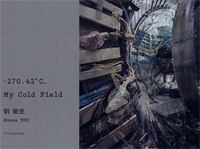
会期:2011/05/28~2011/06/25
AKAAKA Gallery[東京都]
劉敏史(You Minsa)は、2005年にビジュアルアーツフォトアワードを受賞した作品を、翌06年に写真集『果実』(ビジュアルアーツ)として刊行した。エチオピア南部のハマルの人々を撮影した端正なポートレートは、彼の高度な思考力と美意識をよく示す作品だったと思う。ただ、あまりにも隙なく完成され過ぎていて、このままだと袋小路に突き当たるのではないかという危惧もまた感じていた。今回AKAAKA Galleryで展示された新作「-270.42℃, My Cold Field」を見ると、彼が新たな領域に進むことでその危機をうまく脱したことがわかる。以前の作品を知るものにとっては、意外な選択に見えるかもしれないが、これはこれで常に絶対的な他者、あるいは外部の世界に向き合おうとする劉の志向性がよくあらわれた作品といえるのではないだろうか。
テーマになっているのは、つくば市の高エネルギー加速器研究機構(KEK)の施設の内部。素粒子物理学の最先端の施設で、僕はこの方面はまったく門外漢なので正直よくわからないのだが、宇宙創成のビッグ・バンの時に生成された「反物質」を人工的につくり出すという研究を進めているらしい。金属製の機器に無数のコードの束が複雑に絡みあっているさまは、あたかも人間の血管や神経組織の解剖図を見るような生々しさを感じる。産業用ロボットが意識を持つようになり、他の機械類と結合して増殖していく楳図かずおの傑作『わたしは真悟』(1982~86)を思い出したのだが、サイエンスの最先端とアニミズム的な空間はどこかでつながっているのかもしれない。最初は4×5の大判フィルムで撮影していたのだが、それでもまだ情報量が足りないので中判カメラ用のフェーズワンのデジタルバックに変えたのだという。輪郭線がキリキリと立ち上がってくるようなメタリックな色味のプリントも、よくコントロールされていて、見事な出来栄えだ。
2011/06/17(金)(飯沢耕太郎)
安井仲治 写真展 1930-1941

会期:2011/06/06~2011/07/31
写大ギャラリー[東京都]
何度見ても、安井仲治の作品には驚かされる。「安井仲治は日本近代写真の父である」と喝破した森山大道をはじめとして、多くの論者がその天才ぶりに驚嘆し、38歳という早過ぎた死を惜しんでいるが、それでもなおまだ充分な評価を得ているとはいえないのではないだろうか。今回の東京工芸大学中野キャンバス内の写大ギャラリーでの展示を見ても、この人の存在は時代に関係なく底光りをする輝きを放っているように思えるのだ。
今回は新たに収蔵された安井のモダン・プリント30点のお披露目ということで、1930年に「第3回銀鈴社展」に出品された「海港風景」から、早過ぎた晩年の傑作《雪》(1941)まで、ほぼ過不足なく彼の代表作を見ることができた。人によっては、彼の作風が余りにも大きく広がっていて、その正体がつかみにくいと思ってしまうかもしれない。シュルレアリスムの影響を取り入れた「シルエットの構成」(1938頃)のような作品から、メーデーのデモに取材した《旗》《検束》《歌》(以上1931)、切れ味の鋭いスナップショットの「山根曲馬団」シリーズ(1940)など、たしかに同じ作者の作品とは思えないほどの幅の広さだ。だが、現実を内面的なフィルターを介して独特の生命感あふれる映像に再構築していく手つきは見事に一貫しており、どの作品を見ても「安井仲治の世界」としかいいようのない手触りを感じる。『アサヒカメラ』1938年5月号の「自作解説」に「自分が小さい智慧で細工出来ぬ姿に出くわした時は其儘素直にこれを撮ります」と記した《秩序》(1935)のような作品を見ると、彼がアメリカやヨーロッパの同世代の写真家たちと、ほとんど同じ問題意識を共有していたことがよくわかる。この「トタン板の切れっぱし」の集積のクローズアップは、ウォーカー・エヴァンズの写真集『アメリカン・フォトグラフス(American Photographs)』(1938)におさめられた「ブリキの遺物(Tin Relic)」にそっくりなのだ。
なお、会場に置いてあった芳名帳を兼ねたスケッチブックに「写大ギャラリーはオリジナル・プリントを展示する場所だから、モダン・プリントはよろしくないのではないか」という指摘が記してあった。だが、写真家の死後に制作されたモダン・プリントも、オリジナル・プリントの範疇には入る。ただ、写真家自身が最初にプリントしたいわゆる「ヴィンテージ・プリント」とは、位置づけが違ってくることは否定できない。今回のモダン・プリントはほぼ完璧な出来栄えだが、混乱を避けるためにも、このプリントが誰によって、どのような経緯で制作されたのかを、会場のどこかに明記しておく方がよかったのではないだろうか。
2011/06/16(木)(飯沢耕太郎)
平竜二「Vicissitudes 儚きもの彼方より」

会期:2011/06/08~2011/07/10
LIBRAIRIE6[東京都]
あまり他に例のない独特の作風の持ち主だと思う。平竜二は1960年熊本生まれ。高村規に師事してコマーシャル写真の仕事をした後、1988年に渡米し、ニューヨークで栗田紘一郎からプラチナプリントを学んだ。プラチナプリントは光と影の中間の領域を豊かなグラデーションで表現できるが、技術的にはかなりコントロールが難しい。平のプラチナプリントは完成度が高く、ここまで完璧に使いこなせる写真家はあまりいないのではないだろうか。
今回展示された「Vicissitudes 儚きもの彼方より」は二つのシリーズで構成されていて、ひとつはタンポポやオジギソウなど自分で種子から育てた植物を、シンプルに黒バックで撮影したもの。植物のフォルムを、細やかに、愛情を込めて写しとっている。もうひとつのシリーズでは、カメラの前にフィルターを置き、そこに写る影を長時間露光で定着した。光源が 燭のように淡く、弱い光なので、被写体になっている花や昆虫の影に微妙な揺らぎが生じてきている。こちらの「影」シリーズの方が、この写真家の「儚きもの」に寄せるシンパシーと、生きものの微かな命の震えを受けとめる感度の高さをよく示しているように思えた。
日本の写真家で、このように繊細な美意識の持ち主ということになると、中山岩太の1930~40年代の仕事くらいしか思いつかない。「影」シリーズの、どこからともなく射し込んでくるほのかな光の質も、中山と共通している。ただ、中山の濃密なエロティシズムを感じさせる作品と比較すると、平のプラチナプリントがどこかひ弱な印象を与えることは否定できない。さらにこの独自の作品世界を突き詰め、毒や怖さをも秘めた生命力のエッセンスをつかみ取ってほしい。
2011/06/15(水)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)