artscapeレビュー
SYNKのレビュー/プレビュー
MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事
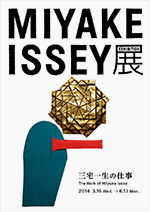
会期:2016/03/16~2016/06/13
国立新美術館[東京都]
1970年の三宅デザイン事務所設立から現在、そしてその未来まで、三宅一生の仕事を展望する大規模な展覧会。3つに分かれた最初のセクションAは70年代。綿ジャージを素材に皆川魔鬼子のプリントデザインを施した《タトゥ》を先頭に、ファッションショウのランウェイのように細長い展示室に服が1列に並ぶ。セクションBは80年代前半。繊維強化プラスチックを用いた《プラスチック・ボディ》、籐と竹を素材とした《ラタン・ボディ》などのシリーズだ。この2つの展示デザインは吉岡徳仁。セクションAの人体は段ボール、セクションBの人体は透明な樹脂でできており、いずれも三宅一生の服を象徴する「一枚の布」をコンセプトに、一枚の板をレーザーでカットしたものだという。セクションCは80年代以降の仕事で、素材づくりからはじまり技術の開発を行ないながらデザインを進める三宅の服づくりは、やがてプロダクトデザインの領域へと拡大する。その代表が「製品プリーツ」や「A-POC」、そして「132 5. ISSEY MIYAKE」だ。展示デザインは佐藤卓。縮小サイズの「132 5. ISSEY MIYAKE」をトルソーに着せる体験コーナーは、やはり佐藤卓が手がけた21_21の「デザインあ」展を思い出させる。この展示室にはプリーツ・マシンが設置されていて、田中一光のポスターモチーフを用いたプリーツの製作が毎日実演される★1。映像インスタレーション制作は中村勇吾。他に合計50分ほどの映像上映がある。
他のデザイナーの展覧会にどれほどの報道陣が集まるのか知らないが、300人程度を収容できる講堂が記者でいっぱいになったといえば、この展覧会への注目度がうかがわれよう。三宅一生は間違いなくスターデザイナーの一人だ。スターの背後には、その仕事を支える多くの人びとがいる。三宅一生が他の多くのスターと異なるのは、その仕事においてスター本人ばかりではなく、協働者たちにもスポットライトが当てられる点ではないだろうか。たとえば今回の展覧会の記者説明会には、企画を担当した北村みどり氏、デザインを担当した佐藤卓氏、吉岡徳仁氏が企画と展示について語り、三宅氏は主にそれを横で聞いている。三宅氏と青柳正規氏が発起人となった「国立デザイン美術館をつくる会」のシンポジウム(2012年)のときも、デザイナーたちのディスカッションを見守っていた三宅氏の姿が印象に残っている。
1987年から99年までコレクションの写真を手がけたアーヴィング・ペン氏との仕事においては、ペン氏の発想の妨げとならないよう撮影に立ち会うことをしなかった。それは「自分自身が堕落しないように厳しい評価をしてくれる人を必要としていた」からだという★2。協働者はアーティストやクリエーターに限らない。紙衣のための和紙工房、日本の毛織物であるホームスパンの工房、プリーツ加工の会社など、素材のつくり手、技術の担い手も積極的に紹介される。外部とのコラボレーションだけではない。仕事はチームで進められる。新しいアイデアもチームから生まれる。チームによって若い人を育てる。本展のタイトルは「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」だが、展示のいたるところに協働とチームによる仕事を確認できる。しかしおそらく最大の協働は来館者とのものだろう。スタッフはもちろん、来館者にもISSEY MIYAKEの服を着ている人が多い。「作品として発表しても、人が使わない限りデザインではない。そして、使い込まれたデザインはデザインした人のものではなく、使った人のもの」★3なのだ。本展図録の序文で三宅氏はデザインミュージアムの構想に触れて次のように記している。「この二十年来、安藤忠雄さんや青柳正規さんはじめ、共鳴してくれるたくさんの人々とデザインミュージアムの設立を呼びかけているのは、人づくりと、世界各都市とを連携するため」だという。服をつくること。服を売ること。展覧会をつくること。ミュージアムをつくること。すべては人をつくり、人と人を結び、未来をつくるためにある。[新川徳彦]
★1──11:00~12:00。金曜日は11:00~12:00、15:00~16:00、18:00~19:00。
★2──「三宅一生インタビュー 未来への提言」(『美術手帖』2011年12月、35頁)。
★3──柳宗理との対談「アノニマウスデザインに向かって」(1998年。森山明子『デザイン・ジャーナリズム─取材と共謀』美学出版、2015年7月、178~182頁に再録)。

会場風景 左:セクションA 右:セクションB

会場風景 セクションC
2016/03/15(火)(SYNK)
おいしい東北パッケージデザイン展 2015 in Tokyo

会期:2016/03/09~2016/04/11
東京ミッドタウン・デザインハブ[東京都]
東北地方の10社10商品に対する新しいパッケージデザイン案を全国のデザイナーから募集し、商品化を目指すプロジェクト。東北経済産業局と日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)による企画の第2回で、応募702点から受賞作・入選作227作品が展示されている。プロのデザイナーとデザイン学生は区別なく審査され、今回は優秀賞10作品のなかに学生3名の提案が選ばれている。商品は麺類や練り物、漬け物などの加工食品と、地元産のラベンダーを使用した芳香剤。各々の企業に対象商品を取材した「ヒアリングシート」に書かれた企業理念やモノづくりの考え方、商品特性、価格、デザイン要件を元にデザインを行なう。地産地消商品やお土産品と位置づけられる商品には販売場所・地域が限定されているものが多いが、これを機に販路の拡大を視野に入れている商品もある。実用性・機能性が求められる商品もあれば、他社製品との差別化が求められる商品もある。それらの要望・要件をどのようにデザインに落とし込むかが問われている。昨年との違いは、優秀賞だけではなく、ノミネート作品から商品化される可能性が示されている点だろうか。
3月11日に開催されたオープニングトークには、昨年度の優勝受賞者3名らが登壇し、受賞作商品化の状況が報告された。それによれば、参加10社10商品のうち2社が辞退、8商品が商品化あるいは商品化に向けて話が進められているとのことだ。発売された商品については良く売れている、バイヤーの反応がよいなどの結果が出ており、現在進行中のものは単品ではなく他商品も含めたシリーズ展開をしたいという要望が出てプロジェクトが進められているという。デザインが良くなったからといって売れるとは限らないし、売上増大の理由がすべてデザインにあるわけではないだろうが、パッケージデザインを変更する作業に関わることでメーカーの側に意識の変化が生じているように見受けられる。すなわち、モノをつくって卸に納めて終わりになるのではなく、商品の力に自信を持ち、それを消費者にどのように届けるのか/売るのかという点に意識的になっていると感じる。これまでデザイン、デザイナーとの関わりが薄かった企業にそのような変化が生じているとすれば、メーカーとデザイナーの双方にとってこのプロジェクトはおおいに意義のある結果を出していることになる。なお、本プロジェクトと同様の試みが北海道でも始まっているそうだ(北海道経済産業局主催:北海道のおいしいつながり|パッケージデザイン展2015)。[新川徳彦]
関連レビュー
おいしい東北パッケージデザイン展 in Tokyo:artscapeレビュー|美術館・アート情報 artscape
2016/03/11(金)(SYNK)
鼻煙壺:沖 正一郎コレクション「小さきものは皆うつくし」

会期:2016/02/14~2016/03/21
渋谷区立松濤美術館[東京都]
鼻煙壺とは、中国の嗅ぎ煙草入れのこと。南米原産の煙草はいわゆる「コロンブスの交換」によってヨーロッパ大陸へと伝来し、やがて世界中に広がった。粉末状のたばこを鼻から吸う嗅ぎたばこは17世紀から18世紀のヨーロッパでフランスを中心に流行し、美麗な嗅ぎ煙草入れがつくられた。嗅ぎたばこの習慣が中国に伝わったのは17世紀後半。そして湿度が高いアジアの気候に合わせて、より密閉度が高い容器がつくられるようになったという。蓋の内側には小さな匙が付いていて、それで中の嗅ぎたばこをすくい、手の甲に乗せて鼻で吸ったり、鼻の粘膜にすりつける。機能が決まっていて、持ち歩くことが前提なので、どれもサイズはだいたい同じ。人前に出して使うものだから、持ち主の趣味の良さを示すために高価な素材、凝った意匠の鼻煙壺がつくられた。
本展に出品されているのは、世界的な鼻煙壺コレクターで、ファミリーマート初代社長の沖正一郎氏のコレクション。沖氏はこれまでに大阪市立東洋陶磁美術館、北京・故宮博物院やロンドン・ヴィクトリア&アルバート博物館、世田谷美術館等に多数の鼻煙壺を寄贈しているが、それ以外にも多くの鼻煙壺を所蔵している。本展では候補に挙げられた鼻煙壺600点から300点が選ばれ、素材別──陶磁・ガラス・金属・貴石・象牙や木製品など──に分けて展示されている。個人的な好みをいうと、貴石を用い、その素材が持つかたちや模様を生かしながらつくられた鼻煙壺はとても魅力的だ。次いで魅力的な素材はガラス。なかでも色ガラスを被せて彫刻を施した鼻煙壺には、貴石を用いたものと同様に惹かれるものがある。沖コレクションには、内絵鼻煙壺といって、透明なガラス製鼻煙壺の内側から特殊な筆を用いて絵が描かれたものが多数ある(これは現代中国でお土産用としてつくられているそうだ)。そのなかでもアメリカ合衆国歴代大統領の肖像が描かれた鼻煙壺は、これまでに他の沖コレクション展でも何度か目にしているので、沖氏のお気に入りだったのだろうか。その沖正一郎氏は、本展会期中の2016年2月20日に89歳で亡くなられた。体調が良ければ本展を見に来る予定もあったそうだが、残念ながら果たせなかったという。ご冥福をお祈りします。[新川徳彦]
関連レビュー
蒐めて愉しむ鼻煙壺──沖正一郎コレクション:artscapeレビュー|美術館・アート情報 artscape
嗅ぎたばこ入れ──人々を魅了した掌上の宝石:artscapeレビュー|美術館・アート情報 artscape
2016/03/10(木)(SYNK)
ウィリアム・モリス自邸「ケルムスコット・ハウス」(英国)
ウィリアム・モリス協会[ロンドン]
モダン・デザインの父として知られる19世紀英国のデザイナー、ウィリアム・モリスの自宅「ケルムスコット・ハウス」(ロンドン、ハマースミス)を訪れた。現在は、ウィリアム・モリス協会が二室を週二日のみ、一般公開している。ひとつは、1階のコーチハウスで小規模な展覧会が開かれる場所、もうひとつは地下の元使用人の部屋である。この邸宅はモリスが1878年から1896年に亡くなるまで居住した場所。彼自身が「ハマースミス・ラグ」と呼ばれるカーペット・織物を織機を使用して製作したほか、また社会主義同盟に没入した場所でもある。晩年に注力した印刷工房ケルムスコット・プレスも、この近くで開始された。モリスはテムズ川沿いに位置するこの家と、所有するもうひとつのマナーハウス(ケルムスコット・マナー)とを船で行き来したという。ロンドンでモリス巡礼をする向きには、モリスが少年・青年期を過ごしたウォルサムストウにある邸宅の「ウィリアム・モリス・ギャラリー」も勧めたい。近年、大規模な改装がされたので、非常に充実して見ごたえのある美術館となっている。[竹内有子]

「ケルムスコット・ハウス」外観

同、内観
2016/03/10(木)(SYNK)
キューバの映画ポスター──竹尾ポスターコレクションより

会期:2016/01/07~2016/03/27
東京国立近代美術館フィルムセンター[東京都]
竹尾ポスターコレクションから、革命期から1990年前後までのキューバ映画のポスター85点を紹介する展覧会。1959年の革命以降、キューバは「映画芸術産業庁(ICAIC)」を拠点として先鋭的な映画を送り出してきた。先鋭的あるいは革命的なのは映画ばかりではなく、そのポスターにおいても同様だったという。デザインにはさまざまなデザイナーや画家が招かれ、自由な解釈によるアーティスティックなポスターがつくられた。しばしばタイトルの文字は小さく、それがなんの映画なのかもわかりづらい(近年の日本の説明過剰な映画ポスターとはまったく逆のデザインだ)。ICAICによれば、ポスターは映画とは独立した芸術作品なので、文字は読めなくて構わないのだそうだ。宣伝臭がしないのは、社会主義革命後に資本主義的な「広告advertisement」が禁じられ「プロパガンダpropaganda」に取って代わられたからでもある。印刷技術の点では、オフセット印刷ではなくシルクスクリーンが用いられ続けている点も、広告としてではなく作品としてのポスターであり続ける証左かも知れない。映画の内容に目を向けると、外国映画のポスターの表現にも惹かれる(これは元の映画ポスターを知っているから、キューバにおける表現や解釈の違いに興味惹かれるということでもある)。社会主義国であるソヴィエトや東欧諸国の映画が輸入されたのはもちろんだが、1960年代後半には娯楽映画の輸入にも力が入れられた。革命後にハリウッドの娯楽映画の輸入が途絶えた代わりに、彼らは日本から映画を買い付けた。とりわけ人気だったのが勝新太郎の「座頭市」。日本以外でシリーズ作品16本が上映された国はキューバ以外にはないのだそうだ。1975年に勝新太郎がキューバを訪問したときは大歓迎されたという。アルフレド・ゴンザレス・ロストガルドによる「座頭市兇状旅」のポスターもまた斬新。はたしてキューバ国民のあいだでこのポスターと勝新のイメージが一致していたかどうかはわからないが。
この展覧会は京都国立近代美術館に巡回する(2016/6/1~2016/7/24)。[新川徳彦]
2016/03/09(水)(SYNK)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)