artscapeレビュー
MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事
2016年05月15日号
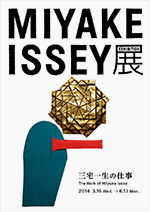
会期:2016/03/16~2016/06/13
国立新美術館[東京都]
1970年の三宅デザイン事務所設立から現在、そしてその未来まで、三宅一生の仕事を展望する大規模な展覧会。3つに分かれた最初のセクションAは70年代。綿ジャージを素材に皆川魔鬼子のプリントデザインを施した《タトゥ》を先頭に、ファッションショウのランウェイのように細長い展示室に服が1列に並ぶ。セクションBは80年代前半。繊維強化プラスチックを用いた《プラスチック・ボディ》、籐と竹を素材とした《ラタン・ボディ》などのシリーズだ。この2つの展示デザインは吉岡徳仁。セクションAの人体は段ボール、セクションBの人体は透明な樹脂でできており、いずれも三宅一生の服を象徴する「一枚の布」をコンセプトに、一枚の板をレーザーでカットしたものだという。セクションCは80年代以降の仕事で、素材づくりからはじまり技術の開発を行ないながらデザインを進める三宅の服づくりは、やがてプロダクトデザインの領域へと拡大する。その代表が「製品プリーツ」や「A-POC」、そして「132 5. ISSEY MIYAKE」だ。展示デザインは佐藤卓。縮小サイズの「132 5. ISSEY MIYAKE」をトルソーに着せる体験コーナーは、やはり佐藤卓が手がけた21_21の「デザインあ」展を思い出させる。この展示室にはプリーツ・マシンが設置されていて、田中一光のポスターモチーフを用いたプリーツの製作が毎日実演される★1。映像インスタレーション制作は中村勇吾。他に合計50分ほどの映像上映がある。
他のデザイナーの展覧会にどれほどの報道陣が集まるのか知らないが、300人程度を収容できる講堂が記者でいっぱいになったといえば、この展覧会への注目度がうかがわれよう。三宅一生は間違いなくスターデザイナーの一人だ。スターの背後には、その仕事を支える多くの人びとがいる。三宅一生が他の多くのスターと異なるのは、その仕事においてスター本人ばかりではなく、協働者たちにもスポットライトが当てられる点ではないだろうか。たとえば今回の展覧会の記者説明会には、企画を担当した北村みどり氏、デザインを担当した佐藤卓氏、吉岡徳仁氏が企画と展示について語り、三宅氏は主にそれを横で聞いている。三宅氏と青柳正規氏が発起人となった「国立デザイン美術館をつくる会」のシンポジウム(2012年)のときも、デザイナーたちのディスカッションを見守っていた三宅氏の姿が印象に残っている。
1987年から99年までコレクションの写真を手がけたアーヴィング・ペン氏との仕事においては、ペン氏の発想の妨げとならないよう撮影に立ち会うことをしなかった。それは「自分自身が堕落しないように厳しい評価をしてくれる人を必要としていた」からだという★2。協働者はアーティストやクリエーターに限らない。紙衣のための和紙工房、日本の毛織物であるホームスパンの工房、プリーツ加工の会社など、素材のつくり手、技術の担い手も積極的に紹介される。外部とのコラボレーションだけではない。仕事はチームで進められる。新しいアイデアもチームから生まれる。チームによって若い人を育てる。本展のタイトルは「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」だが、展示のいたるところに協働とチームによる仕事を確認できる。しかしおそらく最大の協働は来館者とのものだろう。スタッフはもちろん、来館者にもISSEY MIYAKEの服を着ている人が多い。「作品として発表しても、人が使わない限りデザインではない。そして、使い込まれたデザインはデザインした人のものではなく、使った人のもの」★3なのだ。本展図録の序文で三宅氏はデザインミュージアムの構想に触れて次のように記している。「この二十年来、安藤忠雄さんや青柳正規さんはじめ、共鳴してくれるたくさんの人々とデザインミュージアムの設立を呼びかけているのは、人づくりと、世界各都市とを連携するため」だという。服をつくること。服を売ること。展覧会をつくること。ミュージアムをつくること。すべては人をつくり、人と人を結び、未来をつくるためにある。[新川徳彦]
★1──11:00~12:00。金曜日は11:00~12:00、15:00~16:00、18:00~19:00。
★2──「三宅一生インタビュー 未来への提言」(『美術手帖』2011年12月、35頁)。
★3──柳宗理との対談「アノニマウスデザインに向かって」(1998年。森山明子『デザイン・ジャーナリズム─取材と共謀』美学出版、2015年7月、178~182頁に再録)。

会場風景 左:セクションA 右:セクションB

会場風景 セクションC
2016/03/15(火)(SYNK)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)