artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
渡邊聖子「波と爪」

会期:2013/02/25~2013/03/03
みどり荘[東京都]
渡邊聖子がようやく本領を発揮し始めたようだ。今回の渋谷区青葉台のみどり荘(古いアパートを改装した気持ちのいいスペース)で開催された新作展では、写真のプリントや青焼きのコピーをガラス板で押さえたり、サービスサイズのプリントを束にして置いたりするインスタレーションが試みられていた。そのやり方自体は、以前とそれほど変わっていない。だが、特筆すべきは写真と併置されている「波と爪」(あるいはKiki and Lala are in love I watch their love)と題するテキストの方で、その表現力が格段に上がっているのだ。
渡邊は以前からテキストと写真とを組み合わせる作品を発表してきたのだが、とかく言葉が空転する印象があり、その意図がうまく伝わってこなかった。だが、「歌謡曲を下敷きにした」今回のテキストでは、言葉の絡み合いがいい意味で俗っぽくなり、読者にきちんと届いてきているように感じる。「波は傷の形をしている。あなたたちはそこで抱き合っていても何も見ることはできない。窓だけが仄あかるい。それ以外はすべて暗い。見えない。抱擁する」。スリリングなエロスの場面が、畳み込むようにスピードに乗せて綴られていくその内容は、もはや現代詩の領域(むろん映像は重要な役割を果たしているが)に踏み込んでいると言えそうだ。
本展はartdishから刊行された渡邊の作品集『石の娘』の出版記念展を兼ねている。秦雅則『鏡と心中』、村越としや『言葉を探す』、そして今回の『石の娘』と続いてきたartdishのラインアップは、言葉を中心にした写真集という、ユニークな志向性をさらに強めつつあるようだ。このシリーズも次の展開が楽しみだ。
2013/03/03(日)(飯沢耕太郎)
松山賢「生きものカード(甲虫)」
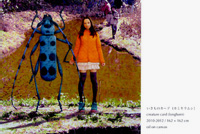
会期:2013/01/018~2013/03/03
アンシールコンテンポラリー[東京都]
カブトムシやクワガタと美少女を組み合わせた絵画。オタクならずとも垂涎のモチーフだ。今回は鉛筆画や水彩画も出ているが、メインは案内状にも使われたS100号の大作《生きものカード(カミキリムシ)》。黄緑色の川(池?)を背景に、青色のカミキリムシとオレンジ色のジャケットを着た少女が正面を向き(カミキリムシは背面)、同じサイズ、同じポーズ(?)で仲よく手(?)をつないでいるところが描かれている。固い殻におおわれた甲虫と柔らかそうな少女の対比、青とオレンジという補色関係、ミクロとマクロの同サイズ化にもかかわらず、破綻なくまとまっている。さらに画面は、細かく分割彩色された明るい風景を基層に、なめらかなグラデーションで表された少女とカミキリムシ、そのカミキリムシの表面に盛り上げた細かいアラベスク模様、という次元の異なる3層から成り立っているのだ。これは学ぶところが多い。
2013/03/03(日)(村田真)
梅田哲也「0才」(大阪市現代芸術創造事業 Breaker Project「ex・pots 2011-2013」)
会期:2014/02/22、23、28、03/01、02、07、08、09
山王郵便局横 空き地[大阪府]
これは街全体が梅田作品か。金網にひっかかるテレコから流れ出す音声に従い案内所へ。展示会場だった廃屋では、半世紀以上前の大阪歌が流れていたかと思うと、突如人が現われ、ぼろぼろの梁をわたり、天井(半壊)に置いてあるプレーヤーにたどり着き、SP盤レコードをひっくり返す……。1階では空き瓶を吹いたり、石を愛でたりしている……。なんだかいろんな人が出たり入ったりしてざわざわしている。ゴルフ練習場でブンブン動く大きな黒い球。空き地。これも作品だっけ? でも、ぱっと見ただけでは、なにが起こってるかなんて全然わからないいつもの街にも見えるのだろう。地域との協力も、遊覧する企画としても完成度が高かった。宣伝文句に寸分違わず、西成に梅田哲也のひとつの集大成を見た。
2013/03/02(日)(松永大地)
大阪成蹊大学芸術学部(環境デザイン学科・美術学科)卒業制作展
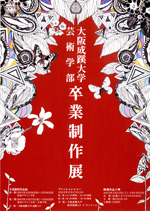
会期:2013/02/027~2013/03/03
大阪成蹊大学南館[大阪府]
2012年度、長岡京(京都府)から現在の相川(大阪府)に移転した大阪成蹊大学芸術学部の移転後初めての卒業制作展。今年は学内での展示で、1期(前期)情報デザイン学科、2期(後期)環境デザイン学科・美術学科と展示会期が分かれていたのだが、私が見に行った2期には環境デザイン学科、美術学科ともに優秀な作品がいくつもあったので、一度で全卒業生の作品を見ることのできない展覧会になっていたのは残念だった。環境デザイン学科・プロダクト・クラフトデザインコースの渡辺宗生が発表していた《kokko》は、木製の棒、ゴム紐、ロープからなるシンプルなユニットで、自由にパーツを組み合わせてスツールやテーブルの脚などにするというキャンプ用のファニチャーキット。“kokko”という「焚き火」を意味するフィンランド語のネーミングは、その音の響きと、気の置けない人々と過ごす暖かなひとときをイメージした「時間」を想い、つけたという。道具として使うためには工夫と知恵が要るのだが、一人では組み立てが難しい場合が多いという点がまた面白い。一緒に過ごす人との協力もその狙いだった。美術学科では、大きく枝を伸ばす松をダイナミックな構図で描いた日本画コース・野口春海の《春は来る》、瀬戸口美紀の《少女の夢》、洋画コース・坂根麻里衣のインスタレーション《モデムちゃん》などが印象に残っている。人数は少ないが、その分、学生達の制作態度や努力、それぞれの感性が鮮やかに見える瑞々しい卒展だった。

《kokko》展示風景
2013/03/02(土)(酒井千穂)
森山大道「写真よさようなら」

会期:2013/02/16~2013/03/16
Taka Ishii Gallery[東京都]
ロンドン、テート・モダンでのウィリアム・クラインとの二人展も無事終わり、森山大道の仕事はさらに大きな広がりを持ち始めている。今回のTaka Ishii Galleryでの個展では、もはや伝説といってよい1972年の写真集『写真よさようなら』(写真評論社)の収録作から10点を展示していた。
『写真よさようなら』は、ある意味で森山の転機となった写真集で、全編「アレ・ブレ・ボケ」の極致と言うべき写真群で構成され、ラディカルな実験意識に貫かれていた(巻末に中平卓馬との対談「8月2日 山の上ホテル」をおさめる)。ところが、この写真集へのネガティブな反応が引き金となって、森山は長期にわたる「大スランプ」に陥ってしまう。1981年に『写真時代』に連載した「光と影」のシリーズで再起するまで、10年近くの苦闘が必要だった。今回あらためて見ても、苛立たしげな身振りで事物の表層を「擦過」していく森山の視線のあり方が、緊張感を孕んで極限近くまで達しつつあったことがよくわかる。唇、ジーンズ、自動車、印刷物の網目など、森山がそれ以後もずっと執着し続ける被写体が、確信犯的に選びとられているのも興味深い。
今回、もうひとつ注目すべきなのは、展示されているプリントが印画紙に引き伸ばされているのではなく、シルクスクリーンで刷られていることだ。森山は1970年代からシルクスクリーンの質感と表現力に着目し、実際に作品も発表してきた。印刷の網点でも印画紙の諧調でもない、シルクスクリーンに特有のぬめりを帯びた灰色~黒のトーンは、とても面白い効果をもたらしている。あの『写真よさようなら』が、新たな生命を得て甦ったと言えそうだ。
2013/03/01(金)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)