artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
夜明けまえ 知られざる日本写真開拓史[北海道・東北編]

会期:2013/03/05~2013/05/06
東京都写真美術館 3階展示室[東京都]
東京都写真美術館で2007年から開催されている「夜明けまえ」の展示も4回目を迎えた。今回は[北海道・東北編]ということで、全国各地の美術館、博物館、図書館、資料館に古写真の所在を問い合わせ、現地調査を繰り返して新たな資料を発掘していくスタイルも、すっかり定着したようだ。特に今回の北海道・東北地方は、幕末から明治期にかけて多くの注目すべき写真家たちが活動した地域であり、横山松三郎、田本研造、武林盛一、佐久間範造(以上北海道)、菊池新学(山形)、屋須弘平(岩手県出身、中米グァテマラで活動)、白崎民治(宮城)らの500点を超える写真群はなかなか見応えがあった。アルバムなどを展示するときに、掲載写真を複写し、壁に映写して見せるやり方もうまくいっていたと思う。
今回は最後のパートに、明治時代の自然災害の記録写真が「特別展示」されていた。ウィリアム・K・バルトンと岩田善平による福島・磐梯山の大爆発後の光景(1888年)、作者不詳の山形・庄内地方の大地震の記録(1894年)、宮内幸太郎が撮影した明治三陸津波の写真アルバム(『中島待乳写真台帳』1896年)など、ちょうど東日本大震災から2年という時期でもあり、時宜を得た好企画だと思う。その資料的価値や迫真性もさることながら、写真家たちが地震や津波による死者の姿を、克明に撮影、記録し、すぐにアルバムのような形で公表していることに強い印象を受けた。東日本大震災後の死者のイメージの扱われ方(ほとんど公表されていない)とは対照的だ。死者の写真を公開すべきかどうかは、きちんと考えて答えを出すべき問題ではないだろうか。
2013/03/13(水)(飯沢耕太郎)
田中智子の乾漆立像 展「此方彼方(こなたかなた)」
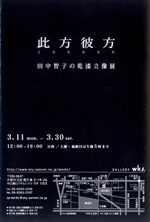
会期:2013/03/011~2013/03/030
Gallery wks.[大阪府]
乾漆技法を用いて人間等身大の立像を制作している田中智子の近年制作の作品を「対」をキーワードに展示した展覧会。私自身は昨夏開催された「隠岐しおさい芸術祭」で西ノ島の焼火神社に展示されていた一対の立像《対になるもの》が記憶に新しい。神社の拝殿という独特の展示空間の作用もあったのだろうが、その神秘的でどこか古雅な佇まいが印象的で、もう一度見たいと思っていたので、今展で展示されていたのは嬉しかった。微笑を浮かべ、エキゾチックな衣装を纏う8点の立像のなかには、角があるものもある。妖怪か妖精か、親近感と違和感を両方覚えるそれらの表情はどれも見れば見るほど豊かで幻想的。どこかで出会いそう、どこにいそうなどと連想が掻き立てられていくのが愉快だ。背景や台座など、工夫が凝らされた展示もその作品世界をいっそう魅力的に見せていた。

展示風景
2013/03/13(水)(酒井千穂)
新聞錦絵─潁原退蔵・尾形仂コレクション─
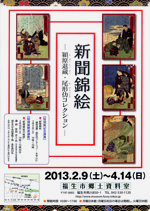
会期:2013/02/09~2013/04/14
福生市郷土資料室[東京都]
新聞錦絵とは、明治7(1874)年から数年間発行された木版多色刷りの一枚物。新聞に掲載された事件や逸話を錦絵と文章でわかりやすく伝えたマスメディアである。本展は、国文学者の潁原退蔵から尾形仂へ受け継がれてきた新聞錦絵のコレクションが同室に寄贈されたことを記念した展覧会。新聞錦絵を中心に約100点の資料が展示された。
新聞錦絵といえば月岡芳年が知られているが、今回展示された新聞錦絵の大半は、「大阪錦絵新聞」のような上方の新聞錦絵。東京の新聞錦絵より判型が一回り小さいが、扇情的な画題を色鮮やかな錦絵と平明な文章で伝える形式は、ほとんど変わらない。取り上げられている出来事は、「夫が浮気した女房を殺害した話」「養女を折檻した鬼婆の話」「外国人が猟に行き誤って子どもを撃ってしまった話」など、センセーショナルな事件が多い。開港によって輸入された西洋由来の鮮やかなインク(とりわけ赤と紫)が、暴力描写を劇的に高めているのも頷ける。
ただ、細かくみてみると、「男性として7年間暮らした女性の話」や「料理屋の娘が華族のお誘いを粋に断った話」、「古狐が娘に化けていた話」など、画題は必ずしも刃傷沙汰に限られているわけではないことがわかる。平たく言い換えれば、「ひどい話」ばかりだけでなく、「おもしろい話」や「良い話」もあったのだ。だとすれば、新聞錦絵とは明治時代に固有のニュース・メディアであったのと同時に、落語や講談のような大衆芸能にも重なりあう、ハイブリッドなメディアだったのではないだろうか。
事実、本展でていねいに解説されていたように、従来の新聞が想定する読者層が知識人だったのとは対照的に、新聞錦絵のそれは一般大衆の婦女子であり、彼らが読みやすいように、新聞錦絵の文章は平仮名を中心に記述され、漢字を用いる場合であっても、すべて振仮名が振られていた。文体も、新聞記事の文章をそのまま転載したわけではなく、同じ内容を五七調に改めることで、言葉が跳ねるようなリズム感をもたらしている。つまり、新聞錦絵の錦絵が劇的に脚色されていたのと同じように、その文章もまた劇的に演出されていたのだ。
「ひどい話」をよりひどく、「おもしろい話」をよりおもしろく、「良い話」をより良く語ること。落語や講談が開発してきた独自の文法と、浮世絵から展開してきた錦絵との合流地点に新聞錦絵を位置づけることができるのではないか。
2013/03/13(水)(福住廉)
第16回岡本太郎現代芸術賞展
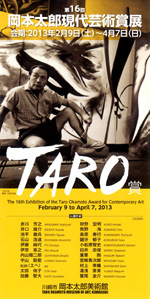
会期:2013/02/09~2013/04/07
川崎市岡本太郎美術館[神奈川県]
今年は739点の応募のうち22組が入選。岡本太郎賞は、茶室の壁から柱、畳、釜、茶碗、花入れ、掛軸にいたるまですべて鉄素材・鉄製品を利用してつくった加藤智大の《鉄茶室徹亭》。これはスゴイ。秀吉の「黄金の茶室」より地味だが、きっと金を失ったんで鉄になったんだろう。でもそれがどーした感は否めない。岡本敏子賞は、宇宙からエイリアンが見た地球の姿を絵画、立体などで表現した石山浩達の《エイリアン・ヴィジョン:アンリミテッド・オイル》。これも労作だが、FRPの立体が村上隆のそれに似てたり既視感がつきまとう。特別賞で気になったのは、桒原寿行《アイ》と小松原智史の《コマノエ》。前者はブタの眼球から取り出したレンズを使って像を映し出す装置で、時間が経つにつれレンズが濁り、像がボケていく過程を見せている。これはおもしろい。ブタの眼球を切り裂く映像はブニュエルの『アンダルシアの犬』を思い出す。さらに鳥とか魚とかイカとか昆虫とかヒトとかさまざまな生物で試してほしい。後者の小松原は会期中、壁3面に貼ったパネルのみならず壁面にも墨でドローイングを増殖させている。その絵柄はボッシュ+山下菊二+ガロのマンガみたいなドロドロのアナクロものだが、時と場所をわきまえずに描き続ける意欲を買いたい。勝手に村田真賞だ。ところで今回、絵画作品が何点かあったが、サイズが巨大なせいかひとつの画像を三つのパネルに連続して描く3連画が多かった。先に挙げた石山の絵画部分がそうだし、ほかに熊野海、宮崎勇次郎、村上幸織、赤川芳之もそう。絵画を出してる大半が3連画だ。なぜ2でも4でもなく3なのか。
2013/03/12(火)(村田真)
奥田輝芳 55 DRAWINGS

会期:2013/03/12~2013/03/17
ギャラリー恵風[京都府]
展覧会初日に55歳の誕生日を迎えた奥田が、語呂合わせなのか、2008年以降のドローイングから55点を選んで個展を行なった。ドローイングといっても画風はタブローと大差がなく、支持体がキャンバスか紙かの違い程度である。ただし、これらの作品はもともと発表を想定しておらず、その分トライアルの痕跡が生々しく残っている。ドットが浮かぶ作品、水平線が何本も並ぶ作品、少ない線で構造物のような形を描いた作品などがあり、時々の関心の変遷と、完成に至る道のりがつぶさにうかがい知れた。絵画作品は最後の表面しか見えないので、制作過程を読み取るのが難しい。時々このようなドローイング展を行なってくれると、観客としては大変助かる。
2013/03/12(火)(小吹隆文)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)