artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
京芸Transmit Program#1 「きょう・せい」展第二期

会期:2010/05/01~2010/05/30
京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]
京都市立芸術大学のギャラリーのオープニング企画、第二期。芦田尚美、今村遼佑、岡田真希人、西上翔平、東明、藤井良子、前川紘士、水田寛、芳木麻里絵ら9名の作品を紹介する。会場は、混とんとしたイメージの第一期展とは異なる作家ごとの個別展示。映像インスタレーション、陶芸、染織、絵画など、作品形態はさまざまだが、素材や技法にも注目したい作家が多く、奇異をてらわないシンプルな展示はとても良かった。この日は『ジャパンタイムズ』学芸部記者イーデン・コーキル氏をゲストに招いたアーティスト・トークも開催。コーキル氏からは、日本のアートシーンを海外に発信する立場から見た京都と東京の違いや、伝統や歴史的文化といった、表現の背景にあるその土地独自の文脈、それを伝える難しさなどが語られた。さらに興味深かったのはカンボジアやラオスなどアジアの国々の美術と教育を例に挙げての、伝統技術と芸大の教育のあり方とその現状、実際のアートマーケットと作家自身の関係性へのアプローチ。議論に発展するほどには至らなかったが、伝統産業や工芸との関わりの深い京都で、表現活動に関わる者にとってはたいへん有意義な内容だったと思う。
2010/05/02(日)(酒井千穂)
向井潤吉 展
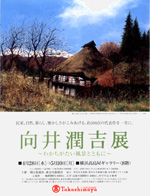
会期:2010/04/28~2010/05/10
横浜高島屋ギャラリー[神奈川県]
向井潤吉といえば、日本の茅葺き民家を描き続けた洋画家。なぜそんなもんを見に行ったかというと、ひとつはすぐれた戦争記録画を描いたから。もうひとつは、油絵でどこまで日本的農村風景に迫れるかということに関心があったから。戦争記録画はもっとも有名な、というよりこれ以外知らないのだが、中国・蘇州の街並に落とす軍用機の大きな影を描いた《影》のみの展示。広い意味では、掘削機を銃のように構えた《坑底の人々》や《献木伐採》も戦争記録画に入るかもしれない。そのほか民家以前では、パリ時代にルーヴル美術館に通って描いたデューラー、コロー、ルノワールらの模写と、同時期に制作したスーティンばりの表現主義的絵画との落差が興味深かった。民家は早くも敗戦の年から描かれ、以後93歳で亡くなるまで半世紀近く続く。同展では水彩画も含め約130点の出品作品のうち、およそ100点が民家の絵で占められていて、最後のほうはうんざりするほど。途中1959~60年に渡欧するが、そのときの風景画と比べてみると、日本の農村風景は圧倒的に土色とくすんだ緑色が多く、赤や深い青がきわめて少ないことがわかる。せっかく油絵具を用いながら原色をそのまま使用する機会が少ないのだ。これは向井に限ったことではなく、日本の油絵の特徴といえるかもしれない。
2010/04/30(金)(村田真)
トーキョーストーリー
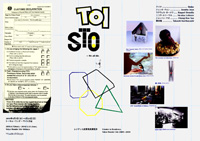
会期:2010/04/07~2010/05/23
トーキョーワンダーサイト渋谷[東京都]
TWS青山のクリエーター・イン・レジデンスに滞在していた6人のアーティストによる作品発表。これがとてもおもしろかった。アバケ(アーティスト名)はホームレスの小屋を建てたり、オリーブの葉をくわえたハトをデザインしたピースと弓矢をデザインしたホープを対峙させたり、ニコラ・ルリーヴルは仮設壁の裏の狭い空間に《細い路地》をインスタレーションしたり、栗林隆は屋台をつくったり、みんなストリート系なのだ。ストリート系をレジデンスさせるとは、都もイキなはからいをしたものだ(知事は知ってるのか?)。唯一オブジェ系のチョン・ジュンホは、木で彫った頭蓋骨を金のバラの花で囲むという秀作を出品。ついでに「ナイキ化」で揺れる宮下公園に行って、アバケの野外作品を鑑賞。充実した展示であった。
2010/04/30(金)(村田真)
阿蘭陀とNIPPON
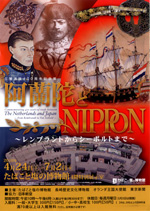
会期:2010/04/24~2010/07/02
たばこと塩の博物館[東京都]
日蘭通商400周年記念展。400年といっても展示の中心はもちろん、オランダが日本と唯一通商を許された江戸時代の約250年に絞られてくる。この間、出島という針の穴のような窓口を通して伝わってくる西洋の文明文化が、いかに誤解されたり拡大解釈されたりしながら日本に根づいていくかが見どころとなる。その観点から見れば、本展には出てないけれど、レンブラントの解剖図と杉田玄白らの『解体新書』が、フェルメールの風俗画と《彦根屏風》をはじめとする室内遊楽図が接点を持ち始めるのだ。ま、ぼくの興味は17世紀オランダ絵画と日本美術の接点だけですけどね。
2010/04/30(金)(村田真)
磯崎新+新保淳乃+阿部真弓『磯崎新の建築・美術をめぐる10の事件簿』

発行所:TOTO出版
発行日:2010年2月25日
これは二人の美術史家、新保淳乃、阿部真弓が、磯崎新にインタビューを行ない、美術と建築を横断しながら語る形式の本である。第一章は15世紀のルネサンスから始まり、一世紀ごとに各章が進み、第六章からは1900~10年代となり、20年ごとに進行し、ラストは1980~90年代を扱う。かつて磯崎は『空間の行間』において福田和也と日本建築史と文学を交差させて討議していたが、今回は建築と美術のクロストークだ。1968年のミラノトリエンナーレの占拠など、いろいろなところで語られるおなじみのエピソードも多いが、美術の文脈から引き出しをあけているために、異なる角度から読む楽しみがある。本書は漫然と歴史を振り返るわけではない。もうひとつのテーマはイタリアである。本書のもとになっているのが、イタリアの建築雑誌『CASABELLA』の日本版を作成するにあたって企画された連載だったからだ。膨大な固有名詞が吐き出され、めくるめく知的な会話が展開する。読者がある程度の西洋建築史や美術史の素養をもっていなければ、知らない言葉の森のなかで途方に暮れるだろう。近年の建築論は身のまわりや現在の問題ばかりに焦点をあてる傾向が強いが、本書は時代と場所のスケール感が圧倒的に大きい。例えば、第三章の17世紀では、パトロンの問題を語っているが、バロックに限定せず、現代の状況についても触れている。もっとも、ここで語られていることくらい、普通に読まれるリテラシーが建築界や学生にも備わっていて欲しいのだが、現状は厳しそうだ。
2010/04/30(金)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)