artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
堀田真悠『新月』
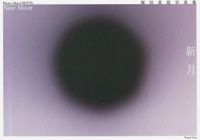
発行所:東京ビジュアルアーツ/名古屋ビジュアルアーツ/ビジュアルアーツ専門学校・大阪/九州ビジュアルアーツ
発行日:2013年11月20日
2013年度の第11回ビジュアルアーツアワードを「新月」で受賞した堀田真悠は1992年、京都生まれの20歳(受賞当時)。同賞の最年少受賞者ということになる。だが、その作品世界の完成度の高さは恐るべきもので、写真を取りまく現在のハード及びソフトの環境を的確に使いこなせば、高度な表現力を年齢にはまったく関係なく発揮できることがよくわかる。
「新月」というタイトルが示すように、彼女が引き寄せられていくのは「見えない闇」の世界である。そこには普通の視力では「見えない」けれども、確実に何かがうごめいていて、時には魅惑的な、時には禍々しく不吉な世界を垣間見させる。堀田はそれらを的確にカメラで捕獲していくのだが、プリントして作品化する時にさらに操作を加えることが多い。彼女をビジュアルアーツ専門学校・大阪で指導した百々俊二によれば、「マットブラックインクを光沢紙で使用することで暗部のテクスチャーは浮きあがり反転したミスマッチで出来たプリント」なのだと言う。撮影・プリントの機材のデジタル化によって、これまでとは違った多様な表現の可能性が生じてきているわけで、堀田のような世代は、それらをごくナチュラルなプロセスとして身につけることができるのではないだろうか。
もうひとつ興味深いのは、彼女の作品全体に貫かれている、琳派を思わせる華麗で装飾的な画面構成である。この奇妙にクラシックな美学は、やはり彼女が「京都と奈良の県境の田園地帯に育った」という風土性に由来するのだろうか。
2013/12/04(水)(飯沢耕太郎)
茂木綾子『travelling tree』

発行所:赤々舎
発行日:2013年10月1日
茂木綾子は東京藝術大学美術学部デザイン科を中退後、1997年に渡独し、映画作家、アーティストのヴェルナー・ペンツェルというパートナーと、二人の子どもを得た。スイスのラ・コルビエールでアーティスト・イン・レジデンスなどの活動をした後、2009年に帰国し、淡路島の廃校になった小学校に住みついて「ノマド村」の活動を展開している。本作はその茂木がヨーロッパ滞在中に撮影した写真をまとめた写真集である。
写っているのは、夫との日々の暮らしの断片、二人の子どもの成長の記録、旅と移動の合間に出会った風景など、文字通りの「個人的な写真」である。にもかかわらず、写真集のページを繰っていると、そこにはまぎれもなく優れた写真家の眼差しが介在していると思えてくる。茂木は「あとがき」にあたる文章で、「なぜ私はこのような写真を撮り続けてきたのか」と自問自答し、その答えとしてそれが「不可解さ」に促されて成立していたのではないかと思い至る。「不可解さ」というのは「自分と自分が含まれるこの世界を満たす有形無形の数限りない出来事のなかで、ふと気になる象徴的で謎めいた物事」のことだと言う。
確かに彼女の写真には、そんな「象徴的で謎めいた出来事」が写り込んでいるものが多い。写真集の表紙にも使われている、窓際の壁にピン止めされた「燃える靴下」の写真もその1枚である。だがそれらのなかには、わかりやすいドラマチックな出来事ではなく、ごく些細な身じろぎ。微かな気配としてしか感じられないものもある。むしろそちらの方が圧倒的に多いだろう。茂木が世界に向けて差し出すアンテナの精度は、12年にわたるヨーロッパでの生活のなかで、少しずつ、だが着実に上がっていったのではないだろうか。その成果が、「不可解さ」の写真の連鎖として目に飛び込んでくるのだ。
2013/12/02(月)(飯沢耕太郎)
植田正治とジャック・アンリ・ラルティーグ ─写真であそぶ─

会期:2013/11/23~2014/01/26
東京都写真美術館 3階展示室[東京都]
東京都写真美術館の「植田正治とジャック・アンリ・ラルティーグ」展は、日本とフランス、ともに20世紀を撮影した写真家である。が、前者は計算された構成的な写真によってシュールな作品をつくり、後者はまさに動きの瞬間を撮るという意味で、二人の手法は対照的だ。ちなみに、ジャックの撮影した年齢をみると、10歳頃からの写真が展示されており、20世紀初頭という時期を考えると、これは相当に裕福な家でないと不可能だと思う。
2013/12/01(日)(五十嵐太郎)
生誕100年記念 ロベール・ドアノー写真展

会期:2013/11/22~2014/01/26
秋田市立千秋美術館[秋田県]
アトリオン内の秋田市立千秋美術館のロベール・ドアノー写真展へ。ドイツ占領時のパリのレジスタンスの活動を撮影した写真は歴史的にも貴重だ。基本的には何気ないパリの日常的な風景(人と街)だが、誰かが何かを見ている状態をとらえた写真が幾つかあって興味深い。カラー写真も初公開されていた。千秋美術館には、岡田謙三1950'sも同時開催しており、彼がニューヨークに渡って、当時流行っていた抽象表現主義の影響を受け、作風を変えた頃の作品を紹介する。ただ、やはり日本的な色使いを感じた。
2013/11/27(水)(五十嵐太郎)
上本ひとし「海域」

会期:2013/11/20~2013/12/03
銀座ニコンサロン[東京都]
上本ひとしは1953年、山口県下松生まれの写真家。靴の販売店を営みながら、1970年代から写真撮影を続けてきたが、2001年にニッコールフォトコンテストでニッコール大賞、長岡賞を受賞したのをひとつのきっかけとして、本格的に写真作家としての活動を開始した。以後、写真集『峠越え』(2005年、翌年さがみはら写真新人奨励賞を受賞)、『OIL 2006』(2007)を刊行するなど、旺盛な創作意欲で力作を発表し続けている。
今回発表された「海域」は山口県徳山湾の沖合にある大津島の周辺を撮影したシリーズである。大津島、及びその近くの光、平生には、太平洋戦争末期に「人間魚雷」回天の基地があり、若い兵士たちが訓練にいそしんでいた。回天は操作が難しく、訓練中に死亡する兵士も多かったという。上本はそのような史実を踏まえながらも、あくまでも現在の瀬戸内海の「海域」の眺めを、しっかりと写しとろうと努めた。その結果として、回天の乗組員たちも日々目にしていたであろう「海の色、島影」は、静かな緊張感をたたえた「風景写真」として、きちんと成立していると思う。薄暮の時間に撮影された写真が多いこともあって、会場全体に、遥か彼方へと連れ去られてしまうような寄る辺のなさ、茫漠とした雰囲気が漂っていた。写真を見ながら、「海くれて鴨の声ほのかに白し」という芭蕉の句を思い起こしていた。
なお、本展は2013年12月19日~28日に大阪ニコンサロンに巡回する。また、展覧会にあわせて蒼穹舍から同名の写真集も刊行されている。
2013/11/27(水)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)