artscapeレビュー
2019年09月01日号のレビュー/プレビュー
永遠の門 ゴッホの見た未来

盛り上げようと思えばいくらでもドラマチックに盛り上げられるはずのゴッホの生涯を、あくまで画家の立場から、画家自身の目で粛々と捉えた主観映画。ここでいう画家とはもちろんゴッホのことだが、監督ジュリアン・シュナーベルのことでもある。シュナーベルが80年代に新表現主義の画家として一世を風靡したことは知られているが、盟友ともいうべき早逝の画家を撮った「バスキア」をはじめ、映画監督を始めてからもつねに画家の立場、画家としての視線を忘れていない。この映画でもゴッホと自分を、表現主義の先駆者とその末裔として重ね合わせている。
ゴッホを演じるのは怪優ウィレム・デフォー。名前からするとオランダ系なので、それでゴッホ役に選ばれたのかと思ったら、ただのアメリカ人だそうだ(笑)。対するゴーガン役のオスカー・アイザックは、顔が似ているだけでなく、いかにも傲岸そうなふてぶてしさをよく出している。それにしてもゴッホより5歳上のゴーガンを、デフォーより2回りも年下の役者が演じているのに違和感を感じさせないのは、両者の名演ゆえだろう。
カメラは手持ちで画家を追い、またしばしば画家の目線で撮られるので、激しく揺れる。見にくいといえば見にくいが、それが観客をゴッホの揺れ動く不安な精神状態に導く。そして最期のシーン。ゴッホの死因はピストル自殺が定説だが、シュナーベルは悪童たちによる暴発説に従った。自殺のほうがいかにも悲劇的で「泣ける」のに、ここではあえてあっけない事故死を採用したのだ。シュナーベルがやろうとしたのは、ゴッホの生涯に感動させることではなく、ゴッホの内側に入って画家の生と死を追体験させることだった。いってみれば、観客をゴッホにする試みなのだ。だからツライ。終わった後、涙が流れて仕方なかった。
公式サイト: https://gaga.ne.jp/gogh/
2019/08/05(月)(村田真)
江成常夫 写真展「『被爆』ヒロシマ・ナガサキ」

会期:2019/07/23~2019/08/19
ニコンプラザ新宿 THE GALLERY[東京都]
「ヒロシマ・ナガサキ」は多くの写真家たちによって撮影されてきた。土門拳の『ヒロシマ』(研光社、1958)のように記憶に食い込んでいる作品も多いし、江成常夫が今回展示した、広島や長崎の原爆資料館に保存されている被爆者の遺品や放射線を浴びた遺物も、東松照明、土田ヒロミ、石内都らが撮影している。その意味では、使い古されたテーマといえなくもないが、江成がここ10年あまり撮影し続けてきた写真群を集成した展示を見ると、その凄みに震撼させられる。
椹木野衣は、本展にあわせて刊行された写真集『被爆 ヒロシマ・ナガサキ いのちの証』(小学館)に寄せたテキスト「十字架の露光=被爆=暴露(エクスポージャ)──江成常夫のヒロシマ、ナガサキ」で、江成の写真の「触覚的」な特質について述べている。そこには、対象との距離が「ゼロ」になるような「触覚的な危機」の体験が、「いのちの証」として刻みつけられているというのだ。これまで原爆遺品、遺物の写真の多くはモノクロームで撮影されてきた。そこでは被写体が象徴的なイコンとして捉えられている。石内都の『ひろしま』(集英社、2008)はカラーで撮影されているが、彼女は遺品を宙を舞うようなあえかなイメージとして提示した。江成は、遺品、遺物にぎりぎりまで接近し、精密なカラー写真によってその物質性を「暴露」しようとする。その愚直ともいうべき撮影の仕方と、各写真に付された詳細な解説によって、われわれはまさに1945年8月6日と9日の、爆心地の地上で3000〜4000度、爆風の最大風速400メートル毎秒という恐るべきエネルギーの場に直面させられるのだ。なお、本展は8月29日〜9月11日にニコンプラザ大阪 THE GALLERYに巡回する。
2019/08/05(月)(飯沢耕太郎)
新鋭作家展 あ、これ、ウチのことです。

会期:2019/07/13~2019/08/25
川口市立アートギャラリー・アトリア[埼玉県]
いちおう審査に関わったので内輪ネタになります。今回8回目を迎えた公募展だが、ただ作品を見て合否を判断するのではなく、1次審査で作品プランを検討し、2次審査で面接して2人に絞る。ここまではよくあるが、同展は地域性を重視するため、1年近く学芸員と相談しつつ現地を取材したり、住人たちと交わったりしながら作品を制作し、発表してもらうという大河ドラマのような流れなのだ。
今回選ばれたのは、蓮沼昌宏と上坂直の2人。パラパラマンガを手回しで見る装置「キノーラ」で知られる蓮沼は、ギャラリーに隣接する団地に住むおもに海外からの移住者に話を聞き、それをパラパラマンガに描き起こしてキノーラで見られるようにした。テーブルと椅子が年季が入っていると思ったら、閉店した団地内のレストランから運び込んだものだという。
美大で建築を学んだ上坂は、プラスチックの衣装ケースを何十個も積み上げて3棟の高層団地に見立て、引き出しのなかにミニチュアの靴や雑貨を置いたり、磨りガラスの奥で人影を動かしたりして部屋のように仕立てている。なんとなく団地の室内をのぞき見る感じ。動く人影も団地の住人の協力を得て撮影したものだそうだ。そんなわけで2人展のタイトルは「あ、これ、ウチのことです」。願わくば、団地の人たちがもっと見に来るように。
2019/08/07(水)(村田真)
木藤富士夫 写真展「公園遊具 playground equipment」

会期:2019/08/07~2019/08/20
銀座ニコンサロン[東京都]
木藤富士夫は1976年、神奈川県生まれ。2005年に日本写真芸術専門学校を卒業後、フリーランスの写真家として活動し始めた。2006年からずっと撮影しているのが、各地の公園に設置されているコンクリート製の遊具である。タコや象の形の滑り台をよく見かけるが、木藤が今回発表した47点の作品を見ると、実に多様な種類があることに驚かされる。電話機、ロボット、魚の骨、巻貝、さらに鬼やガリバーまで、ありとあらゆる造形のオンパレードだ。むろん、子どもの興味を惹きつけるためのデザインなのだが、むしろ作り手の無意識の願望が形をとったような不気味さがある。
木藤の興味も、その百花繚乱のイマジネーションの乱舞に向けられているのではないだろうか。それを強調するために、彼は撮影の仕方にも工夫を凝らしている。撮影は夜におこなわれ、遊具を浮かび上がらせるために数100発から数1000発のストロボを発光させて、その輪郭や細部の質感をくっきりと浮かび上がらせる。最終的にそれらの画像を合成して、一枚のプリントとして完成させていく。結果的に、現実感と非現実感との両方を醸し出す、不思議な手触り感を備えた作品が成立してきた。デジタル化によって、これまでは撮影がむずかしかった状況をリアルに捉えることができるようになったが、本作もその成果のひとつといえそうだ。作品数はすでに200点近くになっているという。木藤はこれまで、8冊の小写真集を自費出版してきたが、そろそろ一冊にまとめる時期がきているのではないだろうか。
2019/08/07(水)(飯沢耕太郎)
原田治展 「かわいい」の発見

会期:2019/07/13~2019/09/23
世田谷文学館[東京都]
中学生のころ、ご多分に洩れず、私も持っていたなぁ。と、思わず懐かしい気持ちに駆られた「OSAMU GOODS(オサムグッズ)」。ミスタードーナツの景品に至っては、オサムグッズ欲しさに、私はドーナツを購入した口である。しかし本展を観て、原田治のイラストレーションの実力はそれだけに留まらないことを痛感した。1970〜1980年代の初期の仕事を見ると、特に雑誌の表紙や挿絵では、同じ人が描いたとは思えないほど、実に多彩なタッチのイラストレーションを描いていたからだ。もともと、米国のコミックやTVアニメ、ポップアートなどから影響を受けたという面も頷けるし、表現力の幅が広い器用なイラストレーターだったのだろう。
とはいえ、それだけでは一世を風靡するイラストレーターにはなれない。原田はその後すぐに「かわいい」という要素を武器に、大きく舵を切っていく。その理由とでもいうべき、原田の言葉がとても印象的だ。「イラストレーションが愛されるためには、どこか普遍的な要素、だれでもがわかり、共有することができうる感情を主体にすることです」。それが「かわいい」だったのだ。しかもそれは巧妙に計算し尽くされた「かわいい」だった。「終始一貫してぼくが考えた『可愛い』の表現方法は、明るく、屈託が無く、健康的な表情であること。そこに5%ほどの淋しさや切なさを隠し味のように加味するというものでした」。ちょっと驚いたような表情や考えるような表情、眠い表情などを浮かべるオサムグッズの少年少女、動物たちには、そんな仕掛けがあったのだ。
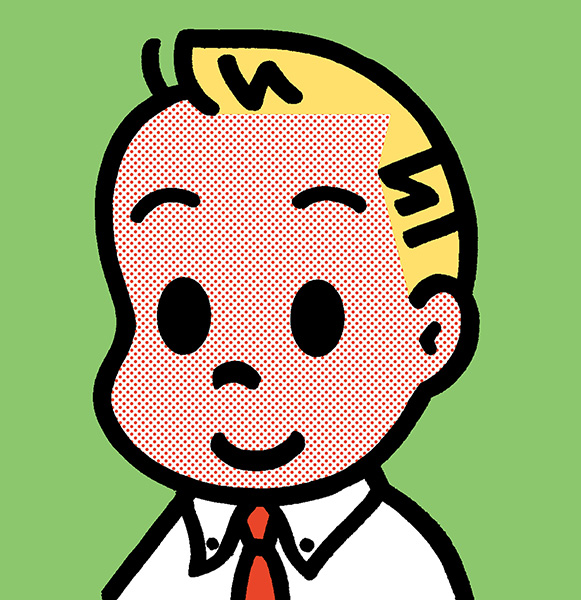 © Osamu Harada / Koji Honpo
© Osamu Harada / Koji Honpo
1970〜1980年代は、グラフィックデザイン業界においてイラストレーション全盛の時代でもあった。原田とも親交があった安西水丸やペーター佐藤をはじめ、田名網敬一、横尾忠則、宇野亜喜良、大橋歩らが活躍した。彼らのなかでも、原田は特にビジネス的に成功したイラストレーターと言える。例えばカルビー「ポテトチップス」のキャラクター、日立「ルームエアコン 白くまくん」のキャラクター、ECCジュニアのキャラクター、東急電鉄の注意喚起ドアステッカー、崎陽軒「シウマイ」の醤油入れ(ひょうちゃん)など、企業広告や各種グッズの展示を観て、あれもこれも、原田の仕事だったことを思い知らされる。「かわいい」は子どもや女子中高生だけが感受する要素ではない。大人も心惹かれ、共感しうる要素であることを改めて実感した。
 会場風景 世田谷文学館
会場風景 世田谷文学館
 会場風景 世田谷文学館
会場風景 世田谷文学館
公式サイト:https://www.setabun.or.jp/exhibition/exhibition.html
2019/08/08(杉江あこ)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)