artscapeレビュー
2020年03月15日号のレビュー/プレビュー
シャンカル・ヴェンカテーシュワラン『インディアン・ロープ・トリック』
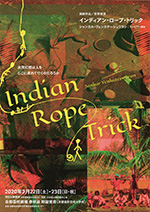
会期:2020/02/22~2020/02/23
京都芸術劇場 春秋座[京都府]
観客が集合的に物語を共有する=共同幻想を生み出す場としての「劇場」に身を置きつつ、「演劇」に対する自己批評をどのように社会批判へと眼差し返すか。繰り返し語られる物語が反復によって強度を増し、「真実」へと接近するプロセスそれ自体を俎上に乗せて冷静に分析することで、劇場、そしてそこに集う観客を没入から覚醒へと反転させることはいかに可能か。KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMNでの『水の駅』(2016)、『犯罪部族法』(2019)と京都での発表を積み重ねてきたインドの演出家、シャンカル・ヴェンカテーシュワランは、本作においても、インドの歴史と現代社会への鋭い眼差しから、極めてクリティカルな問いを立ち上げていた。
舞台上には、広場のように円形の客席が組まれている。観客が席につき始めると、出演者たちはその周囲をぐるぐると歩き回りながら、市場の物売りのような独特のかけ声を発し続ける。音楽的な抑揚をもったその声の重なり合いは、耳に心地よく響く。「市場の広場」の中央に姿を現わした彼らは、担いでいたトランクからさまざまなエキゾチックな品物──楽器、絨毯、蛇の置物、香辛料の小袋などを取り出し、驚くべき効能を謳う口上を述べながら、観客に売りつけようとする(実際に観客のひとりが、「値切り交渉」とともに香辛料を「買わされる」やり取りは、「フィクション」が第四の壁を突き破って「現実」の只中へと侵入してくる事態を序章として突きつけ、示唆的だ)。

[撮影:守屋友樹 主催・写真提供:京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター]
やがて円形広場では、魔術師によるロープを使った見世物についての語りが始まる。魔術師がロープを空高く投げると、ロープは直立し、助手の少年がロープを登って姿を消す。いつまでたっても戻ってこない助手に業を煮やした魔術師は、口にナイフを咥えてロープを登り、その姿も見えなくなる。突如、観客の頭上から少年の悲鳴が聞こえ、バラバラになった手足が降ってくる。ロープから降りた魔術師が魔法をかけると、少年の身体は元通りになって生き返った、という。
本作の前半では、この「インディアン・ロープ・トリック」が、さまざまな時代と主体によって繰り返し語られてきたことが、出演者たちによる「再現」とともにバリエーションとして反復される。14世紀のモロッコ人イブン・バットゥータによる旅行記など、歴史的文献に記された叙述の数々。19世紀になると、欧米人がこの物語の語り手の列に加わる。新聞の発行部数を伸ばすために「フェイクニュース」を紙面に載せた米紙。賞金目的でトリック成功に挑んだ英国人興行師たち。ありえない荒唐無稽な物語が、繰り返し語られる(とりわけ「権威」の担い手によって)ことで、フィクションが事実化していくプロセス自体が提示されていく(一方で、「権威を持たない」と見なされる語り手が語るときは、「嘘」「捏造」として徹底的に攻撃・否定される。「インドでこのトリックを目撃した」と言う女性の証言者が、男性が独占する権威的組織によって異端視され、魔女狩りとして排除されたエピソードがその例だ)。
「物語」の再生産が、ナショナリズムや排他的な社会構造と共犯関係を結び強化する回路について示す例が、前半のラストで語られる「犯罪部族法」である。インド植民地政府が1871年に制定したこの法律は、カースト制度という既存の社会構造を植民地支配の円滑化のために政治的に利用し、「カースト外」に置かれた不可触民のコミュニティを「犯罪部族」に指定し、非定住生活を送っていた彼らを強制的に定住・拘留下に置く差別的な法律だった。「魔術師たちは祈祷師や小商人に転向した。トリックを死守した者は、最後の抵抗として、ロープを登って自ら姿を消した」という語りは、西欧近代が「迷信」を駆逐しつつ、共同幻想によって社会秩序の維持に加担し「現実」を形づくることについてメタフォリカルに指し示す。それは何も、カースト制度だけにとどまらない。フェイクニュース、歴史修正主義者の語る「正しい歴史」、社会的構築物としてのジェンダーに至るまで、私たちの日常を取り巻く常態だ。
また、出演者たちは、「インディアン・ロープ・トリック」の目撃談を語るたびに「再現」を試みるのだが、投げたロープは無様に床に落下し、「吊り具」が堂々と天井から降下し、あるいはトリックが「成功」しても「生き返ったフリ」にすぎず、共同幻想に没入させる装置としての「演劇」「劇場」に対するメタ批判が同時並列的に示される。伝統楽器をリズミカルに操るミュージシャンの生演奏と歌の力も借りて、「京都の劇場」が「インドの市場」へ、「劇場の観客」が「魔術の見物人」へと転位し、演劇の起源の姿がそこに立ち現われる。一方、演じるたびに魔術師と助手の役を交換する仕掛けや流動性は、アイデンティティを固定化しようとする力に絶えず抗い続け、攪拌しようとする抵抗でもある。

[撮影:守屋友樹 主催・写真提供:京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター]
後半では、すでに聞き慣れた「インディアン・ロープ・トリック」の物語に、新しい別の要素が混ぜられて変容する。それは、「井戸を掘るために必要な製鉄技術を得るために、その知識を独占している共同体へ弟子を遣わし、教えを乞う」という、南インドの口承叙事詩に基づくものだ。1)共同体間の対立や排除という要素、2)ロープを投げて上空へ登るのではなく、「井戸を掘って地下深くへ降りていく」という上下のベクトルの反転によって、定型を逸脱・変容させた新バージョンが新しく作り上げられる。出演者たちの頭上から降りてくるのは、「ロープ」と「金属」が合体した「金属のチェーン」だ。彼らは互いの肩や腰を足場にして、「金属のチェーン」をよじ登って姿を消そうと何度もトライするが、ことごとく落下して「失敗」に終わる。ラストシーンでは、1人目の肩に上った2人目の肩をさらに足場にして3人目がよじ登り、「暗転」を迎える。それが一瞬であったなら、「演劇の約束事」として、「暗転=消失」すなわち「トリックの成功」と了解されただろう。だが、その意図的な暗転の「長さ」は、演劇の了解事項を逆手に取って、見る者に不穏な問いを突きつける。「あなたは、『暗転=消えた』と信じますか?」「これは『トリックの成功』であると思いますか?」。

[撮影:守屋友樹 主催・写真提供:京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター]
観客が物語に没入し、共同幻想に浸る演劇空間においては、観客一人ひとりは「私と物語」の閉じた関係性の内に分断されている。一方、本作のラストは、「この新しく変容させた物語を、あなたは信じますか」という問いを、観客一人ひとりに反省的に投げかける。
「円形舞台」の構造も重要だ。舞台と客席を明確に分離して正対させる一般的なプロセニアム式舞台の場合、ほかの観客は意識から消え、「物語とそれを享受する私」の閉鎖系が形成される。しかし、本作の円形舞台の場合、向かい合ったほかの観客の姿が絶えず視界にあるため、自身もまた「観客(のひとり)」であることをつねに自覚しながらの観劇体験となる。共同幻想への没入(と分断)から、人々が同じ場に集いつつも個々が反省的に思考する場へ。「垂直に立つロープ=秩序の構築」/「地下に降りる井戸=不可視化されてきた領域の開示」のように、「劇場」の機能もまた反転させられる。劇場・演劇への自己批判を展開しつつ、それでもなお演劇の力を信じるヴェンカテーシュワランの、強い信念がロジカルな強度とともに差し出された作品だった。
公式サイト:http://k-pac.org/?p=8888/
関連レビュー
シャンカル・ヴェンカテーシュワラン『犯罪部族法』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年01月15日号)
2020/02/23(日)(高嶋慈)
村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』

会期:2020/02/22~2020/02/24
パピオビールーム大練習室[福岡県]
ドキュメンタリーやフィールドワークの手法を演劇に持ち込み、「コミュニケーション(とその断絶)」「再現性と不確定性」「不在と想起」「演劇(本物らしさ)と認知」「モノローグ/ダイアローグ」といった面から演劇を鋭く照射/解体してきた演出家、村川拓也。出世作となった『ツァイトゲーバー』(2011)は、その日の観客から募った「被介助者」役を舞台に上げ、本職の介助者が普段行なっている障害者介助の様子を「再現」する作品である。KYOTO EXPERIMENT 2017で上演された『インディペンデント リビング』(2017)では、この形式を踏襲しつつ、日本、中国、韓国の3カ国からそれぞれ参加した3人の介助者が、順番に普段の介助労働を再現し、介助という営みの普遍性と、言葉の端からわずかに感知される個別的な生のありようが提示された。
本作『Pamilya』も、『ツァイトゲーバー』→『インディペンデント リビング』の系列に位置づけられる作品である。だが、「観客のひとりを被介護者に見立て、本職の介護士が介護を再現する」という枠組みは共通するものの、1)個人の「家」ではなく介護施設が舞台であること、2)ALS(筋萎縮性側索硬化症)など重度身体障害者の介助ではなく認知症の高齢者の介護であること、3)日本で働く「外国人介護士」が登場すること、4)「現在の再現」ではなく時間軸の推移を含むこと、5)介護士が自身の人生や被介護者への想いを語ること、といった複数の要素が加わることで、かなり異なる印象を受け、より作品の枠組みが広がったと感じた。先取りすればそれは、「1日の介護のダイジェスト」の背後に幾重にも積み重なった時間的レイヤーの層──介護士と介護される高齢者、2人の女性それぞれの人生に流れた時間、現在の介護労働者の供給地/かつての侵略地域──を通して、「家族」「介護労働の担い手(専門労働者/家庭内労働者)」について問い、その先に「観客の眼差しこそが舞台上に(不在の)存在を現前させている」という演劇の原理を浮かび上がらせていた。

[撮影:富永亜紀子]
冒頭、(『ツァイトゲーバー』『インディペンデント リビング』と同様に)村川が舞台に上がり、この作品には「フィリピンから来た外国人介護士のジェッサさん」が登場すること、彼女が介護を担当した「エトウさん」という女性の役を女性の観客の希望者に担ってほしいことを告げる(なお、上記2作品とは異なり、被介護者役の観客には「3つの願い事」を好きなタイミングで発話するタスクは課せられていない。私の観劇回では、50代くらいの中年女性が「エトウさん」役を担った)。
ベッドと椅子が置かれただけの簡素な舞台上に、リュックを背負って自転車を押した若い女性が現われる。彼女はゆっくりと舞台を一周し、キーロックの解除、ドアを開ける、ロッカーの扉を開けるといった動作をマイムで、靴の履き替えと着替えは実際に行なう。「おはようございます」というほかの職員への挨拶。ベッドに横たわる「エトウさん」に近づき、「よく眠ったばい?」と九州弁で声をかける彼女。通勤と着替えの準備から始まり、「介護施設での1日の労働」が淡々と再現されていく。ベッドから車椅子への移動、洗顔と身支度、朝ごはんの配膳と介助。入浴。ラジオ体操と、レクリエーションのカラオケタイム。夕食、再びベッドへの移動。そして退勤。「エトウさん」役の観客は、ベッドや椅子に身体を預けたまま、基本的にほぼ無表情で無反応だ。

[撮影:富永亜紀子]
彼女は介助の傍ら、そんな「エトウさん」にずっと声をかけ続ける。「手で食べないで。もうべちゃべちゃ」「自分で食べた方がおいしいよね」、「昨日、娘さんが来たと。良かったね」、「(車椅子に身体を固定する)ベルト外すね。ごめんね、嫌いやね」……。時にぶっきらぼうな口調のなかに、「他人」「お客様」ではない、自身の家族に接するような親密で温かい距離感がにじみ出る。その理由は、介護場面の合間に挿入される、ジェッサ自身のタガログ語による語りによって徐々に明かされていく。
約3年前にフィリピンから二国間EPA(経済連携協定)介護福祉士候補生として来日したこと。「エトウさん」の力強い目に惹かれたこと。噛みついたり手を叩こうとする彼女が、闘おうとしているのだとわかったこと。フィリピンではすべての家に水道があるわけではなく、お風呂の習慣もなく、水辺や雨水で身体を洗うこと。子ども時代に可愛がってくれた祖母が倒れたが、日本で働いているため、世話もできない自分への自責の念。長期休暇のあいだに「エトウさん」が亡くなり、祖母と同じく最期を看取れなかったことへの後悔。最後に会った頃の「エトウさん」は衰弱が激しく、手を差し伸べても叩こうとしなかったこと。
「エトウさん」に自身の祖母を重ねるジェッサの言葉は、だが、至近距離にもかかわらず「マイク」を介して発せられる。一見するとそれは、距離感やコミュニケーションの不成立を強調する「断絶の装置」として残酷に映る(『ツァイトゲーバー』『インディペンデント リビング』においても、介助者は「マイク」を介して被介助者に語りかける)。だが本作で興味深いのは、「施設内のほかの被介護者や職員に話しかける(フリで発話する)際には、マイクを使用しない」というルールである。「エトウさん」に話しかけるときにだけマイクを使用するという対比性が際立つことで、「こんなに近いのに声が届かないが、それでもいま目の前にいる「あなた」に語りかけている」という、断絶ではなく声を届ける装置として「マイク」の役割が肯定的に反転して感じられた。

[撮影:富永亜紀子]
コミュニケーションへの切実な希求は、「エトウさん、私の手を叩いて」という何度も反復される言葉で示される。祖母と「エトウさん」の重なり合い、そしてジェッサ自身の人生と「エトウさん」の人生が重なり合うのが、中盤のカラオケタイムでジェッサが歌う歌謡曲「瀬戸の花嫁」だ。生まれ故郷の島と家族から離れ、海を渡って別の島に嫁ぐ花嫁の心境を歌うこの曲の歌詞に、労働者としてフィリピンから日本へ渡ったジェッサと、おそらく実家を離れて嫁入りしたであろう「エトウさん」の人生が重なる。だが「花嫁/労働者」というズレは、「家族と介護労働の担い手」という問題を浮かび上がらせる。作品タイトルの「Pamilya(パミリヤ)」はタガログ語で「家族」を意味するが、ジェッサ自身の家族についての私的な語りは、より広い社会的文脈へと接続される。家庭内労働者としての「嫁(女性)」が担っていた仕事を、海外からの専門労働者が担うこと。さらに、その労働力の供給源がかつて侵略した被占領地域であることは、日本の近現代という、より長い時間的スパンを射程に含む。
最後に、「観客のひとりが被介護者の役を担う」仕掛けが内包する、複数の役割について考えたい。1)まずそれは、(プロの俳優が登場するのとは異なり)、舞台を見る観客自身の身体と舞台上で起きていることを地続きに連続させる。2)リハーサルも準備もなく舞台に上げられた素人が見せる、どう振る舞ってよいか戸惑う表情の硬さや緊張した無表情は、本人の意志表示やそれを表情から読み取ることが困難なALS患者や認知症の高齢者に接近し、「コミュニケーション」の問題を浮上させる。3)(プロの俳優ではない)介護士の振る舞い方に影響するであろう、「被介護者役をどんな人が引き受けるのか」という最重要素を本番開始までブラックボックスにしておき、演出家のコントロール不可能な状態に置くことで、「いま目の前で起きている事態」のリアリティの度合いが最大限になる。「日々繰り返される労働現場の再現」だが、上演のたびに「被介護者役」とその微妙な反応が異なるため、原理的に「再現不可能な一回限りのナマの出来事」に近づくのだ。「再現可能性」(=演劇)を設定したうえで、「再現不可能性(出来事の一回性)」の予測不可能なリアリティが侵入し、後者が前者の枠組みを揺らす。しかし同時に見る者は、戸惑いや緊張のためにこわばり、プロの俳優のように「動けない」被介護者役の身体に、(不在のはずの)「エトウさん」の身体を投影し、想像的に重ね合わせるという、演劇的行為を行なっている。つまり、いったん「演劇」の内部に予測不可能な出来事の一回性の亀裂を入れたうえで、再び「演劇」を再起動させている。そしてそこで再起動の鍵となる、被介護者役の身体のぎこちなさや硬さは、それを一方的に見つめる私たち「観客の視線」がもたらしていることに気づいたとき、「観客の眼差しこそが舞台上に(不在の)存在を現前させている」という、演劇の原理を突く鋭さに、身震いを覚えるのだ。
キビるフェス2020公式サイト:https://kibirufes-fuk.localinfo.jp/
関連レビュー
村川拓也『インディペンデント リビング』|山﨑健太:artscapeレビュー(2017年12月15日号)
村川拓也『ツァイトゲーバー』|木村覚:artscapeレビュー(2013年03月01日号)
2020/02/24(月・祝)(高嶋慈)
尾崎森平「1942020」

会期:2020/02/18~2020/03/01
ギャラリー ターンアラウンド[宮城県]
仙台の現代美術のギャラリーにて尾崎森平の個展が開催され、トークのゲストとして招かれた。彼は、真っ青の空とクリーム色の地面を背景に「今春オープン」というイオンの看板が立つ《Mirage》や、遠景に山が見える広大な空き地に不動産の宣伝看板が立つ《売り地》など、地方のフラットな風景を簡略化、ならびにやや抽象化しつつ、カラフルな配色で作品を制作している。さて、今回の展覧会のタイトル「1942020」は、イタリアで中止になった1942年のローマ万博の都市EURと、東京2020オリンピックの年号を合体させたものだ。注目すべきは、ムッソリーニが推進したファシズム期のイタリア合理主義の建築をモチーフとしていること。すなわち、尾崎の作品において、現在はフェンディの本社になっているイタリア文明宮(この建物は第12回恵比寿映像祭[2020]において、ローマ・オリンピック1960で活躍したアベベ・ビキラをテーマとしたニナ・フィッシャー&マロアン・エル・ザニの作品でも使われていた)がラブホテルに、あるいはアダルベルト・リベラが設計した会議場は浴場やセレモニーホールに変容している。ほかに列柱(!)があるコンビニ、ムッソリーニが糾弾されたシーンを重ねあわせた洗車場なども展示されていた。
もっとも、本来、EURの街区は人が歩くスケールを超え、ファシズム建築もメガロマニアックな傾向をもち、基本的に巨大であるのだが、尾崎が平坦な日本の地方の風景に溶け込ませると、必然的にサイズを縮小せざるをえない(本人はイタリアを訪れたことがないという)。その変容プロセスは、ゴシック様式のウェディングチャペルとも似て、いかにも日本らしい。モダニズムと古典主義を調停した合理主義の建築が、全然違う文脈に放り込まれることで、少し違和感を残しつつも、意外に地方でありそうなキッチュな建築になっているのが興味深い。尾崎は「表現の不自由展」のように、はっきりと政治的なメッセージを出しているわけではないが、日常に浸透するファシズムを読みとることも可能だろう。一方でそれを簡単に批判するのではなく、ファシズム建築に魅せられるわれわれをも示唆しているかのようだ。
2020/02/25(火)(五十嵐太郎)
UMA / design farm展 Tomorrow is Today: Farming the Possible Fields

会期:2020/02/25~2020/03/28
クリエイションギャラリーG8[東京都]
新しいタイプのデザインスタジオが現われたと思った。いや、新しいというと語弊が少しあるかもしれない。斬新とか、新進気鋭とか、そういう意味ではない。本展は大阪を拠点に活動するUMA / design farmの仕事を紹介した展覧会なのだが、その領域の幅広さに驚いた。ロゴやポスター、パッケージ、商品企画、書籍などのグラフィックデザインから、サイン計画、ピクトグラム、そしてさまざまな施設の仕組みづくりにまで携わっている。もちろん第一線で活躍するアートディレクターなら、このくらいの領域まではやるのかもしれない。nendoをはじめ、分野を横断したデザインスタジオも増えている。しかし従来のアートディレクターやデザイナーとは違う何かを感じた。それは彼らが掲げる、当事者と「ともに考え、ともにつくるデザイン」という点に尽きるのではないか。グラフィックデザインを基軸にしながらも、言わばソーシャルデザインの領域にまで踏み込んだ仕事という印象を受けたのだ。
 展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:UMA / design farm]
展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:UMA / design farm]
それがもっとも如実に表われていたのは、Room Bに展示された三つのプロジェクトである。いずれもプロセスが特徴的ということで、初めにそのプロセスが5コマ漫画でユニークにまとめられていた。例えば奈良県で障害者の就労支援を行なっている福祉施設「たんぽぽの家」では、彼らは冊子のデザインをはじめ、同施設が行なう「Good Job! Project」の協働者を務める。福祉×アート、工芸、デジタルファブリケーションなどさまざまな分野に挑みつつ、障害者の仕事づくりを一緒に模索しているのだ。ここでも当事者とともに考え、ともにつくることを大切にしているため、実に前向きで健やかで、彼ら自身も非常に楽しんでいる印象を受けた。
また、Room Aには「UMA / design farmが考えるデザイン」として1枚のポスターが掲げられていた。そこにはシンプルな図とともにこう記されている。「1. 魅力を最大化する」「2. バラバラになったものを組み立てる」「3. 世界のバランスを考える」「4. なにかの媒介になる」「5. 目に見えない新たな関係性をつくる」。これまでにデザインの定義を多くのデザイナーや評論家たちが説いてきたが、彼らの仕事の特徴をもっとも表わしているように思えた定義は「5. 目に見えない新たな関係性をつくる」だ。ある施設や地域において、人と人との関係づくり、場づくり、仕事づくり、環境づくりというのを、当事者の目線で行なう彼らの仕事はやはりソーシャルデザイン以外の何ものでもない。こうした姿勢はいまの時流にとても合っているし、これからの社会でデザイナーにより求められる要素ではないかと感じた。
 展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:UMA / design farm]
展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:UMA / design farm]
公式サイト:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/tomorrow-is-today/tomorrow-is-today.html
2020/02/28(金)(杉江あこ)
「コズミック・ガーデン」サンドラ・シント展

会期:2020/02/11~2020/05/10(※)
銀座メゾンエルメス フォーラム[東京都]
※3月3日〜3月22日は臨時休館(3月16日現在。最新の状況は公式サイトをご参照ください)
いま、世界中に新型コロナウィルスの感染が広がり大騒動となっている。本展を観たのは2月28日。ちょうど安倍首相が全国の小中高校に臨時休校要請を呼びかけた翌日のことだった。このあたりから全国の美術館の臨時休館が相次いで発表され、私は慌てて展覧会を観に出かけたのだった。マスクは言うまでもなく、トイレットペーパーなどの紙類まで売り切れるし、世の中全体が得体の知れない恐怖に対してパニックを起こしている状態である。この異様な状況は、3.11以後の社会に似ているとふと思い起こした。あのときも震災や津波の恐怖とともに、目に見えない放射線に脅えたのだった。放射線もウィルスも、目に見えないからこそ恐怖が増大する。
例外なく、私も漠然とした恐怖にさらされたひとりだった。マスクを着用し、外出先でもこまめに手洗いと消毒を行ないつつ訪れた本展は、そんな心境をまさに見透かすような内容だった。壁一面に塗られた青の世界にまず圧倒される。淡い青から濃い青へと徐々に変化する青のグラデーションのなかで、白い線画が浮遊している。白い線画は雲や霧、波しぶきのようであり、自分が鳥になって青空を駆け巡り、また海を見下ろしているような気持ちになった。なかなか爽快な眺めである。さらに奥へ進むと、紺碧の空間が待ち受ける。床には絨毯が敷かれ、靴を脱いで上がるよう指示される。絨毯にまで白い線画が飛び跳ねるように及んだそこは、無限の星が瞬く宇宙だった。果てしない宇宙の中に身を置き、寝そべって、静かに星々を眺める時間が用意されていた。
本展のアーティスト、サンドラ・シントが想定したシナリオは、おそらくこの空、海、宇宙の世界までだったに違いない。しかしこのとき、私が感じたのはウィルスの存在である。最初から薄々と感じてはいたが、この宇宙の中に入った途端、幻想的な星々がウィルスの大群に見えて仕方がなかったのだ。目に見えない恐怖が可視化された(ように見えた)瞬間である。だからと言って、恐怖が一層高まったのかと言うとそうではない。むしろ可視化された(ように見えた)ことで、肝が据わったのである。あぁ、もしかすると、こんな風にウィルスが人間の社会を取り巻いているのかもしれない。ならば覚悟を決めて、ウィルスとともに共生しようではないか。言うなれば、こんな心境である。シントが問いかけるのは、「カタストロフや混沌といった状況に直面した時、私たち人間が感情と向き合う時間」だと言う。まさにそんな時間を体験できた。
公式サイト: https://www.hermes.com/jp/ja/story/maison-ginza/forum/200211/
2020/02/28(金)(杉江あこ)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)