artscapeレビュー
2022年02月01日号のレビュー/プレビュー
初沢亜利『東京二〇二〇、二〇二一。』

発行所:徳間書店
発行日:2021年12月31日
2022年に入って、オミクロン変異株による新型コロナウィルス感染者の増加は止まらないものの、2020年から続くパンデミックにも、おぼろげに「終わり」が見えてきたようだ。それに伴い、コロナ禍の状況を写真家がどのように捉えてきたのかを、あらためて検証する動きも出てきた。だが、たとえば東日本大震災などと比較しても、「コロナ時代」を写真で提示することのむずかしさを感じる。ウィルスの脅威を可視化しにくいということだけでなく、マスク姿の群衆や人気のない街といったステロタイプに陥りがちになるからだ。また、2年以上もパンデミックが続いていることで、非日常が日常化し、逆にくっきりとした像を結びにくくなってきているということもある。
初沢亜利も、その困難な課題を引き受けようとしている写真家のひとりだ。既に2020年8月に、1回目の緊急事態宣言下の東京を撮影した写真集『東京、コロナ禍』(柏書房)を上梓しているが、今回、その後の状況の変化をフォローし、衆議院選挙やオリンピック開催の周辺にまでカメラを向けた『東京二〇二〇、二〇二一。』をまとめた。前作もそうだったのだが、本書の掲載写真のベースになっているのは、日々、SNSにアップしていた写真群だという。つまり「写真日記」という体裁なのだが、内向きにステイホームの様子を撮った写真を並べるのではなく(そういう写真はほぼない)、視線が常に外に向いていることに注目したい。
驚くべき行動力で東京中を駆け巡り、横浜に戻ってきたダイヤモンド・プリンセス号、人影のまばらな全国戦没者追悼式、マスク姿で埋め尽くされた初詣の明治神宮、オリンピック反対のデモ、選挙応援演説を終えて虚ろな眼差しを向ける安倍前首相の姿などを丹念に記録していく。とはいえ、全体としてみれば、ジャーナリスティックな題材の写真を点在させつつ、コロナ禍の東京の日常の空気感を炙り出すようなスナップショットを中心に構成しており、その絶妙なバランス感覚が、初沢のドキュメントの真骨頂といえるだろう。
あとがきにあたる「東京の自画像」と題する文章で「撮影者も読者も共に過ごしたコロナ禍だ。前提の共有という点は、これまでにはない本作の特徴だ」と書いているが、たしかに東北地方の被災地、北朝鮮、沖縄など、これまで彼が撮影してきたテーマとはやや異なるアプローチが見られる。日本だけでなく、世界中を巻き込んだパンデミックという共通体験を、どのように受けとめ、投げ返していくのかを手探りで模索する仕事の、最初の成果ともいえるだろう。
2022/01/16(日)(飯沢耕太郎)
ポストバブルの建築家展―かたちが語るとき―アジール・フロッタン復活プロジェクト

会期:2022/01/12~2022/02/19
BankART Station[神奈川県]
タイトルに示されているように、この展覧会は2つの要素からなる。ひとつはフランスで開催された日本人の建築家展、もうひとつはセーヌ川の避難船をリノベーションする「アジール・フロッタン復活プロジェクト」だ。まず「アジール・フロッタン」とは、石炭運搬用につくられた箱船を1929年にル・コルビュジエが難民のための避難所としてリノベーションしたもの。その設計を担当したのが、当時コルビュジエの事務所にいた前川國男だった。それから100年近く、避難所としての役割を終えてからもセーヌ川に係留されていたが、2006年にギャラリーなど文化的に再利用する復活プロジェクトが始動。当初ここで日本の建築展を開く計画があったが、2018年にアクシデントにより沈没し、計画はポシャッてしまう。2020年には前川の縁で日本側が協力し、浮上に成功。現在再生計画が進められている。
日本人の建築家展のほうは、建築史家の五十嵐太郎氏が選んだ1960年以降の生まれの35組の建築家をフランスに紹介するもの。こちらは国際交流基金パリ日本文化会館で開催し、FRACサントル・ヴァル・ド・ロワールを回る予定だったが、コロナ禍により延期され、順序も逆転。その後、兵庫県立美術館を経てBankARTに来た次第。どちらもアクシデント続きなのだ。
BankARTでは、各1平方メートルほどのテーブル上に35組の建築のマケットやプランを載せ、「かたちとは」で始まる建築家のコメントも紹介している。出品は、開館間近な遠藤克彦の《大阪中之島美術館》(2021)、「アジール・フロッタン復活プロジェクト」を推進する遠藤秀平の《Rooftecture OG》(2020)をはじめ、平田晃久の《Tree-ness House》(2017)、西沢立衛の《豊島美術館》(2010)、田根剛の《Todoroki House in Valley》(2018)など。1960年以降の生まれに焦点を当てた理由を、五十嵐氏は次のように説明する。バブル期には奇抜なデザインのポストモダニズム建築が流行したが、バブル崩壊と2度の大震災により派手な形態が忌避され、かたちよりコミュニティの関係が重視されるようになった。しかし奇抜な形態を追求しながら、同時にコミュニティにも関与していく建築は可能ではないか。そんな「ポストバブル世代」の建築家にスポットを当てたのだと。これはバブル期の派手なニューウェイブから、90年代以降、コミュニティを重視するアートプロジェクトに向かった現代美術の流れとも共通する課題だ。
さて、それではアジール・フロッタンは本展のどこに関わっているのかというと、会場に入ればなんとなく見えてくる。細長い展示室を斜めに横切る低い仮設壁が船の輪郭をなぞっているのだ。つまり、アジール・フロッタンの船内で展覧会が開かれているという設定なのだ。内部の仕切り壁や円柱も再現され、展覧会場に立つだけでセーヌ川に浮かんでいる気分、にはならないが、少なくともそのスケール感くらいは味わえる。また、船内に塗り重ねられたペンキのかけらも展示され、あろうことか、ベルリンの壁の破片のように販売されてもいるのだ。
2022/01/19(水)(村田真)
笠木泉『モスクワの海』
会期:2022/01/15~2022/01/22(※戯曲無料公開期間)
笠木泉が主宰する演劇ユニット・スヌーヌーの2作目として昨年末に上演された『モスクワの海』が第66回岸田國士戯曲賞の最終候補作品にノミネートされた。遊園地再生事業団、「劇団、本谷有希子」、ミクニヤナイハラプロジェクト、はえぎわなどの演劇作品や冨永昌敬監督、中村義洋監督らの映画作品で俳優として活躍する笠木は劇作家としても活動しており、2017年に脚本家・鈴木謙一らのユニットであるラストソングスに提供した『家の鍵』は第6回せんだい短編戯曲賞にも最終候補作品としてノミネートされている。アラビア語でツバメを意味する名を持つスヌーヌーでは笠木自身が演出も手がけ、2018年に踊り子ありのひとり芝居としてvol.1『ドードー』を上演。『モスクワの海』は当初は2020年12月にvol.2として上演を予定をしていたもののコロナ禍の影響で延期となり、2021年12月、1年越しでの上演が実現した。実は私はその上演については観ることが叶わなかったのだが、公演は好評を博し、その後、2022年1月15日から22日までの1週間、希望者にpdfファイルを配布するかたちで戯曲が公開された。本稿は(上演の記録写真こそ掲載されてはいるが)その戯曲のレビューとなる。
 [撮影:明田川志保]
[撮影:明田川志保]
主な舞台は川を挟んで「東京の隣」にある街。「急行が止まるし、南武線も走っているから、人はそこそこいるけど、ごった返すかというと、そうでもない」駅から徒歩5分の住宅街にある「二階建ての、古くて、ちいさな一軒家」。そこに住む女1(高木珠里)はあるとき庭でふいに立ち上がれなくなってしまう。たまたま通りがかった女2(踊り子あり)は「手を、貸しましょうか」と申し出るが女1は「大丈夫です!」と頑なで──。
拒絶された女2は一度は立ち去るものの戻り、改めて手を差し伸べ、しかしその手を借りず自力で立ち上がった女1が家の中に戻るのを手伝い、彼女を病院へ連れて行くためのタクシーを呼ぼうと通りへ出る。劇中の時間で起きるのはたったこれだけ、10分程度の出来事だ。
 [撮影:明田川志保]
[撮影:明田川志保]
見ず知らずの人に助けの手を差し伸べるのは案外難しい。ふいに声をかけられた側も警戒する。二人の間には門扉の柵という物理的な障壁もある。「見えているのに、助けられない」。だがそれでも女2は文字通りの障壁を乗り越え、少しだけ女1の側に踏み込む。女1の拒絶を思えばそれは余計なお世話だったのかもしれないが、そうして足を踏み入れた家の中の様子から女2は少しだけ女1のことを知ることになる。パン、せんべい、バナナの皮、割り箸が刺さったまま干からびたサトウのごはん、そこだけがきれいに拭かれた仏壇、民生委員の電話番号が書かれたメモ、溜まった郵便物。それは女1の人生のごくごく一部でしかないが、その一部ですら、加藤伸子という彼女の名前と90歳という年齢すら、女2が踏み込まなければ知り得なかったものだ。それは観客にとっても同じことだ。舞台上にはほとんど何もなく、伸子を演じる高木は90歳ではない。想像力には限界がある。
 [撮影:明田川志保]
[撮影:明田川志保]
ところで、伸子には息子がいる。息子を演じる松竹生は最初から舞台上にはいるのだが、ときおり伸子と言葉を交わしたりはするものの、どういう人物なのかはなかなかはっきりしない。やがてわかってくるのは、それがフジオという名の彼女の息子であり、しかし長年引きこもっていた彼はいまはもうその家にはいないということだ。(基本的には)母親である彼女にだけ見えている息子の姿は、女2が伸子の方に一歩を踏み出そうとしたその一瞬だけ女2にも見えるようになり、彼女は少しだけフジオと言葉を交わす。
フジオはなぜいなくなったのか。53歳のある日、フジオは突然、バイトの面接のために新宿に向かう。「きょうは、気分がいい」からと家を出たフジオは結局、新宿に行くことはできなかった。川の近くの公園でフジオが思い出すのは同級生と、そこで通り魔事件を起こし自ら命を絶った、何年も引きこもっていたという自分と同い年の犯人のことだ(それは実際に起きた事件である)。「みんな、忘れてしまっただろうか」。
渡り鳥の声が「来週汚染水が放出されるよ」と告げる。高校生のフジオはまだ学校に通っていたらしい。フジオはそのときから借りっぱなしになっていたレコードや雑誌をかつての同級生に返そうとする。それはチェルノブイリ原発事故の年のものだ。そういえば、伸子が立てなくなったのは、どこか遠くで「どーん!」という音がした直後のことだった。ひとりの人間がふいに立てなくなることと歴史的な大事故。遠い両者はしかしどこかでつながっている。
 [撮影:明田川志保]
[撮影:明田川志保]
 [撮影:明田川志保]
[撮影:明田川志保]
バイトの面接に行けず、橋の上から川面を眺めていたフジオは、やがてそこから落ちてしまう。「彼は、確かにいろいろあるけどさ、ちょっとふらっとしただけなんだ。薬をちょっとだけ飲みすぎて、ふらっとしただけなんだ。今、今だけなんだ! この瞬間、そうなってしまっただけなんだ!(略)だから、これは、事故なんだよ」。渡り鳥たちの声は悲しくも優しい。集まった鳥たちは落下するフジオを助け、そして彼もまた鳥たちとともに飛び立っていく。その後に描かれる久しぶりの帰宅の場面は、現実か、それとも伸子の空想だろうか。
もしかしたらフジオは救われなかったのかもしれない。だが、伸子の「その瞬間」には女2がいた。遠い悲劇に直接できることはなくとも、想像の及ばないことがあろうとも、そばにいるというそれだけのことで救われる何かがあり、そこからはじまる何かもある。この戯曲はそのことをささやかに、しかし力強く肯定しようとするものだ。
 [撮影:明田川志保]
[撮影:明田川志保]
スヌーヌー『モスクワの海』:https://snuunuumoscow.amebaownd.com/
スヌーヌーTwitter:https://twitter.com/snuunuu
2022/01/20(木)(山﨑健太)
オルタナティブ! 小池一子展 アートとデザインのやわらかな運動

会期:2022/01/22~2022/03/21
アーツ千代田 3331[東京都]
小池一子さんてだれ? と聞かれたとき、どのように紹介すればいいのだろう。そもそも彼女を「さん」づけすべきか迷ってしまう。ぼくは記事を書くとき、慣例的にアーティストの名前は敬称抜きだが、学芸員や評論家などその他の人たちには「氏」や「さん」など敬称をつける。小池さんはいわゆるアーティストではないけれど、ある意味アーティスト以上にアーティスティックなクリエイターだし、なにより今回は展覧会の主役でもあるので、小池一子と敬称抜きで記すべきかもしれない。とはいっても、40年近くおつきあいさせていただいている大先輩、やはり呼び捨てにするのははばかられるので、ここでは敬意を込めて「小池さん」と呼ばせていただきます。
で、小池さんを紹介すると、コピーライター、編集者、クリエイティブ・ディレクター、翻訳者、無印良品の企画・監修者、武蔵野美術大学名誉教授、東京ビエンナーレ共同代表、フェミニスト……。過去の肩書も含めると、元西武・セゾン美術館アソシエイト・キュレーター、元佐賀町エキジビット・スペース主宰者、元十和田市現代美術館館長……まだまだあるかもしれない。実に多彩な活動をされているので、ひとことで言い表わすことはできないが、共通しているのはいずれも名前や顔が表に出ることの少ない裏方仕事であることだ。そんな人物の展覧会とはいったいどんなものなのか。
展示は大きく、前半の「中間子」と後半の「佐賀町」の2部に分かれている。前半は、パルコや西武美術館、イッセイミヤケ、無印良品などのポスターが壁面を埋め、編集者やコピーライターとして関わった『週刊平凡』『森英恵流行通信』などの雑誌、デザイナー田中一光と制作した『JAPANESE COLORING』(リブロポート、1982)、『三宅一生の発想と展開ISSEY MIYAKE East Meets West』(平凡社、1978)などの書籍も公開。特にポスターは華やかで、広告デザイン全盛期の1970-80年代に見覚えのあるものがずらりと並ぶ。昨年開かれた石岡瑛子の回顧展を思い出したが、それもそのはず、石岡と共作したポスターもある。石岡もアートディレクターとして、写真家やデザイナー、イラストレーターらをつなぐ仕事をしていたが、みずから「ものづくり」をするデザイナーでもあった。でも小池さんはあくまで人と人、人と企業や美術館をつなげて新しい価値を生み出すことに徹した。いわば才能と才能との触媒。それが「中間子」の意味であり、役割でもあるだろう。
後半の「佐賀町」とはいうまでもなく、日本では稀なオルタナティブ・スペースとして1983年に誕生した佐賀町エキジビット・スペースのこと。小池さんが主宰したこの特徴あるスペースで、2000年までの17年間に106の展覧会やパフォーマンスを実現させた。今回はそのうち、吉澤美香、大竹伸朗、横尾忠則、シュウゾウ・アヅチ・ガリバー、杉本博司、森村泰昌ら約20人による当時の作品を展示している。しかし考えてみれば、小池一子の名を冠した展覧会なのに、本人の「作品」はなく、20人ものアーティストの作品が並ぶのは、変といえば変。だが、ここに小池さんの「中間子」たるゆえんがある。彼らアーティストは小池さんがいなければ(佐賀町がなければ)現在の地位を築けなかったかもしれないし、これらの作品も日の目を見なかったかもしれないのだ。裏返せば、これらの作品もアーティストも小池さんの「作品」なのだ。といってみたい欲望に駆られるが、そこまではいわないでおこう(もういっちゃったけど)。
ちなみに後半の「佐賀町」の展示スペースは、前半の「中間子」の倍くらいある。現代美術だからポスターより幅をとるのは当然だし、また、小池さんの興味が広告デザインから徐々にアートへと重心を移しているように感じられるので納得だが、そうでなくても「佐賀町」が同展のメインディッシュであることは間違いない。それはタイトルの「オルタナティブ!」からも明らかなように、企画したのが美術館でもギャラリーでもない、佐賀町のオルタナティブ精神を受け継ぐ3331であるからだ。
2022/01/21(金)(村田真)
カタログ&ブックス | 2022年2月1日号[テーマ:フェミニズム、反芸術、ドゥルーズ──田部光子の世界をもっと深く知る5冊]

注目の展覧会を訪れる前後にぜひ読みたい、鑑賞体験をより掘り下げ、新たな角度からの示唆を与えてくれる関連書籍やカタログを、artscape編集部が紹介します。
今回ピックアップするのは、福岡市美術館の企画展、田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」(2022年1月5日~3月21日開催)。国内でも早期からフェミニズムの視点を持って制作を続けてきた女性作家、田部光子(たべ・みつこ/1933-)。本展を出発点に、日本美術における女性作家の立ち位置の変遷や、「反芸術」の流れにおけるパフォーマンスの歴史など、彼女を取り巻くトピックを広くそして深く知るための5冊を、本展の展覧会図録とともにご紹介します。
今月のテーマ:
田部光子の世界をもっと深く知る5冊
※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。
※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。
1冊目:女性画家たちの戦争(平凡社新書)
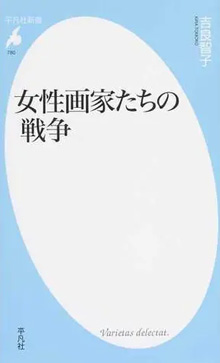
著者:吉良智子
発行:平凡社
発売日:2015年7月17日
サイズ:18cm、215ページ
Point
大正末期から戦前、戦中にかけて、女性画家たちはどのような環境で作家活動をしてきたのか、そして戦争にどう関わったのか──。国内の画壇における女性画家たちの立ち位置とともに、どのような目線で戦争の時代を捉えていたのかを俯瞰できる一冊。田部が生きた時代の前日譚として。
2冊目:アンチ・アクション 日本戦後絵画と女性画家

著者:中嶋泉
発行:ブリュッケ
発売日:2019年9月5日
サイズ:22cm、362ページ
Point
田部とほぼ同時代を生きてきた女性画家たち──草間彌生、田中敦子、福島秀子の3人の視点から見つめ直す戦後美術史。アクション・ペインティングが隆盛した1950〜60年代、それらに男性性を見出す美術界のムードの中で埋もれてしまった女性画家たちの思考をすくい上げる、野心的な研究書。
3冊目:肉体のアナーキズム 1960年代・日本美術におけるパフォーマンスの地下水脈

著者:黒ダライ児
発行:grambooks
発売日:2010年9月1日
サイズ:22cm、632+135ページ
Point
1957年から70年までの日本の前衛美術家の活動のうち特に「反芸術」のなかで生まれたパフォーマンスに着目し、同時代の社会状況を踏まえ詳細に紹介・分析した、日本のパフォーマンス史における重要書。今回の展覧会ポスターのメインビジュアルを飾る田部のパフォーマンスについても言及あり。佇まいも含め重厚な一冊。
4冊目:フェミニズムはみんなのもの 情熱の政治学

著者:ベル・フックス
翻訳:堀田碧
発行:エトセトラブックス
発売日:2020年8月12日
サイズ:19cm、188ページ
Point
日々耳にしている「フェミニズム」がそもそも何を目指したどんな考え方なのか、正直ちゃんと説明できない…。そんな人におすすめしたい本。女性だけでなく誰にでも関係のあるトピックとして、現代的な目線でフェミニズムを捉え直せる入門書。田部が活動初期から抱えていた問題意識の先見性にも改めて驚かされるはず。
5冊目:ドゥルーズの哲学 生命・自然・未来のために(講談社学術文庫)

著者:小泉義之
発行:講談社
発売日:2015年10月10日
サイズ:15cm、245ページ
Point
今回の展覧会のタイトルにもなった「希望を捨てるわけにはいかない」という力強い言葉は、2000年頃に田部氏が本書(2000年刊行の講談社現代新書版)で出会ったもの。一見難解な「差異」に着目したドゥルーズの思想を、時には迂回しながら著者と読み込んでいくことで、世界の捉え方に少し希望が湧いてくる一冊。
田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」
会期:2022年1月5日(水)~3月21日(月・祝)
会場:福岡市美術館(福岡県福岡市中央区大濠公園1-6)
公式サイト:https://www.fukuoka-art-museum.jp/exhibition/tabemitsuko/
田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展覧会図録

編集・執筆:正路佐知子(福岡市美術館)
発行:福岡市美術館
発行日:2022年1月5日
サイズ:H250×W220mm、160ページ
福岡を拠点とする美術家・田部光子の活動を回顧する展覧会、田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」の図録。出品作を含む作品画像や資料・写真を数多く掲載し、田部光子による文章も多数再録。担当学芸員の論考、詳細な文献リストと年表、出品リストを収録(一部日英)。
◎展示会場、福岡市美術館オンラインショップで販売中。
2022/02/01(火)(artscape編集部)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)