artscapeレビュー
2022年02月01日号のレビュー/プレビュー
熊谷聖司「RE FORM」
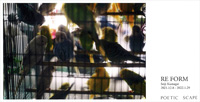
会期:2021/12/08~2022/01/29
POETIC SCAPE[東京都]
熊谷聖司は2013年に『MY HOUSE』(リブロアルテ)という写真集を刊行している。身の回りの光景を、淡々と肩の力を抜いて、だが不思議な哀切さをともなって見えてくる角度から切りとったスナップショットを集めたもので、現在の彼の写真のスタイルの原型となる写真集だった。それから8年余りを経て、まったく同じ判型、レイアウトの『RE FORM』(livers lieu lieu 2021)を刊行した。今回のPOETIC SCAPEでの個展は、そのお披露目の展示である。
写真集のタイトルの付け方に、熊谷の遊び心があらわれている。「本」を「家」と見立てて、「壁の色を変えたり、キッチンに窓を増やしたりするように作品を差し替え」ていったのだという。『RE FORM』というのは、まさにその行為にふさわしいタイトルといえるのではないだろうか。似たような「家」には違いないのだが、その味わいは微妙に違う。写真のテーマ、色合い、画面構成などに配慮して、輻輳するストーリーに沿って写真を並べていく手つきが精妙になった。所々に置かれているピラミッド、コーン、富士山、傘、マスクなど、同じようなフォルムの写真の繰り返しによるリズムの作り方にも、写真家としての奥行きの深さがあらわれている。写真集の掲載作からピックアップした展示も、熊谷の写真の世界に観客を引き込んでいくように、注意深く構成されていた。
なお、今回の熊谷の個展が、POETIC SCAPEの開設10周年にあたる展覧会になるのだという。ギャラリーがある東京・中目黒の住宅街は、あまり行きやすい場所ではないが、熊谷や野村浩、尾仲浩二、渡部敏哉、尾黒久美など、玄人好みのクオリティの高い作品を、コンスタントに展示し続けてきた。写真ギャラリーの運営という点では、厳しい状況が続くが、今後もいい展覧会を開催し続けていってほしい。
2021/12/08(水)(飯沢耕太郎)
ソール・スタインバーグ シニカルな現実世界の変換の試み

会期:2021/12/10~2022/03/12
マンガは紙媒体で読むものだと思っているので、よっぽどのことがない限り美術館やギャラリーのマンガ展に行くことはない。原画やエスキースが公開されようが、作者の用いたペンやインクが出品されようが、わざわざ公共的な空間に赴いて鑑賞するのはまっぴらごめん。春画と同じくひとりプライベートに楽しみたい。でもソール・スタインバーグは見に行ってしまった。ぼくにとっては「よっぽどのこと」なのだ。
いつからスタインバーグに惚れ込んだのか忘れたが、学生時代からであることは間違いない。当時買ったスタインバーグの画集『新しい世界』を引っ張り出してみると、1970年発行とあるから半世紀以上も前のこと(買ったのはその数年後)。なんと出版社はみすず書房で、装丁は瀧口修造。小文ながらハロルド・ローゼンバーグと瀧口が論を寄せるくらいだから、現代美術の巨匠並みの扱いだ。ほかにもホイットニー美術館での回顧展(1978)のカタログをはじめ、イエナ書店や丸善で画集を何冊も買い込むほど熱を上げたが、日本ではほとんど話題に上ることもなく、いつのまにか忘れかけていた。今回久しぶりに名前を聞いて駆けつけた次第。
スタインバーグ(1914-99)はルーマニアに生まれ、イタリアで建築を学んだが、ファシズムから逃れて渡米。以後半世紀以上にわたり、主に『ニューヨーカー』誌を舞台に作品を発表してきた。先にマンガと書いたが、確かにマンガ(コミックではなくカートゥーン)ではあるけれど、マンガを超えたメタマンガというか、現代美術のなかでもとびきり洗練された現代美術と言ってもいいくらいの質を備えているのだ。ローゼンバーグが入れ込むのも無理はない(ちなみにホイットニー美術館のカタログにもローゼンバーグが長文を掲載)。
いつからスタインバーグに惚れたかは忘れたが、最初にどの作品でぶっ飛んだかは覚えている。『ニューヨーカー』の表紙を飾った《9番街からの世界の眺め》ってやつだ。画面の下半分にビルの立ち並ぶマンハッタンの9番街、10番街が描かれ、その上にハドソン川、その上にところどころ岩の突き出た四角い平面(アメリカの国土)があり、その先に太平洋、さらに向こうに中国、日本、ロシアが1本線で表わされている。なんという大胆かつ斬新な世界観であることか! しかもそれを、とても建築を学んだとは思えない雑なパースで描いてみせるのだ。この号の発行日は1976年3月29日だから、ぼくは70年代後半にどこかでこれを目にしてファンになったわけだ。
スタインバーグのいちばんの魅力はウィットに富んだ記号表現にある。たとえば、ひとりの男が相手になにかを延々と話している絵。話の内容はアルファベットらしき線を書き連ねているだけなので不明だが、そのフキダシが大きな「NO」の字になっている。なんだかんだ理屈をつけてるけど、結果は最初から「ノー」だってこと。こうしたアルファベットや記号を用いた作品はたくさんあって、チケット売り場の前に1から12まで数字が並び、6だけ男の姿が描かれている絵は、人間を数字としてしか見ない現代社会への皮肉と読むこともできる。などと解説するのが野暮なくらい、絵=線描そのものに魅力があるのだ。たとえば、天秤の片方に2、4分の3、5、4分の1という数字が載り、もう一方に小さな8が載ってバランスをとっている絵。意味的には正しいのだが、そんなことよりひとつひとつ数字のスタイルを変え、数という抽象概念に個性を持たせているのが笑えるのだ。
スタインバーグのマンガは現代美術といったが、それは現代美術が内容より形式を重視するという意味においてだ。マンガというのはたいてい描かれる意味や内容に笑ったり感動したりするものだが、彼のマンガは「線」「平面」「スタイル」「セリフ」といったマンガを成り立たせている要素そのものをイジる。そのことでマンガが1枚の平面に引かれた線にすぎないことを暴くのだ。しかもそれを現代美術のように深刻ぶらず、軽妙な線でトボけてみせる。こんなに知的でナンセンスなマンガがほかにあるだろうか。展覧会を見た後、久しぶりに画集を引っ張り出して耽溺した。やっぱりマンガはひとり家で読むに限る。
2021/12/11(土)(村田真)
笹岡啓子「The World After」

会期:2021/12/11~2022/01/20
photographers’ gallery/KULA PHOTO GALLERY[東京都]
笹岡啓子は東日本大震災後の2011年4月から、その被災地となった岩手県、宮城県、福島県の太平洋沿岸部を撮影し始めた。それらはphotographers’ gallery での連続個展「Difference 3.11」(2012-2013)で発表されるとともに、2012年3月から刊行され始めた小冊子『Remembrance』(全41冊、KULA)にも収録された。今回のphotographers’ galleryでの個展は、その連作の中から124点を選んで出版した写真集『Remembrance 三陸、福島 2011-2014』(写真公園林、発売=ソリレス書店、2021)の刊行記念展として開催されたものである。
展示作品、及び写真集の収録作品を見て感じるのは、笹岡のアプローチが、震災後に夥しく撮影され、発表された被災地のほかの風景写真とは微妙に異なる位相にあるということだ。倉石信乃が写真集に寄せたテキスト「後の世界に──笹岡啓子の写真と思考」でいみじくも指摘しているように、笹岡は「震災直後の混沌と、2015年から21年までの『見かけ』の『復興』事業による土地の激変」の写真を除外している。つまり「よりシアトリカルでスペクタクルな事物の散乱や、事物の大がかりな再統合の様態はここには録されていない」のだ。結果的に本シリーズは、あくまでも平静な眼差しで撮影されたように見える、どちらかといえばフラットな印象の地誌学的な景観の集積となった。
むろん、個々の撮影時にはかなり大きな感情の振幅があったことは容易に想像がつく。だが、そのブレを極力抑えることによって、笹岡は震災後の「三陸、福島」の眺めを、「3・11」という特異点に収束させるのではなく、より普遍的、歴史的な広がりを持つ風景として再構築しようとした。笹岡が2011年4月に、岩手県大槌町で本シリーズの最初の写真を撮影した時、「写真で見たことがある被爆直後の広島に似ていた」と感じたというのは示唆的である。広島出身の笹岡にとって、「被爆直後の広島」の写真はいわば原風景というべきものであり、以後、彼女はそれを「三陸、福島」の眺めと重ね合わせるように撮影を続けていったということだろう。同時に、それらは写真を見る者一人ひとりにとっての「後の世界」を想起させる説得力を備えている。展示されている写真を見ながら、「どこかで見たことがある」という既視感を抑えることができなかった。
関連レビュー
笹岡啓子「Difference 3.11」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2014年01月15日号)
笹岡啓子「Difference 3.11」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2012年04月15日号)
2021/12/14(火)(飯沢耕太郎)
垣本泰美「Merge Imago」
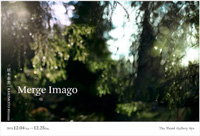
会期:2021/12/04~2021/12/25
1976年、大阪生まれで京都在住の垣本泰美は、1999年に成安造形大学造形学部デザイン科写真専攻を卒業後、The Third Gallery Ayaを中心に写真作品の発表を続けてきた。「少女期の『記憶』をヴィジュアル化する」ことを主なテーマとして続けられてきた仕事は、かなりの厚みとふくらみを持ち始めている。近年は、スイス、スウェーデンなどでのレジデンス体験を元にしたシリーズに、制作の比重が移行し始めているようだ。今回同ギャラリーで7年ぶりに開催された「Merge Imago」展も、2017年12月のスウェーデン滞在中に撮影した写真群で構成されていた。
垣本が当地で特に心惹かれたのは「汽水域」の眺めだったという。真水と海水が混じり合うその場所のたたずまいは、人と人との交流、その記憶や意識の重なりとも通じあうものだった。今回の展示では、水域をテーマに撮影した風景だけでなく、森の樹木、羽ばたく鳥、蝶の標本、水晶などのイメージをちりばめることで、「溶けあってゆく」世界の様相を静かに浮かびあがらせようとしている。強化ガラスに大小のプリント(円型に切り抜いたものもある)を貼りつけ、「間」を配慮しながら壁に並べたインスタレーションが、とてもうまくいっていた。写真作家としての成長を充分に感じさせる、見応えのある展覧会となった。
写真家としての経験を積み、独自の手触り感を備えた写真の世界も、しっかりとかたちをとりつつある。ぜひ、これまでの仕事に撮り下ろしを加える形で、写真集をまとめてほしい。
2021/12/16(木)(飯沢耕太郎)
新納翔「PETALOPOLIS」

会期:2021/12/09~2021/12/26
コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]
新納翔の新作は、都市写真のあり方を再考しつつ、新たな方向性を見出そうとする意欲作だった。撮影対象は現在の東京の風景なのだが、それを仮想都市「PETALOPOLIS(ペタロポリス)」に見立てて再構築している。縦位置の写真の画面の一部を加工して、色味、彩度、質感に配慮しながら、「未来の都市風景の断片」として提示していた。
このようなバーチャルな都市空間を画像化するとき、ともすればグラフィック的な処理に走りすぎて、写真的な見え方が失われてしまうことがよくある。本シリーズでも、看板の字を消すような操作も施しているが、それらを最小限に留め、都市風景としてのリアリティを余り損なわないようにしている。なお、「PETALOPOLIS」の「PETA」とは、国際単位系で1兆の1000倍をあらわす接頭辞である。「MEGALOPOLIS」や「GIGALOPOLIS」という言葉ではもはや追いつかないところまで、現代都市が爆発的に膨張しつつあるのではないかという新納の見立てにも説得力があった。
ちょうど、キヤノンギャラリーSで展示中の土田ヒロミの「ウロボロスのゆくえ」を見たばかりだったので、両作品を比較してみたくなった。土田が撮影したのは30年前の表層化、記号化しつつある東京とその周辺の都市風景であり、新納の「PETALOPOLIS」は逆に30年後の未来を予測したものだ。その両者が交錯したところに、もしかすると2021年現在の東京が姿を現わすのかもしれない。土田や新納だけでなく、複数の写真家たちの作品をつなぎ合わせてみることで、現時点における「東京写真」の全体像が見えてくるのではないかとも思った。
2021/12/17(金)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)