artscapeレビュー
パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー
屋根裏ハイツ『とおくはちかい(reprise)』

会期:2020/07/23~2020/08/02
こまばアゴラ劇場[東京都]
屋根裏ハイツ『とおくはちかい』(作・演出:中村大地)が「reprise」と冠しての全編改訂版として再演された。『とおくはちかい』は仙台を中心に活動してきた屋根裏ハイツが首都圏で上演した最初の作品。この作品で注目を集めた屋根裏ハイツがその評価を確かなものにした『ここは出口ではない』とともにカンパニーの代表作と呼ぶべき作品で、今回はその『ここは出口ではない』と合わせての再演・二都市ツアーとなる。
二幕構成の本作が描き出すのは「大きな地震から半年後と10年後」。一幕では仮設住宅に住む男・ショウくん(渡邉悠生)を友人のハマヤ(三浦碧至)が訪れ、二幕では同じくショウくんが住む復興住宅をハマヤが訪れなんということのない会話を交わす。初演時には地震ではなく大きな火事という設定だったらしいが、今回の再演にあたって、初演版の執筆時から念頭にあったという地震の話へと書き換えての上演となった。
 [撮影:本藤太郎]
[撮影:本藤太郎]
地震があっても同じ土地に住み続け、仕事も変えていないショウくんに対し、ハマヤは地震以前に地元を離れており、二人の会話は久しぶりに地元に戻ったハマヤとショウくんとのあいだの近況報告が中心となる。それらを通して浮かび上がるのは特別な出来事ではなく、互いのなかに蓄積された記憶のあり方そのものだ。
作品のほとんど終わりに至ってショウくんは「揺れて、家がなくなって、避難して、(仮設に)引っ越しして、(ここに)引越ししてっていうのはもうずっとある」「忘れる忘れないとかじゃなくて、ある」と自らの記憶のあり方を言語化しようとする。そこに至るまでに配された何気ないエピソードが呼応し合い記憶の複雑なあり様を浮かび上がらせる中村の筆致は巧みだ。
例えば、一幕に登場する箸と二幕に登場する鍋つかみの対比。仮設住宅への入居とともに支給されたはずの箸は1カ月も経たずに行方不明になってしまうが、高校のときにプレゼントでもらった、しかし思い入れがあるわけではない鍋つかみは震災でも失われず、仮設住宅を経て引っ越した復興住宅で発見される。あるいは駅前の銅像。地震以前に地元を離れたハマヤは失われたそれを震災によるものだと勘違いするが、ショウくんによればそれは地震以前に撤去されていたらしい。
「地元」に関するハマヤの記憶は断続的だが、そもそも人生自体が連続性があるようでなく、ないようであるものだ。ハマヤは自身が料理を始めたのは昔の友人がすえた臭いをまとっていたからだと説明する。その臭いが禁煙を決意させ、それが料理を始めたことにつながっているのだと。しかし説明を始めてみれば本人にもそのつながりははっきりとしない。だが、それでもそれらはどこかでつながっている。つながりははっきりせずとも人生は、時間は流れていく。
過ごした場所と時間の異なる二人の会話からは、それぞれに別様に流れ蓄積してきた時間と記憶が浮かび上がる。地震から半年後と10年後という区切りこそ示されているものの、地震とは関係なく時は流れている。大きなイオンモールができるという巨大な空き地にはかつてスーパー銭湯が建っていたというが、それは震災によって失われたわけではなく、震災後に建てられそして潰れたらしい。ある大きな出来事を振り返るとき、振り返るそのときまでに流れた時間もまた確かにそこにあるのだということを忘れることはできない。
 [撮影:本藤太郎]
[撮影:本藤太郎]
コロナ禍の最中の上演となった今回、二幕に登場するハマヤはマスク姿で現われた。物語的には大きな意味を持つとは思えないそれは、東日本大震災から10年が経とうとする現在を二幕の現在に重ね合わせるためのちょっとした小道具のように思えた。だが、このレビューを書くために読んだ上演台本には次のような文言が記されていた。「未知の疫病が世界を取り巻いている。(略)地域により再建のありようはさまざまで、いまようやく新しい街の着工にとりかかるようなところもあれば、ようやく人が住めるようになったところもある。行政の判断によって、もう人が住むことができなくなった土地もある」。影響の範囲ということで言えば、地震よりもよほど広い範囲で深刻な疫病の被害があったらしきことがこの記述からは窺える。しかし、上演からこの設定を読み取ることは不可能だろう。観客に彼らの事情を知ることはできない。そしてそれはいつもそうなのだ。自らのものでない記憶を私たちは十全に知ることはできない。それでもそこに、寄り添おうとすることはできる。互いの話を聞くというだけのシンプルな作劇の本作には、そのような倫理的な厳しさと温かさが滲んでいる。
9月18日からは『ここは出口ではない』とともに本作の仙台公演が予定されている。また、映像作家の小森はるかが映像編集を担当した東京公演の映像が有料配信されている。『ここは出口ではない』の映像(映像編集:宮﨑玲奈)とともにチェックされたい。
公式サイト:https://yaneuraheights.net/
中村大地インタビュー(passket):https://magazine.passket.net/interview/2020/07/22/yaneura-heights-interview/
関連記事
屋根裏ハイツ『ここは出口ではない』| 山﨑健太:artscapeレビュー(2020年09月01日号)
屋根裏ハイツ B2F 演劇公演『寝床』| 山﨑健太:artscapeレビュー(2019年11月01日号)
2020/07/25(土)(山﨑健太)
ドナルカ・パッカーン『野獣降臨』

会期:2020/07/22~2020/07/26
萬劇場[東京都]
コロナ禍の最中、いかなる戯曲を上演するか。戯曲を上演するという演劇の「方法」は、過去のアーカイブに現在を照らし合わせることで歴史から反省を(あるいは無反省を)引き出すことに優れている。演出家の仕事が上演の結構を整えることにあることは確かだが、その前段階として上演する戯曲を選択することもまた演出家の仕事であり、その腕の見せ所であると言えるだろう。
演出家・川口典成の個人企画「ドナルカ・パッカーン」が今回「緊急上演」したのは野田秀樹が1983年に第27回岸田國士戯曲賞を受賞した『野獣降臨』。伝染病を描いた本作は「野獣降臨」と書いて「ノケモノキタリテ」と読むことからも明らかなように差別を描いた作品でもある。コロナ禍の日本においては残念ながらさまざまな差別の問題が顕在化/激化しており、伝染病と差別を描いた本作の上演はきわめてアクチュアルなものとして現在に立ち上がってくる。
 [撮影:三浦麻旅子]
[撮影:三浦麻旅子]
ほかの多くの野田戯曲と同じように、本作もまた複数の筋と場面が混線し時空間も行きつ戻りつしながら進行していくため、ひと口にあらすじを紹介することは難しいのだが、大まかに言えば二つの物語がDNAの二重螺旋のように絡み合いながら進行し(あるいは退行し?)ていく。ひとつはあばら骨を一本失ってしまったボクサー・アポロ獣一(鎌内聡)の物語。それは地球と人の物語だ。もう一方は月と獣の物語。アポロ11という音をよすがに舞台は月へとジャンプする。獣を人のように変えてしまう伝染病を媒介するという月の兎(那須野恵/人形遣い:海老沢栄)を追う伝染病研究所の所長(丸尾聡)をはじめとする人々。しかし同じように地球では、人を獣のように変えてしまう伝染病が広がっているのだった。獣一が「獣のハジメ」と名乗るように人は獣へ獣は人へ、しりとりがごとく互いの尻にかじりつく。
たとえとしてDNAの二重螺旋をわざわざ持ち出したのは、それこそがこの戯曲の核となる構造だからだ。24本ある人間の肋骨を獣一は一本失い、残ったのは23本。それは人間が持つ46本の染色体のちょうど半分にあたる。人間は両親から23本ずつの染色体を受け継いで一人前のヒトとなる。だからこそ獣一と月の兎はそれぞれ半人前でしかなく、半人+半獣=地球+月でようやく一人前の物語が紡がれることになるのだ。
 [撮影:三浦麻旅子]
[撮影:三浦麻旅子]
戯曲の核に置かれたDNAの構造は伝染病や差別のモチーフとも呼応する。いずれもしばしばその「起源」が問題とされるが(「武漢ウイルス」なるWHOのガイドラインを無視した呼称を思い起こされたい)それはしばしば正統性への執着と裏表の関係にある(管見の範囲では「武漢ウイルス」という呼称を用いた人々とネトウヨと呼ばれる人々は重なっていた)。「宇宙家族アポロは、原始家族と背中合わせの双なりでございます」というセリフは過去(=原始家族)=起源と未来(=宇宙家族)=その結末とが切り離せないものであることを示している。野田はこの作品を「被差別民族」の物語だと明言したそうだが、しかし獣一たち宇宙家族=原始家族はときに聖家族と呼ばれ、物語の結末に至ってその「起源」がイザナギとイザナミの間に生まれた水蛭子にあったらしきことが示唆される。かつて現人神と呼ばれた天皇に一般的な意味での基本的人権は認められていない。差別と正統(性への執着)は表裏一体であり、この戯曲がもっともアクチュアルなのはその点だろう。『野獣降臨』は日本(人)の宿痾を鋭く抉り出す。
 [撮影:三浦麻旅子]
[撮影:三浦麻旅子]
川口は萬劇場がいち早く新型コロナウイルスへの対策を明示したことを受けて公演会場に選んだという。会場の入り口では検温、手洗い、手指靴底の消毒が行なわれ、一席おきに指定された客席はビニールシートで仕切られていた。宇宙飛行士/伝染病研究所所員を演じる俳優たちはフェイスシールドを装着し、観客たる私の「日常」はそのまま舞台上と地続きになる。煩雑であるはずの諸々でさえ劇世界への気分を盛り上げる道具立てになっていたという点においてもこの戯曲の上演は成功していたと言えるだろう。観劇前後の観客への情報提供も徹底していた。フェイスシールド越しの言葉が聞き取りづらい(しかしそれは観客たる私の側の問題でもあったのだろう。上演が進むにつれ耳がチューニングされたのかそれほどは気にならなくなった)など、上演上の課題こそいくつか見られたものの、この状況下でこそ上演すべき戯曲を「緊急上演」した川口の「目」は確かだ。前作『女の一生』初稿版完全上演でも川口は、戦後上演され続けている改訂版ではなく、戦時中に上演された初稿版のドラマツルギーこそが現代日本に通じているのだと示してみせた。日本人作家の手による戯曲に、いまこそ上演すべきは何かという観点から継続的に取り組み、過去の戯曲のなかに現代を照射するドラマツルギーを見出し上演し続けているドナルカ・パッカーン/川口の仕事に引き続き注目したい。
 [撮影:三浦麻旅子]
[撮影:三浦麻旅子]
 [撮影:三浦麻旅子]
[撮影:三浦麻旅子]
公式サイト:https://donalcapackhan.wordpress.com/
関連記事
ドナルカ・パッカーン『女の一生』| 山﨑健太:artscapeレビュー(2020年03月01日号)
2020/07/23(木・祝)(山﨑健太)
ウンゲツィーファ『一角の角(すみ)』

会期:2020/07/15~2020/07/19
吉祥寺シアター[東京都]
『一角の角』(作・演出:本橋龍)はウンゲツィーファによる「連ドラ演劇」。新型コロナウイルスの影響で休館していた吉祥寺シアターの再開後、最初の企画として7月15日から19日まで1日1シーンずつ制作、その成果を毎日20時からライブ配信したものだ。
劇場に観客を入れないという条件を逆手に取り、吉祥寺シアターのさまざまな場所に配置された舞台美術が劇場内部に「街」をつくり出す。俳優たち自ら撮影者となりひとつのカメラを手渡していくことで、1日1カット1シーンの映像作品は紡がれていく(映像:和久井幸一)。登場するのはコウモリ(豊島晴香)、タヌキ(畦道きてれつ)、イヌ(石指拓朗)、ネコ(近藤強、黒澤多生、星美里)、ハト(松井文)、そしてヒト(西留翼)。各話の冒頭とラストには宇宙人(?)らしきものも映し出され、1カットのなかにさまざまな生物の視点が混在する。それは自らとは異なる複数の視点から世界を捉え直す試みであり、そうできたらいいのにという願いのようでもある。他者の視点は誰か/何かを「演じる」ために必要な能力でもあるだろう。
 [撮影:上原愛]
[撮影:上原愛]
 [撮影:上原愛]
[撮影:上原愛]
劇場のなかに出現した、動物たちの生きる「街」。それを構成する舞台美術は作品参加メンバーが持ち寄ったモノらしい。劇場に「外」が持ち込まれ、内と外とが反転する。劇場は宇宙の缶詰か。しかし考えてみれば「街」も「劇場」もヒトの設けた勝手な区分に過ぎない。動物たちは「森」と同じように「街」や「劇場」にテリトリーを広げもするだろう。ヒトにとって舞台の上はどこにでもな(れ)る空間だが、動物にとってのそこはほかの空間とことさらに区別されるような場所ではない。棲みやすさの程度の差だけがそこにはあり、ある種の動物にとって劇場は比較的棲みやすい場所ですらあるかもしれない。だから、ヒトがいなくなった後の劇場に動物が棲みつくというのは十分にあり得る話だ。『一角の角』で映し出される吉祥寺シアターはヒト不在の劇場の、現実にあり得る姿なのだ。
 [撮影:上原愛]
[撮影:上原愛]
『一角の角』の配信と同じ時期、無観客の劇場そのものを「舞台」とした上演の映像がほかにもいくつか配信されていた。それらを観た私が改めて感じたのは劇場という場所の特別さと、そこで演劇ができる/観られることへの悦びや感謝だった。『一角の角』の感触はそれらと異なっている。この作品でもっとも長く映し出されるのは劇場のロビーだ。舞台や客席といった劇場らしい場所は僅かな時間しか映し出されない。『一角の角』は劇場を劇場という機能を持つ場所としてではなく、単にそのようなかたちの、あるいは劇場としての機能を失ってしまった空間として映し出しているようですらある。今回のコロナ禍で多くの演劇関係者は劇場という場所の抱える脆弱性を痛感することになった。だが、そもそもウンゲツィーファ/本橋はこれまでもほとんどの作品をギャラリーや自宅などの非劇場空間で上演してきたのだった。だから、たとえすべての「劇場」という場所がなくなってしまったとしても、「劇場」に集まるという演劇の「かたち」が失われてしまったとしても「野生の演劇」は強かに生き残るだろう。
『一角の角』は和久井による編集と映像の追加を経た有料版が8月7日から配信される予定だ。
 [撮影:上原愛]
[撮影:上原愛]

公式サイト:https://ungeziefer.site/
関連記事
ウンゲツィーファ『ハウスダストピア』| 山﨑健太:artscapeレビュー(2020年07月15日号)
映画美学校アクターズ・コース『シティキラー』| 山﨑健太:artscapeレビュー(2020年04月15日号)
ウンゲツィーファ『転職生』| 山﨑健太:artscapeレビュー(2018年04月01日号)
2020/07/15(水)(山﨑健太)
須藤崇規『私は劇場』 week7

会期:2020/07/14~2020/07/17
パフォーミング・アーツを中心に記録映像を手がける映像ディレクター、須藤崇規によるオンラインパフォーマンス。5月25日より開始され、毎週複数回、YouTubeで生配信され、内容は毎回異なる。本評では、7週目の7月14日の配信内容を取り上げる。
黒画面に白い文字がリアルタイムで入力され、キーボードを打つ音や車の走行音などの環境音が聞こえてくる。本作の構造はいたってシンプルだ。だが、配信時刻が近づくと日付の下の現在時刻が1分ごとに入力/修正され、アーカイブは非公開という「リアルタイム」の重視、ラフなようで周到に計算された音響、「私からあなたへの語り」という親密性、そして思索的な文章と「文字」の入力/黙読/消去という行為そのものによって、「主体」の所在や交換、簒奪の暴力性について問いかける。それは、「演劇」のフィクショナルな仮構の基盤をメタ的に問いつつ、ディスプレイの「向こう側」とこちら、「いまここ」とアクチュアルな世界的出来事とを隔てる距離を再想像/架橋しながら、「劇場」を再定義し直す深い射程を備えていた。
冒頭、現在時刻の表示に続き、「私は文字です」という文言が入力される。この自己言及的な一文は、それをディスプレイ上で「あなた」が読むとき、入力する「私」と黙読する「あなた」とのあいだで、主体の入れ替えや曖昧化が起こっていることについての思索へと展開する。また、手紙(物質)とは異なり、メールの送信は「情報のやりとり」のようだが、実際は「コピーの送信=自己複製」であるとも述べられる。ここで、本作のタイトルおよび題字デザインにも注意を払う必要がある。日本語タイトルは「私は劇場」だが、それは反対側から読まれる鏡文字として裏返っており、さらに英語で表示されたタイトルは「The Theater is You」と、意図的な(私/Youという訳語および主語の)ズレをはらんでいる。この二重性とズレは極めて示唆的だ。「私」と「あなた」の交換可能性、「翻訳」がはらむ(言語に加え)発話主体の置換、鏡像と反転、透明なディスプレイを介して向き合う「こちら」と「向こう側」、その共有可能性とズレ。ここで、黒画面はすなわち劇場のブラックボックスの謂いであり、そこに浮かび上がる白い文字は「台詞」や「字幕」であるとすれば、本作の問題意識はまずもって、「演劇」と発話主体の問題を扱うことにあると言える。
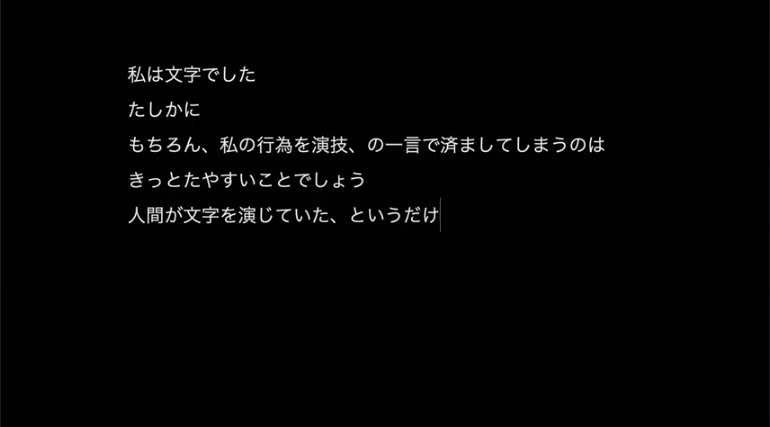
『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
だが、こうした「遊戯(Play=演劇をめぐるメタ的思索)」ではいられない事態になってきたと、「文字」は告げ始める。「世界は文字であふれている」と述べたあと、話題は、香港で国家安全維持法が施行され、「香港独立!」という言葉がデモで使えず、白紙のプラカードを掲げる抗議に変わったことへと移る。この抗議について「私」が何か書けば、「配信」すなわちコピーの拡散を通じて「安全」ではなくなるかもしれないと、「私」は怯え、逡巡し、入力した文章を何度も修正し、口ごもる。いつの間にかキーボードの入力音も環境音も消え、無音が緊迫感を高める。カーソルが震えながら「今まで打ち込まれた入力画面」を辿り直し、もう一度書き出し部分に戻り、書かれた内容を「消去」する。
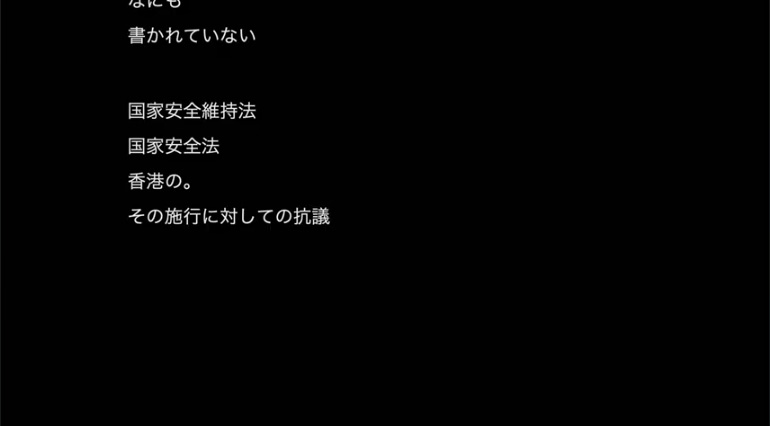
『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
「消去」の暴力を自ら実行したあと、再び「こんばんは 私は文字です」という一文の入力が反復される。そして、この「暗いディスプレイ」が「私」と「あなた」の出会う場所であったこと、すなわち束の間でも「劇場」へと変容していたことが語られる。再び、キーボードの入力音と環境音が流れ始め、現実世界の手触りを取り戻していく。「もう知っているもの、すなわち過去に出会い直すためだけなら、あなたはもう劇場へは行かないだろう」「でも、劇場は、まだ知らないものに出会う場所です」。「ここが劇場」、すなわち「私」と「あなた」が共に立ち合い、出会う場所を「劇場」として希望的に肯定し、再定義しようという、ささやかだが高らかな宣言で締めくくられる。ノイズの音量が、祝福するように加速していく。
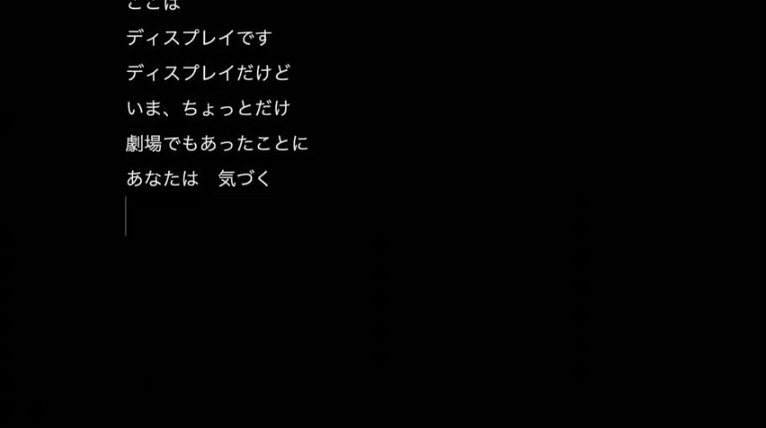
『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
須藤によって「限界劇場 Marginal Theater を作る試み」と定義された本作は、「主体」の変換や転移という「演劇」の原理的要素に自己言及し、香港の白紙デモというアクチュアルな事態とその距離感をディスプレイを隔てた「私」と「あなた」のそれへと敷衍したのち、「劇場」の概念的拡張を試みる。「限界劇場」、すなわちミニマルに切り詰めた手法によって概念的・物理的限界の拡張を同時に推し進める、優れた試みだった。
題字:内田圭
公式サイト:http://sudoko.jp/theaterisyou/
関連レビュー
須藤崇規『私は劇場』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年06月15日号)
2020/07/14(火)(高嶋慈)
シアターコクーンライブ配信『プレイタイム』

会期:2020/07/12
シアターコクーン[東京都]
コロナ禍で約4ヶ月休館していた劇場、シアターコクーンの「再始動」プログラムとして企画された「ライブ配信のための演劇」。観客席も用意されているが、筆者は企画主旨のライブ配信を鑑賞した。照明・音響装置、オーケストラピットの昇降、裏方スタッフの労働など、劇場の物理的機構それ自体のオーガニックな運動を作品化する、梅田哲也の『インターンシップ』が原案。本企画では、演出家の杉原邦生を迎え、岸田國士の戯曲『恋愛恐怖病』(1926)を森山未來と黒木華が演じ、ダンサーの北尾亘(Baobab)やミュージシャンの角銅真実が加わった。
冒頭、懐中電灯の光が暗闇をまさぐり、無人の劇場バックヤードの機材が照らし出される。小さな星のような灯がポツポツと灯り、やがて眩いライトが強烈な光を投げかける。それは、休館の仮死状態の眠りから劇場を目覚めさせる、(疑似)太陽の光だ。低いモーター音のうねりとともに、歯車が回転し、規則正しく並んだロープが巻き上げられ、バトンに吊られた照明機材が上昇していく。それは、劇場の巨大な体内に張り巡らされた、血管、神経、内臓組織だ。カメラは、胎動の音とともに、巨大な体内のなかを迷路のように進んでいく。

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]
舞台袖の暗闇で、劇場の模型をライトで照らしながら眺めている男(森山未來)がいる。彼は台詞を発しながら、狭い通路や階段をライトで照らして探検のように進み、彼の台詞を引き取って続ける女の声に導かれるように、舞台の上へ姿を現わす。そこは、裏方スタッフが打楽器や木琴を運び込み、台本を持った女(黒木華)が歩き回っている、「準備中」の運動に満ちた空間だ。「南京豆が食いたくなった」「燈台に灯がつくまで、ここにいましょうね」「今日はなんだか重大な日だ。胸騒ぎがします」。台詞をリフレインさせ、台本の「読み合わせ」をする二人の周りを、モップ掛けするスタッフが行き交う。上昇と下降を繰り返す吊り照明から身をかわす男の動きはダンス的なムーブメントに接近し、一方その傍らでは、裏方スタッフの恰好をした別の男(北尾亘)がスポットライトのテストの下で回転している。無機的な機械音のノイズ、スタッフの業務連絡、マイクチェックなどの作業音が楽器のチューニングやハミングと交じり合い、ハーモニックに調和していく。ゆっくりと旋回するカメラは、薄暗い客席通路の階段を降りて座席につく観客の姿を映し出す。その反対側の、半透明の幕で遮られた舞台上では、「海面」を演出する青いシートがふわりと掛けられ、生き物のように呼吸する。チューニングの延長のような優しい音響が包み、夜明けを告げる鐘のような音が響き、深い霧笛を思わせる音が舞台上に「海」を目覚めさせる。「開演」、そして衣装を着替えた男と女は、海を見下ろす桟橋のような空中のブリッジに立ち、互いの恋愛観と結婚観を語るなかに恋の駆け引きとプライドが入り混じる会話劇が始まる。煮え切らない男を残して女は立ち去り、傷心の彼は、自己の分身のようなもう一人の男にモノローグを吐露し、シンクロしたダンスムーブメントを展開する。

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]
「演劇」が息づき始める空間を、映像ならではのカメラの運動性を活かして見る者を惹き込み、俳優・ダンサーを脱中心化し、光と影、さまざまな人や機材が交通する活性化された空間として捉え、フィクションの立ち上げをワンカットの「ドキュメンタリー」として撮る。ここで本作の賭け金は、梅田哲也の『インターンシップ』を原案として発展的に拡張させたことにある。劇場の物理的機構の運動や裏方スタッフの作業そのものを作品の素材として用いる『インターンシップ』のサイトスペシフィック性は、「どの劇場で上演しても『コンテンツ』は同じ」という同一性の担保を批評的に解体し、(国内ではKAATに次ぐ)新たな劇場での上演には意義がある。それは、「コロナ禍後の再始動」という面では成功した一方で、「上演批判・劇場批判という作品の本質的要素を、ドラマの充填によって上書きし、損ねてしまう」という両義的な結果となった。また後述するが、秀逸なカメラワーク(渡邉寿岳)は本作の特筆すべき点である一方、「オンライン配信」と「劇場での観劇」の両立は可能かという新たな課題を突き付けた。
私見では、『インターンシップ』のコアは、「舞台上に見るべきものは何もない」という表象批判・劇場批判をリテラルに遂行しつつ、劇場の物理的機構そのものを用いて圧倒的な感覚的体験の強度をつくり出した点にある。通常は不可視の劇場機構や裏方スタッフの作業という「日常」を見せたあと、俳優やダンサーが一切登場しない空っぽの舞台を、即興的なチューニングから不協和と美しさの併存した音響世界が満たし、光と影の交替劇が、夜と死を潜り抜けて再び朝と復活を迎える、壮大で抽象的なドラマなきドラマの非日常性を体感させる。だが本作では、中盤=「開演」以降、「『恋人』と『友達』の境界線をめぐる、男女の駆け引き」「女に翻弄される男」「恋に破れた男のナルシスティックな苦悩」というドラマの充填に取って替わられ、照明や音響の有機的な運動性は劇伴的に退行してしまった。また、岸田國士の戯曲の採用も、「生誕130周年」という祝祭性しかなく、戦前に書かれた戯曲と現代との時代差―「自由恋愛」の登場した大正期/既存の結婚観の残存とのジレンマや、潜在的なホモソーシャルな欲望は掘り下げられず、ファンタジックな演出のなかに曖昧に溶かされてしまう。

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]
また、「定点」も「全体を見渡せる一望」も放棄し、巨大な器官としての劇場空間に潜り込み、洞窟か迷路のような内部を探査し、生きもののように蠢く劇場を捉えるカメラの運動感や流動性は、『インターンシップ』における(ドラマという)中心の欠如と、舞台上を自由に歩き回りながら体感する観客の運動性や移動の自由さとリンクする。その一方で、時折カメラに映り込む「劇場で本作を鑑賞する観客」は、客席に身体を固定され、古典的なプロセニアム舞台との対面を余儀なくされており、身体性の縮減は『インターンシップ』(の発展的展開)の鑑賞体験としては不十分さが残る。感染症が完全に収束するまでは、本作のように、オンライン配信と劇場での上演の並行が(実験性としても収益の面からも)摸索されていくだろう。本作は、「オンラインのライブ配信」の試みとしては成功していたものの、「実際の劇場での鑑賞体験」とのバランスをどう取るか、という困難な課題を改めて浮き彫りにしていた。
なお本作は、7月31日~9月2日の期間、オンデマンド配信が予定されている。
公式サイト:https://www.bunkamura.co.jp/cocoon/lineup/20_playtime/
関連記事
TPAM2018 梅田哲也『インターンシップ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)
2020/07/12(日)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)