artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
田凱「取るに足らないくもの力学」

会期:2021/08/19~2021/09/12
コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]
田凱は1984年、中国・河北省生まれの写真家。2014年に日本写真芸術専門学校を卒業し、2018年の第19回写真「1_WALL」でグランプリを受賞した。
その、故郷の石油産業の街を舞台にした叙事詩的な作品「生きてそこにいて」と、今回の「取るに足らないくもの力学」との印象はかなり違っている。以前のような、やや距離を置いて撮影した風景や人物写真は、今回の出品作にはあまりなく、被写体との関係が親密になってきているように感じた。会場構成も、大小の写真27点を撒き散らすように壁にインスタレーションし、より融通無碍なものになっている。直貼りのプリントとフレームに入れた写真を併用しているのも、これまではなかったことだ。日本滞在が長くなってきたことで、日本の写真家たちの「私写真」的な要素を、積極的に取り入れるようになってきたということだろうか。被写体の幅もかなり広く、人物、風景、モノ、植物などが混在している。共通しているのは、「アンバランスのバランス」といえそうな、微かな揺らぎ、微妙な気配を巧みに嗅ぎ当ててシャッターを切っていることで、そのあたりも日本の写真家たちの表現と呼応しているように感じる。
繊細な、いい仕事だとは思うのだが、以前のようなスケールの大きな画面構成が影を潜めているのはちょっと気になる。ことさら「中国人らしさ」を強調する必要はないが、自分の体質は大事にしてほしい。息の長い仕事ができる写真家なので、次は大作を期待したいものだ。
関連記事
田凱「生きてそこにいて」 |飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2019年08月01日号)
2021/08/25(水)(飯沢耕太郎)
CHIBA FOTO

千葉市美術館、千葉市中央コミュニティセンター ほか[千葉県]
「千葉市で初めて行われる芸術祭」として開催された「千の葉の芸術祭」の一環として、「写真芸術」に特化した「CHIBA FOTO」がスタートした。会場は千葉市中央区エリアと稲毛区エリアの2カ所に分かれ、あわせて13の会場で写真展が開催されている。出品作家は新井卓、宇佐美雅浩、金川晋吾、川内倫子、北井一夫、蔵真墨、佐藤信太郎、清水裕貴、楢橋朝子、本城直季、横湯久美、吉田志穂の12名、それに稲毛海岸の歴史を写真で辿る「海の記憶を伝える 稲毛アーカイブ展」(千葉市民ギャラリー・いなげ 2階)が加わった。
第1回目ということで、まだ手探り状態だが、中堅以上のすでに実績のある写真作家をフィーチャーして、クオリティの高い展示を実現しようとした意図はよく伝わってきた。千葉県在住、あるいは千葉県出身の宇佐美雅浩、川内倫子、北井一夫、佐藤信太郎、本城直季らは、それぞれ自分とかかわりの深いテーマで出品している。父親がJFEスチール(旧川崎製鉄)の千葉工場に勤めていた宇佐美雅浩が、同社社員の協力を得て制作した演出的な群像写真「宇佐美正夫 千葉 2021」(そごう千葉店9階 滝の広場)の展示など、そのコンセプトがしっかりと実現していて見応えがあった。
千葉と直接かかわりのないテーマで出品した作家の場合も、「旧神谷伝兵衛稲毛別荘」の2階スペースで展示された横湯久美「時間 家の中で 家の外で」のように、高度な内容の作品がそれにふさわしい器を整えて展示されていた。会場デザインを統括したアートディレクター、おおうちおさむの能力の高さが充分に発揮されていたといえる。
課題として感じたのは、13の会場が広くちらばっているので、1日で全部回るのはかなりむずかしいということ。わかりにくい場所も多いので、どう回ればいいのかを細かく指示したマップが必要だろう。また、クオリティの高い作品だけが並ぶと、逆に均質な印象が生じてくる。いい意味での玉石混交というか、学生や若手の写真家たちのエネルギッシュな作品も交えるといいかもしれない。長く続いてほしい企画なので、来年以降に期待したい。
公式サイト:https://sennoha-art-fes.jp/chibafoto/
2021/08/22(日)(飯沢耕太郎)
川内倫子『Des oiseaux』

発行所:HeHe
発行日:2021/06/27
元田敬三の『渚橋からグッドモーニング』(ふげん社、2021)もそうなのだが、新型コロナウィルス感染症拡大による緊急事態宣言は、写真家の意識に大きな変化をもたらしたようだ。川内倫子が2020年4月から6月にかけて撮影したのは、千葉の自宅付近で見つけたツバメの巣である。口を開けて餌を待つ雛鳥たちが、次第に大きくなり、もうすぐ巣立ちというところまで成長していく。その間に、季節の変化を示す身辺の風景が挟み込まれている。
川内がツバメたちにカメラを向けたのは、日本中が死の影に覆い尽くされていたこの時期だからこそ、逆に「いのち」が大きくふくらんでいく様子に心惹かれたからだろう。ツバメの営巣は、毎年の見慣れた眺めだが、とりわけ2020年から2021年のコロナ禍の時期においては、特別な意味をもって目に飛び込んできたのではないだろうか。川内はつねに生と死の狭間に鋭敏な意識を持ち続けてきた写真家だが、この時期にはそれが特に研ぎ澄まされていたように感じる。
とはいえ、写真からはそんな切迫感はほとんど感じられない。せっせと餌を運ぶ親鳥も、それを待ち望む雛鳥たちも、「いのち」そのものを体現した姿で、柔らかな光に包み込まれて写っている。川内の仕事としては、メインのものとは言えないかもしれないが、「Des oiseaux(On birds)」というタイトルを含めて、とてもよく考えられ、しっかりとまとめ上げられた写真集だ。なお、本書はフランスのEditions Xavier Barralから刊行された写真集の日本語版である。
2021/08/18(水)(飯沢耕太郎)
元田敬三『渚橋からグッドモーニング』
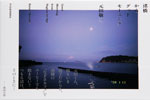
発行所:ふげん社
発行日:2021/08/18
元田敬三は、強い存在感を発する人物に路上で声をかけ、正対して撮影する写真を中心に発表してきた。だが、次第に自分の写真のあり方に疑問をもつようになり、2017年から日付を入れる機能がついたコンパクトカメラにカラー・ポジフィルムを詰め、身の回りの出来事にカメラを向けるようになる。日常の光景をスライドショーの形で発表するトヨダヒトシの仕事を知り、共感とリスペクトを覚えたということもあったようだ。
その「写真日記」のシリーズは、2020年6月にコミュニケーションギャラリーふげん社で開催された「東京2020 コロナの春~写真家が切り取る緊急事態宣言下の日本~」展に出品され、同年9月~10月の同ギャラリーでの個展を経て、小ぶりだが厚みのある写真集にまとまった。
写真集には、2018年7月から2021年5月にかけて撮影した365枚の写真がおさめられている。ページをめくっていくと、2020年4月から5月の新型コロナウィルス感染症拡大にともなう緊急事態宣言期間を挟んで、写真の質が微妙に変わっていることに気がつく。行動範囲が狭まり、神奈川県逗子の自宅近辺の「空と海」に目を向けることが多くなってくる。タイトルの「渚橋」というのは、早朝のアルバイトに出かける時に必ず通る桟橋の近くの、富士山を望む橋のことだ。一緒に過ごす家族にカメラを向ける機会も増えた。その間に、母親の入院と死という大きな出来事もあった。
淡々と気負いなく綴られた「写真日記」だが、どの写真を選び、どう組み合わせるのかは、緊密にプランニングされている。結果として、何事もなく過ぎていくように見える日々の断片が、特別な輝きを帯びて目に飛び込んできた。一見地味な仕事だが、このような作業をベースにすることで、写真家としてのさらなる飛躍を期待できるのではないだろうか。
関連記事
元田敬三「渚橋からグッドモーニング」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年10月01日号)
2021/08/18(水)(飯沢耕太郎)
コウノジュンイチ写真展「遠ざかる風景」

会期:2021/08/09~2021/08/22
ギャラリー蒼穹舎[東京都]
コウノジュンイチがギャラリー蒼穹舎で発表し続けている写真の世界は、このところほとんど変わりがない。2015年に写真集『ある日』(蒼穹舎)を刊行してからも、一定の撮り方、見せ方にこだわり続けている。8月9日~15日、16日~22日の2部構成で展示された本展でも、旅の途上と思しき光景を、やや距離を置いて撮影し、赤錆のような色調に焼き付けたプリントが並んでいた。道を行く人、路傍の猫、寂れたたばこ屋、公園のベンチの後ろ姿の人物、金魚のクローズアップなど、既視感を感じさせる眺めを丁寧に拾い集めている。まさに「遠ざかる風景」というタイトルそのものの写真群である。
見方によっては、変わりばえのしない、後ろ向きの写真の集積といえるが、展示を見ているうちに、その私小説的な味わいが、じわじわと心に食い込んでくるように感じた。ここから何かが生まれてくるかといえば、あまり期待はできないだろう。だが、その赤錆色の眺めは、意外に長く記憶に残っていきそうな気がする。これもまた、日本の写真家たちが長年にわたって積み重ねてきた、日記や随筆のような写真行為、写真表現のあり方のひとつの到達点といえるかもしれない。そう考えると、コウノの写真のたたずまいは、日記的な文章と相性がよさそうにも思える。写真とテキストを組み合わせた展示も考えられるのではないだろうか。
2021/08/16(月)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)