artscapeレビュー
2020年06月15日号のレビュー/プレビュー
クレア・ビショップ『ラディカル・ミュゼオロジー』
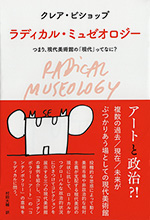
翻訳者:村田大輔
発行所:月曜社
発行日:2020/04/30
『人工地獄―現代アートと観客の政治学』(フィルムアート社、2016)、「敵対と関係性の美学」(『表象』05、2011)の邦訳が紹介されている美術史家・批評家のクレア・ビショップ。本書は、副題の「つまり、現代美術館の『現代』ってなに?」が示すように、「現代美術館」における「コンテンポラリー」の意味を問い直す美術館論である。
ビショップはまず、ロザリンド・クラウスの論考「後期資本主義的美術館の文化理論」(1990)を引きつつ、グローバル資本主義下における現代美術館のあり方を批判する。それは、スター建築家の署名を冠した巨大で派手な建造物の中で、(白人男性が多い)スター作家の個展が開かれるという、「新しさ、クールさ、フォトジェニック」といった「イメージの水準」での「コンテンポラリー」を劇場化する装置に過ぎず、コレクション形成を通した歴史との対話が軽視されているとビショップは指摘する。
またビショップは、「コンテンポラリー」の定義を時代区分で定める態度にも懐疑的だ。それは、「第二次大戦後」、「1960年代」、「冷戦終結の1989年」と、時代の変遷によって絶えず揺れ動いてきたからだけではない。そもそもそうした歴史認識自体が覇権的な西洋中心主義であり、非欧米圏のなかでも、(旧)共産圏、旧植民地およびその終結時期の差異により、「現代」の開始をどこに措定するかが異なるからだ。
ビショップはさらに、「イズムの交代史」としてのモダニズムに顕著な単線的な歴史記述の最先端に刹那的な現在として「コンテンポラリー」を位置づける態度も、未来への前進の代わりに「停滞した現在」しかないというポストヒストリカルな醒めた態度も退ける。これらに代わってビショップが提示するのは、複数の時間性が乖離しながらも重なり合う「弁証法的同時代性」であり、それは過去を通して現在の状況を理解・診断し、その変革の可能性を探る「新しい政治的想像力の基盤」(32頁)であるという。
こうした「弁証法的同時代性」の実践領域としてビショップが評価・分析するのが、コレクションを持つ現代美術館である。歴史的な文化認識の指標の保管庫でありつつ、新たに加わる収集作品によって未来に予見されるオルタナティブな価値基準をつくり上げていくコレクションは、「
ここで、「弁証法的同時代性」の実践領域である「コレクションを持つ現代美術館」と比較されるのが、グローバル化されたビエンナーレと、「年代順展示の廃止に代わって導入されたテーマ展示」である。前者は歴史から切り離された「現在主義」の追認であり、後者は多様な歴史的・地理的差異を新奇なテーマのもとに捨象し、交換可能なものとして等価にしてしまう相対主義であり、市場迎合的であるとして批判される。
では、ビショップが提起するコレクション展示の新たなパラダイムとはどのようなものか。ビショップはそのモデルを、ファン・アッベミュージアム(アイントホーフェン/オランダ)、ソフィア王妃芸術センター(マドリッド)、メテルコヴァ現代美術館(リュブリャナ/スロヴェニア)という三つの現代美術館のコレクション活動から、実践的に引き出す。再制作や過去の展覧会の再構築(ナチス時代の「退廃芸術展」「大ドイツ芸術展」[1937]も含む)によって、コレクション形成の力学を可視化し、過去との時代的距離のうちに現在を測定しようとするファン・アッベミュージアム。また、中東のコンセプチュアルなアートの紹介や、ピカソ作品のパレスチナ貸出プロジェクトは、現代オランダにおけるイスラムフォビアとの対峙を示す。ソフィア王妃芸術センターは、美術作品を映画、出版物、ポスター、雑誌といった視覚文化の時代的文脈に位置付けて紹介すると同時に、ファシズムと植民地支配の負の歴史への反省的思考を促す。メテルコヴァ現代美術館は、共産主義の失墜と旧ユーゴスラヴィアの内戦にどう向き合うかという歴史の表象についての問いを俎上にのせ、コレクション展示の「反復」と差異のうちにメッセージ性を込める。いずれも、欧米の周縁地域に位置し、アーカイブ資料を創造的に活用しながら、現在の政治的課題と歴史への反省的な眼差しの要請が、コレクションの再活性化を駆動させている点が共通する。
本評の執筆時の5月後半、すでにドイツや中国などでは美術館が再開し、非常事態宣言が全国で解除された国内でも6月初旬にかけて再開(予定)が進んでいる。世界的なパンデミックの終息とワクチンの実用化までは、大量集客型のブロックバスター展や海外からの大規模な作品貸出は難しく、国内の他館からの貸出や、特に自館のコレクションを中心に組み立てる企画が増えるだろう。それは、「収集と保存」という美術館活動の根幹に改めて光が当てられる機会である。と同時に、コレクション=価値の一元的な固定化ではなく、つねに生成される「現在」の眼差しの下でいかに過去を再編成し、未来への生産的な投企を行なっていくかという流動的なプロセスであることがより強く問われていく。そうした状況下で、本書の示唆はきわめて大きい。
2020/05/26(火)(高嶋慈)
ミッドサマー

5月末の段階では、東京の映画館が再開しておらず、やはりTOHOシネマズ仙台で『ミッドサマー』と『ブレードランナー』を鑑賞した。いずれも数名の入りしかなく、まだ映画館に人は戻っていない。後者はファイナル・カット版をスクリーンで初鑑賞したが、CGが当たり前になった現代から見ても、なんの遜色もないノワールなSFである。架空と実物の建築・都市を巧みに組み合わせた実在感が強烈だ。またリドリー・スコットらしい煙や霧、照明も美しい。人間よりも人間らしいレプリカントの設定が、作品を普遍的にしている。
さて、ようやく観ることになった話題の『ミッドサマー』は、様々な象徴を散りばめた美術、独特の建築デザイン(三角形のファサードをもつ黄色い神殿、変わった屋根形状の棟など)、音楽、衣装などを通じて、小さな共同体の世界観が綿密に構築されていた。ネットでも解説や謎解きを試みる多くのサイトが登場しているように、本作はすでにカルト的な人気を獲得している。
以前、新宗教の建築を研究した筆者にとって興味深いと思われたのは、サブカルチャーにおけるカルトの描き方である。通常、映画や漫画などでカルトが登場する場合、「実は教祖がひどい奴で、偽物の宗教が暴かれる」というのが、お決まりのパターンだ。しかし、本作はこの飽きるほど繰り返された物語とは違う。正確に言えば、教祖がいるわけではなく、昔から続く村の風習にもとづく夏至の祝祭なのだが、それがインチキだという構えはとらない。むしろ、あくまでも心を病む主人公の大学生ダニーの、心中で失った家族や、不安定な恋人との関係性を軸に、特殊な共同体を描いている。大きな家族に受け入れられ、傷心のダニーが再生する儀式というべきか。
そして客観的にはおぞましい出来事が起きているにも関わらず、笑顔の村人は明るく、花が咲き乱れる風景なのだ。また白夜のために、太陽が沈んでも完全な闇は訪れない。徹底して明るいのだ。だからこそ、ダニーが見せる最後のあの表情が、いつまでも余韻をもって記憶に残る。
公式サイト:https://www.phantom-film.com/midsommar/
2020/05/29(金)(五十嵐太郎)
ウィリアム・モリス 原風景でたどるデザインの軌跡

会期:2020/05/18~2020/06/28
宮城県美術館[宮城県]
久しぶりの美術館への訪問は、やはり関東圏よりもいち早く再開となった仙台の宮城県美術館となった。興味深いのは、新型コロナウイルスの対策のために、いつもと違うモードだったこと。例えば、行列はなかったが、吹き抜けのアトリウムから外構にまで続く、床に記された2m間隔のライン、受付の透明なシールド、チラシや作品リストなど手で触るモノの配布をしない(QRコードによってデータのダウンロードは可能)、講演などのトークイヴェントの中止ほか、会場内でも鑑賞者が立ち止まって密になりやすい映像による展示は止めていた。
現在、延期になっている筆者が関わる展覧会でも、感染防止のために、なるべく什器の間隔をあけること、来場者が不規則に動かないよう動線を誘導し、パーティションやサインによって固定化すること、接触型の展示や配布の中止、入場制限などを検討し、会場デザインの変更も行なわれる。これがニューノーマルとして定着するのかはわからないが、当面は展示の空間にも大きな影響を与えるだろう。

感染対策のために、宮城県美術館の床に記された2m間隔のライン
さて、「ウィリアム・モリス」展では、彼の生涯を振り返りながら、数多くの内装用ファブリックや壁紙のデザインが紹介され、後半では大阪芸術大学の協力を得て、書物の装丁などの活動が取り上げられていた。また織作峰子が撮影したケルムスコット・マナーなど、モリスの過ごした環境や風景の写真も活用されていた。もちろん、中世を理想化しつつ、民衆の芸術をめざし、モダニズムを準備した美術史・デザイン史における重要性は理解しているのだが、どうも動植物をモチーフとしたファブリックや壁紙の意匠は、野暮ったい。むしろ、モリスに影響を受けた小野二郎を軸とした「ある編集者のユートピア」展(世田谷美術館、2019)にも感銘を受けたように、同じ装飾としては、中世風の字体やレイアウトを通じたブック・デザインの方が個人的には好みである。
ちなみに、モリス展の最後となる第6章「アーツ・アンド・クラフト運動とモリスの仲間たち」は、明らかにモダンデザインに変化していた。例えば、ウィリアム・アーサー・スミス・ベンソンの卓上ランプはややアール・ヌーヴォーであり、建築家のチャールズ・フランシス・アンスレー・ヴォイジーによる壁紙のグラフィックは動植物を用いながら抽象度を高め、世紀の変わり目には新しいステージに到達したことが確認できる。

「ウィリアム・モリス」展の展示風景
関連レビュー
ウィリアム・モリス 原風景でたどるデザインの軌跡|SYNK:artscapeレビュー(2017年04月01日号)
2020/05/29(金)(五十嵐太郎)
池田安里『ファシズムの日本美術──大観、靫彦、松園、嗣治』

翻訳者:タウンソン真智子
発行所:青土社
発行日:2020/05/22
「日本ファシズム」という概念的枠組みを設定することで、戦闘や兵士を描かず、一見「政治色を帯びていない」非戦闘画が、いかに戦争と共犯関係を取り結んだかを検証する、意欲的な研究書。欧米圏のファシズム研究理論を取り入れた、日本の戦争美術研究である。著者の池田安里は、日本で生まれ育ち、北米で大学教育を受け、バンクーバーのブリティッシュ・コロンビア大学で執筆した博士論文が本書の元になっている。英語圏における日本の戦争美術研究の逆輸入という点でも、英語で執筆された文章の邦訳という手続きにおいても、外部化された視線の導入という構造が特徴だ。
本書で池田は、近年の欧米ファシズム研究を参照し、ファシズムを「個人主義・合理主義・物質主義などの近代の産物を非難し、集団主義・精神主義・国家の神話に傾倒するイデオロギー」(226頁)と定義した上で、戦時期の日本への適用を試みる(日本の左派研究者の見解を踏襲し、1931年の満州事変を戦争開始時期と見なす)。池田によれば、「日本ファシズム」とは、「ドイツやイタリアでのファシズムと同様、近代化によって破壊されかけている国家の『有機的な共同体(オーガニックコミュニティ)』の復活を掲げる二十世紀初頭のイデオロギー」を指し、「戦時中の日本がどのように近代化の影響に対抗し、伝統と純粋な日本人の精神によって結ばれた国家共同体の『再構築』を求めて民族主義に基づく全体主義を推し進め、民主主義・個人主義・自由主義を主張したアメリカやイギリスへの暴力を正当化したか」(14頁)に着目する。
「ファシズム美術は国家イデオロギーを反映したもの」(64頁)とする分析事例が、横山大観の富士、安田靫彦の中世の武士像、上村松園の美人画、東北の祭りと風習を描いた藤田嗣治の壁画である。
横山大観は、中国伝来の水墨山水画から距離を置き、近代以前の文学的背景や土着信仰から切り離された、「日本」の象徴としての富士にフォーカスを絞り、太陽や桜など同様の象徴的モチーフとのモンタージュによって新たな視覚言語をつくり上げた(ただし、「富士=日本の象徴」は、開国以降の欧米人によるオリエンタリズムの眼差しの内面化であるというねじれた構造がある)。安田靫彦の《黄瀬川陣》(1940-41)は、平家打倒のため、兄・頼朝の元に駆けつけた義経という「兄弟の結束」を描くなかに、(同じく近代以降に「創造」された)「死に殉じる武士道」と「儒教的な上下関係」を暗示する。
上村松園の美人画は、「質素倹約に励む女性」「夫と息子を天皇に捧げた女性」を描くことで、戦時中の模範的な日本人女性像を示す。また、浮世絵を参照しつつ性的要素を排除した松園について、「先駆的なフェミニスト」ではなく、「西洋に染まった性的なモガ」への反動として理解すべきだという主張も興味深い。「戦争協力」を通した公的領域への女性の参入は、「女性と国家は戦争を通してそれぞれの目標を達成するという共生的な関係を発展させた」(190頁)からだ。
東北の祭りと風習を描いた藤田嗣治の壁画《秋田の行事》(1937)は、柳宗悦の民芸や柳田國男の民俗学と呼応しつつ、「近代化に染まっていない、最も純粋で真正の日本」の表象として「東北」を特権視する。
こうした事例を通して本書は、国粋主義的な日本賛美、日本人特有とされる精神性、文化的真正性、(欧米やアジア諸国に対する)優越性、近代以前の美意識の「再発見」、「伝統」との繋がりの回復といった諸相を明らかにしていく。
本書の意義はまず、戦闘や兵士を写実的に大画面で描いた洋画中心の「戦争画(作戦記録画)」ではなく、見えにくい領域に光を当てることで、より包括的・多角的に戦争と美術を考える視座を開くことにある。「純粋な美の領域」か「政治的プロパガンダ」かに二分するのではなく、狭義の「戦争画」はファシズムの部分的要素であり、非戦闘画もまた同じイデオロギーのなかで機能していたと本書は指摘する。
さらに、本書のより広範な射程は、ファシズム・ナショナリズムとモダニズムとの結託・共犯関係である。「伝統的」とされる様式やモチーフを採用しつつ、「物語性や装飾性の排除」「写真的視覚」「平面性や幾何学性の強調」「構図の簡素化」といった(視覚様式としての)モダニズム受容により、刷新と近代化を図った日本画が、体制に与すること。「既存の体制や権威への異議申し立て」としてのモダニズムはファシズムによって消滅したという通念を覆し、モダニズムの美学が真逆の反動的政治学に「収用」(アプロプリエーション)され、変容して存在し続けたと筆者は指摘する。また、台湾や朝鮮といった帝国内部の植民地と同様、東北を「近代化されていない周縁」と眼差す構造は、モダニズムと表裏一体のオリエンタリズムや植民地主義を浮き彫りにする。西洋近代化の推進としての領土獲得は、その外部に「遅れた/純粋な文化の残っている」地域をつねに生み出し、これから帝国の支配領域に組み込まれるべき、未来完了形の領土として欲望するからだ。本書はそうした、「伝統」「古典」がモダニズムを取り込み、あるいは逆にモダニズムが「近代以前」を欲望しながら、国粋的なファシズムと結託していく輻輳的な回路を浮き彫りにしている。
2020/05/30(土)(高嶋慈)
エマヌエーレ・コッチャ『植物の生の哲学──混合の形而上学』

翻訳:嶋崎正樹
発行所:勁草書房
発行日:2019/08/30
本書の著者エマヌエーレ・コッチャ(1976-)は、イタリアに生まれ、現在はパリの社会科学高等研究院(EHESS)で教鞭を執る哲学者である。もともとは中世哲学の専門家として『イメージの透明性(La trasparenza delle immagini)』や、『天使(Angeli)』(ジョルジョ・アガンベンとの共編)をはじめとするさまざまな仕事を手がけてきたが、ここ数年は本書『植物の生の哲学』(2016)や『変身』(2020)をはじめとする、より一般的なテーマの著書により注目を集めている。昨今のコロナウィルス問題をめぐって、『リベラシオン』をはじめとする複数の媒体にコメントを寄せていることからも、同時代の哲学者としてのコッチャの知名度がうかがえるだろう。
さて、本書『植物の生の哲学』については、いくつかの紹介の仕方が考えられる。まず、人間および動物を中心としてきた従来の「生の哲学」に対する何らかのオルタナティヴを模索する読者にとって、本書の議論は大いに示唆に富むはずである。むろん哲学だけではない。生物学をはじめ、およそ「生」に関わるあらゆる学問において周縁に置かれてきた「植物の生」について新たな認識を得たいと願う読者にとって、本書は格好の入口となるはずである。
しかし本書の射程はそれにはとどまらない。著者コッチャの立場は、これまで相対的に軽んじられてきた「植物の生」を尊重しよう、といった程度の「穏当な」ものではないからだ。著者によれば、植物はこの世界にある生のうち、もっともラディカルな形態であるという。なぜか。それは植物こそが、人間や動物よりもはるかにこの世界に「密着」しており、周囲の環境と「溶け合って」いるからである。ゆえに「植物は、生命が世界と結びうる最も密接な関係、最も基本的な関係を体現している」(6頁)。
こうした見通しのもと、本書では植物における運動や四肢の不在が、まるごと肯定的なものとして捉えなおされることになる。植物は動物のように行為によって、あるいは人間のように意識によって、この世界に変化をもたらすのではない。むしろ植物は世界に「浸ること(immersion)」によって、さまざまな生が混合する環境そのものを作り上げている。植物に着目することではじめて見えてくるこの「混合の形而上学」こそ、コッチャが本書において提唱する新たな自然哲学なのだ。
つまるところ本書が提案するのは、呼吸、流体、混合といったキーワードをもとに世界を捉える、壮大なコスモロジー(宇宙論)であると言ってよい。本文の記述そのものは一貫して軽やかだが、全体に散りばめられた註の端々からは、同時代の思想的潮流──たとえば思弁的実在論──への容赦のない批判も垣間見える。本書の最終章(第15章)が唐突に哲学論によって締めくくられているのも、故なきことではない。「植物の生」をめぐる哲学は、最終的に、われわれの従来の思考の枠組みそのものの転換をともなわざるをえない──いくぶん簡略的なかたちながら、本書はそのようなところにまで届く、遠大な問題系を描出している。
2020/06/01(月)(星野太)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)