artscapeレビュー
2020年06月15日号のレビュー/プレビュー
須藤崇規『私は劇場』
会期:2020/05/28〜
『私は劇場』は映像ディレクターの須藤崇規によるオンラインパフォーマンス。映像ディレクターとしての須藤はこれまで、チェルフィッチュや東京デスロック、マームとジプシー、あるいは横浜ダンスコレクションなど、パフォーミング・アーツを中心に多くの記録映像を手がけてきた。演出意図を汲み取りそれを映像へと転換/拡張する能力に長けており、体験型のパフォーマンスや劇場以外の空間での上演の撮影を請け負うことも多い。私自身も2020年2月にy/nとして上演した『カミングアウトレッスン』で記録映像を担当してもらったことがあり、的確かつまったく退屈しない(舞台芸術の映像ではこれが難しい)編集に感銘を受けた。
そんな須藤が手がけたオンラインパフォーマンスはどのようなものだったのか。『私は劇場』とはいかにも挑戦的だ。「私」とは誰なのか。「劇場」とはどのような意味なのか。
内容は回ごとに異なり、1回あたりの上演時間は20〜30分程度。配信はYouTubeを通して行なわれ、アーカイブは公開されていない。ライブでのみ楽しむことができる形式だという点では舞台芸術に近いかもしれない。以下は私が視聴した6月3日(水)の内容に基づく記述となる。
形式はいたってシンプルだ。配信時刻が近づくと黒地に白文字で日付と時刻が表示され、時間の経過に合わせて時刻は1分ごとに入力し直される。配信時刻ちょうどになるとそのまま「上演」が始まる。『私は劇場』は画面上に映し出される文字によるオンラインパフォーマンスなのだ。どうやら文字はリアルタイムで入力されているようで、ときおりタイプミスも見られる。キーボードを打つ音の背後からは電車の走行音や人混みの喧騒も聞こえてくる。駅前だろうか。あるいは線路沿いの窓際か。「あなた」と語りかけてくる「私」と過ごす時間は、キーボードを打つ音が聞こえる距離感からか、なぜかしら親密なものに感じられた。
 『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
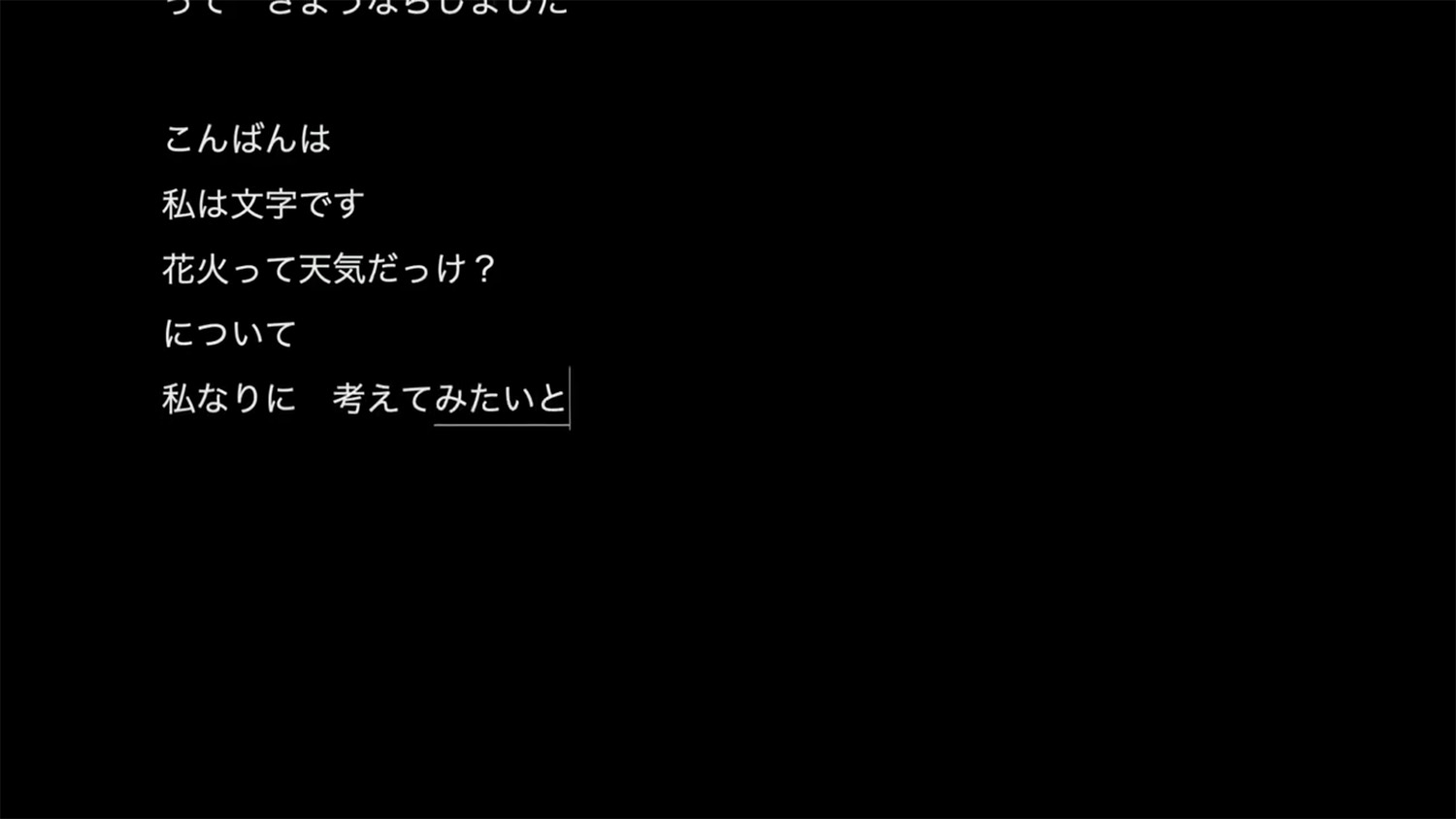 『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
「こんばんは 私は文字です」という挨拶を踏まえれば、『私は劇場』というタイトルは「文字は劇場」と変換され、なるほどそれはひとつの納得できる答えではある。それが戯曲でなくとも、文字を読むという行為には演劇的な何かがある。誰かが書いた文字を読むとき、私はなかばその「誰か」になっているだろう。文字を読む時間は文字を書く時間と重なり合う。文字は演劇の生まれる場所、すなわち劇場だ。
3日(水)の話題は「花火って天気だっけ」。これはどうやら前日に予告されたものらしい。しかしこの疑問はすぐに「花火は文字です」「天気は文字です」という二つの文章に基づいた(間違った)三段論法によって「私って私だっけ」というアイデンティティを巡る問いにジャンプし、「私」はそれにうまく答えることができない。「私」は続けて「私が誰かを傷つけることに無責任でいたくないって思っているのか」「ちゃんと責任を取りたいと思えているのか」と問いを発し、しかし「そこ」に存在しているのは「私」の意志ではないとも言う。
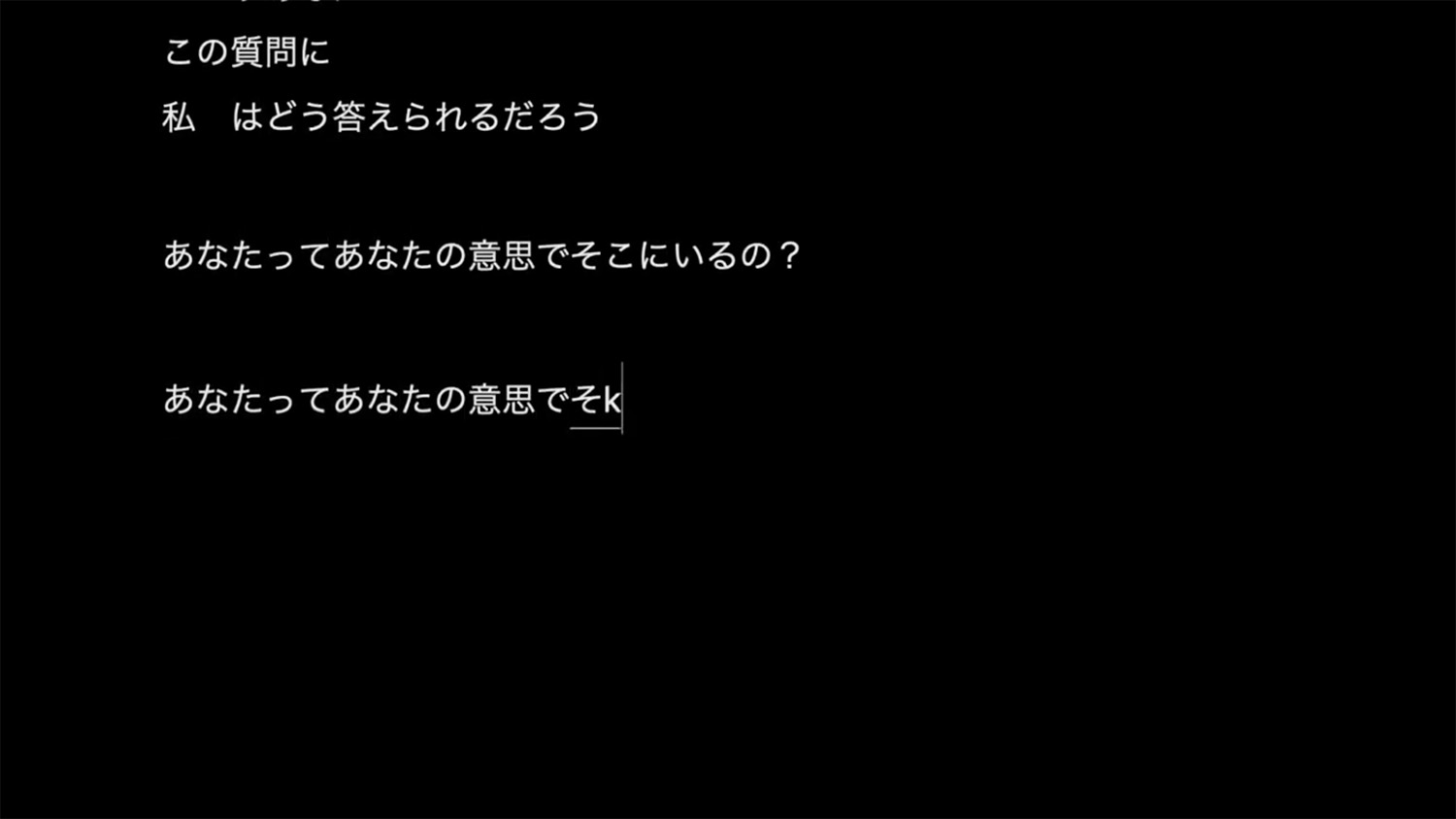 『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
「私」は例えば「別の国で自分たちの尊厳を守るために立ち上がろうと必死でしている人々」「その人たちが掲げようとしているプラカード」にもいて「いまもいますよ」と言う。これはもちろん、2020年5月にミネソタ州ミネアポリスで白人警官が黒人男性に暴力を振るい死に至らしめた事件に端を発する大規模なデモを念頭に置いたものだろう。気づけば打鍵音も周囲の音も消え、無音のなかで流れる文字に親密さはない。私は遠い国の、しかし決して遠くはないはずの問題に思いを馳せる。主体と意志、発せられた言葉/文字と責任。
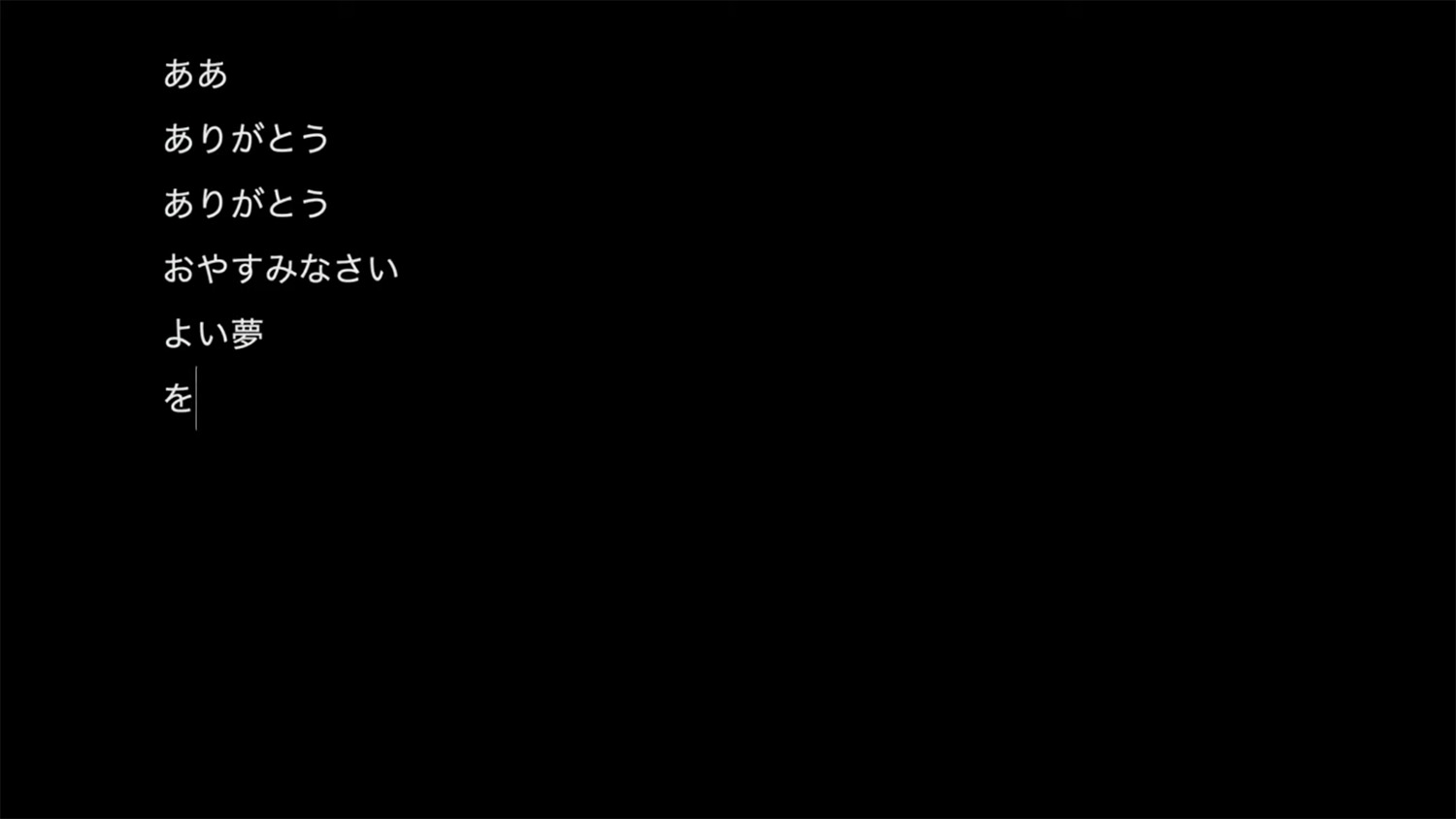 『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
演劇は「いまここ」にそれとは異なる時間をより合わせ、同時にその隔たりを改めて顕在化する。『私は劇場』はシンプルな形式を使って軽やかにそれをやってのける優れたオンラインパフォーマンスだ。配信は少なくとも7月初旬までは続くことが予告されている。
公式サイト:http://www.sudoko.jp/
2020/06/03(水)(山﨑健太)
藤原辰史『分解の哲学──腐敗と発酵をめぐる思考』

発行所:青土社
発行日:2019/07/10
新型コロナウィルスの感染拡大とともにあったこの数カ月間、国内外を問わず、さまざまな人々がこのウィルスと、それがわれわれの社会におよぼす政治的・経済的・文化的影響について言葉を発してきた。むろん、それはいまだ過去形で記述されうるようなものではなく、現在もまたその只中にあることは確かだろう。とはいえ目下のところ、そのうちもっとも広く読まれた日本語の文章のひとつが、藤原辰史「パンデミックを生きる指針──歴史研究のアプローチ」★であることは断言してよいと思われる。今年の4月2日に発表されたこの学術的エセーは、「B面の岩波新書」というウェブ媒体で公開され、先行きの見えない現状を前に戸惑う人々に、文字通り一定の「指針」を与えることとなった。
ちょうどこのエセーの公表と前後して、著者・藤原辰史(1976-)のこれまでの著書を読み返していた。前掲の「パンデミックを生きる指針」は、農業史を専門とする著者が、約100年前のスパニッシュ・インフルエンザをおもな比較対象として、コロナウィルス感染拡大の渦中にある現在、および未来についての見通しを平易かつ求心的な言葉により示した名文であった。ここで著者は「虚心坦懐に史料を読む技術を徹底的に叩き込まれてきた」ひとりの歴史家として、パンデミックに直面した人々の「楽観主義」に警鐘を鳴らそうとしている。
他方、わたしの関心は、こうした「歴史研究のアプローチ」の見本とも呼べるようなエセーにではなく──もちろんそれはそれで興味深く読んだが──この著者が一貫した執念とともに取り組んできたひとつのテーマにあった。すなわち「食べること」である。
ここしばらく、気づけばいつも「食べること」について考えていた。むろん、わたし一人のみならず、自由な外出を大幅に制限されたこの約2カ月は、ふだんの日常においてその感覚を摩耗させていた人々にとっても、多かれ少なかれ「食べること」に意識的にならざるをえない期間であったはずだ。毎日の食事はひとり、もしくは同居する家族に限られ、友人や同僚といつものようにテーブルを囲むことは叶わない。食事のメニューは自炊かテイクアウトに限られ、自宅以外の空間で日常の息抜きをすることも難しい。道行く人々の減少と反比例して、Uber Eatsの黒いバッグを背負った自転車は日増しに目立つようになる。かたやスーパーマーケットはいつも以上に盛況で、リモートワークに切り替えることもできず、食べ物の流通を維持するために外で働いている人たちへの敬意は増すばかりである──等々。
さて、農業史家としての藤原辰史の仕事には、トラクターと戦車、化学肥料と火薬、毒ガスと農薬をはじめとする、いわゆる「デュアルユース」の問題がつねに中心にあった(『トラクターの世界史』中公新書、2017年など)。くわえてここ数年は、そうした狭義の歴史学の仕事にとどまらず、「食べること」から人間存在を──ひいては世界そのものを──根本的に捉えなおそうとする刺激的な試みが目立つようになった。「人間は、生物が行き交う世界を冒険する主体というよりは、生きものの死骸が通過し、たくさんの微生物が棲んでいる一本の弱いチューブである」(『戦争と農業』集英社インターナショナル新書、2017年、190頁)という達観したヴィジョンからさらに進んで、「分解」を鍵概念とする壮大なコスモロジーを開陳したのが本書『分解の哲学』である。
雑誌『現代思想』における連載を核とする本書の目次には、ネグリ=ハート、フリードリヒ・フレーベル、カレル・チャペックをはじめとする、一見すると接点を見いだすことが困難な名前がならぶ。あるいはまた、壊れたものに愛着を示す「ナポリ人」をめぐるゾーン=レーテルの見識、「糞虫」を活写するファーブル、あるいはそれを翻訳する大杉栄の筆の冴え、さらにはここ数年小さくないブームを巻き起こしている「金繕い」(金継ぎ)についての考察にいたるまで、本書が博捜するフィールドはきわめて広大だ。
終章「分解の饗宴」でまとめられているとおり、こうした多彩なトポスの先には、「食を通じた人間と非人間の関係の統合的分析」や「生と死という二項対立から漏れ出る生物および非生物の形態の分析」といった壮大な問題系が控えている。いずれにせよこうした「分解」論が、「脱領域的かつ拡張的に『食現象』を再考する」(318頁)ことに結びつけられている点に、個人的には何より興味をひかれる。それに「哲学」という言葉を冠することに、著者は「正直いまでもためらいがある」(324頁)という。だが、本書が投げかける問い、たとえば「なぜ、食べる方が『上位』で食べられる方が『下位』なのか」(239頁)という根本的な問いがひとつの「哲学」であることを疑う理由は、少なくともわたしには見当たらない。
★──藤原辰史「パンデミックを生きる指針——歴史研究のアプローチ」(「岩波新書編集部 B面の岩波新書」)https://www.iwanamishinsho80.com/post/pandemic
2020/06/05(金)(星野太)
デザインを記録し継承するもの展 グッドデザイン賞年鑑の10年・2010-2019

会期:2020/06/03~2020/07/14(※)
※本ギャラリーでは新型コロナウイルス感染防止対策として、場内の人数制限を行っています。希望日時に必ず入場したい人は「ファストチケット(無料)」をお申し込みください。
日本国内でもっとも知られたデザイン賞といえば、言わずもがなグッドデザイン賞だろう。日本国内では85.5%の人が「グッドデザイン賞を知っている・聞いたことがある」そうだ(公益財団法人日本デザイン振興会による2014年12月インターネット調査)。確かにGマークは「デザインが良い」というお墨付きになり、他商品との差別化を多少図れるかもしれない。しかしデザイナーの立場からすると、いわゆる“名誉”となるデザイン賞は世界にもっとたくさんある。例えばドイツのiFデザイン賞やレッド・ドット・デザイン賞などだ。その点で、設立から60年以上が経ち、やや飽和状態となったグッドデザイン賞自体にもブランディングが必要なのではないかと思う。つまりデザイナー自身が誇れる賞となるために。
2010年度にグッドデザイン賞審査委員長にプロダクトデザイナーの深澤直人、副委員長にグラフィックデザイナーの佐藤卓が就任したことを機に、受賞年鑑『GOOD DESIGN AWARD』が大幅にリニューアルした。深澤が「こんな存在感の本が欲しいんだ」と言って、それこそドイツのデザイン賞の分厚い年鑑をアートディレクターの松下計の目の前に置いたという。背幅が数センチメートルある、分厚く重いハードカバーの年鑑がこうして生まれ、以後、同じ装丁の年鑑が10年続いた。2010年当時、紙媒体はデジタル媒体に取って代わられると叫ばれていたにもかかわらず、時代と逆行するかのように、深澤は物質としての本を強くアピールしたのである。これはまさに年鑑を活用したグッドデザイン賞のブランディングの一環ではないか。

本展ではその10冊の年鑑を閲覧可能な方法で展示するとともに、編集、撮影、レイアウト、印刷、紙、装丁など、年鑑づくりに関する秘話を紹介している。例えば本文の紙は上質紙の「ヴァンヌーボスムース-FS」を基に紙色を変えたオリジナルで、「sandesi(サンデシ)」という名前がついているとか、ロングライフデザイン賞は全ページにわたって同じグレー背景で商品撮影をしているのだが、そのグレーの発色が転ばないように5色のインキで刷っているとか、非常にマニアックな秘話が公開されていて興味深かった。本に限らず何でもそうだが、細部を職人的に丁寧につくり込んでいくと、全体の精度が上がる。物質的な存在感とともに、精度の高い年鑑に仕上げたことは、グッドデザイン賞の価値を上げることにもつながったのだろう。さて2020年度からはアートディレクターが交代し、年鑑の制作方法も変わるという。次からはどんな形態で、どんなメッセージを伝えるのだろう。
公式サイト:https://www.g-mark.org/gdm/exhibition.html
2020/06/06(土)(杉江あこ)
範宙遊泳『バナナの花』#1

会期:2020/06/05〜
『バナナの花』#1は範宙遊泳が「むこう側の演劇」として始めた新たな試みの第一弾。合わせて発表された「むこう側の演劇宣言」で作・演出の山本卓卓は「場の共有こそが演劇の根源的なアイデンティティ」だとし、ならば「観客が赴く場所は、劇場であろうと野外であろうとオンラインであろうと、場であることに変わらない」「劇場を剥奪された我々は、新たな場をみつけ、その場所を劇場とすることができる」と力強く宣言する。「演劇は一度死んだのです。でもこれから蘇ります」とも。
今回、YouTubeの範宙遊泳公式チャンネルで配信されたのは連作の第一作。約15分と短めの映像(編集:埜本幸良)で物語の全体像はいまだ掴めないものの、オンラインという条件に対応しつついかにも範宙遊泳らしい導入となっている。映像は無料公開されているので、レビューの続きを読む前にぜひ本編をご覧いただきたい。
登場人物は二人の男。ひとりは33歳、独身、彼女なし、アルコール中毒、趣味はアダルトビデオウォッチング、元詐欺師、前科一犯のブドウヤバナナ、人呼んで「穴蔵の腐ったバナナ」。もうひとりは「穴蔵の腐ったバナナ」をマッチングアプリで「釣ろう」(=騙して小銭を稼ごう)とする百三一桜(ひゃくさいさくら)。「穴蔵の腐ったバナナ」は百三一から送られてきたメッセージを「釣り」だと見抜き、しかし「君は変われる」と励ましの言葉を送りつけた挙句に「これでおいしいものでも食べてよ」と1万円を課金する。百三一は反発と苛立ちを覚えながらも「会えませんか? 男ですけど」とメッセージを送るのであった。

#1で描かれているのはここまでだ。近年の範宙遊泳はいわゆる社会規範のなかで生きづらさを抱える人々を多く描いてきた。「穴蔵の腐ったバナナ」にせよ百三一桜にせよ、その意味でいかにも範宙遊泳らしい登場人物なのだが、物語の全貌が明らかでないいまの段階でそこに踏み込むことはひとまずやめておこう。だが、物語とそれを描く手法とは切っても切れない関係にある。山本自身の宣言の言葉を借りればそれは「むこう側」への想像力を起動させるためのものだ。
冒頭、長方形の画面の左半分に「穴蔵の腐ったバナナ」の自己紹介文らしきものが文字として映し出されていく。右半分はさらに四分割され、それぞれにどこか無人の室内を映している。自己紹介を読み上げる声。やがて四分割されたマスの左下に男(福原冠)が現われ「穴蔵の腐ったバナナがそれをマッチングアプリに書き込んだのは2018年6月」と語る。一瞬、彼が「穴蔵の腐ったバナナ」なのだろうと思うが、直後、左上のマスに男がもうひとりが現れる(埜本幸良)。どうやら彼こそが「穴蔵の腐ったバナナ」らしい。

範宙遊泳はプロジェクターとプレゼンテーションソフトを使って舞台上に文字などを投影し、それらと俳優を「共演」させることで観客の想像力に働きかける手法を用いてきた。現代を生きる私たちは、コミュニケーションの多くを文字=画面を介して行なっている。舞台/画面上に文字が投影され、観客がそれを読むという形式は、そのようなコミュニケーションのあり方を演劇に導入するための実践でもあるだろう。「想像力を使おう 言葉の先に人がいる」と「穴蔵の腐ったバナナ」は歌う。文字を読む私はその向こうの「相手」とコミュニケーションをしているつもりだが、それは私の想像力の産物でもある/でしかない。百三一桜という名前は「穴蔵の腐ったバナナ」が一方的に名づけたものだった。
だから、冒頭で福原を「穴蔵の腐ったバナナ」だと誤認する私の想像力は、ある意味では間違っていない。実際、作中に登場する「穴蔵の腐ったバナナ」のメッセージの多くは百三一=福原によって読み上げられることになる。私は「穴蔵の腐ったバナナ」の言葉を福原の声で受け取るのだ。
分割された画面で彼らの姿を映す四つのマスのうち二つはどうやら、彼らのスマホの画面=カメラ越しの風景らしい。そこにはときにセルフィーを撮る「穴蔵の腐ったバナナ」の様子が、ときにアプリに届いたメッセージを読んでいるらしい百三一の顔が画面いっぱいに映し出される。それらは残る2コマに映る固定カメラで捉えられた(=「現実」の?)彼らの姿と文字通り地続きだ。現代人の多くは「現実」と画面の中の二つの世界を生きている。曖昧に揺らぎ、ときに容易に乗り越えられてしまうその境界のあり方を示す映像表現が巧みだ。

そう言えば、「穴蔵の腐ったバナナ」がマッチングアプリに登録したのは、『君の友達が君自身だ』という自己啓発本を読んで友達をつくろうと思い立ったからだった。画面越しにコミュニケーションをする「友達」は私自身を映し出す。「むこう側」でもそうだろう。コミュニケーションはいつもすれ違っていて、それは画面越しだろうが対面だろうが変わらないのかもしれない。二人の男の出会いはどこに向かうのか(あるいは出会わないのか)。『バナナの花』#2の配信は7月初旬に予定されている。
公式サイト:https://www.hanchuyuei2017.com/
2020/06/07(月)(山﨑健太)
佐々木敦『小さな演劇の大きさについて』
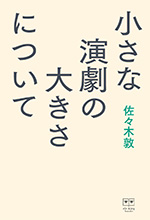
発行所:Pヴァイン
発行日:2020/06/20
批評家・佐々木敦による初の演劇論集『小さな演劇の大きさについて』がPヴァインから刊行された。これまで、テン年代以降(2000年代以降と言ってもいいかもしれない)の小劇場演劇を広く扱った書籍は徳永京子・藤原ちから『演劇最強論』くらいしかなく、それも2013年と7年も前の出版であることを考えると(ユリイカの「この小劇場を観よ!」特集も2005年と2013年に発行されたきりである)、本書は現在の小劇場で何が起きているかを知るためのいまのところ唯一の手段であり、演劇関係者必携の書となるだろう。
『小さな演劇の大きさについて』は三部構成。「『現代口語演劇』のアップデート」と題された第一部の目次に並ぶのは岡田利規/チェルフィッチュ、平田オリザ/青年団、松田正隆/マレビトの会、三浦基/地点といった名前だ。佐々木は『即興の解体/懐胎』(青土社、2011)の第二部でチェルフィッチュと青年団の演劇について論じており、章題の「アップデート」が示す通り、まずは彼らのその後の展開が論じられる。「即興」の問題系を論じるのに演劇が召喚されたのは、それが「現前性/一回性」と「再現性/反復性」の双方を本質とする芸術だからだった。いかにして相矛盾するそれらは可能となっているのか。マレビトの会や地点もまたそのような演劇の原理との関わりのなかで論じられ、読者は演劇作家たちの、そして佐々木の思考を通して複数の方向から演劇の原理へアプローチすることになる。
第二部は「アングラ・不条理・笑い」。第一部が原理論だとするならば対をなす第二部は存在論とでも呼ぶべきだろうか。ケラリーノ・サンドロヴィッチ/ナイロン100℃、松井周/サンプル、宮沢章夫/遊園地再生事業団、飴屋法水、古川日出男。彼らの作品の分析を通じ、人間と世界とがどのように存在しているか/し得るか、それをいかに語り得るか/語り得ぬかが論じられる。一般的に、不条理といえばアングラ演劇、アングラ演劇といえば60年代だが、不条理は決して過去のものとなったわけではない。それは通奏低音のようにいまもそこにあるのだ。
第三部には前二部とは異なり一貫したテーマはなく、また、コアな舞台ファン以外には名前も知られていないであろう作家/劇団も多数登場する。多くが30代以下の若手作家だ。
佐々木は前書きにあたる「小さな演劇の小ささについて」で「小さな演劇」の「『小ささ』には、大きなものをも含む、さまざまなことを考えさせてくれる、たくさんのヒントが潜んでいる」と書いている。だが、ほとんどの演劇はモノとしては残らない。ほかの多くの芸術と比べて、それらの演劇の「大きさ」が事後的に「発見」される機会と可能性は圧倒的に少ない。だからこそ、リアルタイムでそこにある「大きさ」を、その可能性を読み取り記述する伴走者が(おそらくほかのジャンル以上に)必要となる。第三部には伴走者としての佐々木の仕事が結実している。
一部二部で取り上げられた作家/劇団たちはすでに一定以上の評価を得ている。優れた作品に触発され書かれた優れた批評には当然読み応えがある。だが、佐々木はそれらの作品に向けるのと同じ、あるいはそれ以上の熱量をまだ若い作家/劇団の可能性を見出し記述することにも振り分けている。佐々木は半ば自虐的に自らを「生まれつきの、無類のマイナー好き、マージナル好きなのだ」と書いてみせたりもするが、私はここにこそ批評家の誠実と見識を見る。批評家とは未知に可能性と悦びを見出す者だ。第三部のタイトルは「新しい演劇はどこにあるのか?」。本書は小劇場演劇のシーンを網羅的に取り上げたものでは決してないが、多くの「新しい演劇」の可能性が記されている。本書を読み、ぜひとも「新しい演劇」のある場所に足を運んでいただきたい。
公式サイト:http://www.ele-king.net/books/007589/
2020/06/08(月)(山﨑健太)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)