artscapeレビュー
2021年01月15日号のレビュー/プレビュー
渦巻く智恵 未来の民具 しめかざり

会期:2020/11/28~2020/12/27
世田谷文化生活情報センター 生活工房[東京都]
2020年の年末、私は早々にしめかざりを自宅の玄関扉に飾った。注文していたしめかざりが早めに届いたせいもあるが、コロナ禍に見舞われた災厄年に一刻も早く別れを告げ、吉兆の訪れを願って新年を迎えたいという思いがあったのかもしれない。いままでしめかざりにそれほど興味はなかったのに、こんな気持ちになるなんて、人生は何があるのかわからない。本展へ足を運んだのも、こうした経緯があったからだ。本展を企画制作した森須磨子はグラフィックデザインの仕事のかたわら、全国各地へ「しめかざり探訪」を20年近く続ける、言わばしめかざり通である。その探訪の軌跡を物語る日本地図や記録写真を眺めていると、いやはや、こんな人もいるのだなと感心せざるを得なかった。また、元は神社に張られたしめ縄がどのような造形的展開を遂げて、「輪飾り」や「玉飾り」「前垂れ」といった系統のしめかざりになったのかを示した図式が非常にわかりやすく、そこにグラフィックデザイナーらしい視点も感じた。しめかざりは、福を授ける歳神様を正月に家に迎え入れるための目印である。その目印という点に、彼女はデザインの原点を見ているのかもしれない。
 展示風景 生活工房3F 第1室「しめかざり時空探訪」[撮影:本田犬友]
展示風景 生活工房3F 第1室「しめかざり時空探訪」[撮影:本田犬友]
 展示風景 生活工房3F 第1室「しめかざり時空探訪」[撮影:本田犬友]
展示風景 生活工房3F 第1室「しめかざり時空探訪」[撮影:本田犬友]
「月下のしめかざり」と題した展示室では、大晦日の夜をイメージした黒い空間に種々さまざまな形のしめかざりが展示されていて圧巻だった。形をしっかりと見せるために、彼女は橙や裏白(うらじろ)、譲葉(ゆずりは)などの装飾を取り除いて写真を撮り、記録するという。この展示室でも基本的に藁もしくは藁と紙垂(しで)だけのしめかざりが展示されていて、その試みがなんとも良かった。藁そのものの素の表情は迫力があり、人の手仕事をつぶさに見て取ることができたからだ。鶴、亀、松竹梅、海老、椀、杓子など、見たことのないしめかざりの形も多く、藁だけでこんなにも豊かな表現ができることに驚いた。しめかざりをつくりながら、人はそこに願いを込めるのだろう。来年はどうか良い年でありますようにと。本当に、2021年は良い年になることを心から願いたい。
 展示風景 生活工房4F 第2室「月下のしめかざり」[撮影:本田犬友]
展示風景 生活工房4F 第2室「月下のしめかざり」[撮影:本田犬友]
公式サイト:https://www.setagaya-ldc.net/program/500/
2020/12/23(水)(杉江あこ)
お寿司『土どどどど着・陸』

会期:2020/12/25~2020/12/27
THEATRE E9 KYOTO[京都府]
「SF×稲作中心の古い行事が残るローカルなコミュニティ」という、一見、異色の組み合わせの演劇。だが、「見知らぬ異星に不時着してしまったエイリアン」=「新規の移住者」という視点から徹底して異化して描かれるため、「一過性のリサーチやレジデンスで地域の魅力を再発見/消費」という態度への強烈なカウンターとして機能する。
舞台中央には土のかまどと鍋が置かれ、その背後の板塀からは、柿の実をつけた枝が顔をのぞかせる。板塀の向こう側では、全身にキノコを生やした猿のような動物(ダンサーの竹ち代毬也)が身をくねらせ、柿の実をむさぼり、釜の中の飯を狙って侵入してくる。板塀の端には、ミニチュアの社(?)のような装置にご神体の白い蛇(?)のような不思議なものが巻き付き、この板塀は、家屋の内/外の境界であるとともに、人間/野生の領域を区切る象徴的な結界でもあるのだろう。

[撮影:松本成弘]
この簡略化された光景のなかに、着ぐるみのように膨れた宇宙服を思わせる衣装とヘルメットを付けた女性(筒井茄奈子)が立ち、混乱したモノローグをうわずった高い声で発し続ける。細い材木を円筒形に束ねた桶のような物体の中から、声(大石英史)が断続的に応答する。駄々をこねる幼い子どもとの会話、ご近所や地域の婦人会の人々とのやり取りのようだ。廃油を収集してロウソクを作るリサイクル活動、花壇の手入れなどの美化活動、食育という3つの「イインカイ・イインカイ」をはじめ、たくさんある自治会や婦人会、青年団の謎ルールの数々。意思疎通の困難さや価値観の齟齬は、会場のあちこちに仕込まれたスピーカーから流れる録音音声の効果とも相まって、壊れかけた通信機が発する混線した声を聴いているようだ。
あいさつ活動や見守りは「監視されている」という不安を焚きつけ、害獣の駆除は「よそ者としての疎外感」とオーバーラップする。一方、「不時着した異星で暮らす人々との会話」の合間には、田植えや農事に関するさまざまな一年間の行事が(実際に地域に住む女性2人によって)紹介され、自然のサイクルとともにある暮らしが示される。「私の生まれた星ではもっと個別だった」とつぶやく、「不時着」した女性。彼女は、古い行事を引き継ぐ食育活動での「のり巻き」づくりに対して、「私は負けない/巻けない」と宣言するが、最終的に待っているのは「(のり巻きを)巻けちゃった/負けちゃった」というオチである。「(命を)食べることの肯定、命の循環」という通奏低音が、緑と闇の濃い地域に暮らす実感として浮かび上がる。

[撮影:松本成弘]
地域に赴いてリサーチする滞在制作型の作品と本作が一線を画する特異性は、リサーチ対象をエキゾチシズムとして対象化するのではなく、自身を「エイリアン」の立場に徹底して固定化する視点の取り方にある。外部から侵入した観察者である自身の立ち位置は透明化したうえで、「珍しい風習や祭り、美しい自然、歴史の痕跡が豊富な地域」を一種の異文化として他者化するのではなく、そのようなものは所与の環境としてすでにそこにあり、自らを「その価値観やルールになじめないエイリアン」とする態度は、作・演出の南野詩恵の誠実さでもある。南野が主宰する「お寿司」はまた、衣装作家でもある彼女自身が手掛ける衣装と身体のあり方も注目だ。本作では、「SF」というフィルターに加え、「私の身体になじまない」異物感や防衛心理を強調する、服というよりも「装置」「拘束具」のような衣装によって、移住者として暮らす地域との距離が取れたのではないか。
ラストシーンで、上空から降ってくるのは、迎えに来た母船ではなく、正月を祝う鏡餅である。彼女は最後まで防護服のような宇宙服を脱ぐことはないものの、「それでも毎日ご飯は食べるし、この土地で生きていく」というしたたかさを感じた。

[撮影:松本成弘]
公式サイト:https://osushie.com/
2020/12/25(金)(高嶋慈)
プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRING
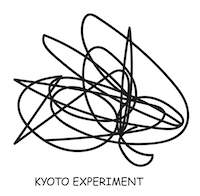
会期:2021/02/06~2021/03/28
ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、京都伝統産業ミュージアム、京都府立府民ホール“アルティ”ほか[京都府]
新型コロナウイルスの影響で、例年通りの秋開催から今春に会期変更となった「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRING」(以下KEX)。フェスティバルの立ち上げから10年間ディレクターを務めた橋本裕介に代わり、川崎陽子、塚原悠也、ジュリエット・礼子・ナップの3人が共同ディレクターを務める新体制に移行した。川崎とナップはそれぞれKEXで制作と広報を務めており、塚原はcontact GonzoとしてKEXに何度も参加してきた一方、「KOBE-Asia Contemporary Dance Festival #3」(2014)などでのディレクター経験も持ち、それぞれの経験や得意分野を活かした連携が期待される。併せて一新されたロゴも斬新だ。
プログラム構成の大きな変化は、国内外の先鋭的な作品を上演するプログラム「Shows」に加え、アーティストが協働して3年間にわたり関西の地域文化をリサーチする「Kansai Studies」、そしてトークやワークショップなどを通じて多角的に思考を深める「Super Knowledge for the Future(SKF)」の3本柱で構成される点だ。また、関西を拠点とするアーティストを積極的に取り上げ、アジア圏のアーティストの紹介に力を入れている点も、注目すべき変化である。
上演プログラム「Shows」では、関西より、ダンサーの中間アヤカと垣尾優、音遊びの会が選出。中間は、2019 年初演のソロ作品『フリーウェイ・ダンス』を、京都版としてリ・クリエーションする。ダンスの専門的な訓練を受けていない人たちから提供してもらった「初めて踊ったときの記憶」を「振付」として踊るこの作品は、自己/他者、ダンス/日常的な所作といった境界に加え、「出入り自由で庭のような上演空間」「『ごはんの時間』も挟む4時間に及ぶ上演時間」といった仕掛けにより、「ソロダンス作品」の既存の枠組みをゆるやかに解体させていく。contact Gonzoの元メンバーで、近年は自身のソロ作品も発表する垣尾優は、「ダンスそのものに正面から向き合うことで、混沌とした『動く』ことの原初的考察」になるという新作を発表予定。また、知的障害のある人を含むアーティスト集団「音遊びの会」は、即興的なセッションを中心に演奏活動を行なっているが、今回、小説家・作詞家・ラッパーのいとうせいこうを迎え、「音と言葉のセッション」をテーマにしたコラボレーションを行なう。同じく関西の音楽シーンの紹介という点では、BOREDOMS、想い出波止場など多数のバンドで活動してきたミュージシャン、山本精一のディレクションのもと、関西の実験的表現の系譜をたどるプログラムが組まれている。
また、「Kansai Studies」では、大阪の建築家ユニットdot architectsと、京都の演出家・和田ながらが、「水」をテーマに関西各地のリサーチを行ない、ウェブサイトでのリサーチ過程の公開を経て、2022年度に3年間の成果を発表する予定だ。

中間アヤカ&コレオグラフィ『フリーウェイ・ダンス』
[Photo by Junpei Iwamoto]
アジア圏からは、インドネシアのヴィジュアル・アーティスト、ナターシャ・トンテイと、タイの若手演出家、ウィチャヤ・アータマートが参加。ナターシャ・トンテイの『秘密のグルメ倶楽部』は、人体を模した料理を、ホストの彼女自身とパフォーマーが食べるというパフォーマティブ・ディナー。ポップでグロ可愛い世界観のなかに、カニバリズムや過剰消費といった問題が潜む。また、多くの国際フェスティバルで高い評価を受けたウィチャヤ・アータマートの『父の歌(5月の3日間)』は、バンコクの小さなキッチンを舞台に、亡き父を偲ぶ姉弟の会話を通して、個人的な日常のなかにタイの政治史が交差するさまを描き出す。

ナターシャ・トンテイ『秘密のグルメ倶楽部』
[© Natasha Tontey]
KEXは過去10年を通して、「常識」「タブー」を激しく揺さぶるような挑発的な作品を取り上げてきたが、その実験性やラディカルな批評性は健在だ。特にジェンダーやセクシュアリティ、身体の表象をめぐる思考を挑発的に展開するのが、オーストリアの振付家のフロレンティナ・ホルツィンガー、カナダの振付家・ライブアーティストのデイナ・ミシェル、カナダのアート&リサーチ集団、ママリアン・ダイビング・リフレックス/ダレン・オドネルによる3作品である。フロレンティナ・ホルツィンガーの『Apollon』(映像での上映)は、バレエの名作『アポロ』の神話的世界をベースに、6名の女性パフォーマーが出演。マシントレーニング、バレエのバーレッスンからスプラッターやワイヤーアクションが悪趣味なまでに展開し、女性の身体やジェンダー表象に問いを投げかける。デイナ・ミシェルは、ソロ作品『Mercurial George』の記録映像と新作映像作品『Lay them all down』の2本立てを上映。独自のダンス言語と繊細なジェスチャーで、自身のアイデンティティやセクシュアリティを問う。ママリアン・ダイビング・リフレックス/ダレン・オドネルは、各国でワークショップを重ねて上演してきた『私がこれまでに体験したセックスのすべて』の日本版を上演する。多様なバックグラウンドを持つ60歳以上のシニアたちが、リアルな性体験を通して人生を語っていくという対話型演劇だ。

ママリアン・ダイビング・リフレックス/ダレン・オドネル『私がこれまでに体験したセックスのすべて』(オーストラリアでの上演、2017)[Photo by Jim Lee]
最後に、舞台芸術全体に対する相対化の視線として、キュレーター・映像作家の小原真史が企画する展覧会「イッツ・ア・スモールワールド:帝国の祭典と人間の展示」がある。1903年に大阪で開催された第五回内国勧業博覧会で、アイヌ、沖縄、台湾などの先住民を「展示」した「学術人類館」をはじめ、19世紀末から 20世紀初頭に欧米諸国の博覧会で行なわれた同様の「人間の展示」の資料写真を紹介する。帝国主義と表裏一体の植民地主義や人種差別への検証とともに、家屋や生活用具を「舞台装置」のように設え、民族衣装をまとった「異民族」が日常生活を再現するさまを眼差す行為はある種演劇的でもあり、本展は、演劇あるいは劇場という装置に対する再帰的な批評性として機能するだろう。

小原真史「イッツ・ア・スモールワールド:帝国の祭典と人間の展示」「学術人類館」(第五回内国勧業博覧会)1903年、個人蔵
公式サイト:https://kyoto-ex.jp/
KYOTO EXPERIMENTロゴ © 小池アイ子
2020/12/25(金)(高嶋慈)
ベートーヴェン「第九」と『音楽の危機』

会期:2020/12/26
横浜みなとみらいホール[神奈川県]
年末になって、ようやく生のドラムが入った音楽をライブで聴くことができた。コロナ禍において執筆されたすぐれた芸術論である岡田暁生『音楽の危機—《第九》が歌えなくなった日』(中公新書)が指摘したように、「録楽」と違い、聞こえない音も含むような、リアルな空気の振動こそ、ライブの醍醐味である。そして同書が問題にしていた三密の極地というべき近代の市民文化の音楽とホールの象徴が、年末の風物詩となっているベートーヴェンの交響曲「第九」だった。壇上の先頭中央に指揮者と4人のソリスト、これを囲むようにオーケストラのメンバーがところ狭しと密集し、さらにその背後にひな段を組んで、合唱団がずらりと並ぶ。すなわち、大人数を前提としたスペクタクル的な作品である。無言の演奏だけならともかく、ハイライトの「歓喜の歌」では、一斉に飛沫が発生するだろう。果たしてコロナ禍において「第九」は可能か、というのが、『音楽の危機』の問いかけだった。また同書は、音楽の時間構造のほか、それが演奏される空間=ホールの刷新も提唱した芸術論でもある。筆者は2020年の暮れ、横浜みなとみらいホールにおいて、読売日本交響楽団の演奏による「第九」をついに聴くことができた。
当然、通常の演奏形態ではない。パイプオルガン前の高所の座席に観客の姿はなく、代わりにソーシャル・ディスタンスをとりながら、通常の半数に厳選された合唱隊を分散配置する。また独唱の4名も最前線ではなく、小編成になったオーケストラの後に並ぶ異例のパターンだった。それゆえ、正面の席は、いつもより遠くから声が聴こえ、人数も少ないことから、音圧の迫力は足りなかったかもしれない。が、逆に筆者が座っていた、指揮者がよく見えるオーケストラ真横の二階席は、思いがけず、最高の特等席と化した。なぜなら、第四楽章で合唱隊が起立し、全員が一斉に黒マスクを外して歌いだすと、すぐ斜め前から同じ高さでダイレクトに声が突き刺さる。しかも正面の真下からはオーケストラの音が湧き上がるのだ。まるで「第九」の音空間の只中にいるような、忘れられない貴重な体験となった。平常時であれば、絶対にこんな聴こえ方はしない。また読響としても年末の最後の公演であり、この一年は音楽が抑圧されていたことを踏まえると、それが解放されたかのような喜びが爆発した演奏だった。
2020/12/26(土)(五十嵐太郎)
Creation Project 2020 160人のクリエイターと大垣の職人がつくるヒノキ枡「〼〼⊿〼(益々繁盛)」

会期:2020/12/01~2021/01/20
クリエイションギャラリーG8/ガーディアン・ガーデン[東京都]
もう10年近く前、岐阜県のものづくり支援の仕事に私が携わったとき、岐阜県大垣市が枡の全国生産量の8割を担うことを知った。なかでも頑張っている製造事業者が大橋量器であることも。当時から同社は枡のヒノキ素材と技術を用いて、円すい形や斜めに傾いた塔形などの斬新な酒器を開発していて、未来志向の事業者だなという印象を抱かせた。だから本展の枡の製作が大橋量器だと知り、十分に頷けたのである。
枡はもともと、米などの穀物を計る道具だ。それがお祝いの席でピラミッド状に積まれて演出される酒器となり、いまに至る。結局、それ以上は発展しづらいため、大橋量器はさまざまな形状に挑み、酒器のほかインテリア小物への展開を探っているのだ。しかし本展を観て、また別の可能性を感じた。枡の表面に個性豊かなグラフィックやイラストレーションを施すことで、違う表情を持つことに気づいたのだ。本展はクリエイションギャラリーG8とガーディアン・ガーデンの2会場にわたり、160人のデザイナーやイラストレーターらがデザインした枡を一堂に会した展覧会である。枡=酒を取っ掛かりにデザインした作品、文字によるメッセージ作品、幾何学模様を生かした作品、動物のイラストレーションを載せた作品など、会場では種々さまざまな枡が見られた。大橋量器にも模様を入れた「カラー枡」という商品はあるが、言わばここまでぶっ飛んだデザインではない。枡の形はオーソドックスであっても、その表面がユニークになることで、計量道具や酒器を越えて用途の幅が広がる。例えばリビングや書斎などで小物入れや飾りにしても良さそうに思えた。また本展は展示だけでなく販売も行なっており、販売収益金は国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン」に寄付される。これまで枡に関心や馴染みがなかった人も、これを機に手に入れてみるのもいいだろう。
 展示風景 クリエイションギャラリーG8
展示風景 クリエイションギャラリーG8
 展示風景 クリエイションギャラリーG8
展示風景 クリエイションギャラリーG8
 展示風景 ガーディアン・ガーデン
展示風景 ガーディアン・ガーデン
公式サイト:http://rcc.recruit.co.jp/creationproject/
2021/01/06(水)(杉江あこ)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)