artscapeレビュー
書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー
カタログ&ブックス | 2021年8月1日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
アナザーエナジー展:挑戦しつづける力──世界の女性アーティスト16人

執筆者:片岡真実、マーティン・ゲルマン
デザイン:加藤賢策(LABORATORIES)
発行:フィルムアート社
発行日:2021年7月9日
サイズ:A4判変型、364ページ
森美術館「アナザーエナジー展:挑戦しつづける力 ─世界の女性アーティスト16人」公式図録。
1950年代から1970年代にかけて活動を始め、2021年の現在に至るまで世界各地で制作活動を続ける女性アーティスト16人に光を当てます。絵画、映像、彫刻、大規模インスタレーションにパフォーマンスなど、それぞれ初期作品から代表作、本展のための新作までを収録。 ジェンダー、人種、民族など、近年、世界各地で広がっている多様なアイデンティティに対する理解にもつながる1冊です。
関連記事
アナザーエナジー展:挑戦しつづける力 ─世界の女性アーティスト16人|村田真:artscapeレビュー(2021年08月01日号)
Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる展公式図録
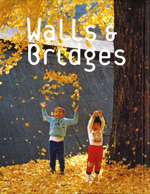
出展作家:東勝吉、増山たづ子、シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田、ズビニェク・セカル、ジョナス・メカス
発行:東京都美術館
発行日:2021年7月
サイズ:19.7×15.4cm、271ページ
2021年7月から東京都美術館にて開催されている「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」展の公式図録。
リボーンアート・フェスティバル2019 公式記録集─いのちのてざわり

デザイン:groovisions
発行:ART DIVER
発行日:2021年6月30日
サイズ:B5判変形、224ページ
東日本大震災からの復興を願って開催される芸術祭「Reborn-Art Festival」。延べ44万人以上が来場した、第2回「Reborn-Art Festival 2019」を完全収録した公式カタログ決定版!「ART」「MUSIC」「FOOD」の3つの柱で構成されるフェスティバルを200ページにわたるカラーページで鮮やかに再現。
テアトロン 社会と演劇をつなぐもの

著者:高山明
発行:河出書房新社
発行日:2021年7月27日
サイズ:四六判変形、268ページ
さまざまな分野と交差することで演劇を拡張し、社会と芸術表現との接続を追求する高山明=Port B。いま最も過激な演劇を手がけ世界的に評価される演出家による、現代社会=演劇論。
関連記事
高山明/Port B『光のない。─エピローグ?』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年04月15日号)
Port B「サンシャイン63」──地肌と声の行路|阿部一直(山口情報芸術センター):キュレーターズノート(2009年04月15日号)
村上慧 移住を生活する

著者:村上慧
執筆者:川瀬慈、辻󠄀琢磨、野中祐美子
編集:野中祐美子
編集補助:大場さやか
写真:木奥恵三、村上慧
発行:金沢21世紀美術館
発行日:2021年3月31日
サイズ:22.0×15.0cm、803ページ
発泡スチロール製の家を背負って移住生活をするアーティスト村上慧によるプロジェクト「移住を生活する」の約6年間の記録を収めたアーティストブック。家はあるが土地のない村上は、毎日家を置くための敷地を交渉し獲得する。日々の出来事や思考の断片を日記に綴り、土地のある家を「攻撃するつもりで」ドローイングを描く。敷地写真やドローイングのキャプションにはその土地の住所が充てられる。北は青森、南は熊本。社会の矛盾や公共に対する疑問、あらゆる事故や災害を目の当たりにし、自分たちの生き方そのものを見直す必然性を「移住を生活する」で表現してみせる。ページをひとたび開けると、日記、ドローイング、地図、写真によってあっという間に読者も「移住を生活する」の当事者になれるだろう。
関連記事
個と公の狭間での実践と、終わらない問い──展示と本を通して見せる「村上慧 移住を生活する」|野中祐美子(金沢21世紀美術館):キュレーターズノート(2021年06月15日号)
村上慧 移住を生活する|村田真:artscapeレビュー(2021年04月01日号)
「ミヒャエル・ボレマンス マーク・マンダース|ダブル・サイレンス」、「村上慧 移住を生活する」、「アペルト13 高橋治希 園林」|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2021年03月15日号)
日常のあわい

出展作家:青木陵子+伊藤存、岩崎貴宏、小森はるか+瀬尾夏美、小山田徹+小山田香月、下道基行、髙田安規子・政子、竹村京
寄稿:益田ミリ
デザイン:大原大次郎
発行:青幻舎
発行日:2021年6月30日
サイズ:B5判、120ページ
金沢21世紀美術館で開催中の特別展「日常のあわい」公式図録。
7組11名の作家が、私たちが意識せざるをえなくなった「日常」について今一度見つめ直す。意識しないと見過ごしてしまう生活のなかのささやかな創造行為に着目した作品や、突然の喪失や災害に向き合う心の機微を捉えた作品、そして形を変えて続いていく日常をあらわにする作品を紹介。これらを通して、日常と非日常のあわいにある「現在(いま)」が浮かびあがる。
つくる理由 暮らしからはじまる、ファッションとアート

著者:林央子
デザイン:小池アイ子
発行:DU BOOKS
発行日:2021年6月1日
サイズ:四六判、312ページ
インディペンデントな創作によって独自の境地を切り開いていった1990〜2000年代の作家たちを再検証し、刊行後の反響から美術展へと発展した『拡張するファッション』。本書はその著者・林央子による待望の書下ろし新作。現在を生きる同時代の表現者たちの声を拾う。
思考する芸術──非美学への手引き

著者:アラン・バディウ
翻訳:坂口周輔
発行:水声社
発行日:2021年6月30日
サイズ:四六判、296ページ
芸術と哲学の関係はいかなるものなのか?
芸術を真理との関係から問い直し、ダンス、映画、演劇、散文、詩を例に作品でも作者でもなく出来事的な切断によって先導される《芸術的布置》の次元を見定める渾身の芸術論。
光学のエスノグラフィ フィールドワーク/映画批評

著者:金子遊
発行:森話社
発行日:2021年6月22日
サイズ:四六判、288ページ
撮ること、観ること、考えること──。これらの営みの総体として、映画は形成されている。
ロバート・フラハティからジャン・ルーシュへと連なる映像人類学をはじめ、アピチャッポン・ウィーラセタクン、王兵、ツァイ・ミンリャン、エドワード・ヤンといったアジアの映画作家まで、人類学的フィールドワークと映画批評を横断し、映像のなかに個を超えた人類の歴史、習俗、営みを見出す。
丹下健三建築論集(岩波文庫)

編著:豊川斎赫
発行:岩波書店
発行日:2021年7月15日
サイズ:文庫判、288ページ
世界のTANGE──。国際的建築家として丹下健三の名を知らしめたのは、その作品のみならず、彼の論説と思想であった。人間と建築にたいする深い洞察と志。「美しきもののみ機能的である」との言葉に象徴される独自の美意識。建築の化身と呼ばれた不世出の建築家による重要論考を集成する。二巻構成のうちの建築論篇。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
2021/07/31(土)(artscape編集部)
脇坂真弥『人間の生のありえなさ──〈私〉という偶然をめぐる哲学』

発行所:青土社
発行日:2021/04/30
「こんなことはありえない」──おそらく誰もが、大なり小なりそうした感覚に襲われたことがあるはずだ。それは、いま目の前にある現実がにわかには受け入れがたい、こんなことはとうてい信じられない、という「非現実の感覚」(229頁)である。もちろん「こんなことはありえない」という言葉は、思いもよらぬ幸運に恵まれた人の口から放たれることもあろう。しかし概して言えば、この「ありえない」という感覚、すなわち「なぜ──ほかの誰でもなく──それは〈私〉に到来しなければならなかったのか」という問いをもっとも強く誘発するのは、いわゆる「不幸」の経験をおいてほかにない。
本書が問題とするのは、この何とも言葉にしがたい感覚である。「人間の生は
ヴェイユのこうした言葉を、たんなる個人の感傷として片づけるのはたやすい。事実、ヴェイユに対して周囲から寄せられた反応は、おおよそこの類いのものであったようだ。しかし本書の著者は、これをたんなるナイーヴな感慨として切り捨てることも、そこから人間の「不幸」一般をめぐる理論を打ち立てることもしない。田中美津やシモーヌ・ヴェイユ、あるいはエンハンスメントの倫理やアルコール依存症からの回復を導きとして本書が執拗に問いかけるのは、ある極限的な経験のなかで到来する「なぜ〈私〉なのか」という問いである。
巻末の「初出一覧」を見るとわかるように、本書は著者の過去20年以上におよぶ息の長い思索がもとになっている(284-285頁)。そこで論じられるテーマは、時代ごとに一見ばらばらなようでいて、「なぜ〈私〉なのか」という問いにおいて驚くべき一貫性をみせている。くわえて強調しておきたいのが、ごく整然とした理路のもとに書かれているにもかかわらず、本書が問題をただ抽象的な次元で論じる哲学的「偶然」論とはまったく異なる手触りをもっていることだ。そもそも、この「なぜ〈私〉なのか」という──すぐれて実存的な──問いは、それを説得的な「理論」に仕立てあげようとすればするほど、それぞれに固有の現実から乖離していくことをまぬがれない。本書はそのことにきわめて自覚的であり、各章の端々では、ある個別的な生の苦闘をどこまで普遍的な理論へと開くことが可能か、という逡巡自体が問題とされている。ここには、どうあっても別様ではありえなかった「生」の光輝と汚辱がたしかに書き留められている。これだけでも十分に驚くべきことである。しかしなおかつ著者は、その特殊性をいたずらに神秘化して押し黙らせるのではなく、その繊細な思索によって、個々の特殊な生を救済するための努力をやめない。特殊性と普遍性の架橋の不可能性を自覚しつつ、なおもそれを記述すること──わたしはこれが、哲学になしうる最大の仕事のひとつだと思う。そして本書は、それに成功したごく例外的な作品たりえている。
2021/07/22(木)(星野太)
三野新『クバへ/クバから』

発行所:三野新・いぬのせなか座写真/演劇プロジェクト制作実行委員会
発行日:2021/06/30
三野新(1987-、福岡生まれ)は、演劇と写真を結びつけるというユニークな活動を展開してきた「写真家」である。今回の新作『クバへ/クバから』では、小説、詩歌、デザインなど、多彩な方向性を持つ創作集団「いぬのせなか座」と組んで、「写真集制作」そのものを演劇として上演することを試みた。2018年8月からスタートしたプロジェクトは、途中、何回かの座談会、写真展などの開催を経て、最終的に「いぬのせなか座叢書4」として刊行された写真集『クバへ/クバから』にまとまった。
そのようにして形をとった「写真集」は、錯綜する写真、テキスト、イラストの複合体として編み上げられている。中心的なテーマ(被写体)は、沖縄をはじめとする南方地域に自生する植物クバ(ビロウ)である。クバは、日本の古代においても沖縄の創世神話においても神木=聖なる植物として崇められてきた。三野はそのクバの植生分布の北限が彼の生まれた福岡県であることを知り、自らの記憶や体験と、沖縄(奄美諸島を含む)の歴史文化とを重ね合わせつつ探求する、何度かの旅を企図する。その過程で「沖縄を、いま、東京から撮影する」ことの意味が、写真やテキストを通じて問い返されていくことになる。
「写真集制作」を通じて、沖縄をめぐる使い古された言説、イメージを「新たな配置、名付け、撮影行為のなかで攪拌させていく」という意図は、山本浩貴+h(いぬのせなか座)による装丁・レイアウトを含めてとてもうまく実現していた。ただ、演劇化のプロセスを経ることで、三野の「クバ」に寄せる初発的な動機もまた「攪拌」してしまったことも否定できない。創作行為のテンションとリアリティを保ちつつ、この方法論をさらにさまざまなかたちで展開することはできないのだろうか。『クバへ/クバから』の上演を、これで終わらせるのはややもったいないと思う。
関連記事
カタログ&ブックス | 2021年7月15日号[近刊編]:artscapeレビュー(2021年07月15日号)
2021/07/21(水)(飯沢耕太郎)
ツヴェタン・トドロフ編『善のはかなさ──ブルガリアにおけるユダヤ人救出』

翻訳:小野潮
発行所:新評論
発行日:2021/07/15
戦後フランスで活躍した思想家ツヴェタン・トドロフ(1939-2017)は、もともとブルガリアに生まれ、大学卒業後にフランスに移住し、生涯をそこで過ごした。そのトドロフも数年前にこの世を去ったが、かれが1999年に編纂した書物が、このほど日本語に翻訳された。それが本書『善のはかなさ──ブルガリアにおけるユダヤ人救出』である。
本書は、第二次世界大戦中のブルガリアの政治状況をめぐる、このうえなく貴重なドキュメントである。1941年、当時のブルガリア王国はドイツ・イタリア・日本の枢軸国に加わった。それと前後して、ナチスドイツの圧力のもと、ブルガリアでも反ユダヤ的な政策が取られるようになる。その最たるものが1941年1月21日に公布された「国民保護法」である。
しかし結果的に、ブルガリアのユダヤ人は誰一人として収容所に送られることはなかった。これは言うまでもなく、当時のヨーロッパにおいて「類を見ない」(ハンナ・アーレント『エルサレムのアイヒマン──悪の陳腐さについての報告』[1963])ことであった。本書は、その経緯と、それがいかにして可能になったのかを示す資料集である。その立役者としては、代議士ディミタール・ペシェフ、国王ボリス三世、ブルガリア正教会ステファヌ主教をはじめとする複数の人物が浮かび上がる。しかしトドロフが言うように、この出来事の背後にいたのは、たったひとりの「至上の英雄」ではなかった。そのような結果がもたらされたのはいくつかの複合的な理由によるものであり、とりわけそれは、つねに歴史に翻弄されてきたこの国の類稀な「良心」に支えられていた、というのがトドロフの考えである(62-63頁)。
いまからおよそ20年前、トドロフがどのような使命感から本書を編纂したのか、いまとなってはその意図を推し量るほかない。本書のタイトルは若干わかりにくいのだが、ここでいう「善のはかなさ(fragilité du bien)」とは、むろん善の無力さのことではなく、それが脆弱でありつつも可能であることの謂いである。編者とはいっても、本書におけるトドロフの解説は最小限に抑えられており、かわりにさまざまな立場の人間が残した当時の文書が大半をしめる。これらの資料は、戦時中、誰がどのような立場で何を行ない、何を行なわなかったのかをまざまざと伝えている。ごくありきたりなことを言うようだが、本書の一読を通じてあらためて痛感させられるのは、後世に事実を歪みなく伝えるための「公文書」の重要性である。
2021/07/19(月)(星野太)
アラン・コルバン『草のみずみずしさ──感情と自然の文化史』

翻訳:小倉孝誠、綾部麻美
発行所:藤原書店
発行日:2021/05/30
著者アラン・コルバン(1936-)は現代フランスを代表する歴史家のひとりである。とくに今世紀に入ってからは『身体の歴史』(全3巻、2005/邦訳:藤原書店、2010)や『感情の歴史』(全3巻、2016-17/邦訳:藤原書店、2020-)をはじめとするシリーズの監修者として広く知られている。表題通り「草」をテーマとする本書もまた、著者がこれまで中心的な役割を担ってきた「感情史」の系譜に連なるものである。
本書の特色は、その豊富なリファレンスにある。原題に「古代から現代まで(de l’Antiquité à nos jours)」とあるように、本書にはおもに思想・文学の領域における「草」をめぐる記述がこれでもかというほどに詰め込まれている。同時に歴史家としての慎ましさゆえか、個々の文献に対するコメントは最小限に抑えられている。それゆえ、コンパクトな一冊ながら、本書は西洋世界における「草」をめぐる言説の一大カタログとして読むことができる。
本書のもうひとつの特色は、イヴ・ボヌフォワ、フィリップ・ジャコテ、フランシス・ポンジュをはじめとする現代詩人の言葉がふんだんに登場することだろう。「草」というテーマから、読者はウェルギリウス(『牧歌』)、ルソー(『孤独な散歩者の夢想』)、ホイットマン(『草の葉』)をはじめとするさまざまな時代の古典を思い浮かべるにちがいない。しかし意外なことにも、本書で紹介される著者たちのなかには、20世紀後半から現代にかけての作家・詩人が数多く含まれている。コルバンのこれまでの仕事から、本書もまた「草」をめぐる「さまざまな感情の歴史(histoire d’une gamme d’émotions)」と銘打たれてはいるが、個人的にはこれを「草の文学史」をめぐるガイドブックとして読むことをすすめたい。
いっぽう、ここでいう「草」があくまで西洋のそれに限定されていることは、本書の訳者が早々に指摘する通りである(「小倉孝誠「本書を読むにあたって」)。ただしそれは、本書の別の慎ましさを示すものでこそあれ、その瑕疵となるものではいささかもない。
2021/07/19(月)(星野太)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)