artscapeレビュー
2017年12月15日号のレビュー/プレビュー
TAKT PROJECT「SUBJECT ⇋ OBJECT」
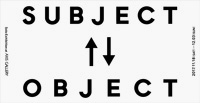
会期:2017/11/18~2017/12/03
アクシスギャラリー[東京都]
デザインの展覧会はもはやモノを見せることではない、思考を見せることである。本展を見て、そう強く感じた。TAKT PROJECTは、吉泉聡をはじめとする4人から成るデザイナー集団である。彼らはプロダクト、グラフィック、建築とそれぞれに異なる専門領域を持つため、ひとつのプロジェクトに対して、横断的に思考することができるうえ、ワンストップでデザイン提案できることが強みだ。新進気鋭のデザイナー集団として、いま、デザイン業界で注目されている。そんな彼らが設立5年目にして初の個展を開いた。

展示風景
アクシスギャラリー
撮影:林雅之
本展では、TAKT PROJECTがこれまでに行なってきた自主研究プロジェクトを中心に7つの事例が展示されていた。いずれも主題「SUBJECT」に対し、それを具現化した物「OBJECT」を展示するという構成である。その一つひとつの主題はまさに「問いかけ」とも言うべきで、彼ららしい思考のプロセスが見て取れる。例えば「素材とプロダクトの境界線を探る」という主題では、電子部品とアクリル樹脂を混ぜ合わせた電気が通る複合材で、懐中電灯や電気スタンドとして機能する物体を作った。一般的に、家電は電子部品が外装材で覆われた作りになっている。しかし彼らは粘土をこねて器を作るかのように、素材そのものが製品となるようなシンプルな家電の作り方を探った。
このように「こうあるべき」という既成概念や枠組みから抜け出すことで、別の可能性につながるのではないかと彼らは思索する。最もユニークな主題だったのは「音楽的に創造する」で、街で環境音を録音するフィールド・レコーディングに着想を得て、レコーダーの代わりにハンディー3Dスキャナーを持ち、街でさまざまな物の形を採取し、そのCADデータを元に新たな造形を作った試みである。おそらくデザインに関わりのある者以外は、これらの主題はややマニアックに映るに違いない。しかも展示物は、今すぐ製品化できるものばかりではない。それでもあえて問いかけるのは、彼らが慣習通りのデザイン手法に満足することなく、何かしらのブレイクスルーを常に求めているからだ。こうした姿勢を持ち続けているからこそ、彼らから革新的なデザインが多く生まれているのである。

TAKT PROJECT《COMPOSITION》
撮影:林雅之
2017/11/17(金)(杉江あこ)
マリメッコ・スピリッツ──パーヴォ・ハロネン/マイヤ・ロウエカリ/アイノ=マイヤ・メッツォラ

会期:2017/11/15~2018/01/13
フィンランドのファブリックブランド、マリメッコの人気が日本で高まったのは2000年代に入った頃だろうか。ちょうど北欧デザインのブームと相まって、あの明るい赤とピンクの花柄ファブリック「ウニッコ」を街中でもよく目にした。ただしマリメッコの社史を調べると、1972年に日本と米国で海外ライセンス契約を結んだとあるから、実はそれより30年近く前から日本に入っていたことになる。当時は一時のブームで終わるのかと思っていたが、そうではなかった。今なお人気は健在で、むしろ定番化したように見える。それほど多くの人々を魅了し続けるマリメッコの魅力とは何なのか。
現在、マリメッコには新旧合わせて30人近くの契約デザイナーがいる。そのうち、才能あるパターンデザイナー3人、パーヴォ・ハロネン、マイヤ・ロウエカリ、アイノ=マイヤ・メッツォラの仕事を紹介したのが本展だ。いずれも30〜40代の若手ばかり。ファブリックはもとより、展示の見どころは原画であった。フェルトペンで描いたような素描から、水彩画や切り絵など、それはもう種々様々。切り絵は日本の伊勢型紙のようでもあり、それを原画にしたファブリックは独特の雰囲気を持っていた。つまりマリメッコに人々が魅了される理由はここにあるのではないかと思う。デザイナーが自由にアイディアを練り、丁寧に一筆一筆を手描きしたものだからこそ、原画に力があるのだ。手作り(クラフト)の魅力である。

左:Aino-Maija Metsola 《Juhannustaika(真夏の魔法)》 (2007)
右:Paavo Halonen《Torstai(木曜日)》 (2016)
一方で、本社内にあるプリント工場の様子が映像で紹介されていた。そこに映るのは巨大なロール式スクリーン印刷機である。毎年、100万メートルの生地をプリントしているのだという。これを見ると、マリメッコはあくまでも工業製品(プロダクト)で成功を収めてきたブランドであることを思い知る。当然、そうでなければ世界進出はできていない。クラフトとプロダクト、一般的には相反するこの両面を併せ持ったブランドだからこそ、今のマリメッコの人気があるのだろう。本展ではさらに「JAPAN」をテーマにした作品も展示されており、その解釈は三者三様で興味深かった。
2017/11/17(金)(杉江あこ)
野生展:飼いならされない感覚と思考

会期:2017/10/20~2018/02/04
21_21 DESIGN SIGHT[東京都]
「野生的なものはエレガントである」。野生とエレガント。一見、相反する言葉にも思えるこの印象的なメッセージから始まる本展は、終始、野生とはいったい何なのかを私たちに突きつけてくる。思想家、人類学者、宗教学者である中沢新一が展覧会ディレクターを務めた本展は、大きく言えば、別名「南方熊楠展」とも言うべき内容であった。会場の前半では、明治時代に米国や英国に渡り、世界的に活躍した博物学者の南方熊楠を取り上げ、南方が後世に残した研究資料に基づいて野生を紐解いていく。中沢はこれまでに南方に関する著書を数多く執筆してきた。例えば偶然の域を超えた発見や発明、的中を南方は「やりあて」と呼んだことや、AとBの関係性でしかない「因果」という西洋思想に対し、AとB、C、D、E……とありとあらゆる事物がつながり合っている「縁起」という仏教思想に着眼したことなどを紹介する。それが人間の心(脳)に野生状態を取り戻すことになると。

展示風景 野生への入り口
21_21_DESIGN SIGHT
撮影:淺川敏
後半では、さらに野生の捉え方を発展させていく。自然と人間とをつなぐ存在を「野生の化身」として、日本人はそれらを「かわいい」造形にする特異な才能を持っていたことを紹介する。「野生の化身」は縄文時代の土偶に始まり、現代の「ハローキティ」や「ケロちゃんコロちゃん」といったキャラクターにまでおよぶ。理由や理屈なく「かわいい」と思う心の赴き、それこそが野生なのだと言わんばかりに。

展示風景 「かわいい」の考古学:野生の化身たち
21_21_DESIGN SIGHT
撮影:淺川敏
冒頭のメッセージで中沢は「まだ管理され尽くしていない、まだ飼いならされていない心の領域」を「野生の領域」と呼んだ。いま、世の中を見渡すと、野生とは真逆のAI(人工知能)の研究に熱心である。AIが人間の知能をはるかに超え、近い将来、人間の仕事の多くがAIに取って代わられるとも言われている。そんな時代だからこそ、中沢はあえて「野生の領域」の大切さを訴えたのではないか。つまりAIへのアンチテーゼである。人間が持ち、AIが持たざるもの、それは一言で言えば野生の感覚と思考なのだ。
2017/11/17(金)(杉江あこ)
レアンドロ・エルリッヒ展:見ることのリアル

会期:2017/11/18~2017/04/01
森美術館[東京都]
まず初めに暗い通路に通され、ゆるやかなスロープを上っていく。なにが起きるのか期待を持たせる憎い演出だ。広い空間に出るとボートが数隻プールにプカプカ浮かんでいる。《反射する港》と題する作品だ。しかしよく見ると、水面に映ってるボートの反射像が揺らがないので、実際には水がなく、ボートを上下対称につなげて揺らしているだけであることに気づく。いきなりカマしてくれるじゃねーか。ほかにも《教室》、《眺め》、《試着室》など趣向を凝らした装置がいっぱい。
最初はおもしろいけど、しょせんトリックアートにすぎない。と思っていたが、見ていくうちにそんな素朴な作品でないことに気づく。これらはいずれも絵画と関連の深い「窓」と「鏡」から発想されたものなのだ。最初の《反射する港》は鏡、マンション住人の生活をのぞき見る《眺め》は窓、迷路のような《試着室》は鏡といった具合。なかには《雲》のように窓とも鏡とも結びつかない作品もあるが、これは発想が陳腐だし、完成度も低い駄作だ。逆に窓と鏡の双方を結びつけたのが、最後の《建物》と題するインスタレーション。床に窓のあるビルの壁を再現し、観客がその窓に手をかけて横たわると、斜め上45度の角度に据えられた巨大な鏡に、窓から落ちそうな観客の姿が垂直に映るという仕掛け。観客参加型で、しかも撮影可能なインスタレーションだから、まさにインスタ映え。
2017/11/17(金)(村田真)
没後70年 北野恒富展

会期:2017/11/03~2017/12/17
千葉市美術館[千葉県]
北野恒富というと、甲斐庄楠音や岡本神草(来年5月から千葉市美でもやる)らとともにデロリ系の日本画家だとなんとなく思い込んでいたが、違った。たしかに大作の《淀君》や大正期のポスターなどは多少デロっているものの、むしろ鏑木清方(東京)、上村松園(京都)と並ぶ大阪の美人画を代表する画家として知られているそうだ。そういわれれば、襖の前の芸妓を描いた《鏡の前》と《暖か》の対作品などはそそられるものがある。ちなみに《鏡の前》は黒い着物に赤い帯、《暖か》は赤い着物に黒い帯と対照的で、前者は着物に飛天、後者は襖に若衆が描かれるなど工夫が凝らされている。しかし美人画だけでなく、雨に煙る街並を描いた《宗右衛門町》や、前面に柳を大きく配した《道頓堀》など風景画も負けず劣らず妖しい雰囲気が漂う。ちなみに《宗右衛門町》は川端龍子、小林古径、下村観山ら日本美術院の21人が連作した『東都名所』の1点で、東京の名所を描く組物なのにひとり恒富だけ大阪の宗右衛門町を描いているのだ。
2017/11/19(日)(村田真)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)