artscapeレビュー
2017年12月15日号のレビュー/プレビュー
『RE/PLAY Dance Edit』

会期:2017/11/25~2017/11/26
京都芸術センター[京都府]
「東京デスロック」主宰の演出家、多田淳之介による、「演劇」のフィールドから「ダンス」を鋭く照射する、秀逸かつプロブレマティックな作品。まず、本作に至るまでの経緯を簡単に辿っておく。前身と言えるのが、2006年に演劇作品として上演された『再生』。「ネットで誘い合った若者たちが集団自殺をはかる」という設定の下、錠剤を飲んだ若者たちが爆音でかかる音楽の中で約30分間踊り狂った後、倒れていく。これを3セット繰り返すことで、負荷をかけられて疲弊していく生身の身体の「リアル」と「反復構造/繰り返せないこと」を提示した。2011年に再演された『再/生』では、東日本大震災を契機に、「疲弊しきった身体が何度も立ち上がり、再び踊ろうとする」姿を強調することで、「死」から「生命力の肯定」へのシフトが企図された。そして、「We dance 京都2012」にて、ダンサーとの共同作業を委嘱された多田は、『RE/PLAY』を発表。出演者は俳優からダンサーに替わり、3セットの繰り返しではなく、同じ曲を何度も反復するという構造上の変化がとられた。横浜、シンガポール、カンボジアでの再演を重ね、日本人ダンサーと現地ダンサーからなる多国籍の出演者によって上演されたのが本作である。
『RE/PLAY Dance Edit』の構造的特徴は、タイトルが示すように「反復と中断」にあり、それは楽曲の再生とダンサーの運動の双方において徹底して遂行される。冒頭、一列に並んで客席と相対した8名のダンサーたちは、ポーズを決めて静止した後、次々と床に倒れる。『We Are The World』の曲がかかり、ダンサーたちは短い身振りの反復→静止ポーズ→倒れ込む、をひたすら繰り返し続ける。音楽は何度も一時中断するが、彼らは意に介さず、ロボットのように淡々と反復に従事し続ける。また、見続けているうちに、各人が何パターンかの身振りを繰り返していることが分かってくる。例えば、直角に曲げた腕を上下に振る、四つん這いで軽くジャンプしながら移動するなど、体操のような動作が多い。意味の発生を回避したニュートラルな動作が選択され、感情を込めず無機質なトーンで行なわれるため、「振付」の強制力の下で搾取されるダンサー=労働者の身体が前景化し、それへのささやかな抵抗として、「音楽にノること」「反復することの快感」への拒絶が提示されていると理解される。
序盤で『We Are The World』が2回流れた後、ビートルズの『オブラディオブラダ』が10回連続でこれでもかと繰り返される。変容の兆しが起きるのは、半ばあたりからだ。額で光り始める汗は、運動量の蓄積とそれがもたらす熱量の発生を告げる。荒く上がり始める息と、比例する肉体的な高揚感。反復/できないこと、生身の身体がそこにあること。無機質な手触りだったものが、目の前で如実に変容していく。曲の7回目頃からは、ダンサーたちの動きは速さと激しさを増し、早回しのように舞台上を縦横に行き交う。曲の切れ目の「無音」に響く荒い息遣いが、運動量の激しさを音響的に物語る。
そして、「打ち上げでの会話」を模したやり取りが日/英で交わされるシーンを挟み、終盤、『今夜はブギー・バック』、『ラストダンスは私と』、最後にPerfumeの曲が3回連続でかかる。ここに至って熱気と高揚感は最高潮に達し、水を得た魚のようなダンサーたちは、ブレイクダンスの回転技、バレエ、カンボジアの古典舞踊の動きなど、各人の「得意技」を次々と披露し始め、さながら他流試合のダンスバトルの闘技場のような様相となった。
その生の過酷な闘技場は、「ダンス」をめぐる幾重もの問いが係争される場でもある。単なる「動き」と「ダンス」を線引きする境界はどこにあるのか? 見る側の認識の問題か、パフォームする側の意識か、制度に帰着するのか? どこまでが「振付」で、どこまでが「内発的な情動」から出た動きなのか? 私たちは、反復が生む熱量の蓄積と音楽の高揚感によって、身体的疲労がその閾値を超え、ランナーズハイのように熱狂的な陶酔へと変容する身体のありようをまざまざと見せつけられる。ドラッグのような魅力と、集団的な高揚感に飲み込まれる危険性も。
だからこそ、終盤近くの「会話の挿入」という「演出」には疑問が残る。「関西のダンスシーンに疎い関東のダンサーへの揶揄やツッコミ」「カンボジアではダンサーは公務員扱いであること」など、出演者の「多文化・多国籍」性、ダンスのバックグラウンドの多様性、在住する都市や国の文化的相違をアピールするのが狙いだろう。だが、安易に言語に頼らずとも、彼らの身体が既にダンスの履歴や身体性の違いを雄弁に語っている。また、「直接的なコンタクトが一切なく、個々人が舞台上で「孤絶」しているにもかかわらず、次第に醸成されていく集団的な高揚感や一体感」の効果が軽減してしまう。それはバックグラウンドが異なる者同士が同じ場で共存する希望であるとともに、集団的な熱狂がはらむ危険性と表裏一体でもある。その両面を提示しながら、この過酷なまでの時間に耐えた出演者たちに拍手を送りたい。


撮影:前谷開
2017/11/26(日)(高嶋慈)
ワードプレイ ワセニ・ウォルケ・コスロフ

会期:2017/11/23~2017/01/31
中村キース・ヘリング美術館[山梨県]
快晴。いつもとは逆の左手に富士山をながめながら小淵沢へ。今日は第9回中村キース・ヘリング美術館国際児童絵画コンクールの授賞式。世界中から公募した4~17歳の子どもの絵(今回は計1240件集まった)を、年齢別に3部門に分けて審査。ぼくも選ばせてもらったので、授賞式に出席して賞状を渡さなければならない。受賞者の約半数は香港、シンガポール、バングラデシュ、アメリカ、カナダ、ブルガリアといった外国の子。ぼくが選んだのは東京の村田奏満くん(たまたま苗字が同じ)、イギリスのクローディア・ピピスさん、マレーシアのムハンマド・ハジム・ビン・アーマド・ナザリくんの3人で、クローディアさんとムハンマドくんは欠席。そりゃ子どもの絵の表彰式のために海を越えて山梨まで来ないよね。と思ったら、わざわざ駆けつけた家族も何組かいた(交通費は自腹)。この授賞式のあと、子供たちも参加してワセニさんがワークショップを行ない、夜には「ワセニ展」のレセプションパーティーが開かれた。授賞式に合わせてパーティーを企画したのか、パーティーに合わせて授賞式を設定したのかよくわからないけど、晩秋の八ヶ岳山麓が人でにぎわった。
で、ようやく「ワセニ展」の話だが、ワセニ・ウォルケ・コスロフはエチオピア出身でアメリカ西海岸に住むアーティスト。その作品は「ワードプレイ」というタイトルにも示されているように、言葉、文字をモチーフに展開した絵画。最初にエチオピアのアムハラ語をベースにした一覧表仕立ての絵があり、展示が進むに連れ徐々に色が増え、文字に絵が絡みつき、ゴーキーを思わせる初期の抽象表現主義風の絵画に変化していくプロセスがたどれる。と思ったら、別に制作年順に並べているわけではなく、文字と絵画のあいだを行きつ戻りつしているらしい。変わらないのは画面をグリッド状に分割していることと、文字を発展させた記号のような黒い線描が骨格になっていること。もしキース・ヘリングとの共通性があるとしたら、この黒い記号的な線描表現だろう。絵画としては特に新鮮みがあるわけでもないし、現代アフリカのプリミティヴアートに括られてしまう可能性もあるが、むしろジャズやエチオピア音楽などポップカルチャーとの関係から見直したほうが、新たな発見があるかもしれない。
2017/11/26(日)(村田真)
渡部敏哉「Somewhere not Here」
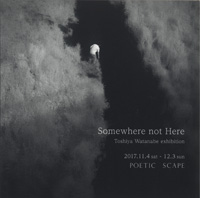
会期:2017/11/04~2017/12/03
POETIC SCAPE[東京都]
渡部敏哉は1966年福島県生まれ。多摩美術大学在学中の1990年に「期待される若手写真家20人展」(PARCO主催)に選出されるなど注目を集めるが、同大学卒業後は広告代理店に勤めて、しばらく写真作品を発表しない時期もあった。2013年、東日本大震災後に故郷の福島県浪江町をカラー写真で撮影した「18 months」のシリーズをPOETIC SCAPEで展示して「再デビュー」を果たす。
今回発表された「Somewhere not Here」は、2010年頃から撮り続けられているモノクローム作品である。「18 months」が、原発事故によって立ち入りが制限されて非日常化した街並を、むしろ平静に日常的な視点で捉えたシリーズであるのに対して、「Somewhere not Here」では「日常を被写体としながらも、その奥底に見え隠れする不明瞭なもの」を浮かび上がらせようとしている。具体的な方法論としては、デジタルカメラの画素をわざと荒らしたり、フィルターによる赤外線撮影を試みたりすることで、見慣れた眺めを、どこか不吉な空気感が漂う「ここではないどこか」の光景に変質させている。そのような、一見対照的なアプローチを同時に展開しているところに、渡部の写真家としての奥行の深さを見ることができるだろう。
ただ、2016年に「Steidl Book Award Japan」に選出され、2018年に写真集が刊行される予定という「18 months」と比較すると、「Somewhere not Here」はまだ完成途上という印象を受ける。一点一点がかなり独立しており、それぞれに物語性を感じるので、それら全体を統合するテキストをつけるということも考えられるのではないだろうか。
2017/11/26(日)(飯沢耕太郎)
プレビュー:ダンスボックス・ソロダンスシリーズvol.2 寺田みさこ『三部作』

会期:2018/01/19~2018/01/21
ArtTheater dB Kobe[兵庫県]
「ソロダンス」によるフルレングス作品の上演をシリーズ化する企画、「ダンスボックス・ソロダンスシリーズ」の第2弾。本公演の特徴は、世代、バックグラウンド、ダンスのキャリアが大きく異なる3名の振付家が、それぞれ「寺田みさこ」を振り付ける点にある。寺田は、幼少より培ってきたバレエを基礎とし、コンテンポラリーダンスの領域を横断しながら活動している。対する振付家の顔ぶれは、即興的かつ過激な身体の接触で知られるcontact Gonzoの塚原悠也、韓国を代表する気鋭のダンサー、振付家のひとりであるチョン・ヨンドゥ、KYOTO EXPERIMENTに過去3回参加し、極限的な肉体や暴力性を観客に突きつけてきたブラジルのマルセロ・エヴェリン。高い身体能力や運動の正確性を持つ寺田の身体を通して、それぞれの振付家のダンス観や身体論の差異と比較が提示されるとともに、「寺田みさこ」という固有のひとつの身体がどこまで可塑的な変容の振れ幅をもって立ち現われるのか、期待したい。なお本作は、2月に開催される「横浜ダンスコレクション2018」においても上演が予定されている。
2017/11/27(月)(高嶋慈)
プレビュー:大坪晶「Shadow in the House」

会期:2018/01/06~2018/02/18
アートラボあいち[愛知県]
大坪晶の写真作品《Shadow in the House》シリーズは、時代の変遷とともに所有者が入れ替わり、多層的な記憶を持つ家の室内空間を被写体としている。歴史の痕跡の記録であると同時に、ダンサーが室内で動いた身体の軌跡を長時間露光撮影によって「おぼろげな影」として写し込むことで、何かの気配や亡霊の出現を示唆する。それはまた、複数の住人の記憶が多重露光的に重なり合い、もはや明確な像を結ぶことのできない記憶の忘却を指し示すとともに、それでもなお困難な想起への可能性を開いてもいる。大坪は近年、日本各地に残る「接収住宅」(第二次世界大戦後のGHQによる占領期に、高級将校とその家族の住居として使用するため、強制的に接収された個人邸宅)を対象とし、精力的なリサーチと撮影を続けている。
《Shadow in the House》は写真作品だが、ダンサーとの協同作業や、「接収住宅」の所有者の遺族や管理者への聞き取り、接収関連資料のリサーチなども含む複合的なプロジェクトである。筆者はリサーチや批評文の執筆というかたちで参加している。今回のアートラボあいちでの個展では、新たに愛知県内で撮影した4件の接収物件についての新作が発表される。合わせて、接収関連文書、手紙、占領下の名古屋にあった「アメリカ村」の地図、占領期の雑誌などの資料と、「接収住宅」に関わった個人の思い出の品や写真なども展示される予定だ。パブリックな記録と個人の記憶が交差する地点から、「住宅」という私的空間における異文化の接触、それがもたらした建築的・文化的・身体的な戦後日本の変容、記憶の継承について考える機会となるだろう。
関連レビュー
大坪晶|白矢幸司「Memories and Records」|高嶋慈:artscapeレビュー
2017/11/27(月)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)