artscapeレビュー
2019年10月15日号のレビュー/プレビュー
小嶋崇嗣「PARFUM」

会期:2019/10/01~2019/10/06
KUNST ARZT[京都府]
消費社会において、物理的実体としての「商品」に付随する「脇役」を用いてジュエリーを制作し、さまざまな価値の転換を図る作家、小嶋崇嗣。本個展では、プラモデルのランナー(組み立て前のパーツを枠の中に固定・連結する棒状の部分)と、「シャネルN°5」の香水瓶の蓋、それぞれを用いた2つのシリーズが展示された。
プラモデルのランナーを素材に用いたブローチのシリーズでは、通常は組み立て後に捨てられる端材を「ジュエリー」に仕立てることで、「無価値なゴミ」を「高価な宝飾品」へと転換させる。いずれも、突起のついた棒を立体的に交差させた構築的なデザインだが、それぞれのカラーリングは、ガンダム、エヴァンゲリオンなど戦闘ロボットアニメのメカを想起させる。実体的な機体がなくとも、特徴的なカラーリングによって「キャラクター=商品」を識別させる。例えば、コンビニ各社が看板に用いるカラーバーをミニマル・ペインティングに擬態させた中村政人の作品のように、「色という記号の抽出によって、ブランドやキャラクターを非実体的に想起させる」という点で、二重の意味での消費社会批判となっている。加えてここでは、一般的には「男性向け」であるプラモデル(の端材)を、女性が身につけるジュエリーに作り変えることで、「商品に内在するジェンダー」を転倒させるという戦略性も指摘できる。

RUNNER_brooch [撮影:畔柳尭史(Polar)]
一方、「シャネルN°5」の香水瓶の蓋を用いたジュエリーのシリーズ《PARFUM》では、多面カットが施されたガラスの蓋を宝石に見立てて、ネックレス、リング、ブローチが制作されている。ガラスの蓋は爪留めでセットされ、留め具などのパーツもすべてシルバーで作られ、ジュエリー制作の技術が基盤にあることがうかがえる。香水瓶は、香水を販売するための容器だが、消費者の欲望を刺激するためのブランド戦略の象徴とも言える装置だ。小嶋は、実体的な商品そのもの(液体としての香水)ではないが、消費を促すための記号として商品価値を支える存在を「ジュエリー=商品」に変換するという転倒の操作によって、「私たちの欲望や価値を支えているものは何か」「付随的な周縁部分にこそ商品の本質が宿るのではないか」という問いをあぶり出す。だがここで、シャネル自身が実は「イミテーションの宝石」を売り出した事実を思い出すならば、単にパロディや引用による消費社会批判にとどまらない、批判とオマージュを兼ね備えた両義性を見出せるだろう。

model: TANI MAO
加えて本展の構成は、「(不在の)身体と記憶」へと言及する拡がりを持っている。「N°5」が発売されたのは1921年であり、約100年間、世代や時代を超えて無数の女性たちがこの香りを身につけてきた。小嶋の作品は使用済みの香水瓶を用いており、身にまとうと、見知らぬ誰かの残り香が漂う。ジュエリーに使用した蓋以外の瓶でつくったシャンデリアが天上から吊られ、「N°5」が発売された時代のクラシックな壁紙が張られ、ジュエリーの置かれた背後の壁には、鏡が長年置かれていたような跡が残る。消費社会への批判とともに、「かつて身につけていた女性」への想像を促す、親密な空間が立ち上がっていた。

会場風景 [撮影:畔柳尭史(Polar)]
2019/10/01(火)(高嶋慈)
Boyan Manchev『Clouds. Philosophy of the Free Body』
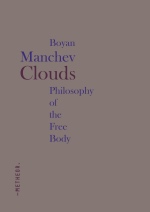
発行所:Metheor
発売日:2019/09
ソフィアおよびベルリンを拠点とする哲学者ボヤン・マンチェフは、2年前、母語であるブルガリア語で新著『雲』を上梓した★1。過去に英語、フランス語、イタリア語をはじめとする複数の言語で著されてきた哲学的散文とは打って変わって、同書は全体にわたり断片的な、ほとんど詩的と言ってもよいテクストによって構成されている。「雲とは……である」というセンテンスの執拗な反復に貫かれたこの書物では、ボードレール、ブレイク、シェリーをはじめとするわずかな例外を除けば、明示的に第三者のテクストが引用されることもない。そのスタイルは、ジョルジュ・バタイユの思想を主要な導きの糸とする『世界の変容──ラディカルな美学のために』(Éditions Lignes, 2009)や、ドストエフスキー、アルトー、ブランショらの作品をつねに傍らにおいた『変身と瞬間──生の脱組織化』(La Phocide, 2009)といった旧著(いずれもフランス語)のそれとは際立って対照的である。
筆者がマンチェフ本人から『雲』の話を聞いたのは、彼がドラマトゥルクとして関わる「メテオール」という集団が、新たに同名の出版レーベルを立ち上げたときのことだった。アニ・ヴァセヴァ(演出家、アーティスト)、レオニード・ヨフチェフ(俳優)、ボヤン・マンチェフ(哲学者、ドラマトゥルク)の3名を中心とするメテオールの舞台作品は、すでにブルガリア国内で高い評価を獲得し、その次のステップとして、同名の叢書の設立を計画しているところだった。それからわずか2年ほどのあいだに、メテオール叢書から刊行されたブルガリア語の書籍はすでに8冊におよぶ★2。そして、同叢書から刊行される9冊目の書物にして、はじめての英語の書物となるのが、ボヤン・マンチェフによる『雲』の英訳(本書)である。
はじめにも述べたように、本書は「雲」にまつわるいくぶん詩的なテクストである。同書の「プロレゴメナ」(序文)によれば、雲についての書物は、同時にそれ自体が雲のような書物でなければならない。著者の言い方に倣えば、「雲についての書物(book on clouds)」は、同時に「雲の書物(book of clouds)」にして、「雲のなかの書物(book in clouds)」でもなければならない(p. 15)。要するに本書がめざすのは、雲をめぐる抽象的な思索それ自体を、雲の形象へと接近させることである。これも著者が述べていることだが、「新たな哲学」は「新たな形式」の発明と不可分である(p. 16)。複数の文体を矢継ぎ早に切り替えていく『雲』の叙述形式もまた、まさしくそうした「新たな形式」を生み出すために選ばれたものにほかならない。
形式面だけでなく、内容面でもひとつ、本書の読みどころを紹介しておきたい。本書でもっとも特権的な人物として扱われるのは、哲学者でも文学者でもなく、ロンドン生まれの科学者ルーク・ハワード(1772-1864)である。もともと気象学には門外漢でありながら、若い頃から雲におおいに魅せられていたこのイギリス人は、のちに今日までつづく雲の分類の基本形を作り上げたことで知られる。かのゲーテとも交流のあったハワードによる雲の研究を、本書は──いささか驚くべきことに──カントの『判断力批判』(1790)とともに読むことを提案する。
なるほど、1783年に起こったアイスランドの大噴火が象徴的に示すように、雲はカントが同書で「崇高」と呼んだ自然現象と容易に結びつくものである。しかし、それはまだ物事の一面にすぎない。天空のいたるところで集合・離散を続け、そのたびごとに姿を変える雲は、噴火や雷鳴といった「崇高な」自然の象徴である以前に、私たちの思考を刺激する「形」をともなった「不定形な」現象の最たるものである(ここで著者はカントとともに、バタイユの名にも抜かりなく言及している)。そしてそれを、カントが「美的理念」と呼んだもの、すなわちいかなる概念もなしに、しかし思考を大いに刺激する理念に結びつけるのだ(p. 78)。そのような理念を産出する、「概念−以前のマグマ」としての雲(p. 80)──著者マンチェフが雲のうちに見いだすのは、「美」や「崇高」の手前に位置する、そうした感覚と理念の媒介のアナロジーなのである。
★1──同年にソフィアとプロヴディフの二都市で行なわれた『雲』のリーディング公演については、次の拙文のなかで詳述したことがある。星野太「アペイロンと海賊──『雲』をめぐる断章」、小林康夫編『午前四時のブルー』第1号、水声社、2018年。
★2──http://desorganisation.org/index.php/en/
2019/10/07(月)(星野太)
國分功一郎『原子力時代における哲学』

発行所:晶文社
発売日:2019/09/25
前著『中動態の世界』(第16回小林秀雄賞)に続く著者の2年半ぶりの新著が、本書『原子力時代における哲学』である。とはいえ、本書は2013年に行なわれた全4回の連続講義をもとにしており、そこには2011年の福島第一原発事故以来、原発をめぐるあらゆる議論が背負うことになった「緊張感」(317頁)が生々しく刻印されている。
本書の導入にあたる第一講「一九五〇年代の思想」では、核兵器、およびその「平和利用」を謳った原子力発電に対して、過去いかなる議論が重ねられてきたのかが紹介される。たとえば、原子力に対して過去なんらかの理論的考察を行なった哲学者に、ギュンター・アンダースとハンナ・アレントがいる。しかし、アンダースの批判対象はほぼ核兵器に限定されていたし、「核の平和利用」を謳う原発についての考察を行なっていたアレントも、それを技術による疎外という図式に引きつけて論じるにとどまっていた。著者によれば、いまだ多くの人々が原子力に「夢」を見ていた20世紀半ばにおいて、原子力そのものに根本的な批判を加えていた哲学者はただ一人しかいない。その人物こそ、かのマルティン・ハイデッガーである。
本書の中盤は、そのハイデッガーのテクストを実際に読んでいくかたちで進む。とりわけ、そのほとんどが講義録であるハイデガーの著作集のなかでも、生前に刊行された例外的な書物のひとつである『放下』が読解の中心に位置づけられる(講演「放下」は1955年、著書としての『放下』の刊行は1959年だが、本書で述べられるように、その成立経緯はきわめて複雑である)。その前提として、比較的よく知られるハイデッガーの技術論や、ソクラテス以前の自然哲学に対する関心にまで視野を広げつつ(第二講)、著者は本書最大の関門である対話篇「放下の所在究明に向かって」を、慎重かつ大胆に読み進めていくのだ(第三講)。
とはいえ、「科学者」「学者」「教師(賢者)」を登場人物とするこの謎めいたハイデッガーの対話篇が、いったい原子力の何を明らかにしてくれるというのか──いつものごとく、大きな問いへとむけてゆっくりと、しかし着実に歩みを進めていく本書の結論を、ここで明らかにすることはしない。ただ、これは本書の議論が深まる後半(第三講・第四講)に顕著なのだが、『スピノザの方法』における「真理」、『暇と退屈の倫理学』における「環世界」、そして『中動態の世界』における「中動態」概念などに立脚しながら開陳される著者の思想は、これまでの仕事から驚くほどに一貫している。考察の対象となるテーマはそのつど異なっていながら、著者の問いはいつも「この」時代にむけられてきたことを、読者は本書を通じて身をもって感じることになるだろう。本書の読後に「原子力時代」とはつまるところ何か、と問われれば、それは「完全に自立したシステム」(271頁)を夢見るナルシシズムに満たされた時代だ、ということになろう。「原子力時代における」哲学の仕事とは、そのような時代にいかなる哲学が可能かを考えることにほかなるまい。
[hontoウェブサイト]
2019/10/07(月)(星野太)
カタログ&ブックス│2019年10月
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
公の時代

著者:卯城竜太(Chim↑Pom)、松田修
発行:朝日出版社
発行日:2019年9月26日
定価:1,800円(税抜)
サイズ:四六判、322ページ
官民による巨大プロジェクトが相次ぎ、炎上やポリコレが広がる新時代。社会にアートが拡大するにつれ埋没してゆく「アーティスト」と、その先に消えゆく「個」の居場所を、二人の美術家がラディカルに語り合う。
身体を引き受ける トランスジェンダーと物質性(マテリアリティ)のレトリック

著者:ゲイル・サラモン
翻訳:藤高和輝
装幀:近藤みどり
発行:以文社
発行日:2019年9月13日
定価:3,600円(税抜)
サイズ:四六判、376ページ
「LGB fake-T」として、不可視化されてきたトランスジェンダーの身体。本書は、現象学や精神分析をトランスジェンダー理論として読み直す。「身体自我」、「身体図式」などの概念を駆使して、トランスジェンダーの身体経験を理論的に考察。「身体とは単なる物質的なものではなく、身体イメージの媒介によってはじめて生きられる」というトランスジェンダーの身体経験の分析を通じて身体そのものを問い直し、「感じられた身体」と「物質的な身体」の不一致や心身二元論を乗り越える枠組みを提示する。トランスジェンダースタディーズの重要書。
ジュディス・バトラー絶賛!
アフター・カルチュラル・スタディーズ

著者:吉見俊哉
発行:青土社
発行日:2019年7月20日
定価:2,600円(税抜)
サイズ:四六判、352ページ
〈文化〉と〈政治〉をめぐる問いを深化させてきたカルチュラル・スタディーズの大いなる蓄積の後に、どのような批判的な知を構築し直せるのか? そして、新自由主義により社会が分断され、現実の基盤が崩壊するなかで、どのような知を追い求めればいいのか? 〈連帯〉へと向かう、挑戦の書。
空蓮房 仏教と写真

著者:谷口昌良、畠山直哉
デザイン:木村稔将
発行:赤々舎
発行日:2019年10月7日
定価:2,500円(税抜)
サイズ:190mm×130mm、176ページ
2006年に、谷口昌良が寺院の一角に瞑想のための空間として構えた「空蓮房」。
そこで開かれた写真展示を振り返り、その活動と書かれた言葉に思いを巡らす。
谷口が仏教と写真術を同時に考えて語る理由や意義を、畠山直哉によって 「翻訳」し「解釈」したものでもある本文は、いま写真芸術に最も必要とされることは何なのか、
その深化した議論を喚起するための問いかけであり、「祈り」である。
光の子ども3

著者:小林エリカ
デザイン:五十嵐哲夫
発行:リトルモア
発行日:2019年9月
定価:1,800円(税抜)
サイズ:A5判、264ページ
第一部、完結。
戦争、科学、ファシズム、女たち、地震、デマ──
重層的なテーマを、和紙に描かれた漫画、テキスト、写真や図など膨大な資料のコラージュで表現。
〈放射能〉と、今日直面するエネルギー問題のつながりを読みとくアート・コミック。
写真の物語 イメージ・メイキングの400年史

著者:打林俊
発行:森話社
発行日:2019年7月24日
定価:3,200円(税抜)
サイズ:四六判変型、488ページ
写真の誕生から180年。いまではさまざまなイメージがメディアに溢れ、誰もがあたりまえに接している「写真」とは本来どのようなものなのだろうか。
写真発明の前史から現代までの400年の歴史を、発明競争、技法の開発、大衆の欲望、美術やメディアとの相互関係といった観点から豊富な作品例とともにたどり、交錯する歴史から、「モノ」としての写真とその発展をめぐる人々の物語を描き出す、気鋭の写真史家による新たな写真史。作品図版も多数掲載し、入門書としても最適。
ゲンロン10

編集長:東浩紀
著者:高橋源一郎、原武史、家入一真、桂大介、長谷敏司、三宅陽一郎、大森望、ドミニク・チェン、山本貴光、吉川浩満、高橋沙奈美、本田晃子、高山明、ユク・ホイ、イ・アレックス・テックァン、黒瀬陽平、速水健朗、海猫沢めろん、松山洋平、辻田真佐憲、東浩紀、上田洋子
発行:株式会社ゲンロン
発行日:2019年9月26日
定価:2,400円(税抜)
サイズ:A5判、328ページ
ゲンロンの機関誌『ゲンロン』は、2019年の秋に第2期に入りました。
『ゲンロン』第1期は2015年冬刊行の『ゲンロン1』に始まり、2018年秋刊行の『ゲンロン9』で終了しました。『ゲンロン10』は、1年の準備期間を経ての、第2期再創刊号となります。第2期の『ゲンロン』は、半年から9ヶ月の期間をおいて、不定期に刊行される予定です。
第2期の編集長も、第1期に続いてゲンロン創業者の東浩紀が務めます。第1期の『ゲンロン』は、戦後日本の哲学と文芸批評の伝統をアップデートする試みとして、読書界で高い評価を得ました。第2期の『ゲンロン』は、そのレガシーを継承しつつも、より広い読者を対象とした新たな知的言説の創出に挑みます。
YCAM BOOK


編集:渡邉朋也(YCAM)
編集協力:青柳桃子(YCAM)、石井草実(YCAM)、岡崎里美(YCAM)、橋本奈々美(YCAM)、松冨淑香(マツトミ企画制作室)
アートディレクション:三迫太郎
デザイン:三迫太郎、福田奈実
表紙撮影:山中慎太郎(Qsyum!)
発行:山口情報芸術センター[YCAM]
発行日:2019年9月
定価:2,000円(税込)
サイズ:B5判、72+128ページ
YCAMの取り組みをご紹介する冊子「YCAM BOOK」が完成しました。この冊子は、YCAMの多岐に渡る活動をご紹介するとともに、YCAMがある山口県の観光地・宿泊・飲食店の情報をご案内するものです。
YCAMの概要や周辺の情報を紹介する「YCAM GUIDEBOOK 2019-2020」と、2018年度のYCAMの活動を振り返る「YCAM ANNUAL REPORT 2018-2019」の2冊で構成されており、両者合わせて200ページを超える大ボリュームです。購入はYCAM1階のチケットインフォメーションのほか、全国の書店などでも販売中です。お見かけの際はぜひご購入ください。
建築学生ワークショップ出雲2019 ドキュメントブック

制作・編集:特定非営利活動法人アートアンドアーキテクトフェスタ
アートディレクション:平沼佐知子(平沼孝啓建築研究所)
発行:特定非営利活動法人アートアンドアーキテクトフェスタ
発行日:2019年9月14日
定価:1,852円(税抜)
サイズ:A4判、126ページ
建築等の分野を専攻する大学生や院生を対象にした地域滞在型のワークショップ、「建築学生ワークショップ出雲2019」の作品や制作の様子などを豊富な写真で紹介する。実施制作に向けた経緯をまとめた冊子付き。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
2019/10/15(火)(artscape編集部)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)