artscapeレビュー
2018年07月15日号のレビュー/プレビュー
百々武「もう一つのものづくり MOTTAINAI ARIGATAI」

会期:2018/06/14~2018/06/20
キヤノンギャラリー銀座[東京都]
百々武が2017年に刊行した『もう一つのものづくり』(赤々舎)は、とても興味深いテーマの写真集だった。被写体になっているのは岡山に本拠を置く産業廃棄物処理会社、平林金属の作業場である。OA機器や家電から自動車や船舶まで、驚くほど多種多様な廃棄物を「選別・破砕・切断・解体・圧縮」して、リサイクル資源として活用していく現場が、克明に描写されていた。
今回のキヤノンギャラリー銀座の個展では、基本的には写真集のコンセプトを活かしつつ、展示作品のインスタレーションに工夫を凝らしている。かなり大判のプリントに引き伸ばされ、アクリル加工された写真(15点)には、それぞれの画面にのみエリアスポットライトで光を当て、あたかも現代美術の彫刻作品を思わせる産業廃棄物のフォルムや質感を強調している。また、金属やプラスチックの塊を、黒バックで「宝石のように」撮影し、モザイク状に並べて背後からの透過光で浮かび上がらせるインスタレーションもあった。この種の作品の場合、どうしても「モノ」中心の構成になりがちだが、作業員の存在をきちんと取り込み、ヒトの匂いのする空間として撮影していたのもよかったと思う。
大事なのは、産業廃棄物処理という仕事が、「処理ではなくものづくり」であり、その現場は「factoryではなくfarm」であるという認識が、きちんと貫かれているということだ。写真を通じて、そのことをけっして押し付けがましくなく、謙虚な姿勢で伝えようとしていた。「farm」としての工場というのは面白い観点だと思うので、被写体の幅を産業廃棄物だけでなく、もっと広げていってほしい。なお本展はキヤノンギャラリー名古屋(2018年7月5日~7月11日)、同大阪(2018年7月19日~7月25日)にも巡回する。
2018/06/20(水)(飯沢耕太郎)
池田葉子「Crystalline」
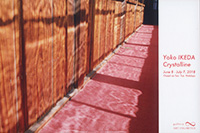
会期:2018/06/08~2018/07/07
池田葉子は今年の1月に、「壁面をきらびやかに埋め尽くすヨーロッパ古典絵画」の展覧会をたまたま見て、作品を「コレクティブに見せる」展示の仕方に強い印象を受けた。今回のgallery ART UNLIMITEDの個展では、そのパワフルな視覚的効果を再現するために、一番大きな壁に大小さまざまな写真18点を、「結晶体=Crystalline」に見立てて展示構成していた(ほかに11点を出品)。
京都、北海道、ロサンゼルス、ロンドン、台北など撮影地はさまざまだが、被写体の切り取り方には独特の美意識とリズムを感じる。クローズアップで、何が写っているかわからないほどに抽象化された写真が多いのだが、色味をコントロールして柔らかいトーンでまとめているので、目に気持ちよく飛び込んでくる。今回、特に特徴的だったのは「結晶体=Crystalline」といっても輪郭がくっきりと際立った鉱物質ではなく、どちらかといえばエッジがぼかされた有機的な印象を与える、画面の一部がブレたりボケたりした作品だった。フレームの色や材質もそれぞれの写真で変えるなど、会場全体のインスタレーションも注意深く整えられていて、新たな方向に踏み出していこうとする強い意欲を感じた。
2016年に第32回東川賞新人作家賞を受賞したことで、池田の写真家としての営みに弾みがついてきているようだ。こうなると、モノや風景だけでなく、ヒトを撮影した写真も見たくなってくる。
2018/06/21(木)(飯沢耕太郎)
片山達貴「voice training」
会期:2018/06/19~2018/06/30
「アァー…」「エー…」「ウァー…」という引き伸ばされた母音が、二重に重なり合いながら響く。2面プロジェクションの映像ではそれぞれ、互いの口や鼻、喉を指で触り、相手の発声を操作しようとする2人の男性の姿が映される。唇を横や上下に引っ張る、丸くすぼめさせる、鼻をつまむ、喉に接触する。相手からの干渉を受けるたびに、母音の音が変化し、あるいはくぐもった声となる。片山達貴の映像作品《ボイストレーニング_1》では、互いの発生器官に介入し、こねくり回し、身体に外側から力を加えて声を変化させることで、「声」が可塑的なものであることが音響的に示される。

片山達貴《ボイストレーニング_1》 2018
片山によれば、本作の制作に至る経緯として、結婚相手の母親が中国残留孤児2世(ネイティブの中国語話者/日本語は第二言語として成人後に習得)であり、意思疎通をはかるために、彼女と行なった中国語の発音練習を記録した映像作品《口づくり》があるという。差し向かいで発音練習をひたすら繰り返す行為は、自身の母語と向き合うきっかけになり、「自分の口は母語によって形づくられ、母語に制限されている」感覚が芽生えた。そこから、「自分の声はどこまで自分だけのものと言えるのか」という疑問が派生し、外部からの影響/自らの意志がせめぎ合うあわいを探ろうと、本作を制作したという。
「新しく家族になる人とのコミュニケーションをはかる」というポジティブな目的で始められた《口づくり》とは異なり、《ボイストレーニング_1》では、性差、年齢差、異言語の話者であること、「教える-模倣する」といった2者間のさまざまな差異はフラットに均され、声に介入し変化させる加圧的な「外側からの力」が何であるのかは、曖昧にぼかされている。ゆえに、見る者はそこにさまざまな「力」の発露を想像することが可能だろう。それは、ジェンダーや社会的立場など、日常的に私たちの身体的ふるまいを規定する社会的な関係性であり、「訛りの矯正」「正しい発音」「標準語」といった、教育やマスメディアを通して「国民の身体」として統制・均質化しようとする力である。あるいは、もしこの2人が異言語話者であった場合(例えば、日本語話者と韓国・朝鮮語話者であった場合)、「支配的言語の強制」「母語の剥奪」といった植民地的暴力を想像することも可能だろう。本作は、「_1」と銘打たれているように、パフォーマーを変えてシリーズ化が構想されているという。シリーズ化を通して、テーマの発展とより深い掘り下げに期待したい。
2018/06/23(土)(高嶋慈)
サポーズ・デザイン・オフィスの社食堂、「堺町ビルプロジェクト」
[東京都]
代々木上原の谷尻誠、吉田愛が率いるサポーズ・デザイン・オフィスの社食堂にて、ランチを食べる。土曜の昼だったが、かなり賑わっていた。半地下の空間であり、事務所のエリアとの間に間仕切りはなく、食堂から働いている様子がまる見えだった。仙台の卸町の倉庫を転用した阿部仁史のアトリエも、レクチャーの開催時、横でスタッフが仕事をしていたが、社食堂は天井が低い分、もっと近接した感じである。もともとはスタッフもうまくて健康的な料理を食べられるようにと谷尻さんが始めたプロジェクトらしい。飯田善彦の事務所も大量の蔵書があることを活かし、1階をブック・カフェとして開放していたが、これらは《CASACO》が住宅を開くように、事務所を開くタイプの試みと言えよう。
広島市において、サポーズ・デザイン・オフィスによる「堺町ビルプロジェクト」を見学した。場所は川を隔てて、《広島平和記念公園》のすぐ近くである。自社運営(!)のホテル《THE PLACE》を建設する前に、敷地にある解体予定の古いアパートを活用し、10組のクリエイターの表現スペースとして開放するプロジェクトだ。したがって、期間限定である。劇団が活用する部屋は上演中のため、室内を見ることができなかったが、401号室の竹村文宏の「絵画を構築する」、402号室のCarlosによる「解体を構築する場R」、ほかに2A号室のmasmによる絵画と空間インスタレーションなどが印象に残った。いずれもホワイトキューブではなく、さらに現状復帰も要請されない条件を生かし、建築空間と深いつながりをもつアートを展開している。ただし、ゴードン・マッタ=クラークのような壁や床を切りとるほど、ラディカルな介入ではない。それでも、「解体を構築する場R」は、畳や押し入れなど、日本のアパートならではの部位をうまく読み替えていた。サポーズ・デザイン・オフィスは、モノのデザインだけではなく、コトを起こすことに長けている。
 サポーズ・デザイン・オフィスの社食堂
サポーズ・デザイン・オフィスの社食堂
 サポーズ・デザイン・オフィスの左がオフィス。右が厨房
サポーズ・デザイン・オフィスの左がオフィス。右が厨房
 「堺町ビルプロジェクト」入り口
「堺町ビルプロジェクト」入り口
 竹村文宏「絵画を構築する」
竹村文宏「絵画を構築する」
 Carlos「解体を構築する場R」
Carlos「解体を構築する場R」
 masm「Gallery ‘ROOM-A’」
masm「Gallery ‘ROOM-A’」
2018/06/23(土)(五十嵐太郎)
平田オリザ『日本文学盛衰史』
吉祥寺シアター[東京都]
高橋源一郎の小説を原作とした平田オリザの演出による演劇『日本文学盛衰史』を見る。数多くの文豪が次々に登場するため(俳優も性別を超えて、役をかけ持ちしたり、最後は胸に名札をつけていた)、最初は誰が誰なのかを把握できず、とまどうが、現代にも射程を伸ばしながら、日本近代文学史の諸問題を考えさせる内容だった。すなわち、明治期の文学者が言文一致を模索し、内面を発見する一方で、国家と言語の関係を意識した歴史を、和風建築の料亭で開催された4人の葬儀を通じて、ポストモダン的に検証していく(ラストは駆け足で、AIが小説を執筆するようなSF的な未来予測も!)。これまでとは異質の語りと身ぶりを演劇において提示したチェルフィッチュの『三月の5日間』も引用されるなど、笑わせるシーンも少なくない。それにしても、原作に込められた濃密な情報量と、さまざまな参照群を演劇化する平田の手腕は見事である。
われわれが当たり前だと思っている、小説という形式や世界の認識。それが近代においてどのように生成したかは、柄谷行人の『日本近代文学の起源』などでも論じられたテーマだが、小説や演劇という方法によっても実験的に表現可能であることに驚かされた。特に演劇はライブであるからこそ、いままさに起きている日々の時事問題も組み込みながら、随時、台詞を改変していく(例えば、開演前のナレーションにおける「日本大学盛衰史」という読み違え)。現在、日本の政治は、言葉と文書を徹底的に軽く扱い、ジョージ・オーウェルのディストピア小説『1984』のような事態がリアルに進行している。そうしたタイミングだからこそ、いま「日本文学盛衰史」が演じられることに大きな意味があるはずだ。ところで、この演劇を見ながら、やはりまったく新しい経験をすることになった日本近代建築でも同じようなことができないかと考えさせられた。
2018/06/23(土)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)