artscapeレビュー
2021年05月15日号のレビュー/プレビュー
崇仁地区をめぐる展示(前編)「タイルとホコラとツーリズム」Season8 七条河原じゃり風流
会期:2021/03/20~2021/05/05
京都市下京いきいき市民活動センター[京都府]
本稿では、京都市の崇仁地区の地域性や歴史に向き合った2つの取り組みを前編と後編に分けて紹介する。まずその前に、「なぜ近年、この地区でアートが展開されているのか」という背後の文脈について、この京都駅東部エリア(崇仁地区)と隣接する東南部エリア(東九条地区)をめぐる近年の動向を概説する。
両地域ともに、2023年度に予定されている京都市立芸術大学の移転に向けて、大きな変化のただなかにある。移転予定地である崇仁地域は、高齢化や建物の老朽化が進んでいたが、移転に向けて解体工事が進行中だ。同地域では、「芸大移転整備プレ事業」として、移転予定地にある元崇仁小学校の教室を利用したギャラリー(校舎の解体に伴い2020年に閉鎖)での展示やさまざまなアートプロジェクトが展開されている。崇仁地区の空き地を利用した展示の先駆例としては、PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015で、廃棄された資材を用いて仮設的な公園の祝祭的空間を出現させたヘフナー/ザックス《Suujin Park》がある。
隣接する東九条地区では、芸大移転を見据え、文化芸術や若者を基軸とした地域活性化をめざす「京都駅東南部エリア活性化方針」が2017年に京都市より打ち出された。今年3月には、契約候補事業者にチームラボが選定され、チームラボの作品を展示するミュージアム、アートギャラリーのテナント誘致、学生や地域住民が利用できるギャラリー、カフェなどを備えた複合施設の開業が計画されている。同地域には、2019年、民間の小劇場THEATRE E9 KYOTOがオープンしており、若手アーティストの共同スタジオが定期的にオープンスタジオを開くなど、崇仁とともに「文化芸術のまち」として今後さらに発展していくことが期待される。一方、両地域は、西日本最大の被差別部落であった歴史や在日コリアンが多く住む地域であることなど、複雑な負の歴史をともに持ち、ジェントリフィケーションにアートが加担することの功罪を考える必要がある。
また、京都市は、2017年度より東九条にて、文化芸術によって多文化共生社会をめざすモデル事業を東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス(HAPS)へ委託して実施。2017年度はダンサー・振付家の倉田翠が、2018年度は美術作家の山本麻紀子が、それぞれ地域の福祉施設や住民と協働して制作活動を行なった。2019-2020年度は対象地域を崇仁に移し、「京都市 文化芸術による共生社会実現に向けた基盤づくり事業 モデル事業」との名称で、主催であるHAPSの企画のもと、山本麻紀子と「タイルとホコラとツーリズム」の2組のアーティストが参加した。

[撮影:麥生田兵吾]
本稿の前編では、上述の2019-2020年度の京都市モデル事業の一環として行なわれたアートプロジェクト「『タイルとホコラとツーリズム』Season8 七条河原じゃり風流」を取り上げる。美術家の谷本研と中村裕太のユニットである「タイルとホコラとツーリズム」は、京都の街中に点在する「タイル貼りのホコラ」の路上観察学的なリサーチを起点に、民俗学、生活史、暮らしのなかの土着的な信仰、ツーリズムと消費といった観点から、分野横断的な制作を行なってきた。
本プロジェクトでは、明治42(1909)年、柳原尋常小学校(崇仁小学校の前身)が建設される際、地域住民が一体となって、鴨川の河原の土砂を運んで建設用地を整備した「砂持ち」に注目した。住民たちは揃いの衣装や仮装によって、土砂を運ぶ「労働」を「祝祭」に変えていたという。谷本と中村がもうひとつ着目したのは、芸大建設予定地や周辺の市営住宅の老朽化・建て替えに伴い、地域にあったお地蔵様のホコラが寺社などに移動されて路傍から姿を消したことである。そこで谷本と中村は、河原から運んだ砂利で、市営住宅の公園の砂場に「お地蔵様のモザイク画」を描き、忘れられたかつての風習を自らの肉体を駆使して再現・再演することで、「労働」と「信仰」の両面から地域の歴史に光を当てた。この試みは、京都~滋賀県の大津を繋ぐ白川街道を、道中のホコラや石仏に花を手向けながら歩き、商品の運搬という「労働」と「信仰」の結びつきを身体的に再体験して伝える過去の取り組み「season3 《白川道中膝栗毛》」などとも共通する。

[撮影:麥生田兵吾]

[撮影:表恒匡]
完成したモザイク画は、市営住宅の上階から撮影され、大きく引き伸ばした写真が地域内の市民センターの外壁に見守るように掲げられた。また、制作過程の記録写真を、「砂持ち」やお地蔵様にまつわる聞き取りとともに掲載する「かわら版」が制作され、発行毎に地域の全戸へ配布することで、プロジェクトの成果が地域へと還元された。この「かわら版」は、下記のウェブサイトでPDFが閲覧できる。
HAPSウェブサイトhttp://haps-kyoto.com/tht8_jarifuryu/
(後編に続く)
関連レビュー
タイルとホコラとツーリズム season3 《白川道中膝栗毛》|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年09月15日号)
PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015|高嶋慈:artscapeレビュー(2015年05月15日号)
2021/04/22(木)(高嶋慈)
崇仁地区をめぐる展示(後編)『Suujin Visual Reader 崇仁絵読本』刊行記念展

会期:2021/04/17~2021/06/20(会期延長)
京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]
(前編から)
後編で取り上げるのは、京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAでの『Suujin Visual Reader 崇仁絵読本』刊行記念展である。同ギャラリーでは毎年、海外作家を招聘して展覧会、ワークショップ、レクチャーを実施しており、2019年度の招聘作家であるジェン・ボーが行なったワークショップ「EcoFuturesSuujin」が本展の経緯にある。ボーは、1922年に京都で採択された日本初の人権宣言「全国水平社創立宣言」に着目し、この宣言を「雑草や植物を含むすべての種の平等」へと拡張的に更新するための草案をつくるワークショップを行なった。また、崇仁の歴史や魅力を視覚的に伝えるための本の編集にも着手。その刊行記念展である本展では、ワークショップ参加者で崇仁にあるアトリエで制作する森夕香が描いた挿画が展示された。

[写真:来田猛 提供:京都市立芸術大学]
柔らかいタッチと色彩で描かれた森の挿画は、現在の街の生活風景で始まり、その歴史を辿り直していく。現在と過去、そのあいだの連続性と断絶を媒介するのが、すでに解体されて姿を消した崇仁小学校の校舎である。前編で紹介した「『タイルとホコラとツーリズム』Season8 七条河原じゃり風流」でも参照された小学校建設のための「砂持ち」に始まり、学び舎の風景、水平社宣言の起草、住民たちが自ら設立した柳原銀行とその移転・資料館設立へと続く。2000年代以降は、小学校でのビオトープ建設、閉校、市民活動の場としての利用、芸大移転に向けたさまざまなアートプロジェクトの展開、新校舎の建築プラン、ボーのワークショップの様子へと続いていく。最終ページには、意味ありげな「何も描かれていない白い余白」が残されている。その空白は、「解体工事による現在の空き地」を物理的に喚起するとともに、それに伴う「記憶の消滅や忘却」を示唆する。一方そこには、「まだ見ぬ未来の可能性の余白」への希望もせめぎ合う。
この白紙のページは、徐々にさまざまな描き込みで埋められ、「空白」があったことそれ自体も忘却されていくだろう。記憶の忘却やジェントリフィケーションにアートがどう対峙しえるのか、今後大きく様変わりするであろう地域の変遷とともに注視していきたい。

[写真:来田猛 提供:京都市立芸術大学]
*緊急事態宣言延長をうけ、5/31まで休館。
関連レビュー
ジェン・ボー「Dao is in Weeds 道在稊稗/道(タオ)は雑草に在り」|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年07月15日号)
2021/04/22(木)(高嶋慈)
美術ヴァギナ
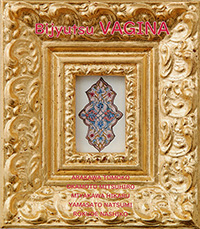
会期:2021/04/23~2021/05/09
KUNST ARZT[京都府]
「美術ペニス」展(2013)、「モノグラム美術」展(2014)、「ディズニー美術」展(2015)、「フクシマ美術」展(2016)、「天覧美術」展(2020)の企画シリーズをとおして、男性器、著作権、フクシマ、天皇制といった「タブー」や表現規制について問題提起してきたKUNST ARZT。「天覧美術」展が前年のあいちトリエンナーレ2019における「表現の不自由展・その後」中止に対する批判的応答であるのに対し、本展の背景には、昨年夏、美術家・漫画家のろくでなし子に対して「わいせつ」と認めた最高裁判決がある。ろくでなし子自身も参加した本展は、表現規制に対する異議申し立てと「表象を自己肯定的なものとして女性自身の手に取り戻す」エンパワーメントという点では評価できる一方、後述するように、ジェンダーの観点からはある種の後退や限界を抱えてもいた。
はじめに、本展の起点にあるろくでなし子の逮捕と裁判について概要を記す。ろくでなし子は、自らの女性器を型どって装飾を施した「デコまん」シリーズの展示と、クラウドファンディングの出資者に自身の女性器の3Dデータを返礼として配布したことを理由に、2014年に二度逮捕された。前者の作品展示については東京高裁での二審で無罪が確定したが、後者は2020年、最高裁で「わいせつ電磁的記録等送信頒布罪」の判決が下された。

会場風景 [Photo: OFFEICE MURA PHOTO]
本展の意義はまず、無罪確定後に裁判所から返却された「デコまん」3点を展示し、「逮捕の対象となった問題作だから見せない」とする自主規制や排除に対峙する点にある。また、3Dデータ配布が問題視された理由には、「第三者による複製可能性」と「ネット上での流通・売買の可能性」があると思われるが、3Dデータを出力した造形物を用いた「新作」の展示は、「これは電子データの配布ではない」として裏をかくしたたかな戦略性を見せる。
性(器)表現への規制や検閲に対する異議申し立てとして、本展は「美術ペニス」展と対をなす企画だが、最大の違いは、女性器(を含む女性の身体)が男性によって一方的に表象され、性の対象として消費され、「淫ら」と断罪されてきた不均衡の構造と歴史がある。誰が表象と搾取の主体で、「わいせつ」の判断や線引きは誰によってなされるのかを問い、「表象を自己肯定的なものとして取り戻す」こと。この点で、ろくでなし子の「デコまん」は、フェミニズムアートの系譜に位置づけられる。「ポップなかわいさ」や「無害なゆるキャラ」を装った「まんこちゃん」のゆるさは、むしろ戦略的である。型どりした女性器をフェイクファーやアクセサリー、スイーツの形のパーツで装飾した「デコまん」は、ネイルアートやデコ電(キラキラのパーツなどで装飾した携帯電話)と同様、「カワイイ」と気分をアゲるために装飾し、装飾パーツの「盛り」によって「隠すべきもの」を自分自身が楽しむものとしてポジティブに反転させる。女性器のモチーフをネイルアートとして表現する宮川ひかるの作品では、「私の身体と性は他人の所有物や消費対象ではなく、私自身のものである」というメッセージが、ネイルチップすなわち実際に身に付ける装飾品であることで、より強化される。

ろくでなし子《押収されたデコまん3点》(2021) [Photo: OFFEICE MURA PHOTO]

宮川ひかる《マンネイルサンプルチップ》(2021) [Photo: OFFEICE MURA PHOTO]
「わいせつな行為と表現」を処罰の対象として規定する現行の刑法の枠組みが明治期の旧刑法で形づくられたように、「わいせつ」の概念が近代化の所産であることを示してみせるのが、山里奈津実と荒川朋子の作品である。山里は、男性向けアダルトグッズの断面図を金泥で細密描写し、軸装によって宗教的な図像に昇華させることで、性器が持つ「聖と俗」の両極性をあぶり出す。そこには、「これは女性器の機能を代替する機械であり、性器そのものの描写ではない」として規制や検閲をすり抜ける戦略と同時に、性の商品化に対する疑義がある。また、原始的な形象の木彫につけまつげやウィッグ用の毛髪を用いて「毛を生やす」荒川の造形作品は、豊穣や多産を祈る古代の祭具や呪術的な神具を想起させる。

山里奈津実 左より《No.23 x》《No.23 y》(2020) [Photo: OFFEICE MURA PHOTO]

荒川朋子《ふさふさ》(2014) [Photo: OFFEICE MURA PHOTO]
ただ、本展企画者でKUNST ARZT主宰の岡本光博の作品と、ろくでなし子の新作には、ジェンダーの偏差的な視線や固定的な規範がこびりつく点で疑問が残る。ダジャレや記号的な遊戯性を駆使する岡本の作品は、「ウェットティッシュの取り出し口が女性器の割れ目の形をした、ピンク色のティッシュボックス」と、購入者のみ内部に封入されたものを覗ける《まんげ鏡》である。「自慰行為のおとも」と「覗き見」の対象であることを疑わない両者は、男性の「エロ」の視線の対象にすぎないことをさらけ出す。
また、ろくでなし子の新作は、「まんこちゃん」のゆるキャラ人形と自身の女性器の3Dデータを出力した造形物を、「子ども用玩具」の無邪気で無害な世界に潜ませたものだ。前者では、ピンク色の「まんこちゃん」がやはりピンクを基調とした女児向けおままごとセットのドールハウスで暮らし、後者では、男児の人形が乗り込むオープンカーや電車、飛行機をよく見ると、人形を座らせる操縦席が割れ目の形になっている。ここでは、女性器(を持つ身体)は「おままごとセットが備えられた家」すなわち「家事=女性の再生産労働の領域」に再び囲い込まれてしまう。また、「3Dデータの作品化」は一見挑発的だが、「女体」=文字通りクルマや飛行機の「ボディ」として、「男性が思いのままに操縦し、またがり、使役する対象」として再び客体化されてしまう。この点で、(例えばろくでなし子自身が乗り込んで操縦する《マンボート》と比べると)、ジェンダーの観点からは批評的退行と言える。
本展をとおして、女性器の即物的な表象のみや、「わいせつか表現の自由か」という二項対立的な図式だけでは不十分なことが見えてくる。本展は、表現規制への異議申し立てを出発点に、問われるべき必要な視座を抽出するためのひとつの通過点である。

ろくでなし子《3D まんこトレイン+3D まんこエアプレイン+3D まんこオープンカー》(2021) [Photo: OFFEICE MURA PHOTO]
関連レビュー
天覧美術/ART with Emperor|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年06月15日号)
VvK Programm 17「フクシマ美術」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年01月15日号)
ディズニー美術|高嶋慈:artscapeレビュー(2015年06月15日号)
2021/04/24(土)(高嶋慈)
鈴木マサルのテキスタイル展 色と柄を、すべての人に。

会期:2021/04/25~2021/05/09(※)
※新型コロナウイルス感染防止対策により開催中止。その後の開催については未定だが、詳細が決まり次第、東京ドームシティ Gallery AaMoのホームページにて告知。
いま、日本でもっとも旬なテキスタイルデザイナーといえば、鈴木マサルだろう。自身のファブリックブランド「OTTAIPNU」をはじめ、マリメッコやカンペール、ユニクロといった国内外の人気ブランドから、傘や鞄、ストール、Tシャツ、ハンカチ、タオル、靴下などのテキスタイルプロダクトを数々発表しているからだ。もしかすると、あなたの家にも彼がデザインしたテキスタイルプロダクトがひとつくらいあるかもしれない。現在、彼は仕事の領域がさらに広がり、家具や建築空間、街頭フラッグなども手がけているという。そんな彼の過去最大規模の展覧会として企画されたのが、「鈴木マサルのテキスタイル展 色と柄を、すべての人に。」である。プレスリリースやチラシ、彼自身のSNS投稿などを見て、私も同展をとても楽しみにしていた。が、悲しいかな、直前に緊急事態宣言が発令されて開催中止となってしまった。ちょうどゴールデンウィークにかけての会期だったためだ。
会期の数日前から鈴木が設営風景をSNSで発信するのを見ていたので、開催中止が発表された際、あまりにも無念だったろうなと同情を寄せてしまった。そんな思いに駆られた人は当然私だけではなかったようで、ドローンによる会場撮影やダンサーによるパフォーマンスが急遽企画されるなど、彼を応援する動きがいくつか見られた。読者の方にはそれらの映像をお楽しみいただきたいと思う。
会場ウォークスルー映像
5月8日配信ライブ「森下真樹と鈴木美奈子、色と柄と踊る。」
さて、私は会期直前のプレス内覧会を観た。タイトルどおり、色と柄に包まれる展覧会だった。まず、天井から吊り下がった大きなファブリック作品が来場者を出迎えてくれる。奥の空間の宙には120点もの開いた傘! 会場は周遊式になっていて、鈴木がこれまでに手がけたテキスタイルプロダクトや家具がゾーンごとにずらりと並んでいた。なかでも興味深かったのは、手描きの原画やスケッチ、アートパネル、絵刷り(製版を紙の上で確認する試験刷り)などをパッチワークのように展示したコーナーだ。彼のデザインの持ち味は手描きから生まれるカジュアルさやほっこりとした温かさである。そこに豊かな色彩が加わり、人々の気持ちを明るくさせる。ファブリックブランド「OTTAIPNU」を始める際、「会社で何か嫌なことがあった時、帰り道に衝動買いしてしまうようなものを作ろう」と考えたという解説が印象に残った。そう、彼が生み出すデザインはまさに価値創造なのだ。気分を高揚させ、感情的に満足させる。そんなデザインがいまのコロナ禍では強く求められている気がした。
 展示風景 東京ドームシティ Gallery AaMo[撮影:三嶋義秀(Styrism Inc.)]
展示風景 東京ドームシティ Gallery AaMo[撮影:三嶋義秀(Styrism Inc.)]
 展示風景 東京ドームシティ Gallery AaMo[撮影:三嶋義秀(Styrism Inc.)]
展示風景 東京ドームシティ Gallery AaMo[撮影:三嶋義秀(Styrism Inc.)]
 展示風景 東京ドームシティ Gallery AaMo[撮影:三嶋義秀(Styrism Inc.)]
展示風景 東京ドームシティ Gallery AaMo[撮影:三嶋義秀(Styrism Inc.)]
公式サイト:https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/event/masaru_suzuki.html
2021/04/24(土)(杉江あこ)
「さいたま市民の日」記念企画展 第6回「世界盆栽の日」記念・「さいたま国際芸術祭 Since2020」コラボレーション展 ×須田悦弘・ミヤケマイ
会期:2021/04/23~2021/05/19
さいたま市大宮盆栽美術館[埼玉県]
本展は「さいたま国際芸術祭2020」招聘アーティストの作品とさいたま市大宮盆栽美術館が所蔵する盆栽とのコラボレーション展である。招聘アーティストは須田悦弘とミヤケマイの2人で、彼ら現代アーティストによって盆栽飾りがどのように変身するのかが見どころだった。恥ずかしながら、本展を観るまで私は盆栽に関してまったく知識がなかった。さいたま市に大宮盆栽村があることも、そこが日本一有名な盆栽産地であることも初めて知ったくらいである。したがって盆栽飾りを「席」と数えることや、普段、盆栽は屋外にあり、客をもてなすためにわずか数日間だけ屋内に入れて飾ることなども一から教わった。本展では須田が1席、ミヤケが7席の作品を発表。須田は盆栽ではなく、盆器とのコラボレーションを試みた。同館が所蔵する「均釉楕円鉢」という鮮やかで厚ぼったい青磁の鉢の底から、自身の彫刻作品である一輪の可憐な菫の花を“咲かせ”、そこに本物の生がないにもかかわらず、生き生きとした生命感を表現したのである。
 須田悦弘《菫》(2021)木彫・彩色、木 均釉楕円鉢(大宮盆栽美術館)
須田悦弘《菫》(2021)木彫・彩色、木 均釉楕円鉢(大宮盆栽美術館)
対してミヤケは盆栽飾りや床飾りの伝統様式に則りながら、1席ごとに物語性のある作品をつくり上げた。盆栽飾りの基本は三点飾りである。三点とは掛軸、盆栽、添えもの(水石や小さな草もの盆栽)のことで、確かに三点が絶妙なバランスで配置された空間は黄金比的な美しさがあることを思い知った。そもそも彼女は日本の工芸品や茶事などに造詣が深く、床の間のしつらえに倣った作品をよく発表している。本展への参加が決まった際には「テンションが上がった」と明かす。そのため彼女の真骨頂とも言うべき作品群が本展では観られた。例えば最初の席では「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」という英語フレーズを刺繍したレース模様の草木染めの掛軸を掲げ、外来種のアメリカツタの盆栽と、伊達冠石の上に水晶玉のようなガラス玉を載せた水石を展示した。様式は伝統的でありながら、一つひとつの要素は洋物であり現代的である。この外し方が実に彼女らしい。「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」はラグビーワールドカップの盛り上がりにより有名になった言葉だが、彼女はこの言葉を現代のデジタル社会やコロナ禍と結びつけ、良くも悪くも個と世界との即時的なつながりを示唆する。ほかの席でも同様にユニークな外しとコンセプトを打ち出し、“新しい”盆栽飾りを披露してくれた。決してオーソドックスなスタイルではないが、私のように盆栽に無知な者に対しても門戸を開くにはアートは有効だ。その点で実に画期的なコラボレーション展であると感じた。
 ミヤケマイ《One for All, All for One 知足》(2021)和紙・金箔・銀箔・刺繍・レース模様の草木染め・クリスタル(軸先) 《未来 Crystal Ball》伊達冠石・耐熱ガラス・水 アメリカツタ(大宮盆栽美術館)
ミヤケマイ《One for All, All for One 知足》(2021)和紙・金箔・銀箔・刺繍・レース模様の草木染め・クリスタル(軸先) 《未来 Crystal Ball》伊達冠石・耐熱ガラス・水 アメリカツタ(大宮盆栽美術館)
 ミヤケマイ《月は東に日は西に Things That Dose Not Change》(2021)絹・山椒花紋金襴・麻・銀箔・洋紙・アクリル・顔料・神代杉(軸先) 斑入り石菖、虫かご、バッタ いちょう(大宮盆栽美術館)
ミヤケマイ《月は東に日は西に Things That Dose Not Change》(2021)絹・山椒花紋金襴・麻・銀箔・洋紙・アクリル・顔料・神代杉(軸先) 斑入り石菖、虫かご、バッタ いちょう(大宮盆栽美術館)
公式サイト:https://www.bonsai-art-museum.jp/ja/exhibition/exhibition-7167/
2021/04/25(日)(杉江あこ)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)