artscapeレビュー
2023年02月15日号のレビュー/プレビュー
Study:大阪関西国際芸術祭 2023
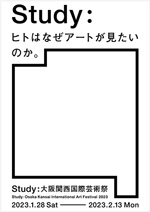
会期:2023/01/28~2023/02/13
大阪府立中之島図書館、釜ヶ崎芸術大学、kioku手芸館「たんす」、グランフロント大阪、THE BOLY OSAKA、船場エクセルビル、飛田会館ほか[大阪府]
日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開催される2025年に予定されている大阪関西国際芸術祭のプレイベントの第2弾。キュレーター陣や会場は昨年からの続投をベースに、新たに追加された。会場ごとに各キュレーターが手がける企画展や個展の集合体として構成され、さらにアートフェアも組み込むなど、より複合化した。本稿では、メイン会場のひとつ、元オフィスビルの船場エクセルビルでの展示に焦点を当てる。
同じ日付の会期だった昨年(2022年1月28日~2月13日)と2回目の今年の間に横たわるのが、ロシアによるウクライナ侵攻という世界史的事件だ。船場エクセルビルでは、昨年も、ポーランド美術が専門の加須屋明子、ポーランド出身のキュレーター/評論家のパヴェウ・パフチャレクのキュレーションにより、ポーランド出身・在住の作家を多く紹介していた。今年は、上記2名と、アジアの美術の専門家ネットワークであるプロダクション・ゾミアが共同キュレーションした「再・解釈」展を開催。侵攻前の2010年代前半にポーランドに移住したウクライナ出身の3名のアーティストを紹介する。ウクライナからの避難民を最も多く受け入れ、結び付きの強い隣国ポーランドを通して、侵攻や分断への抵抗が示される。
ユリア・クリヴィチとタラス・ゲンビクが侵攻を契機に結成したパフォーマンスグループ「『ひまわり』連帯文化センター」は、古いオフィスビルを抗議と連帯のための空間に変貌させた。壁には、帝国主義の告発と脱植民地化を訴えるテキストが日本語と英語で埋め尽くされるとともに、来場者がメッセージを書く余白を残した。また、ウクライナの国花であるひまわりの種の配布とともに、種を撒くパフォーマンスの記録映像などを展示した。

「『ひまわり』連帯文化センター」(ユリア・クリヴィチ、タラス・ゲンビク)、マルタ・ロマンキフ《緊急キオスク》(2023)
[photo by Kohei Matsumura]
ユリア・クリヴィチの《予感、現在進行形》(2015)は、親ロシア派の政権に抗議するデモ隊が機動隊と衝突した「ユーロ・マイダン革命」、クリミア併合、ドンバス戦争の直前の2013~2014年に帰郷した際に撮った写真を編集した本と、その本をめくりながら語る映像で構成される。何かが起こりつつあるという予感、デモ隊への当局の弾圧が語られ、視覚的には美しい写真が不吉なイメージに変貌していく。虹のかかる黒海の青い海。零下20度で受けた放水がたちまち凍りつき、樹氷のように白く輝く樹。写真集は、折り畳んだ冊子をハードカバーに挟み込んだようなつくりで、冊子のページは下半分のみ糸で縫われ、いまにもバラバラにほどけそうな不安定さや脆さを体現する。

ユリア・クリヴィチ《予感、現在進行形》(2015)
[photo by Kohei Matsumura]
同様に侵攻前にポーランドへ移住したマルタ・ロマンキフは、家政婦や介護士といった女性のケア労働を扱う作品とともに、映像作品《ヨーロッパを夢見た》(2022)を展示。12個の星の連なる王冠を被り、青いドレスを着た作家が「EUの旗(欧州旗)」の擬人化を自ら演じながら、平等、自由、多様性、人権の尊重など「ヨーロッパの崇高な精神的理念」を語り続ける。だが、使用されるテキストはウクライナの記事からの抜粋であり、「ウクライナという“外部”の視線から理想化された西ヨーロッパ像」は、民主主義社会への強い希求と同時に、「政治的シンボル」の虚構性(例えば「自由の女神像」が象徴する、移民にとっての「自由の国アメリカ」のような)を露呈させ、両義的だ。

マルタ・ロマンキフ《ヨーロッパを夢見た》(2022)
[photo by Kohei Matsumura]
「移民」「移住」「越境」といったキーワードでつながるのが、ベトナム人のトゥアン・マミのインスタレーション《ベトナムから移された庭(No.6)》(2023)である。発砲スチロールの箱や植木鉢に植えられているのは、日本への輸入が禁止されているベトナムの植物だ。マミは、大阪在住のベトナム人が故郷から持ち込み、株分けして食材として育てている植物を集め、オフィスビルの一室を「庭」につくり変えた。映像では、食材と食文化の強い結び付きや、植物が故郷の味や民間療法の知恵を受け継ぐ手段でもあることが語られる。「持ち込み禁止の植物」が移住先の地で根付いているさまは、入国管理、移民・難民の生と重なり合う。「害虫や病原菌の侵入」「ネイティブの生態系の侵害」を理由に正当化される「外来種の排除」は、移民・難民に対する排除のメタファーとしても機能する。

トゥアン・マミ《ベトナムから移された庭(No.6)》(2023)
[photo by Kohei Matsumura]
「ひまわりの種」は「連帯の印」として持ち込みと配布が推奨される一方で、国境の越境が禁止される植物もある。マミの作品がウクライナ出身の作家たちの作品と「日本」で並置されることで浮かび上がるのが、難民や避難民をめぐる日本のダブルスタンダード的状況だ。非欧米圏の人間に対しては極めて厳しい難民認定を課す一方、ウクライナからの避難民は「国際的協調」のアピールのもと受け入れる。本展の意義は、「植物と越境」の対照性により、まさにこうした日本のダブルスタンダードを可視化して突きつけることにあった。
また、同じビル内では、日雇い労働者の街として知られる西成のあいりん地区で2012年に開講した「釜ヶ崎芸術大学」が、昨年に続いて参加。釜ヶ崎で暮らす人々が書いた習字や創作物で空間を埋め尽くす。「疎外された他者をアートは招き入れることができるのか」という問いを昨年から引き継ぎつつ、その射程を大阪のローカルな地域から世界規模へと広げていた。

釜ヶ崎芸術大学 展示風景
[photo by Kohei Matsumura]
公式サイト:https://www.osaka-kansai.art/
関連レビュー
Study:大阪関西国際芸術祭|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年02月15日号)
2023/01/27(金)(高嶋慈)
神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』

会期:2023/01/28~2023/01/29
ロームシアター京都 ノースホール[京都府]
「見えない隣人」であるイミグレーション(移民)、すなわち「幽霊」についての、あるいは「幽霊」が語る演劇作品。神里雄大は沖縄出身のペルー移民の父を持ち、南米やメキシコ、沖縄などを旅しながら、「越境」「旅」「家族とルーツ」「文化的ハイブリッド」「島」といったテーマで創作してきた。
本作は、那覇文化芸術劇場なはーととの共同製作。「タイの幽霊」「ボリビアの幽霊」「沖縄の幽霊」という3つの語りが、本人として登場する3名の俳優により、それぞれ語られる。「タイの幽霊」では、「サンプル」主宰の劇作家・演出家でもある松井周が登場。「久しぶりに会った(見えない)旧友」にタイのお土産を渡し、タイに移住した経緯について語る話は、焼酎についてのウンチクから始まり、脱線や飛躍を経て「オチ」に至る。ラオスの「ラオラオ」という蒸留酒が、中継貿易で栄えた琉球に伝わり、焼酎や泡盛のルーツになったこと。「ラオラオ」と泡盛を融合した「美らラオ」の工場をラオスにつくったこと。事務所はタイのバンコクに置き、バーで一目惚れした美女と同棲するが、彼女は動作も食べ物の好みも自分とそっくりなドッペルゲンガー的存在で、夜しかやって来ない。渋滞に巻き込まれたタクシーの車内で、歩道に彼女を見た気がするが、直後に事故に遭い、写真を撮りまくる野次馬を見たこと(タイでは、事故ナンバーが「あたる」からと宝くじを買うらしい)。「幽霊」は「彼女」ではなく、(自覚のない)彼自身だったのだ。

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』@那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場 [撮影:大城亘]
「ボリビアの幽霊」では、沖縄出身の俳優、上門みきが、戦後にボリビアへ移住した沖縄移民の歴史について、沖縄のイントネーションで語る。聞き役の大村わたるは、「無知で無邪気なマジョリティの日本人」の戯画化を演じる。60年前に沖縄から移民した祖父に、年金を受け取る手続きを頼まれたこと。1954年に移民団が「うるま移住地」に入植したが、ほどなく伝染病が流行し、再移住を余儀なくされたこと。日雇いで日銭を稼ぎながらの過酷な道中。彼女の語りはいつしか、かつての祖父と思しき青年の一人称のモノローグに憑依していく。「自分の土地と安心できる空間がほしかった。私がそれにとり憑かれたからって、誰が責められるだろう」。過酷な道中のある夜、久しく忘れていた夜空を見上げると、満天の星に戦死した家族の顔が重なる。

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』@那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場 [撮影:大城亘]

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』@那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場 [撮影:大城亘]
「沖縄の幽霊」では、「本土から沖縄に移住した」という大村わたるが語り手に回る。沖縄の本屋に入ると、日本兵の幽霊など怪談本が多く、「歩行者の1/3は幽霊」という都市伝説のある国際通りで歩行者の観察を始めたこと。だが彼はそれと知らず、(おそらく幽霊の)「隣人のマコさん」という女性に出会っている。「あなたは分かってるようで分かってない。あなたには歴史がない。背負うものがないということは、幸せなのかもしれないね」と言って笑う「マコさん」。
そして「第四部」では、松井、上門、大村の3名が会し、(おそらくお供えの)酒を飲みながら語り合う。「マコさん」は「いつも赤い浴衣を着ている」と語られ、赤い浴衣を羽織って現れた上門を見た大村は「え、マコさん?」と驚くが、「マコさんじゃなくて、みきさんだよ」と上門は主張し、自他や生死の境は曖昧に流動化する。「植民地って何なの?」と問う大村に対し、上門/マコさんは「土足で上がりこんできて、色んな線を引くこと」と返す。彼女は「歴史の重みに囚われ続ける幽霊」という抽象化された存在であると同時に、「ヤマトンチュには見えない沖縄」の擬人化でもある(ただしここには、「なぜ被支配者側が女性にジェンダー化されるのか」という根深い構造が、未だに「とり憑いて」いる)。

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』@那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場 [撮影:大城亘]
dot architectsによる舞台美術も秀逸だ。頭上の闇にきらめく無数の灯は、上門/移民の青年が語る「ボリビアで見上げた満天の夜空」と同時に、松井が語る「ベトナム戦争時、物資のルートだったため、世界一空爆を受けた国であるラオス」に降り注ぐ爆弾の光でもある。「まだ不発弾や地雷が残っていて経済発展を妨げている」と言う松井に対し、上門は「似たような話を聞くね」と返し、ボリビア、ラオス、沖縄(戦)の夜空がつながり合う。
焼酎ビジネスのため日本からタイへ、沖縄からボリビアへ、本土から沖縄へ。3つの移住の話は、「沖縄」で交差する。酒盛りする3名が座る「黒い帯状の道」は、海上の交易路や移民を乗せた船の航路、見えない「国境」や分断線であると同時に、出会うはずのない者どうしが会する時空のエアポケットでもある。
同窓会に現われるはずの友人を「俺たちいつまで待ってるんだろう」「まだ来ないね」と繰り返す松井の台詞は、ベケットの『ゴドーを待ちながら』を想起させる。「幽霊」すなわち「死者の時間」は停止・凝固しており、もはや前には進まない宙づり状態、「永遠に引き延ばされた現在」という不条理性にあることを示唆する。
だが、「凝固した時間」を抱える死者は、「空間」にも囚われ続けるのだろうか? 一般的に幽霊は、不慮の死を遂げた場所に出るなど、「土地」に拘束されている。では、故郷を離れた移民は幽霊にな(れ)るのか? そのとき霊の執念は、海を隔てた遠い故郷へ向かうのか? 「自分だけの土地がほしかった」という強い念が勝るのか? 本作が投げかけるのは、「移民の幽霊は存在するのか?」という命題だ。それは、「南米やハワイなどへ渡った日本人移民の忘却」という意味での不在化であり、「人工的に引かれた見えない線を越境する者は、自身も見えなくなってしまう」ことの比喩でもある。「タイで事故死した、自覚のない幽霊」「象徴的に擬人化された沖縄の幽霊」「見えているのに自覚のない人」の3名の会話は、「どこかで会った」「いや、初対面」と噛み合わず、決定不可能な揺らぎを抱えている。可視と不可視の境をさまよう「幽霊(たち)」の捉えどころのなさは、モヤモヤとした消化不良を抱えながら、断片的な語りのなかに、見えない触手や菌糸のように細い糸を伸ばしてつながり合い、「境界線」の強固さを溶かし出していくのだ。
公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/96130/
関連レビュー
KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2017 神里雄大/岡崎藝術座『バルパライソの長い坂をくだる話』|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年12月15日号)
2023/01/28(土)(高嶋慈)
渡邊耕一「毒消草の夢 デトックスプランツ・ヒストリー」

会期:2022/12/20~2023/02/05
Kanzan Gallery[東京都]
渡邊耕一は前作『Moving Plants』(青幻舎、2015)で、日本原産の植物、イタドリ(虎杖)が、ヨーロッパ各地で繁茂している状況を追ったシリーズを発表した。やはり植物をテーマとした今回の「毒消草の夢 デトックスプランツ・ヒストリー」では、江戸末期の本草学者、馬場大助が、自著に「コンタラエルハ(昆答刺越兒發)」という不思議な名前で記している植物を求めて世界各地に足を運んだ。その足跡は香港、インドネシア、オランダ、日本(和歌山)、メキシコにまで及び、その謎の植物の姿が、少しずつ明らかになっていった。
風景写真、図鑑等の複写、映像などを使って、その旅の過程を示した展示もしっかりと組み上げられている。同時期に青幻舎から刊行された同名の写真集とあわせて見ると、体内の毒を消すデトックスの効果があるというこの薬草の分布の状況が、立体的に浮かび上がってくる。渡邊の写真家としての視点の確かさと、知的な探求力とが、とてもうまく結びついた写真シリーズといえるだろう。
イタドリや「コンタラエルハ」は、植物学者ではない限り、単なる雑草として見過ごされてしまいがちな植物である。だが、それらを別な角度から眺めると、歴史学、人類学、経済学などとも関連づけられるユニークな存在のあり方が見えてくる。渡邊が次にどんなテーマを見出すのかが興味深い。彼のアプローチは、植物以外の対象でも充分に通用するのではないかと思う。
公式サイト:http://www.kanzan-g.jp/watanabe_koichi.html
関連レビュー
渡邊耕一「Moving Plants」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年04月15日号)
渡邊耕一「Moving Plants」|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年01月15日号)
2023/01/31(火)(飯沢耕太郎)
マイヤ・イソラ 旅から生まれるデザイン

会期:2023/03/03〜
ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテ、YEBISU GARDEN CINEMAほか全国順次ロードショー[全国]
大らかな花模様の「ウニッコ」などで知られる、マリメッコを代表するデザイナー、マイヤ・イソラ(1927-2001)。彼女の足跡をたどったドキュメンタリー映画が間もなく公開される。ドキュメンタリー映画というと、さまざまな関係者へのインタビュー映像や記録映像、監督独自の見解を述べるナレーションなど「第三者の視点」で構成されることが多いが、本作はそれとは少し異なっていた。撮り下ろしのインタビュー映像はマイヤの実娘クリスティーナに対してのみで、あとは本人の日記や家族に宛てた手紙を読み上げる「自分語り」でほぼ構成されていたからだ。そこに当時の様子を映し取ったアーカイブ映像や写真、またアニメーション化されたマイヤの絵画やデザイン画が小気味良く挟み込まれていく。そのため観る者は彼女の内面へと知らず知らずのうちに入り込んでいき、自分の内面とも同化するような感覚に陥るのである。彼女の体験や感情がどのように創作へ結びついていったのかがまさに手に取るようにわかり、大変に興味深かった。
 監督:レーナ・キルペライネン 出演:マイヤ・イソラ、クリスティーナ・イソラ、エンマ・イソラ
監督:レーナ・キルペライネン 出演:マイヤ・イソラ、クリスティーナ・イソラ、エンマ・イソラ
2021年/フィンランド・ドイツ/フィンランド語/100分/カラー・モノクロ/ビスタ/5.1ch/原題:Maija Isola 英題:Maija Isola Master of Colour and Form
後援:フィンランド大使館 配給:シンカ + kinologue
© 2021 Greenlit Productions and New Docs
マイヤの人生は、旅そのものだった。フィンランド南部に生まれ、少女時代を戦時下で過ごし、19歳で娘を出産した後に芸術大学へ進学。マリメッコでデザイナーとして仕事を始めた後もヨーロッパ中を巡り、パリに何度か滞在し、また北アフリカのアルジェリアや米国のノースカロライナ州へも移住するなど、つねに移動を繰り返した。その間に三度の結婚と離婚を経験し、いくつかの恋愛もした。旅と自由、恋愛が、彼女の創作の源だったのだ。

「母にとって恋は芸術活動の1つでした。新しい恋人からエネルギーをもらって自身の作品に活かすのです」と娘が証言する。一方で、マイヤは孤独も深く愛した。「孤独というものを私は決して恐れない。孤独はむしろ私の望むものであり、心のやすらぎさえ覚える」と日記で独白している。つまり新しい土地や人々との出会いでインスピレーションや情熱を得た後は、誰にも邪魔されずひとりで創作に没頭したことの表われなのだろう。そうした自身のバランスを取るためにも、三度の結婚と離婚が必要だったようにさえ思える。また、彼女はデザイナーとしてだけでなく画家としても活躍し、亡くなるまで絵を描いていたという。「創作は生きている実感を得る唯一の手段だ」という言葉が実に印象的だった。彼女の人生はまた、創作そのものでもあったのだ。

公式サイト:https://maija-isola.kinologue.com
2023/01/31(火)(杉江あこ)
金サジ『物語』

発行所:赤々舎
発行日:2022/12/22
在日コリアン三世という自らの出自を踏まえて、独自の神話的世界を構築し、写真作品として提示する仕事を続けている金サジが、最初の写真集をまとめあげた。ジェンダー、植民地主義、戦争、自然破壊、文化的軋轢など、さまざまな問題を抱え込んだ老若男女が展開する壮大なスケールの「物語」は、複雑に絡み合いつつ枝分かれしていく。それだけでなく、大地、樹木、岩、さらに火や水などの神話的形象が随所にちりばめられ、レオナルド・ダ・ヴィンチなどの西洋絵画のイコノロジーまでが取り入れられている。野心的なプロジェクトの成果といえるだろう。
ただし、それぞれのヴィジョンに対する思いが強すぎて、それが金の神話世界においてどのような位置にあるのか、どう展開していくのかが伝わりきれていないように感じた。彼女自身の短いテキストが写真の間に挟み込まれ、巻末には早稲田大学教授の歴史学者、グレッグ・ドボルザークによる解説「トリックスターとトラウマ」が付されているのだが、それでもなかなかうまく全体像が形をとらない。もしかすると、ガルシア・マルケスの『百年の孤独』のような、長大なテキストが必要になるのかもしれない。また、主人公にあたるようなキャラクターが成立していれば、「物語」としての流れを掴みやすかったのではないだろうか。
とはいえ、金の写真家としてのキャリアを考えると、これだけ豊かなイマジネーションの広がりをもち、しかもそれらを説得力のある場面として定着できる能力の高さは驚くべきものだ。日本の写真界の枠を超えて、国際的なレベルでも大きな評価が期待できそうだ。
関連レビュー
金サジ「物語」シリーズより「山に歩む舟」|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年12月15日号)
2023/02/05(日)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)