artscapeレビュー
2022年12月01日号のレビュー/プレビュー
合田佐和子展 帰る途(みち)もつもりもない

会期:2022/11/03~2023/01/15
高知県立美術館[高知県]
高知市出身の作家、合田佐和子の回顧展が高知県立美術館で開催されている。2016年に合田が亡くなってから最初の大規模な回顧展と言えるだろう。筆者はこれまで、「合田佐和子 影像─絵画・オブジェ・写真─」(渋谷区立松濤美術館、2003)や「瀧口修造:夢の漂流物 同時代・前衛美術家たちの贈物 1950s〜1970s」(世田谷美術館、2005)などを通じて合田の作品を観る機会があった。しかし今、改めて合田の活動を振り返ることは、これまでとは異なる視点で彼女の作品を受け止める契機となるのではないだろうか。
今回の展覧会がとりわけ印象的だったのは、初期から晩年まで次々と変遷を遂げる合田の作風を等価に扱おうという姿勢である。合田は、作家活動を始めた最初期から、瀧口修造や白石かずこらに見出され、その後も唐十郎や寺山修司のポスター原画や舞台美術を手掛けるほか、沢田研二、桃井かおり、ルー・リードとの仕事など、彼女自身の容姿や華やかな交友関係とともに紹介されることの多い作家である。また、1971年から油彩画に着手し、マレーネ・ディートリッヒやマリリン・モンローといったスター俳優の映画のスチルやブロマイドから選ばれた主題を扱う代表作からも、マスメディアが作り出すイメージやジャーナリスティックな言説と相性が良く、そこから生み出される関心や評価と不可分な作家と言えるだろう。それゆえ、他者から付与される言説によって合田の主体性が覆い隠され、同時代の理想の女性性を強調した形で取り上げられることに、時に居心地の悪さを感じることがあった。本展では、こうした筆者の持つ違和感に対し、正面から取り組もうとする姿勢を読み取ることができた。

合田佐和子展会場風景[撮影:井波吉太郎]

合田佐和子展会場風景[撮影:井波吉太郎]
私が今一度合田の作品に惹かれたきっかけの一つに、1970-80年代の唐十郎と寺山修司との仕事が挙げられる。この時期、合田はハレーションが起きたかのような光の効果を取り入れた映画俳優のポートレートを中心に油彩画を手がけている。並行して、同様の作風の原画を提供することにより、唐十郎率いる劇団状況劇場の「おちょこの傘持つメリー・ポピンズ」(1976)や寺山修司率いる天井桟敷がPARCO西部劇場で上演した「バルトークの中国の不思議な役人」(1977)などのポスターが制作されているのだ。合田の原画とポスターの関係を追っていくと、原画が印刷物としてレイアウトされることにより、さらに魅力を増していく様子がよくわかる。同時代の物語やスキャンダルを取り入れた戯曲を得意とする唐と西洋の古典をパラフレーズする寺山という対照的な持ち味の両者が、共に合田のイメージを採用した点は興味深い。実際、状況劇場の「鐡假面」(1972)のポスターに登場する縄で縛られた男が、「バルトークの中国の不思議な役人」の舞台美術にも採用されるという引用関係が認められるという。寺山の舞台の書き割りには、このほかにも合田が手がけたプリンスライターの宣伝ポスターに用いられているイメージが転用されるなど、イメージの連鎖が幾重にも張り巡らされることによって倒錯的な効果を生み出していたが、その媒介となったのが合田の作品なのである。

左:合田佐和子《おちょこの傘持つメリー・ポピンズ》(1976)個人蔵
右:劇団状況劇場「おちょこの傘持つメリー・ポピンズ」ポスター(1976)個人蔵

合田佐和子《中国の不思議な役人》(1977)個人蔵
本展が示すように、合田自身、生涯を通じてオブジェ、人形、油彩画、ポラロイド写真、映像、色鉛筆によるドローイングなどさまざまなメディアによる表現を試みている。そうした融通無碍な作風には、見る/見られる関係のなかに成立する一瞬のなかに表現の活路を見出していく姿勢が窺える。合田の作品をさまざまな言説から解き放ち、身近な素材によって制作されたエフェメラルな作品を改めていま、直視することができるように思われるのだ。ソテツ並木や路面電車など、初めての高知での風景も相まって、解放されていく感覚に満たされる展覧会であった。
2022/11/17(木)(伊村靖子)
サトウアヤコ「日常記憶地図『“家族”の風景を“共有”する』」

会期:2022/11/23~2022/11/27
トーキョーアーツアンドスペース本郷[東京都]
会場には、たくさんの椅子があって、観賞者が机の上にある地図、言葉が書かれた単語帳のようなものや、ファイルに挟まっている文献のコピーを静かに読んでいる。机は大きく三つ点在しており、それぞれ、ある人物が家族について知りたい、知りたかったが叶わなかったという思いから「日常記憶地図」に取り組んだ様子が並べられたものであった。それぞれの尋ね手から見て、叔母/父の1940〜50年代の佐渡(新潟)、父の1950年代の鯖江(福井)、母/叔母の1960年代のジアデーマ(ブラジル)についての「日常記憶地図」が会場では示されている。
「日常記憶地図」は、サトウが2013年に開発したメソッドで、任意の人物へ「場所の記憶」について聞くことを通して、普段の関係性ではわからないその人を知ることができるというものだ。手順がパネルとハンドアウトに書かれていた。ハンドアウトには「日常記憶地図」の使い方から心づもりまで丁寧かつ簡潔に掲載されている。
〈手順〉
・思い出したい時期の地図を用意する。
・地図に、当時の家の場所、よく行く場所/道をなぞる。
・場所/道それぞれ、よく行った理由や習慣、思い出した記憶を書く(聞く)。
・最後に「愛着のある場所」について聞き、当時の生活圏を囲む。
サトウによるハンドアウトでも示唆されているが、「日常記憶地図」が可能にするのは、固定化された昔語りの解体である。写真をよすがに語るのとも、語り伝えてきた記憶を再び手繰り寄せようとするのとも違う。目の前に地図があり、その場所、ある風景について話そうとするとき、特異的な事象よりも、反復していた移動や行為、すなわち日常がベースとなる。これは、オーラルヒストリーの収集にあたって、尋ね手が年表を携えて編年的に問うことと、似て非なる行為だ。同じ地図を見て、同じ風景をお互いが初めて見ようとすることになるメソッド。このとき、語り手と尋ね手の記憶の量の不均衡は、いったん留保される。このことが本展における“共有”なのかもしれない。
正直、わたし自身はそれぞれが地図を辿ろうとするときの、その思慕がぽろっとこぼれる欠片で、居ても立ってもいられなくなってしまったのだが、パネルには、各人が体験を振り返って、落ち着いたコメントを寄せている。そのなかのひとりは、自身に子どもがいないこともあり、何かを残しておきたいという気持ちがあったかもしれないと綴っている。
「家族」のことを知っているようで、それぞれの役割を離れたときの家族のことはまるで知らないという、他者としての家族にサトウは目を向け、「日常記憶地図」を育んできた。このとき、サトウがハンドアウトで記す「そしてその記憶は、10年、20年後にまた別の“家族”に“共有”される可能性を持つ」の引用符は何を意味しうるのか。それは場所が誰かにその記憶を再度発生せしむる可能性のことなのかもしれない。その場所がたとえ消えたとしても。家族がいないとしても。
会場にある展示台には、「あなたの風景は失われることはない」「並んで風景を眺める」「人はそれぞれの世界を持つ」「日常の中で日常の話はできない」と書かれた紙片がそれぞれ置かれている。ハンドアウトにも同様の言葉が掲載されていた。何らかの切実さを抱え、尋ね手となる誰かへ向けた言葉だろう。「あなたの風景は失われることはない」。その場所がたとえ消えたとしても。家族がいないとしても。
展覧会は無料で観覧可能でした。
公式サイト:https://www.tokyoartsandspace.jp/archive/exhibition/2022/20221123-7125.html
日常記憶地図:https://my-lifemap.net/
2022/11/27(日)(きりとりめでる)
中林舞ソロ企画『ゴーストの友人』

会期:2022/11/23~2022/11/27
SCOOL[東京都]
快快の久しぶりの新作として8月に上演された『コーリングユー』は快快の恩師であり「極私的」という言葉を発明した人物でもある「詩人・鈴木志郎康を原作にした舞台」だった。鈴木の詩を無数に引用して構成された作品はしかし同時に、快快という集団と出演していたメンバー自身の体験をもとにした演劇、言わば「私演劇」でもある。快快のメンバーのつくるソロ作品にも、大道寺梨乃の『ソーシャルストリップ』『それはすごいすごい秋』や日記映画、野上絹代が三月企画として上演した『ニンプトカベ』、山崎皓司のドキュメンタリー『Koji Return』とごく個人的な体験から立ち上げられているものは多い。今回、快快の元メンバーである中林舞のソロ企画として上演された『ゴーストの友人』(出演・演出:中林舞、脚本:北川陽子)もまた、一見したところそれらの系譜に連なるもののようにしてはじまる。
 [撮影:加藤和也]
[撮影:加藤和也]
会場のSCOOLに入ると白いテーブルクロスのかかった大きな丸テーブルが中央に置かれている(舞台美術:佐々木文美)。その周囲には形のまちまちな椅子。水場のあるカウンターにはコーヒーサイフォンが置かれていて、そのカウンターと丸テーブルを挟んで対面するような位置に緩く弧を描いて客席が配置されている。カウンターから右手に視線をずらすと床に直置きのモニター。その画面には中林が三鷹駅の改札を出てSCOOLの扉にたどり着くまでの様子を捉えた映像が繰り返し流されている。だが、その動きはどこかギクシャクして見える。よく見ると中林以外の人々は逆向きに歩いている。どうやらこれは中林がSCOOLから三鷹駅の改札へと逆向きに歩いた映像を逆再生したものらしい(映像:林靖高、中林舞)。
 [撮影:加藤和也]
[撮影:加藤和也]
開演ブザーが鳴ると中林はコーヒーサイフォンの仕組みを説明しながら実際にコーヒーを淹れてみせる。夫が買ってきたサイフォンで最近ようやくコーヒーを淹れられるようになったのだなどという中林の語りはしかし、気づけばそのサイフォンを買ってきたという夫のそれへとすり替わり、喫茶店の奥さん、常連客、マスター、店の前で雨宿りをする小学生などなどと次々にその視点を変え世界を広げていく。観客は中林が巧みに演じ分けるキャラクターの連なりに寄り添い、まるでゴーストのようにともに物語世界のなかを移動していくことになる。その旅路はそれだけでも十分に楽しい。なるほどこれは「私演劇」ではなく中林が無数のキャラクターを演じ分けるタイプのひとり芝居らしい。
 [撮影:加藤和也]
[撮影:加藤和也]
かと思えば、連なりの先にはふいに子供時代の中林と思しき人物が現われたりもするのだから油断がならない。子供時代の中林にはときたま窓の外に現れるゴーストの友人がいたのだという。ドンドンドンドンドンとノックの音がする。それは大人になった中林自身だ。かつての「私」が窓の外にいる「私」に何か言おうとした次の瞬間、世界は崩れ落ちる。膨張を続けて最後には完全に消え去ってしまう極大サイズの宇宙のイメージがコーヒーサイフォンのフラスコに生じる真空状態のイメージと重なり合い、崩れ去った世界はフラスコ内へと戻っていくコーヒーとともに再び中林の日常へと収縮する。
 [撮影:加藤和也]
[撮影:加藤和也]
 [撮影:加藤和也]
[撮影:加藤和也]
作中には『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』のセリフなどともに宮沢賢治「春と修羅 序」から「あらゆる透明な幽霊の複合体」という一節が引用されている。複数の役を演じる俳優という存在がゴーストに重ね合わせられていることは明らかだろう。この作品自体もまた、中林らが摂取してきたフィクションの複合体であり、それは彼女たち自身についても言えることだ。あるいは、現実と虚構を往還する俳優の姿をフラスコとロートを行き来するコーヒーサイフォンの液体と重ねて見ることもできる。往還のたびに変化し続ける俳優はまさに「あらゆる透明な幽霊の複合体」なのだ。
 [撮影:北川陽子]
[撮影:北川陽子]
ムービングライトなどの照明(松本永)と複数チャンネルによる音響(佐藤こうじ、田上篤志)は、いわゆる劇場としての設備が整っているわけではないSCOOLに「ゴースト」のモチーフを立体化するのに大きな役割を果たしていた。そうして立ち上げられた虚構の世界はしかし、終演とともに消滅を迎えることになる。「あくせどぅつぉーがうぃさたぅ」と発した中林は5回ドアをノックするとSCOOLの扉を開け外に出ていく。虚構は現実へと解き放たれ、中林もまた現実の世界へと帰還する。だがそれはすでにかつての中林ではない。フラスコからロートへと吸い上げられた水が再びフラスコに戻るときにはコーヒーになっていたように、中林もまた幾分かは「しびれるような香り」をまとっているはずだ。それは観客についても言えることだろう。劇場でひとときの虚構を体験した観客はやがて現実へと戻っていく。もしかしたら少しだけ「心うきうき」した状態で。『ゴーストの友人』とはフィクションの謂であり、それを立ち上げることこそが俳優の謂でもある。そしてそれが中林の仕事なのだ。ならば、これはやはり「私演劇」と呼ぶべき作品なのだろう。
中林舞:http://nakabayashimai.com/
2022/11/27(日)(山﨑健太)
カタログ&ブックス | 2022年12月1日号[テーマ:ウォーホルをこの人はどう見ていたか? 個人の記憶と時代が交差する5冊]

言わずと知れたポップ・アートの旗手ウォーホル。1956年の初来日時の京都と彼の接点にも目を向けた大回顧展「アンディ・ウォーホル・キョウト」(京都市京セラ美術館で2022年9月17日~2023年2月12日開催)に際し、日本の作家や芸術家たちがウォーホルに向けた個人的な眼差しが時代背景とともに垣間見える5冊を選びました。
※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。
※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。
協力:京都市京セラ美術館
今月のテーマ:
ウォーホルをこの人はどう見ていたか? 個人の記憶と時代が交差する5冊
1冊目:見えない音、聴こえない絵(ちくま文庫)
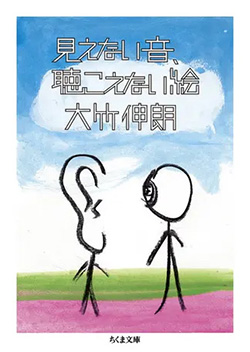
著者:大竹伸朗
発行:筑摩書房
発売日:2022年8月10日
サイズ:15cm、363ページ
Point
アーティスト・大竹伸朗によるエッセイ集。大量消費社会の合わせ鏡としてのウォーホル作品に対する著者の問題意識が綴られる「ウォーホル氏」の章だけでなく、子供時代の雑誌や漫画との衝撃的な出会い、コラージュという手法に目覚めた瞬間など、著者の現在の作家活動にもつながる記憶のディテール描写に気づけば夢中に。
2冊目:ウォーホルの芸術 ~20世紀を映した鏡~(光文社新書)

著者:宮下規久朗
発行:光文社
発売日:2010年4月
サイズ:18cm、294ページ
Point
日本でのウォーホルの回顧展にも関わった美術史家の目線から、メディアを通してセンセーショナルにつくり上げられていった国内でのウォーホルのイメージと、実は多くの人が深くは理解していないであろう美術史上での彼の作品の意義を俯瞰的に解説。ウォーホルという人物を知るうえでの最初の一冊としてもおすすめです。
3冊目:サブカルズ(角川ソフィア文庫 千夜千冊エディション)
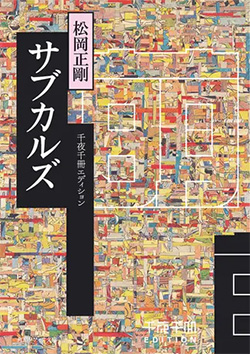
著者:松岡正剛
発行:KADOKAWA
発売日:2021年1月22日
サイズ:15cm、428ページ
Point
現代の知の大家・松岡正剛による「サブカル」に関する書評集。1世紀前のアメリカにサブカルチャーの起源を見出し、日本の漫画・ラノベに至るまで、植草甚一、都築響一、東浩紀などの著書も網羅。ウォーホル『ぼくの哲学』評では「とびきり猜疑心が強くて、ひどく嫉妬心が強い」ウォーホルの人物像を魅力的に描いています。
4冊目:CONTACT ART 原田マハの名画鑑賞術
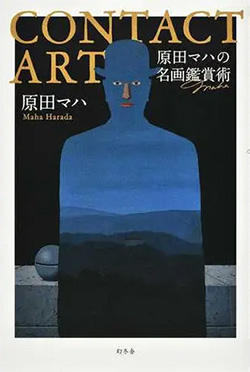
著者:原田マハ
発行:幻冬舎
発売日:2022年10月26日
サイズ:20cm、191ページ
Point
作家・原田マハが日本各地の美術館を訪ね、モネ、ルソー、東山魁夷など名だたる絵画と向き合い語られる、彼女流の作品解説。福岡市美術館で鑑賞するウォーホルのシルクスクリーン作品「エルヴィス」の章も収録。「美術館大国」として日本を少し違った角度から見つめ直すこともできる、アートファンに広く薦めたい一冊です。
5冊目:自画像のゆくえ
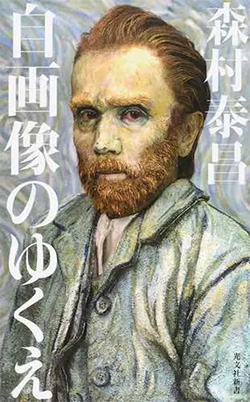
著者:森村泰昌
発行:光文社
発売日:2019年10月17日
サイズ:18cm、615ページ
Point
絵画や作家に扮したセルフポートレイト作品を通してアイデンティティとイメージの関係を問い続ける美術家・森村泰昌が「自画像」という軸で語り直す、世界と日本の美術史。ウォーホル作品を深く読み解く第8章だけでなく、ダ・ヴィンチ、ゴッホから現代日本のコスプレ文化やセルフィーに至るまでの、その射程の広さに驚嘆。
アンディ・ウォーホル・キョウト
会期:2022年9月17日(土)~2023年2月12日(日)
会場:京都市京セラ美術館 新館「東山キューブ」(京都府京都市左京区岡崎円勝寺町124)
公式サイト:https://www.andywarholkyoto.jp/
[展覧会図録]
「アンディ・ウォーホル・キョウト」公式図録

編集:ソニー・ミュージックエンタテインメント、イムラアートギャラリー
発行:ソニー・ミュージックエンタテインメント ©2022-2023
発行日:2022年9月17日
サイズ:A5判型(145×210mm)、340ページ
出品作品のカラー図版と詳細な解説文、本展キュレーターのホセ・ディアズ氏(アンディ・ウォーホル美術館)の「ウォーホルと日本:1956年」と山田隆行氏(京都市京セラ美術館)の「アンディ・ウォーホル・イン・キョウト─ウォーホルの京都滞在(1956年)を振り返る─」論文を収録。1956年のウォーホル来日時の足跡をたどり、ウォーホル芸術に日本が与えた影響を考察します。ニューヨークの「ファクトリー」を二度訪問し、生前のウォーホルと交流のあった美術家・横尾忠則氏によるエッセイも必読! その他にもアンディ・ウォーホル美術館のアーカイブをまとめた『A is for Archive』からファッションをテーマとした「F is for FASHION」を本書のために翻訳。1956年と1974年の二度の日本訪問を記録した貴重な写真を多数収録した永久保存版。
◎展覧会会場にて販売中。
2022/12/01(木)(artscape編集部)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)