artscapeレビュー
2015年12月01日号のレビュー/プレビュー
若手芸術家・キュレーター支援企画 1 floor 2015「対岸に落とし穴」
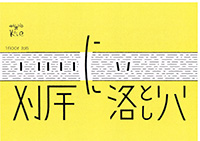
会期:2015/10/31~2015/11/23
神戸アートビレッジセンター[兵庫県]
若手アーティストを対象とした公募企画。8回目の今回は、パブリック空間の壁面にフレスコ画を描く川田知志と、シェプドキャンバスに図形的イメージを描く作品などで知られる山城優摩が、神戸アートビレッジセンター(KAVC)のギャラリーとコミュニティスペース「1room」で展示を行なった。まず圧倒されたのは川田の作品だ。今回彼はフレスコ画ではなく、KAVCの版画工房でシルクスクリーンを制作。畳280畳分もの版画をタイル状にカットし、吹き抜けの壁や柱に貼り付けて広大な空間を埋め尽くした。一方、山城の作品はこれまでのラインだが、一部の作品を台座に設置して量販品の金属部品やプラスチック製品と組み合わせるなど、絵画と立体をまたぐ展示を行っていた。両者の関係はまるでライバルであり、競り合いのなかでともに限界を超えていくような爽快感が感じられた。美術展でこのような感慨を得たのは久しぶりだ。
2015/11/01(日)(小吹隆文)
横尾忠則──続・Y字路

会期:2015/08/08~2015/11/23
横尾忠則現代美術館[兵庫県]
本年9月に、第27回高松宮殿下記念世界文化賞(絵画部門)を受賞したことでも話題になった横尾忠則。2000年以降のライフワークとでもいうべき「Y字路」シリーズ作品の続編でもある本展では、相変わらず、彼の旺盛な実験精神を体感できた。Y字路とは、そもそも横尾が郷里に戻って撮影した風景写真に由来する。画面中央に浮かび上がる建物とその手前で二又に分かれる道、つまり伝統的絵画とは異なって二つの消失点をもつ絵画である。その二つの道先にはなにが待っているのか、見る者に不思議でことさら不穏な印象を与える。今回は、2006年以降に制作されたものを中心に、「温泉」シリーズ・全国の美術館でコスプレの公開制作「PCPPP(Public Costume-play Performance Painting)」をした作品と映像・「黒いY字路」シリーズ等、約70点が展示された。そのなかでも彼の実験魂がいかんなく発揮されていたのが、黒いY字路シリーズ。ホワイト・キューブならぬ、真っ黒に塗られたブラック・キューブの室内に、漆黒で絵画対象を故意に「見えないようにした」Y字路作品が並ぶ。この発想といい、伝統的な西洋美術のありようをあの手この手で「編集」してしまう才能は、デザイナーとして活動した経験をもつ彼ならではのものだろう。実際、「グラフィックデザインも絵画も、僕の中では区別がなくなった」と述べている横尾。80歳を迎える来年も、活躍がいっそう楽しみだ。[竹内有子]
2015/11/01(日)(SYNK)
障害(仮)

会期:2015/09/12~2015/12/13
鞆の津ミュージアム[広島県]
同館のキュレーター、櫛野展正は、現在のところ日本でもっとも野心的かつ挑戦的な企画を打ち出している学芸員である。死刑囚、ヤンキー、老人など、従来の「障がい者」にとどまらない、さまざまなアウトサイダーたちによる造形や表現を紹介してきた。「アウトサイダー・アート」や「アール・ブリュット」というより、むしろ「美術」そのものの外縁を拡張した功績は非常に大きい。
今回の展覧会は、「障害(仮)」。末尾の「(仮)」に、櫛野の批評的な問題提起が込められている。それは、障がい者によるアウトサイダー・アートやアール・ブリュットが抱え込む純粋で無垢な性質に対する根本的な疑いである。例えば山下清の作品がそうであるように、アウトサイダー・アートやアール・ブリュットの作品には、そのような純粋性によって語られることが非常に多い。アール・ブリュットの生みの親であるデュビュッフェも、精神障がい者による表現行為のなかに純粋無垢な精神性を求めていたことは間違いない。けれどもデュビュッフェの前提には、西洋近代が標榜していた普遍的な美の概念への対抗心という一面があった。その純粋性は、いわば敵対関係に位置づけられていたのだ。
逆に言えば、そのような敵対性を見失った純粋性は、個性の無批判な賞揚や優劣を退ける批評嫌悪に結びつきやすい。言うまでもなく、健常者による作品が玉石混交であるのと同じように、障がい者による作品に優れたものとそうでないものがあるのは当然だ。障がい者という属性が自動的に作品の質を底上げすることにはならないし、なってはならない。アウトサイダー・アートやアール・ブリュットが美術の現場に定着するにつれ、それらの純粋性はいつのまにか非常に偏ったものになってしまったのである。
そのような偏りを是正するという意味で、アウトサイダー・アートやアール・ブリュットという概念のリハビリテーションを試みたのが本展である。参加したのは、「アイ・プロジェクト」で知られるチンパンジーのアイをはじめ、好きな施設職員の痕跡が残るあらゆる物を収集している武田憲昌、フェルトや毛糸などで食品サンプルを制作している三浦和香子など14名。基本的にはなんらかの障害をもつ人々が中心だが、現代美術から会田誠と百瀬文を招聘しているところが大きな特徴である。というのも、このような展覧会の構成は、同館でも開催した全国規模の巡回展「TURN」展と相似形をなしているからだ。それゆえ今回の企画展は、前述したような障がい者をめぐる偏った純粋性を再生産しかねない「TURN」展に対する櫛野展正からの批判的応答と言ってよい。
とりわけ注目したのが、小林一緒とあそどっぐ。小林はもともと調理師として働いていたが、アルコール性神経炎を患い、歩行困難となる。以来、自宅で毎日の食事を非常に緻密に描いたイラストレーションを描き続けている。展示されたおびただしい数の作品を見ると、小林の執着心のある視線がひとつひとつの食材はおろか、パッケージやラベルのデザインにまで及んでいることがわかる。あまりにも細かい場合はシールをそのまま転載したり、「めくり」を入れて紙面を重層化するなど工夫が凝らされている。
小林の作品が面白いのは、それが食事とその記録という主従関係をみずから反転させているように見えるからだ。本来であれば食事の記録としてのイラストレーションは、あくまでも食事という出来事の副産物だった。けれども小林のイラストレーションは非常に緻密に描き込まれるため、多大な時間を費やすそれが食事そのものを圧倒しているようにも見える。食事のイラストからイラストのための食事へ。そのような反転が起こりうるほど、小林にとってのイラストレーションは彼自身の生と分かちがたく結びついているのである。
あそどっぐは熊本県在住のコメディアン。脊髄性筋萎縮症をもつため顔と指をわずかにしか動かすことができない。24時間介助を必要とする寝たきりだが、みずからの障害をネタにした自虐的なコントをYoutubeなどで精力的に発表している。むろん、その笑いは自身の身を削るという意味で、ブラック・ユーモアである。けれども本展で展示された新作のコントを見ると、彼のネタが非常に緻密に練り上げられた構成であることがよくわかる。ストレッチャーや布団の上に身体を横たえているため、画面的にはほとんど動きがない。しかし物語の構成と言葉の選定を研ぎ澄ますことによって見事にオチまで鑑賞者を導くのだ。彼のある意味不自由な身体によるネタと比べると、いわゆるお笑い芸人の芸がいかに無駄な身体の動きと不必要な言葉によって飾られていることか。あそどっぐの芸の醍醐味は自虐的なネタによる障害問題の焦点化だけではなく、必要最低限の身体と言葉によるミニマル・コメディーを追究している点にあるのだ。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京都はアール・ブリュットの拠点を整備することを明言している。つまりアウトサイダー・アートやアール・ブリュットは、この先さらなる再編成の過程に巻き込まれると考えてよい。そのとき、「社会包摂」という名のもとで、いったい何が排除されるのか。
2015/11/03(火)(福住廉)
琳派400年記念:琳派からの道──神坂雪佳と山本太郎の仕事

会期:2015/10/23~2015/11/29
美術館「えき」KYOTO[京都府]
この秋、京都では、琳派400年を記念する展覧会が目白押しである。そんななか、琳派の継承者、神坂雪佳と現代美術の作家、山本太郎の二人展が開催された。
神坂雪佳の出品作品は、京指物の老舗、宮崎家具による家具や箱物、宮崎家具所蔵の図絵をはじめ、川島織物セルコン(旧・川島織物)による染織品などおよそ40点である。小さな飾り棚、華やかな金蒔絵の硯箱、多色使いの窓掛け用紋織、袱紗、団扇、屏風、短冊、茶碗など多種多様な品々にはそれぞれふさわしい図柄が配されており、雪佳が希代のデザイナーだったことをいまさらながら実感させられた。宮崎家具も川島織物も、明治期には西欧の意匠や技術を採り入れながら日本独自の室内装飾を目指した企業である。こうした企業と協力関係を維持するコミュニケーション能力もまたデザイナーの資質のように思われる。なにより、とくかく上手いのである。形象を単純化、簡略化することによってそのものをよりそのものらしく表現することを「便化」というが、雪佳の図案にはその妙味を見ることができる。
さて翻って現代美術家、山本太郎の作品は屏風や掛け軸、絵画などおよそ40点である。立ち雛にはキューピッド、杜若には玩具のアヒル、菊慈童には缶ビールなど、古典的な画題と現代的なモチーフとの組み合わせが見所だ。なかでも俵屋宗達の《風神雷神図屏風》を引用した《マリオ&ルイージ図屏風》は、その大胆な趣向が話題になっている。いま、京都国立博物館では俵屋宗達俵、尾形光琳、酒井抱一の描いた三対の《風神雷神図屏風》が75年ぶりに揃って展示されている。会場は違えど、第四の一対ということになる。
琳派の特徴のひとつはその洒脱さにある。軽く、あっさり、さっぱりと。雪佳の場合はそれが便化として表現される。一方、山本の場合は、洒脱というよりもむしろ洒落、晒れや戯れといったほうがふさわしいように思われる。[平光睦子]
2015/11/03(火)(SYNK)
画家の詩、詩人の絵──絵は詩のごとく、詩は絵のごとく

会期:2015/09/19~2015/11/08
平塚市美術館[神奈川県]
表題のとおり、絵画と詩の関係性を探る展覧会。画家からは萬鐡五郎や松本竣介、田島征三、小林孝亘ら、詩人からは高村光太郎、萩原朔太郎、宮沢賢治、稲垣足穂、北園克衛、瀧口修造ら、63名による絵画と詩があわせて展示された。
注目したのは、画家の詩。詩人のそれが全般的にいかにも難解で長大な傾向があったのとは対照的に、画家の詩は軒並み簡潔明瞭で、そうでありながら言葉の奥行きと広がりを感じさせるものが多かったからだ。例えば鴻池朋子は「あるひ洪水がきて すべてを流してしまう 地球は変化こそが 本性」と書いたが、それは過去の歴史としても読めるし、未来の予言としても受け止めることができる、非常に神話的な詩である。また、村山槐多の詩は「走る走る走る 黄金の小僧ただ一人 入日の中を走る、走る走る ぴかぴかとくらくらと 入日の中へとぶ様に走る走る 走れ小僧 金の小僧 走る走る走る 走れ金の小僧」というもの。猛烈なスピード感とほとばしる熱情、そしてそれらの背後に潜む焦燥感は、槐多の絵画にも見出すことができる若々しい詩情である。
絵と言葉の関係性は根深い。色彩や線、形態など絵画の形式性を重視するフォーマリズム批評の価値基準からすると、文字による物語性や文学性は排除の対象にほかならなかった。文字は絵画の自立性を損なうと考えられたからだ。だからこそ文字は絵画の画面から周到に取り除かれ、結果として挿絵やイラストレーションを本画より下位に置く序列的な構造が形成された。だが、本展で示されたのは、そのような文字が絵画の存立を脅かす脅威ではなく、むしろれっきとしたひとつのメディウムであるという厳然たる事実である。
そのもっとも明示的な例証が、O JUNの作品だったように思う。展示された作品は、階段を降りてくる女の子を描いた《オリルコ》(2013)。最低限の線によって構成された、いかにもO JUNらしい絵画だが、そこにあわせて展示された詩は、「のうちゃん あした ひあくまんえんもてこい」。この詩は、鴻池や槐多のように絵画と直接的に照応しているようには思えないが、だからといってまったく無関係というわけでもないように思われる。言い換えれば、詩と絵画が同じ焦点を共有することで同心円状のイメージを生成するわけではないが、それぞれ異なる中心点をもちながら、しかしそれでもなお、結果として楕円状の輪郭が描き出されているような気がするのだ。
イメージを豊かにするためには、絵画であれ詩であれ、ヴィジュアルであれテキストであれ、それぞれのメディウムに備えられた固有の特性を存分に発揮するのがいい。センスのいい若いアーティストたちは、すでにこのことを知っている。本展の行間には、フォーマリズムの残滓をなかなか振りほどくことができない現代美術への根本的な問題提起が隠されていたのではないか。
2015/11/04(水)(福住廉)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)