artscapeレビュー
2021年12月15日号のレビュー/プレビュー
土田ヒロミ「ウロボロスのゆくえ」

会期:2021/11/29~2022/01/17
キヤノンギャラリーS[東京都]
土田ヒロミは1939年の生まれだから、今年82歳になるはずだ。普通ならリタイアしてもおかしくない年代であるにもかかわらず、その創作意欲はまったく衰えていない。今回キヤノンギャラリーSで開催した「ウロボロスのゆくえ」展でも、新たな領域にチャレンジする姿勢が全面的に表われていた。
とはいえ、展示されていたのはバブル経済の崩壊の時期だった1990年代前半に撮影された「産業考古学」(1991-2004)と「Fake Scape(消費の風景)」(1995-2000)の2シリーズである。「産業考古学」は「日本の高度経済成長を支えてきた基幹産業の生産現場」を記録するプロジェクトで、工場地帯の光景をその物質性を強調して撮影している。一方「Fake Scape(消費の風景)」では、「大都市郊外の国道線路沿線(主に国道16号)に現われていた消費者が誘導する異様な意匠の店舗の風景」にカメラを向けた。興味深いのは、この2シリーズを合体させることで、1990年代における生産と消費の現場のうごめきが、あたかも合わせ鏡のように出現してくることである。それこそが、土田が今回の写真展のタイトルに「ウロボロス」(自分の尻尾をくわえた蛇、あるいは竜の表象)という名辞を付した理由だろう。同時にその「異様な」眺めが、2020年代の現代の都市風景のプロトタイプであることが、鮮やかに浮かび上がってきていた。
本展では、過去作にあらためてスポットを当てつつ、それらを再解釈、再構築しようとする土田の営みが、実り多い展示として実現していた。彼には、まだ現在も進行中のプロジェクトがいくつもある。現役の写真作家として、さらなる活動の広がりを期待できそうだ。
2021/12/06(月)(飯沢耕太郎)
藤岡亜弥『アヤ子江古田気分/my life as a dog』
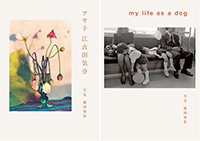
発行所:私家版(発売=ふげん社ほか)
発行日:2021/09/16
藤岡亜弥は1990年から94年にかけて、日本大学芸術学部写真学科の学生として、東京・江古田に住んでいた。今回、彼女が刊行した2冊組の小写真集は、主にその時代に撮影した写真をまとめたものだ。『アヤ子江古田気分』には、「木造の古い一軒家の2階の八畳ひと間」に大学卒業後も含めて8年間住んでいた頃のスナップ写真が、大家の「82歳のおばあさん」との暮らしの記憶を綴った文章とともに収められている。『my life as a dog』は、「大学生のときに夢中になって撮った」という子供たちの写真を集めたものだ。
どちらも彼女の後年の作品、『私は眠らない』(赤々舎、2009)や第43回木村伊兵衛写真賞を受賞した『川はゆく』(赤々舎、2017)と比べれば、「若書き」といえるだろう。とはいえ、奇妙に間を外した写真が並ぶ『アヤ子江古田気分』や、牛腸茂雄の仕事を思わせるところがある『my life as a dog』のページを繰っていると、混沌とした視覚世界が少しずつくっきりと像を結び、まぎれもなく一人の写真家の世界として形をとっていくプロセスが、ありありと浮かび上がってくるように感じる。「若書き」とはいえ、そこにはまぎれもなく藤岡亜弥の写真としかいいようのない「気分」が漂っているのだ。
木村伊兵衛写真賞受賞後、広島県東広島市に移住した藤岡は、いま、次のステップに向けてのもがきの時期を過ごしているようだ。写真学科の学生時代をふりかえることも、その脱皮のプロセスの一環といえるのだろう。だがそれとは別に、2冊の写真集をそのままストレートに楽しむこともできる。笑いと悲哀とが同居し、どこか死の匂いが漂う写真たちが、じわじわと心に食い込んでくる。
2021/12/06(月)(飯沢耕太郎)
HOKUTO ART PROGRAM ed.1 後編

会期:2021/10/30~2021/12/12
中村キース・ヘリング美術館[山梨県]
いまキース・ヘリング美術館では、40年近く前にぼくがニューヨークで撮ったキース・ヘリングの写真を展示してくれているのだが、なかなかコロナ禍が収まらず、ようやくタイミングを見計らって行くことができた。ちょうど今週まで「HOKUTO ART PROGRAM」という企画展もやっているし。これは山梨県北杜市にある清春芸術村、中村キース・ヘリング美術館、平山郁夫シルクロード美術館など5つの施設が、「芸術と観光という二つの要素を多面化し、『時間をかけてここに来ていただくことの価値』を磨き続け」ようとの主旨で始めたもの。ここではSIDE COREと脇田玲の2組が出品していた。どちらもキース・ヘリングやグラフィティに関連づけた作品となっている。
SIDE COREは《IC1(Imaginary Collection1)》と題して、高床式の小屋を制作。小屋の床には丸い穴が3カ所開いており、下から首を突っ込んで内部をのぞき見る仕掛けだ。のぞいてみると、室内にはストリート系のペインティングや版画がびっしり展示され、ネズミのぬいぐるみやスニーカーの空箱なども置いてある。作者がもらったり買ったりしたコレクションだそうで、3つの穴から見える作品群にはそれぞれ異なる意味が与えられているという。しかしこうして床スレスレの目線で見上げると、なんだか自分がネズミにでもなったような気分。さらに室内にはカメラが据えられ、のぞいた人の顔が外のモニターに映し出される仕掛けなのだ。タイトルの「IC1」はニューヨークのPS1、「イマジナリー・コレクション」はアンドレ・マルローの「空想の美術館」に由来するだろう。グラフィティや美術史の知を盛り込んでいる。

SIDE CORE《IC1(Imaginary Collection1)》 展示風景[筆者撮影]
脇田玲の作品は《アランとキースのために》と題された映像で、電子計算機の開発に関わった数学者のアラン・チューリング(1912-54)と、キース・ヘリング(1958-90)の時を超えた対話の場を創出するもの。チューリングは化学物質が相互に反応して拡散していく形態形成について考察したが、映像はモルフォゲンと呼ばれるその形態形成のパターンが、キースの絵とよく似ていることを示している。原理はさっぱりわからないけど、作品は一目瞭然、点が線になり枝葉のように四方に伸びていく様子は、まさに空間を埋め尽くしていくキースのドローイングそのもの。空間を線で均等に、効率的に埋めようとすると必然的にこういうパターンになるのだ。これはおもしろい。ちなみに2人ともホモセクシュアルだったらしい。
*脇田玲の展示会期:2021年10月16日(土)〜2022年5月8日(日)
SIDE COREの展示会期:2021年10月30日(土)〜2022年5月8日(日)
2021/12/06(月)(村田真)
大道兄弟『My name is my name is…』

発行所:桜の花本舗
発行日:2021/09/16
毎月、たくさんの写真集が送られてくる。だが、ほとんどが自費出版のそれらの写真集のなかで、何か書いてみたいと思わせるものはそれほど多くない。大道兄弟という未知の二人組が、自分たちの写真をまとめた『My name is my name is…』も、最初はなんとなく見過ごしていたのだが、そのうちじわじわと視界に入ってきて、気になる一冊として浮上していた。
どうやら二人は1994年山梨県生まれ、大阪府堺市育ちの双子の兄弟(YukiとKoki)のようだ。赤々舎などでアルバイトをしながら、写真を撮り続け、Zineを既に40冊余り出している。『My name is my name is…』が最初の本格的な写真集である。モノクロ、カラーが入り混じり、被写体との距離感もバラバラだが、どこか共通の質感を感じさせる写真が並ぶ。特に、人の写真にその眼差しの質がよく表われていて、真っ直ぐに向き合いつつも、暴力的にねじ伏せようとはしていない。共感をベースにしながらも、なかなかそれを伝えることができないもどかしさと、コミュニケーションへの切実な渇望が写真に表われている。と思うと、そっけない、だが体温を感じさせるモノの写真もあり、被写体をあまり厳密に定めてはいないようだ。まだ海のものとも山のものともつかないが、写真を通じて世界と深くかかわっていこうとする、ポジティブな意欲が伝わってくる写真が多かった。
どれがYukiの写真でどれがKokiの写真かは、あえて明確にしていない。「兄弟」というユニットに徹することで、個人作業を超えた共同性が芽生えつつあるのが逆に興味深い。可能性を感じさせる一冊だった。
2021/12/07(火)(飯沢耕太郎)
HOKUTO ART PROGRAM ed.1 前編

会期:2021/10/30~2021/12/12
清春芸術村[山梨県]
「HOKUTO ART PROGRAM」を見に、清春芸術村を初訪問。清春という名称は最初、白樺派との関連で「せいしゅん(青春)」と読んでいたが、正しくは「きよはる」で、もともとここの地名だったと初めて知った。もちろん「青春」にもダブらせているんだろうけど。そんなわけで、ご多分にもれず青春時代に白樺派に感染したぼくではあるが、この芸術村ができたころ(1980年代)にはすでに免疫ができていたため足が向かず、ようやくいい年こいて訪れたってわけ。どうでもいいけど。
ここは「HOKUTO ART PROGRAM」の中心だけあって、デヴィッド・ダグラス・ダンカンによる晩年のピカソを捉えた写真展をはじめ、アトリエ系の建築家6人による「テント」の提案、映画監督の河瀨直美による映像インスタレーション、芸術と科学の融合を目指したバイオアート、イラストレーターとしても知られる長場雄のインスタレーションなど盛りだくさん。 まず、広い敷地内に点在しているテント群。長谷川豪は、花を包むように透明の筒を地面に立てて支柱にし、光を遮断する布地のテントを張っている。内部は暗闇で、てっぺんから花にスポットライトのように自然光が差す仕組みだ。永山祐子は3つのしずく型の透明なテントを設置。起き上がりこぼしのようにさまざまな方向を向いているが、地面に固定されているので転がる心配はないらしい。藤村龍至はモンゴルのパオ(包)と同じ構造で、《脱東京・遊牧民の包》を創出。寝るためではなく過ごすための、半分開いて半分閉じた「クロープン(clopen)」なテントを目指したという。 これらはいずれも、会期の40日間だけ屋外展示されるという前提条件の下につくられたそうだ。
かたわらに建つ谷口吉生設計のルオー礼拝堂は、河瀨直美の個展会場と化している。中央に壺を置いてナナカマドやクロガネモチなどを生け、それを取り囲むように半透明のオーガンジーのスクリーンを張り、河瀨のルーツである奄美、沖縄の森や海を撮った映像を映し出している。中央の植物は朽ちていくが、そこにレイヤーとして永遠の映像を干渉させることで、過去と未来を往還させている。その向かい側に建つ白樺派の図書資料を集めた白樺図書館では、長場雄が本棚やテーブルをシートで覆い、キャンバスに転写した自作のイラストを無造作に立てかけている。アートとイラストを股にかける彼がテーマにしたのは、前者に存在し、後者には存在しない「搬入」だという。なるほど、搬入作業中の様相だ。
現代美術展だと思って行ったら、確かに現代美術の文脈に則った作品ばかりだが、作者は建築家、映画監督、イラストレーターといった面々。それゆえ新鮮な刺激も多かった反面、どこか物足りなさを感じたのも事実だ。まあいずれにせよ、白樺派の夢を実現したような場所でこんな展覧会を見られるとは思わなかった。

河瀨直美 作品展示風景[筆者撮影]
公式サイト:https://www.hokutoartprogram.com
2021/12/07(火)(村田真)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)