artscapeレビュー
2021年12月15日号のレビュー/プレビュー
フィリア―今道子

会期:2021/11/23~2022/01/30
神奈川県立近代美術館 鎌倉別館[神奈川県]
今道子の作品は、写真という表現領域においてはかなり異色のものといえる。何しろ今が撮影しているのは、魚介類、果物、野菜などの「食べ物」や、剥製の動物、衣服、装飾品、あるいは人体などを組み合わせて作ったあり得ないオブジェであり、現実世界の再現・記録という、普通は写真の最も基本的な役目と考えられている要素はほとんど顧慮されていないからだ。そこに出現してくるマニエリスティックな画像の世界は、ほとんど今の夢想が形をとったものであるようにも見える。とはいえ、写真以外の制作手段(絵画、版画、彫刻など)で彼女の作品世界が成立するかといえば、それは不可能だろう。その緻密で、蠱惑的で、ときにはユーモラスでもある作品世界は、平面上にリアルな幻影を出現させる写真の魔術的な力の産物以外の何者でもない。その意味では、今の仕事は19世紀の写真術の発明以来積み上げられてきた、イメージの錬金術師としての写真家たちの系譜を正統に受け継ぐものともいえるだろう。
代表作100点余りによる、今回の神奈川県立近代美術館 鎌倉別館での個展は、今の初期作品から新作までを概観することができる貴重な機会となった。それらを辿り直すと、写真という表現手段を手にして、身辺の事物をテーマに作品を制作し始めた初期から、精力的に活動を続けている現在に至るまで、彼女の姿勢がほとんど変わっていないことに気がつく。とはいえ、たとえば2010年代以降のメキシコ体験をベースにした作品群のように、新たな刺激を取り込みつつ、より多元的、多層的な広がりを加えていこうとしていることが見て取れる。2001-2002年頃に集中して制作されたカラー写真のシリーズ、障子をモチーフにした「時代劇」風の連作(2010)、生きている蚕を使った作品(「目の見えない蚕」、2017)、ブレを意図的に取り入れた作品(「めまいのドレス」、2013)など、近作になればなるほど、融通無碍にさまざまな手法、スタイルを模索するようになってきている。初期から近作まで25点を「祭壇」のように配置した「フィリア」のパートなど、インスタレーションにも工夫が凝らされていた。タイトルの「フィリア」(philia)とは「──愛」を意味するギリシア語の語尾だという。今道子の「現実と非現実との間のようなもの」に対する偏愛を、うまく掬いとったいいタイトルだ。
2021/11/23(火)(飯沢耕太郎)
井津健郎「未発表作品展1975-2016『井津建郎 地図のない旅』」「地図のない旅」「もののあはれ」

[東京都]
井津健郎は1971年に渡米し、ニューヨークを拠点として作家活動を続けてきた。だが、昨今のアメリカの社会・文化状況への疑念が大きくなったこともあり、日本に帰国することを選択する。来年からは、金沢に居を構えて写真作品を制作していく予定だが、ひとつの区切りとして東京の三つのギャラリーで「活動50周年記念展」を相次いで開催した。
蔵前のiwao galleryでは、渡米直後の1975年から近作まで、これまで発表せずにしまい込んでいたヴィンテージ・プリント27点が「蔵出し」されていた。それらを見ると14×20インチ判の大判カメラで、「聖地」のたたずまいを撮影し、緻密かつ重厚なプラチナプリントで発表する生真面目な写真家という井津のイメージが大きく揺らいでくる。杉本博司とシェアしていたというスタジオで撮影したファッション写真風のポートレート、ヌード写真、静物や花の写真など、作風の幅はかなり広く、軽やかに遊び心を発揮したような作品も含まれていた。
ルーニィ・247ファインアーツでの展示では、井津の写真家としての転機になったという、1979年にエジプト・ギザのピラミッドを撮影した写真をはじめとして、イギリス、フランスなどの石造遺跡を撮影した写真群が並ぶ。プラチナプリントを使いこなすことができるようになり、写真家としての視点を完全に確立しテーマが定まってくる、1979〜1992年制作の充実した作品群である。
注目すべきなのは、PGIではじめて発表された新作の「もののあはれ」だろう。能面、神社の神域、そして枯れていく草花という3部構成の写真群には、日本への帰国を契機として、新たな領域に踏み出していこうという井津の意欲がみなぎっている。当然ながら、「もののあはれ」という日本の伝統的な美意識の探究が大きな目標なのだが、それをあくまでもアメリカ在住の時期に鍛え上げた、被写体の細部の物質性をしっかりと把握・描写していく視点のとり方と、高度な撮影・プリントの技術によって成し遂げようとしていることが興味深い。本作はまだ完成途上とのことだが、それが完全に形をとった時に、彼の新たな代表作となるのではないかという予感を覚える。
「未発表作品展1975-2016『井津建郎 地図のない旅』」
会期: 2021/11/17〜2021/11/28
会場:iwao gallery
「地図のない旅」
会期:2021/11/23〜2021/12/05
会場:ルーニィ・247ファインアーツ
「もののあはれ」
会期:2021/11/24〜2022/01/21
会場:PGI
関連レビュー
井津健郎「ETERNAL LIGHT 永遠の光」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年02月01日号)
2021/11/24(水)(飯沢耕太郎)
松江泰治 マキエタCC

会期:2021/11/9~2022/1/23
東京都写真美術館[東京都]
松江泰治といえば俯瞰した風景写真を撮る人、くらいしか知らなかった。でもその写真は、被写体が自然だろうが都市だろうが影が少なく乾いていて、ひと目で松江が撮った写真だとわかった。ま、その程度の認識しかなかった。今回の展覧会はここ10年あまりの都市の写真ばかりを集めたもの。松江の作品をまとめて見たいという思いもあったが、なにより地図や俯瞰写真を眺めるのが好きなので見に行ったというのが正直なところ。なんだろうね、俯瞰するのが好きという性癖は。朝トイレに入るときは必ず備え付けの地図帳を開くし、飛行機に乗っても窓側で晴れていればずーっと外を眺めている。それは大げさにいえば「神の視点」を得られるからではないか、と思ったこともある。
で、展覧会。出品作品には都市の俯瞰写真ばかりだが、「ATH」とか「UIO」とか「JDH」といったアルファベットに数字を併記したタイトルしか記載されていないので、それがどこの都市なのかわからない。でも建物の様式や色合い、密度などでだいたいヨーロッパか中東か東アジアかくらいは見当がつく。そうやって楽しんでいると、あれ? なんかおかしいぞ、これ実景じゃないじゃん、と気がつく。実景と、都市の模型の2つのシリーズが混在しているのだ。あらためて解説を読むと、タイトルの「マキエタCC」の「CC」はシティ・コード、つまり「ATH」とか「UIO」などの都市の略号で実景の写真、「マキエタ」はマケットのポーランド語、つまり都市の模型を撮った写真のことなのだ。いやーまんまと騙されるところだった、てか、そのくらい予習してから行けよ。まーとにかく、どちらも同じ手法で撮影されているので最初は気づかなかったが、数えてみると「CC」より「マキエタ」のほうが多いではないか。
松江の風景写真に共通しているのは、よく晴れていること、画面に地平線や水平線が入っていないこと、場所が特定できる建造物は避けること、高所から斜めに俯瞰していること、画面全体にピントを合わせていること、順光で撮影していること、などだ。そのため影がほとんどできず、遠近感もあまりなく、匿名性が強く、平面的に感じられる。絵でいえば、奇妙なことに、風景画よりむしろオールオーバーな抽象画に近い。現代美術として評価されるゆえんだろう。「マキエタ」のほうもほぼ同じ条件で撮っているらしく、タイトルも「CC」に準じているので紛らわしいことこのうえない。とりわけ紛らわしいのが最後の展示室にあった「TYO」の4点。何度見ても模型とは信じられないくらい精巧につくられた「マキエタ」なのだ。
もうひとつ特筆すべきは、4つの展示室のそれぞれ中央に水平に置かれた作品。最初の1点は博物館の内部を俯瞰した写真で、ほかの風景とは趣を異にするが、よく見ると小さく写っている人物が動いており、映像であることがわかる。次の1点は逆に群衆が騒がしく動き回る青果市場、残りの2点は「CC」と同じ都市風景で、粒のような人や車が動いている。視点が固定されているので、誰かが言ったように「動く写真」というほかない。これを見ると、建築や都市は写真でも映像でも静止しているので同じだが、人や車はその隙間を血液のように絶えず動き回っていることが改めてわかる。もし静止し続けている人がいれば死人だろう。また、もしこれを1万倍速で撮れば、もはや人や車は消え、今度は建築や都市が生き物のようにニョキニョキとうごめくのが見て取れるはず。これは時間的な「神の視点」といえるかもしれない。さまざまに妄想が膨らむ写真展である。
2021/11/26(金)(村田真)
遥かなる都市展
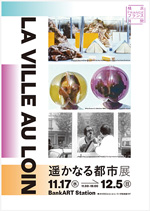
会期:2021/11/17~2021/12/05
BankART Station[神奈川県]
アーティストによる都市への介入や、建築家集団による都市のアート化の試みを記録した映像作品が公開された。アーキズームやスーパースタジオといった伝説的な建築家集団など、映像は全部で13本。うち60-70年代が7本と過半数を占め、90年代が1本で、2001年以降が5本と年代が偏っている。80-90年代が少ないのは、ポストモダニズムにかまけて建築もアートも前衛が後退し、保守化したせいだろうか。全部見たわけじゃないけど、チラッと見ておもしろかったのが、チャールズ・シモンズの《小さな家、冬》と、ジョルディ・コロメールの《アナーキテクトン、バルセロナ》の2本。
チャールズ・シモンズは、崩れかけた建物の一画に極小の手製レンガを積み上げて廃墟のような構築物をつくるアーティスト。映像は1974年のもので、ニューヨークやベルリンでの活動が記録されている。彼の作品は写真か、完成品しか見たことがなかったが、それがビルの廃墟に勝手に積み上げていくストリートアートだったと初めて知った。当時、路上で破壊活動をしたりデモンストレーションしたりするアーティストはいても、このように路上で勝手に作品をつくるアーティストはまだほとんどいなかった時代だから、彼こそ「ストリートアート」の先駆者といってもいいかもしれない。現在でも知ってか知らずか、ビルの隙間にミニチュアの廃墟みたいなものを組み立てるストリートアーティストがいるが、そういう若いアーティストにもぜひ見てほしいドキュメントだ。
ジョルディ・コロメールはバルセロナをはじめ、大阪、ブカレスト、ブラジリアなど世界各都市で「アナーキテクトン」なるプロジェクトを展開してきたアーティスト。アナーキテクトンとはアナーキーとアーキテクトン(ギリシャ語で「都市建築家」)の合成語だという。映像は2002年にバルセロナで撮られたもので、ビルの模型を棒の先に取り付けて実際のビルの前でデモンストレーションするというもの。コマ落としの映像なので、本物のビルと模型がほぼ同じ大きさで近づいたり、重なったりするシーンは思わず笑ってしまう。さっき見た松江泰治の「マキエタCC」を思い出す。
2021/11/26(金)(村田真)
遥かなる都市展
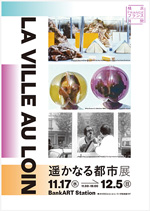
会期:2021/11/17~2021/12/05
BankART Station[神奈川県]
会場には映像を投影する9面のスクリーンのみ(そのうち4面は、2つの壁の表裏=両面を使用)。都市への批評的な提案をテーマとしながら、立体的な表現がないので、物足りないのではないかと思ったが、杞憂に終わった。1960年代や70年代に撮影された、興味深い作品がいくつか含まれており、しかも全体を鑑賞できるような各作品が適度な長さの映像だったのもありがたい。なお、この展示は「横浜フランス月間2021」のイベントとして開催されたものだが、前半は特にイタリア人が多く、後半もオーストリアやアメリカの建築家やアーティストを含み、むしろフランス人は少数派である。さて、建築の観点からは、いずれも「アーキラボ:建築・都市・アートの新たな実験展 1950-2005」 (森美術館、2004-2005)などでオブジェとしては見たことがあったが、アーキズームの《ノーストップ・シティ》(1971)やスーパースタジオの「基本的な行為:人生《スーパーサーフェス》(1972)の映像を初めて実見したのが大きな収穫だった。後者は地球の表面を均質なスーパー・グリッドで覆う《コンティニュアス・モニュメント》のプロモーション・ビデオといった趣である。
同時代のラディカルな建築家集団、アーキグラムが映像を制作していたことは、日本でDVD化されたことで知っていたが、アーキズームやスーパースタジオも試みていたわけである。かつてル・コルビュジエはその建築・都市論を映像化し、山本理顕は修士論文のためにアニメーションを制作していた。フィルムの時代における建築家による映像の系譜はまだ全容がわからないので、今後のテーマとなりうるだろう。さて、同展では、ハウス・ルッカー・コーの《イエローハート》(1968)と、フィレンツェ中心部の運動をとりあげたUFOの《都市現象no.6》(1968)が、改めて1968年の文化革命と空気膜のオブジェの強いつながりを示していた。ウーゴ・ラ・ピエトラ《街を取り戻す》(1977)は、ミラノ周辺に生成したセルフビルド的な家屋群を紹介している。またアント・ファームの《メディア・バーン》(1975)は、アメリカのアイコンである自動車とテレビを衝突させるパフォーマンスだった。なるほど、これらの作品は、やはり映像でしか伝えられないものだろう。
2021/11/27(土)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)