artscapeレビュー
2022年03月01日号のレビュー/プレビュー
阪口正太郎「私的風景の形成」

会期:2022/01/11~2022/01/24
ニコンサロン[東京都]
阪口正太郎という作者は初めて聞く名前だが、秋田公立美術大学美術学部美術学科コミュニケーションデザイン専攻の教授を務めており、写真の世界で活動してきた人ではないようだ。そのキャリアが、今回の個展の出品作にもよく現われていて、どれを見ても、写真表現の領域を逸脱、あるいは拡張している。プリントの上にドローイングを施した作品が多く、糸でかがったり、巻きつけたり、コラージュを試みたりしたものもある。手法自体はそれほど珍しいものではないが、制作の動機とプロセスに無理がなく、のびのびとした、スケールの大きな作品世界が成立していた。
特に、森、海、樹木など自然を被写体とした写真に、鹿や熊のような動物、「魚人間」など、神話的な形象を描き加えた作品に面白味を感じる。風景写真をドローイングや糸などを使って「私的風景」として再構築しようとする、意欲的な仕事といえるだろう。植田正治が1980年代に発表した「風景の光景(私風景)」シリーズを思い出した。
実はこの展覧会は、阪口が不慮の事故で負傷したために、中止になる可能性があった。何とか作品の準備ができて、無事開催できたのはとてもよかったのだが、展示作品のフレーミングや会場のインスタレーションに関しては、まだ完全に満足のいく形でできあがっているようには見えなかった。そのあたりを、しっかりと仕上げることができたならば、よりクオリティの高い展示になったのではないだろうか。このユニークな作風を、さらに大きく育てあげ、秋田の風土に根ざした作品に結びつけていってほしい。
2022/01/20(木)(飯沢耕太郎)
Museum of Mom's Art ニッポン国おかんアート村

会期:2022/01/22~2022/04/10
東京都渋谷公園通りギャラリー[東京都]
叔母が昔、いらなくなったネクタイを使って器用に人形をつくってくれた。どこかにそんな教室かサークルみたいなのがあって、そこで覚えたのだろう。早くに連れ合いを亡くした叔母は、時間だけはあり余っていたから。でもその人形も、見慣れた柄とはいえ別に愛着が湧くわけでもなく、かといって捨てるのも忍びなく、結局どこかに仕舞い込んだまま忘れ去られている。これなどは典型的な「おかんアート」だろう。
展覧会をのぞくと、あるわあるわ、PPバンドを編んでつくった犬、軍手をリサイクルしたウサギ、緑色の紐を巻いてできたカエル、半透明のリボンを組み合わせた金魚、毛糸で編んだキューピーの服や帽子、マツボックリの笠のあいだに縮緬を詰めた置き物などなど。動物系が多く、カワイイけどなんの役にも立たない、けど邪魔になるほど場所をとらない、と油断しているうちに増殖して始末に負えなくなるオブジェたち。
同展をキュレーションした都築響一氏によれば、「メインストリームのファインアートから離れた『極北』で息づくのがアール・ブリュット/アウトサイダー・アートだとすれば、正反対の『極南』で優しく育まれているアートフォーム、それがおかんアートだ」。確かに、あり余るヒマと日用品にあかせてつくるおかんアートは、やむにやまれぬ衝動に突き動かされるアウトサイダー・アートの対極にあるが、しかし芸術性や経済的価値を追求するファインアートからの距離はアウトサイダー・アートに近いかもしれない。カッコよくいえば「ブリコラージュ」ということになるが、むしろ「ポップ民藝」といったほうがわかりやすい。民藝と同じく一つひとつは下手物だけど、それが何百何千と集まると体系が見えてきて、芸術的オーラまで帯びてくるから不思議だ。
会場に並ぶのは数千点。数が多ければ多いほど見る者は楽しめるけど、集め出せばキリがないし、なにより美術品と違ってすぐ飽きるので何度も見たいものではない。それでも、素材やモチーフに時代や地域性が感じられ、おかんのセンスの移り変わりもわかるという点で、歴史的・資料的価値は大いにある。これはやはりMoMA(Museum of Mom’s Art=おかん美術館)を設立すべきだろう。下手物といわれた民藝が100年後に東京国立近代美術館で回顧されたように、おかんアートもひょっとしたら本物のMoMAからお声がかかるかもしれない。

「Museum of Mom’s Art ニッポン国おかんアート村」展 会場風景[筆者撮影]
2022/01/22(土)(村田真)
喜井豊治展「壁画から天使まで」
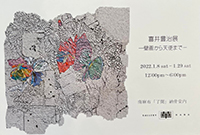
会期:2022/01/8~2022/01/29
ギャラリー華[東京都]
ぼくがモザイクに興味を持つようになったのは喜井豊治のおかげだ。数年前、彼が所属するモザイク会議の定期展にぼくを審査員として採用してくれたからだ。本来モザイクは床や壁に石のかけらを貼りつけて完成させるので、フレスコ画などと同じく「不動産美術」といえる。不動産美術は基本的に注文がなければ制作できないので、依頼主の要求に沿った職人仕事になり、表現内容はある程度制約されざるをえない。そこで多くのモザイク作家は展覧会に出したり売ったりするため、タブローとしてのモザイク画を制作している。モザイク会議の展覧会も、今回の個展も、そうした発表の場のひとつだ。
ついでにいうと、モザイク展の審査でぼくが重視したのは、いま述べたようなモザイクの成り立ちをどれだけ作品に反映しているか、そして、油絵でもフレスコ画でもないモザイクならではの新しい表現がされているか、という点だった。つまり、不動産美術の記憶を止めつつ現代を表現すること、それがタブローとしてのモザイク制作のモチベーションでなければならない、と勝手に考えていた。モザイクの素人がいうのもおこがましいが、今回の喜井の作品はまさにそれを実現しているように思えた。
その作品の多くは、灰白色の石の小片を部分的に規則正しく、部分的にランダムに並べ、ところどころ草花や火や水を表わす緑、赤、青などの石をはめ込んだもの。しかも外縁が矩形ではなく不定形なので、パッと見、瓦礫と化した廃墟の床を真上から俯瞰したような印象がある。彼がテーマにするのは「人のいない景色の物語」。自然破壊が進んで無人になった世界を表わしているらしい。例えば、青い石をうねるように並べた《クレージー水ドラゴン》は川の氾濫や大津波を、白い石から赤い石を炎のように立ち上らせた《山は燃え川は暴れる》は、大火事か火山の噴火を思わせる。不動産美術の記憶を蘇らせると同時に、現代または近未来の日本を暗示するような表現といえるだろう。だが、いちばん共感したのはその作品より、会場に掲げられた彼の言葉だ(以下、ステートメントから抜粋)。
「話すのも気恥ずかしい陳腐な自然破壊のテーマです。それでもこのテーマを選ぶのは、石のかけらを組み合わせた画面にドリルで穴を開け、ハンマーでたたいて壊し、また組み合わせる。そういう破壊衝動に意味を持たせるためです」
ここから読み取れるのは、モザイク作家としての恥じらいと矜恃だ。「破壊衝動に意味を持たせる」というのは、形而上的な表現内容と形而下の創作行為との埋めがたい距離を縮めようとする努力にほかならない。もうひとつ指摘しておきたいのは、「話すのも気恥ずかしい陳腐な自然破壊のテーマ」は、売れ筋ではないということ。彼の主な仕事は壁画制作であり、その一部は会場に写真パネルで紹介されている。東京を中心に各地の公民館や図書館、地下鉄駅などに壁画を設置しているが、見たところ「自然破壊」をテーマにした作品はないようだ。先述のようにモザイクは依頼主の希望に沿って制作されるので、自然破壊のようなネガティブなテーマは好まれない。そうした壁画では需要のないテーマを、彼はタブローとしてのモザイク画で実現させようとしているのだ。ここに彼の恥じらいと矜恃の理由がある。
2022/01/22(土)(村田真)
樋口明宏「Margaret─少女マンガ彫刻」
会期:2022/01/07~2022/02/03
MA2 Gallery[東京都]
少女マンガに登場する典型的なキャラクターを木彫にした作品が15点ほど。少女マンガのキャラクターといえば、大きなおめめにキラキラの瞳、尖った鼻に長い髪が特徴だが、それを荒削りに彫っている。マンガというのは平面の世界だから、現実にはありえない表現もしばしばある。だいたい顔は斜めの角度からカッコよく見えるように描かれるので、目や鼻や口の位置関係が矛盾している場合が多く、立体化しようとするとそのツケが回ってくる。おそらくフィギュアの原型師の苦労もそこにあるが、それを強引に立体化するからおもしろい。
樋口はこれまで昆虫の標本に繊細な装飾を施したり、仏像をポップなフィギュアに修復したり、卓越した技術によって古典とポップ、ハイとロー、西洋と日本、平面と立体のあいだを往還し、攪拌し、組み合わせてきた。この「少女マンガ彫刻」も、卑俗でチープな少女マンガを、仏像や神像といった聖なるイメージが強い木彫に接続した手腕が鮮やかだ。なかには「ピキッ」といった擬音が彫ってあったり、背景に放射線が刻まれたりして笑えるが、彩色は控えめで、近代彫刻のような風格さえ漂う。器用だなあ。
角材から彫っているので、大半は側面や天地が平面で断ち切られている。そのため、まるで彫刻が立体的な1コマに収まっているようにも見える。3次元コマ割りというか。これを積み重ねていけば、4次元の立体少女マンガができるかもしれない。

「Margaret─少女マンガ彫刻」展 展示作品[筆者撮影]
2022/01/22(土)(村田真)
開館40周年記念 白井晟一 入門 第2部/Back to 1981 建物公開

会期:2022/01/04~2022/01/30
渋谷区立松濤美術館[東京都]
一昨年の世田谷美術館の「作品のない展示室」、昨年の大阪市立美術館の「美の殿堂の85年 大阪市立美術館の展示室」と、コロナ禍で企画展が開けないこともあって、ここ2年ほど作品を並べないで展示室だけを見せる展覧会が相次いでいる。府中市美術館の「池内晶子展」もほとんど空っぽだったが、よく見ると糸が垂れ下がっていたっけ笑。空っぽの展示室を見せるのは、企画展が開けないならいっそのこと展示室を開放して、美術館建築について再認識してもらおうとの意図がある。「白井晟一入門」の第2部も、ガランドウの展示室を公開しているが、これは企画展が開けないからではなく、まさにこれ自体が企画展であり、白井の設計した美術館全体を「作品」として体験してもらうためだ。ちなみに第1部の「白井晟一クロニクル」は見ていないので、白井については無知に等しい。
また個人的な話になるが、ぼくが最初に松濤美術館を訪れたとき(かれこれ40年ほど前)、ファサードが要塞のようにいかついことや、建物の中央に楕円形の吹き抜けの池があること、展示室の壁面が大きくカーブしていること、上階にお茶しながら鑑賞できるサロンがあることなど、美術館にしてはクセが強くてあまり好きになれなかった。いまでも好きとはいえないが、ほかの凡百の美術館と違って唯一無二のデザインであることには敬意を払いたい。コレクションや活動内容は別にして建物だけでいうと、例えば東京都現代美術館とどっちを残してほしいかと聞かれれば、迷わず松濤美術館を選ぶくらいの愛着はある。
今回初めて美術館の平面図を見た。ファサードが凹むように湾曲しているが、そのカーブは建物の中心に位置する池の楕円形や、その奥の展示室のカーブとも呼応していることにあらためて気づく。また当初案では、エントランスから真っ直ぐ進んで池をまたいでブリッジを渡り、回廊から展示室を見下ろしながら地下に降りていく導線だったという。ところがスペースの都合で、エントランスからブリッジを渡らず左側のロビーを抜けて階段を降り、展示室に行くように変更された。ブリッジと回廊は普段は閉鎖されているが、この期間は公開されているので、ブリッジを渡って回廊に出て展示室を見渡してみた。すると、階段を降りて展示室に入る現在のアプローチとでは、展示作品とのファーストコンタクトがまったく異なるであろうことが想像できた。この導線の変更は、設計者にとっても来館者にとっても残念なことだ。
地下の展示室から螺旋階段を上って2階へ行ってみる。普段は意識していなかったが、この螺旋階段もなかなか味わい深い。2階の展示室は大きいサロンミューゼと小さい特別陳列室に分かれ、サロンでは以前コーヒーが飲めたと記憶する。特別陳列室は小さくて天井も低いので、素描や小品など近い距離で作品を鑑賞できるようになっている。つまり地下の展示室に比べて親密な空間を目指しているのだ。しかしこうした空間の差別化も徐々になし崩しになり、均質化して、ほかの美術館とあまり変わらなくなってしまった。白井によれば、「デパートの展覧会場の二番煎じみたいなことを追わない、創意によった使い方のできる区民のための美術館を計画した」が、果たしてどこまで実現しているのか。

渋谷区立松濤美術館の螺旋階段[筆者撮影]
2022/01/27(木)(村田真)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)