artscapeレビュー
2023年12月15日号のレビュー/プレビュー
中間アヤカ『踊場伝説』(KYOTO EXPERIMENT 2023)、インキュベーション キョウト 福井裕孝『シアター?ライブラリー?』

[京都府]
既存の劇場空間のなかに、もしくは都市の空き地に、仮設的な場をつくり、独占するのではなく、どのように場を開いて共有するか。本稿では、「劇場」の機能や意義を拡張・再定義するような試みとして共通し、同時期に開催された中間アヤカと福井裕孝の上演企画を取り上げる。
KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2023のプログラムとして上演された中間アヤカ『踊場伝説』は、市営住宅の跡地に仮設の「劇場」をつくり、1週間にわたって公開リハーサルを行なうとともに、「劇場レパートリー」として新作ソロダンスを上演した。また、最終日には、関西のベテランダンサーのソロダンス作品を中間が継承して上演した。
現存する市営住宅を背に、T字型に組まれた巨大な木組みの仮設舞台が空き地に出現する。通路状に伸びた高い舞台から、埠頭のように突き出した中央のスロープが異様な迫力を放つ。セノグラフィ(舞台美術)を手がけたのは、建築を媒体とするコレクティブ、ガラージュ。ソロダンスということもあり、「舞台に立つことの孤独」を一身に引き受けているような中間の姿が際立った。本企画のもうひとつの軸は「関⻄ダンス史における伝説のリサーチ」であり、舞台下の空間では展示も行なわれたが、「怪談風に仕立てた証言ビデオ」や資料のスクラップブックのスキャンデータをタブレットで閲覧するなど、散漫に感じられた。

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]
むしろ本企画の最大の目玉は、最終日の公演終了後、ショベルカーによる「舞台の解体作業」の公開にある。中央スロープにショベルカーのアームが遠慮なく打ち下ろされ、無残に解体されていく舞台。ダンスが「消失」によってこそ強度を獲得し、見る者の記憶に残るとするならば、「劇場」もまた、「解体ショー」というスペクタクルを上演する転倒によって、記憶のなかに強度を保って刻みつけられ、伝説化するのではないか。そうした皮肉やねじれさえ読み取れる。一方、本企画で特筆すべきは、「空き地の劇場」を文字通り共有地(コモンズ)として開いていく姿勢である。中間は「仮設の劇場」を独占するのではなく、午前中のリハーサルと夜の公演のあいだの午後の時間を、他の団体の公開稽古の場としてシェアした。

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]
一方、「ものの配置と秩序の再構築」という手法で演劇や劇場機構をメタ的に問い直す福井裕孝は、空間の自由度の高いロームシアター京都ノースホールに、「仮設のライブラリー」を出現させた。会場には図書館のように書架が配置され、演出家や研究者、アーティストらがそれぞれの視点でセレクトした私物の書籍がコメント付きで並べられ、観客は自由に手に取って読むことができる。この空間では同時に、福井自身と同世代のダンサーや演出家(内田結花、お寿司、レトロニム、新聞家)の作品の上演や、読書会も開催された。空間設計はREUNION STUDIOによる。

[撮影:中谷利明]
福井はこれまで、「テーブル」を「舞台」に見立て、パフォーマーがさまざまなものを配置する運動を見せる無言劇『デスクトップ・シアター』を上演してきた。本企画も、この「テーブル」の役割の多重性や揺らぎが基底にある。「図書館の読書テーブル」が、そのまま「上演の舞台」となる。観客はどこに座って上演を眺めてもよく、本を読むだけでもいい。

福井裕孝『デスクトップ・シアター』上演の様子[撮影:中谷利明]
福井自身の『デスクトップ・シアター』のほか、新聞家は、その日の観客から参加者を募って戯曲を朗読する実験的な朗読会を試みた。「朗読」も「感想を話す会話」もほぼ同じトーンで行なわれることが、むしろ心地よく、逆に傾聴の姿勢を誘う。また、レトロニムは、「サーチ・エンジン」をテーマとする作品を上演した。「聞いた話」「見た夢」をボソボソと語る俳優のモノローグからキーワードを拾い、「図書館の検索システムに打ち込んで本を探す」行為がモニター上で同時進行する。テーブルに寝そべった俳優と、傍らでキーボードを打ち込む演出家の姿はカウンセリングのようでもあり、書架に並ぶ本が誰かの夢の記録のようにも見えてくる。

レトロニム『サーチ・エンジン』上演の様子[撮影:中谷利明]
無言劇、ダンス、一般観客による朗読、抑制的な語りといった性格もあり、「パフォーマンスの上演」と「読書にふける観客」が同じ空間で共存していたことが興味深かった。劇場も図書館も公共空間だが、両者が重なり合ったとき、互いを排除するのではなく、より自由度の高い空間が出現する。「個人の本棚をシェアする空間」としての仮設的な図書館が、さらに「上演空間のシェア」となる。そして福井も中間も、建築設計の専門家らと協働しながら仮設的な上演空間を立ち上げ、同世代のアーティストに開いて共有する姿勢に希望を感じた。
中間アヤカ『踊場伝説』(KYOTO EXPERIMENT 2023)
会期:2023年10月9日(月・祝)~15日(日)
会場:養正市営住宅6棟跡
(京都府京都市左京区田中馬場町6)
インキュベーション キョウト 福井裕孝『シアター?ライブラリー?』
会期:2023年10月12日(木)~15日(日)
会場:ロームシアター京都ノースホール
(京都市左京区岡崎最勝寺町13)
関連レビュー
福井裕孝『デスクトップ・シアター』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年08月01日号)
2023/10/15(日)(高嶋慈)
横山大介「言葉に触れる身体のためのエチュード」

会期:2023/09/24~2023/10/28
VISUAL ARTS GALLERY[大阪府]
マイノリティの当事者が、マイノリティとしての自らの身体的な経験を、それをもたないマジョリティと共有することは可能なのか。それがコミュニケーションを介した共同作業として行なわれるとき、「マイノリティ/マジョリティ」「教える/教えられる」といった関係性の反転や流動化こそが賭けられているのではないか。そのときアートは、社会的なエチュード(練習)として存在し始めるだろう。
吃音をもつ写真家の横山大介は、他者とのコミュニケーションの方法として、深い断絶を感じる会話よりも、カメラを通して視線を交換する行為の方がしっくりくるという感覚から、被写体と真正面から向き合って撮影したポートレートのシリーズ「ひとりでできない」を中心に発表してきた。本展では、音楽家らと協働し、自身の吃音を、「他者の身体への移植を経由して自らへ再移植する」行為を通して見つめ直した映像作品《言葉に触れる身体のためのエチュード》が発表された。

「言葉に触れる身体のためのエチュード」展示風景(2023)、VISUAL ARTS GALLERY
横山は、妻や友人との日常的な会話、ホテルのチェックイン時の会話などを録音し、そのなかから自身の吃音の特徴が出ているフレーズを抽出した。その音声データを、菊池有里子(音楽周辺者)に依頼し、「吃音スコア」として譜面化した。さらに、その譜面を中川裕貴(音楽家、チェロ奏者)に渡し、譜面を見ながら音声データを繰り返し聞いてもらい、スネアドラムでリズムを刻む「演奏」に置き換えてもらった。映像作品は、横山が「吃音スコアの演奏」を中川から教えてもらいながら「練習」する行為を記録したものだ。身体性が如実に現われる打楽器として、スネアドラムが選ばれた。また、菊池が手書きで書いた譜面を、さらに横山がトレースした「吃音スコア」も展示された。

「言葉に触れる身体のためのエチュード」展示風景(2023)、VISUAL ARTS GALLERY

シリーズ「言葉に触れる身体のためのエチュード」より(2023)HD Video[© Daisuke Yokoyama]
吃音とは、発話しようとしたときに思うように言葉が出ない障害であり、3つの症状がある。「ぼ、ぼ、ぼ、ぼくは」のように最初の音を繰り返す「連発」、「ぼーーくは」のように最初の音が引き伸ばされる「伸発」、「……ぼくは」のように最初の音が出てこない「難発」の3つである。横山が抽出したのはごく短いフレーズだが、「連発」と「伸発」の両方が混在するような場合もある。例えば、《言葉に触れる身体のためのエチュード #001「かかからだやろ」》では、「か、か、かーらだやろ」という発音が、「タン、タン、スー、タタタタッ」という音の連なりとして聴こえる。「か、か、」の連発は強く短く叩き、「かー」と伸びる音はスネアドラムをブラシでこする奏法で表現され、最後の「らだやろ」は短く小刻みに叩かれる。短いフレーズだが、音の緩急や強弱をつけながら「演奏」するのは難しく、「ここは間髪入れずに」「もう一度」といったアドバイスやダメ出しを中川から受けながら、横山は何度も反復練習する。最初に中川が「お手本」の演奏を示すのだが、練習のなかで横山自身が「ここはちょっと違う」「この音の部分をもっと強く」といった修正を加える場合もある。「どちらが教えているのか」は曖昧に揺れ動き、横山と中川は互いに教え合ってズレを修正しながら「吃音のリズムの再現」に近づけていく。それは正解のない、近似値を手探りで探っていく共同作業だ。

シリーズ「言葉に触れる身体のためのエチュード」より(2023)HD Video[© Daisuke Yokoyama]
ここに本作の肝がある。例えば、映画『英国王のスピーチ』(2010)のように、「吃音を直す」矯正訓練として、「正しい発声」をもつ人が、もたない人に一方的に教える関係ではなく、「吃音のリズムを身体のなかにもっていない人」と、そのリズムを共有するためのレッスンなのだ。2ビートや4ビートのような型のあるわかりやすいリズムではなく、極めて複雑で変則的なリズムであるがゆえに、その「再現」は難しい。吃音の矯正訓練が、「他者の身体感覚に介入してエラーを書き換えようとする行為」であるとすれば、本作で起きているのは、むしろ、非当事者の中川の側において、「他者の身体のリズムが自身の身体に侵入し、書き換えられる」という事態だ。譜面化というかたちで「身体から切り離された声」は、演奏によって再現する行為を通して、その身体的なリズムをもたない人と共有するための手段となる。
そして、ワンフレーズを何度も反復する練習のプロセスを見ているうちに、観客である私もまた、傍らの譜面と見比べ・聴き比べながら、脳内でそのリズムをトレースし、イメトレ的に反復再生していることに気づく。本作に冠せられた「エチュード(練習)」は、何重もの意味をはらんでいる。それはまず、横山自身が、譜面化とドラム演奏への置換という二重の外部化の手続きを経て、自身の吃音を身体的に再インストールするための「練習」である。そこでの他者の介在は、「吃音のリズム」をもっていないマジョリティがどう身体化して共有できるか、という社会的なレッスンでもある。「ネガティブ」とされる特性について、腫れ物に触るようにではなく、当事者と非当事者がともにリラックスした状態で、どう身体的な経験として共有できるかというレッスン。
エチュードには「習作」の意味もあるが、本作での試みは、例えば観客も実際にドラムを叩く練習に参加するワークショップを開くなど、さらなる発展の可能性があるだろう。それは、アートの社会的な意義の拡張でもある。
関連レビュー
Kanzan Curatorial Exchange「写真の無限 」vol.1 横山大介「I hear you」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年06月15日号)
2023/10/28(土)(高嶋慈)
倉敷安耶「あなたの髪のひとつ(だった)」

会期:2023/10/27~2023/11/12
haku[京都府]
男性中心主義的な視線によって付けられてきた傷を、表象のレベルと物質的なメディウムのレベルの双方においてどう回復し、ケアすることができるか。東西の宗教や美術史とジェンダーの関係を問い直し、ジェンダー化されたケア役割を、シスターフッド的な関係性として戦略的にどう反転させることが可能か。本展はこうした実践に貫かれている。そのために倉敷安耶が用いるのが、デジタルコラージュと転写という2つの技法/操作だ。
本展で倉敷がモチーフとするのは、マグダラのマリアと小野小町。「髪」を共通項とし、キリスト教と仏教の教義や死生観を描いた絵画において、「宗教」「道徳」を口実に、男性の性的な視線の対象物として表象されてきた2人の女性像である。マグダラのマリアは、磔刑に処されたイエスの遺体に香油を塗るために墓を訪れ、イエスの復活に最初に立ち会った人物とされる。キリスト教の教義の体系化の過程で、「罪深い女」(イエスの足を涙で濡らし、自身の髪の毛でぬぐい、接吻して高価な香油を塗り、イエスに罪を赦された娼婦)と同一視された。そのため、西洋古典絵画では、「洞窟に隠遁し、自身の罪を悔いる元娼婦」という図像で描かれることが多い。だが「隠遁した聖者」であるにもかかわらず、「胸や肩をはだけ、白い肌を露にし、恍惚の表情を浮かべる若く美しい女」として描かれてきた。「洞窟」という閉鎖空間もまた、覗き見的な消費の視線を示唆する。
一方、小野小町は伝説的な絶世の美女とされるが、晩年は容貌が衰え、野ざらしになって死んだとされ、「九相図」のモデルとして描かれた。「九相図」とは、「どんな美女でも死ねば肉体は朽ち果て、骨と化す」という無常観や肉体の不浄さを、肉体の腐敗の9段階に分けて描写した仏教絵画である。若い女性の死体が徐々に腐敗し、ガスで膨らみ、体液が流れ出し、ウジがわき、鳥獣に食い荒らされ、骨だけになる。煩悩を払い、肉体の不浄さや無常さを説く絵画だが、なぜ女性の身体だけが「不浄」とされるのか。そこには同時に、「美女の死体」を視姦するポルノグラフィックな欲望もあるのではないか。

倉敷安耶 ドローイング《発酵の九相図》(2023)水彩用紙、アクリルメディウム転写、ワイン[撮影:久保田智広]
倉敷は、引用画像のコラージュによって、マグダラのマリアと小野小町を同一平面上で出会わせる。《祝福と喪葬のための香油塗り》では、西洋古典絵画に描かれたマグダラのマリアと、絵巻物や日本画から引用された小野小町が、互いに香油をかけ合う。それは祝福を表わすと同時に、弔いの行為としてのケアでもある。《九相図》で引用されたのは左右2人の人物ともマグダラのマリアだが、裸体で横たわる右側のマリアは髪を黒に、かつ長く加筆され、野ざらしの死体となった小野小町のようにも見える。この2つの引用画像はエロティックな欲望が顕著な例であり、左側のマリア(ピーテル・パウル・ルーベンス)は肩と胸元を大きくはだけ、右側のマリア(19世紀フランスの官展画家ジュール・ジョゼフ・ルフェーブル)は全裸でなまめかしいポーズをとり、あからさまにポルノグラフィックな図像だ。

倉敷安耶《祝福と喪葬のための香油塗り》(2023)木枠、ウール生地、アクリルメディウム転写、油彩、糸[撮影:久保田智広]

倉敷安耶《九相図》(2023)木枠、ウール生地、アクリルメディウム転写、油彩、糸[撮影:久保田智広]
だが、倉敷の作品では、ひざまずいたマグダラのマリアが接吻して香油を塗るのはイエスの足ではなく、小野小町/マリア自身である。イエスの遺体を清めて弔うというケア役割は、(男性ばかりの12使徒ではなく)マグダラのマリアすなわち女性の役割としてジェンダー化されつつ、男性の性的視線の対象物として表象されてきた。倉敷は、「男性をケアする」という奉仕的役割を、女性どうしが互いをケアし合うものとして、シスターフッド的に反転させる。
そして、男性の視線によって一方的に表象・消費されてきた「傷」をまさに可視化するのが、転写による画面のテクスチャである。ボロボロになった皮膚のように表面が剥がれ、こすれ落ち、亀裂が走り、穴のあいた傷口から支持体の内部が露出する。倉敷は、通常は下絵として用いられる転写技法をあえてそのまま見せることで、イメージに物質的な層をまとわせ、文字通り受肉させる。本展出品作では「メディウム転写」の技法が用いられている。転写したいイメージを紙にインクで印刷し、アクリルメディウム樹脂を塗った支持体の表面にその紙を貼り付け、乾燥させてインクが定着した後に、水で濡らして紙の部分をこそぎ落として転写させる。その際に生じる亀裂やスクラッチを、倉敷は積極的に表現技法として活用している。

倉敷安耶《九相図》(部分)(2023)木枠、ウール生地、アクリルメディウム転写、油彩、糸[撮影:久保田智広]
「視線」の暴力性は、性的な視線はもちろん、好奇や侮蔑の視線を向けられた相手を「物理的には傷つけない」ことによって巧妙に覆い隠されている。だが目に見えなくとも、そこに確かに傷は存在する。マグダラのマリアや小野小町の九相図の絵画に向けられ続けてきた性的な視線が、もし本当に物理的に画面を暴力的に貫いたら、このようにボロボロに傷ついていたのではないか。倉敷は、歴史的絵画が何百年も視線の暴力に晒され続けてきた傷を可視化・物質化したうえで、「その痛みをケアし合う」シスターフッド的な関係性を描くことで、表象のレベルにおいて傷の回復を試みる。そして物理的なレベルでは、「画面の傷」を実際に糸で縫い合わせて「修復」を施す。倉敷の絵画は、痛みの可視化であるとともに、そうした二重のケアと修復の行為なのだ。

[撮影:久保田智広]
2023/11/05(日)(高嶋慈)
竹之内祐幸「Warp and Woof」

会期:2023/10/06~2023/11/18
PGI[東京都]
PGIで開催されてきた竹之内祐幸の個展をこれまで何度か見て、いい作家だとは思うのだが、いまいちその輪郭、方向性を掴みきれないでいた。だが今回の「Warp and Woof」展に彼が寄せたテキストを読んで、「なるほど」と腑に落ちるものがあった。
竹之内は取材で「ヒッピーの集落」を訪れ、自分の世界とはまったく異なる習慣や振る舞いを目にして大きなショックを受けた。そのときに、一緒に行った編集者が「普段の自分とかけ離れた“際”の世界を知ると、自分の心の地図が広がった気がしませんか」と話してくれたのだという。それを聞いて「自分の身の回りの景色だけでなく、それを構成しているもっと大きな世界にも目を向けよう」と思い、望遠レンズで遠い風景を撮影し始めた。
そういう目で見ると、竹之内の写真ではいつでも「自分の心の地図」を広げようという思いがかたちをとっているように感じる。ある被写体にカメラを向けるとき、その対象物を超えた「もっと大きな世界」を常に意識しているというべきだろうか。そのため、展覧会や写真集には、何をどんな目的で撮影したのかよくわからない、意味づけをはぐらかすような写真が並ぶことになる。今回の展示では、その狙いは被写体の選択だけでなく、会場構成にも及んでいた。大中小のフレームが用いられているだけでなく、大きなフレームに窓を切り、そこに小さな写真を25-27枚はめ込んで縦横に繋げていく作品もある。さらに3面マルチの映像作品もあり、「心の地図」をさまざまなかたちで描き出していこうとする彼の意図がよく伝わってきた。
昆虫や鳥、水の表面、岩山、樹木、後ろ姿の人物など、竹内が拾い集めてきたものたちは穏やかに自足しているように見えて、何か別なものにメタモルフォーゼしかねないような、やや不穏な気配も感じさせる。「心の地図」を声高に押しつけるのではなく、慎み深く、そっと差し出すような彼の姿が、写真の行間から浮かびあがってくるような展示だった。なお展覧会に合わせて、FUJITAから同名の写真集(デザイン:藤田裕美)が刊行されている。
竹之内祐幸「Warp and Woof」:https://www.pgi.ac/exhibitions/8962
2023/11/08(水)(飯沢耕太郎)
ビジター・キュー

会期:2023/11/11~2023/11/12
MINE[大阪府]
「上演」と「展覧会」という制度的フレームは、「観客」「視線」を介してどのように批評的に交差しえるのか。展覧会というフォーマットのなかで、演劇性はどのように立ち上がるのか。
本展のキュレーションは、俳優の瀬戸沙門、美術家の武内もも、演出家の野村眞人からなる京都のアート・コレクティブ「レトロニム」(旧称「劇団速度」)。元マンションビルの各階と周辺の公園を会場に、美術家・俳優・演出家の5名が参加し、時に作品が「移動」しながら2日間のみ開催された本展は、そうしたひとつの実験だったといえる。会場の「MINE」は、京都と滋賀の県境にある共同スタジオ「山中suplex」が、別棟として大阪の市街地に展開するスペース。2022年12月から約1年間、外部のクリエイターを招聘して企画やイベントを行なってきた。
「ものの配置と秩序の再構築/テキストの設置」という対照的な手法ながら、「幽霊」「不在」「主体」といったキーワードから演劇を批評的に扱うのが、演出家の福井裕孝と俳優の米川幸リオン。福井は、生活家電や日常雑貨、これまでMINEを利用したアーティストの制作の痕跡など、展覧会の開催にあたって不要と判断されたさまざまな「もの」に着目。それらを展示会場から撤去する代わりに、「バックヤードの構成物のみでつくり上げたインスタレーション」を制作した。ペットボトル飲料、扇風機やドライヤーなどの家電、ハンガー、清掃用具、文房具などが几帳面に規則正しく並べられている。福井は昨年、京都の小劇場で同様に「ロビーやバックヤード、楽屋などにある備品や機材をすべて舞台上に集合させ、規則正しく並べた状態で上演する」という試みを行なっており、今回はその「展覧会バージョン」といえる。

福井裕孝《無題(MINEを収納する)》[筆者撮影]
「観客の目に触れるべきではない」「特に見られる価値がない」と判断される、通常は透明化されたものたち。福井は、そうした「展示」「上演」の幽霊たちを可視化し、居場所を与えると同時に、厳密な配置のルールによって空間を再秩序化する。むしろ、「もの」たちは自由なふるまいを許されず、秩序の再構築のために召喚されているのだとすれば、ここには、キュレーターが「作品」を、演出家が「出演者」を扱う態度こそがメタ的に問われているといえるだろう。そのとき観客に突きつけられるのは、「作品同士の関連性」でも「意味の解釈」でもなく、「意味を読み取るべき主体」としての自らの共犯性とナンセンスだ。
一方、米川幸リオンは、会場のあちこちに小さなテキストの紙片を設置した。見逃されるような小ささだが、換気扇の表面に、開いた窓の向かいにある壁に貼られた紙片に気がつくと、建物の細部に注視が向かっていく。「わたしは」という語りは、換気扇や障子の破れ目といった「これまで見えていなかった幽霊」が語り出し、ものが主語としてふるまい出すように見えてくる。あるいはノートパソコンの画面は、「わたしとあなたとの間にのみ起こる現象」としての上演について語り続ける。だが、画面に表示される文章は入力と消去を繰り返し、ノートパソコン自体もキャリーカートに載せられて会場内を「移動」し、紙片には「ゆくゆくは引き剥がされる」と記されるように、その「上演」自体、どこにでも貼り付け可能である一方、消去の痕跡すら残さず消えてしまう。まさに、「ビジター(観客)」が「キュー(きっかけ)」となって上演が立ち上がるが、それは「観客の視線」が存在する瞬間しか持続できない。
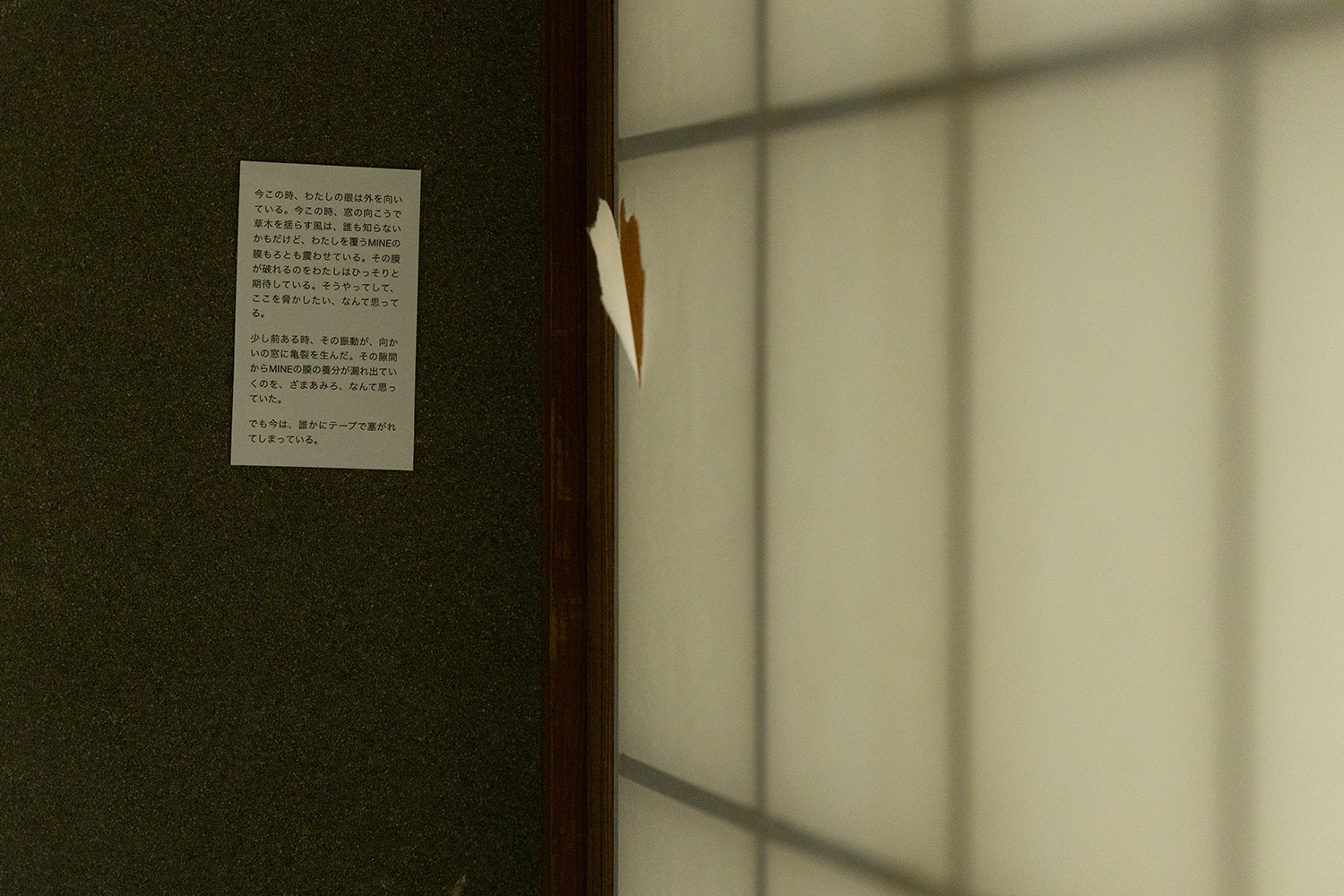
米川幸リオン《「わたしの」テキスト1~10》より[撮影:中谷利明]

米川幸リオン《ビジター・キュー「上演」のテキスト》[撮影:中谷利明]
移動性や仮設性、他者の介入が上演/作品を起動させることは、宮崎竜成の移動型作品《絵の成り立ちデバイス》へとつながる。宮崎は、可動する仮設壁に穴を開けた装置を自作。穴をのぞいて見えた景色を描いた絵を仮設壁に貼り、装置を移動して穴から見える景色が変わるたびに新たな絵を貼り替えていく。制作/展示が一体化した装置であり、展示会場に面した公園に設置された装置は、公園に来た人が自由に移動させてよい。「なんだろう」と穴をのぞく行為が「ビジター(観客)」を出現させ、その視線の痕跡を、時間のズレとともに、宮崎を介して見る者は共有する。

宮崎竜成《絵の成り立ちデバイス(インフラを数える)》[撮影:中谷利明]
そして、キュレーターのレトロニムは、各作品の前に「観客席として椅子を設置する」という仲介/介入を行なった。(長尺の映像作品をのぞいて)展覧会としては不自然さや違和感を与える仕掛けであり、椅子は両義性を帯び始める。文字通り居場所を与える一方、視点の固定化や「一人しか座れない」という独占性など制限と表裏一体だからだ。あるいは、椅子の脚の位置をテープで示しただけの床にスポットライトを当てた「透明な椅子」は、観客という存在を「不在」によってこそ浮かび上がらせる。

レトロニムによる「観客席(椅子とバミリ)」[撮影:中谷利明]
ただしそこには、「ジェンダーの不均衡な構造によって不在化された幽霊のような観客」もいるのではないかと問題提起するのが黒木結だ。黒木は、「作品」としてのサニタリーボックスをトイレに設置し、買い取り検討を要請するテキストを掲示した。黒木は以前、MINEでのイベントに参加した際、トイレにサニタリーボックスがないことに気づいた経験から、山中suplexのメンバーに対して会期終了後に買い取りをお願いし、不可の場合はその理由の回答を黒木自身のHPとSNSで公表するまでのプロセスを作品としている(12月6日の執筆時点でまだ回答は公表されていない)。

黒木結《サニタリーボックス》[撮影:中谷利明]
「サニタリーボックスの買い取り」は単に物品の購入で終わりでなく、ゴミの処分という継続的なケアワークまでを含む。「自分たちには必要ない」「男性に掃除させるのか」という理由ならば、「スタジオの外部の利用者や観客には必要な人もいる」という想像を欠いた男性中心主義の露呈にすぎない。サニタリーボックスに限らず、「見えていないこと」は無意識の排除であり、当事者にとっては抑圧にほかならないからだ。
ビジター・キュー:https://yamanakasuplexannex.com/programs/23015.html
関連レビュー
福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)
劇団速度『わたしが観客であるとき』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年01月15日号)
劇団速度『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)
2023/11/11(土)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)