artscapeレビュー
2016年12月15日号のレビュー/プレビュー
世界遺産 ラスコー展 ~クロマニョン人が残した洞窟壁画~

会期:2016/11/01~2017/02/19
国立科学博物館[東京都]
待望のラスコー展! これが国立西洋美術館ではなく、隣の国立科学博物館で開かれるところに、洞窟壁画の立ち位置が示されている。ラスコーの洞窟壁画は「西洋美術」の範疇に入らないばかりか、美術史の枠からも外れた考古学の対象であるということだ。会場に入るとまず、ラスコーの洞窟壁画が発見された経緯や洞窟の構造がパネルやマケットによって紹介され、使われた顔料やランプ、石器などが展示されている。つい忘れてしまいがちだが、そもそも洞窟内は真っ暗で、岩肌は平らでも垂直でもなく凸凹しており、絵具も筆もないなかで、記憶と想像を頼りに絵を描いたという事実。チンパンジーも絵を描くが、あれは人間が画材を与えたから描けるのであって、画材も環境も整っていないなかで絵を描いたというのは、やはり人類にとって大きな一歩というか転換点だったに違いない。
ひととおり予習をしたあとで、いよいよ実物大レプリカの登場となる。これは壁画のなかでも《黒い牝ウシとウマの列》《泳ぐシカ》《井戸の場面》など5場面を凹凸まで精密に再現したもの。もちろん洞窟内部に入ったほどの臨場感はないけれど、最初に絵を描いた原始人の気分をそれなりに味わわせてくれる。ただ一定時間ごとに明かりが消えて線刻された部分だけライトアップするのは、啓蒙的サービスのつもりだろうけど余計なお世話だ。どうせやるなら明かりをランプの焔のようにゆらゆら揺らめかせて、当時の人たちには動物の絵がどのように見えていたか(たぶん動いているように見えたのではないか)を示してほしかった。
2016/11/04(金)(村田真)
開館90周年記念 アーカイブズ資料展示 造形講座と東京都美術館

会期:2016/11/03~2016/12/04
東京都美術館[東京都]
1926年開館の東京都美術館も今年で90歳。新築移転してからでも40年以上たつ。なぜ都美館は団体展の貸し会場となったのか、戦時中どれだけ戦争画展が開かれたのか、読売アンデパンダン展における前衛美術家との攻防はどうだったのか……。その1世紀近い歴史の資料を公開するのかと期待して行ってみたら、ぜんぜん違う。立体造形講座とか平面造形講座とか、都美館で開かれていた造形講座の資料しかない。しかもラウンジの片隅にパネルを並べただけの小展示。チラシをよく見たら、小さく「造形講座と東京都美術館」とサブタイトルにあるのを見逃していた。ガーン! すぐ帰ったわ。
2016/11/04(金)(村田真)
かんらん舎(1980-1993):Daniel Buren/Tony Cragg/Imi Knoebel
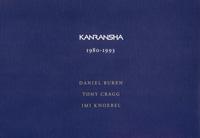
会期:2016/10/22~2016/11/19
ギャラリー小柳[東京都]
ギャラリー小柳で「かんらん舎」の展覧会? そもそもかんらん舎のことを知らない人も多いと思うので簡単に紹介すると、70年代末ごろは夭逝の画家の作品を扱っていたが、80年代に入るといきなりヨーロッパの現代美術に転換。それもトニー・クラッグやダニエル・ビュレンら当時最先端のアーティストに新作を依頼するという徹底ぶり。スペースは小さいけれど国際的に注目された画廊なのだ。今回はどうやらギャラリー小柳がかんらん舎の展覧会を開くのではなく、かんらん舎がギャラリー小柳を借りて展覧会を開いたということらしい。どっちでもいいけど。出品はダニエル・ビュレン、トニー・クラッグ、イミ・クネーベルの3人。ビュレンは黒と緑のストライプ模様の透明ガラスを壁に止めた《壊れたガラス》、クラッグはペンキがはがれかけた漂流物の木を壁に三角形に配置した《山と湖》と、ところどころ穴の開いた磨りガラスの器をテーブル上に並べた《静物》、クネーベルは木の板に荒々しく傷をつけて黒く塗り込めた《黒い絵》。それなりに時代を感じさせるが、特にクネーベルの作品には心がざわめく。
2016/11/04(金)(村田真)
山城知佳子作品展
会期:2016/11/04~2016/11/06
MEDIA SHOP | gallery[京都府]
自らの身体パフォーマンスを記録した初期作品3点(《OKINAWA 墓庭クラブ》(2004)、「オキナワTOURIST」3部作(2004)より《I Like Okinawa Sweet》《日本への旅》)と、近作の《沈む声、紅い息》(2010)を上映する展覧会。両者の対比から見えてくるのは、政治性をはらんだ現実の場所=背景のスクリーン/その手前で行なわれるパフォーマンスという固定化された二層のレイヤー構造から、潜行/浮上という垂直方向の運動のベクトルへ、という構造的な移行である。
《OKINAWA 墓庭クラブ》では、サンバイザーにミニスカート姿の山城が、沖縄の伝統的な亀甲墓をバックに、ダンス・ミュージックに合わせてキレのよいダンスを披露してみせる。《I Like Okinawa Sweet》では、米軍基地のフェンスの前で、汗ばむ肌を見せてアンニュイな仕草をする山城が、差し出されたアイスクリーム(Sweet=甘言)を延々となめ続ける。《日本への旅》では、国会議事堂の前で、沖縄の墓の写真を掲げた山城が抗議するかのように叫ぶが、聞こえてくる音声は「首里城」「長寿」「マンゴー」「夕陽の美しいビーチ」「モノレール開通」などの観光PRや「外から見た沖縄」のイメージである(「〜だと思われます」「〜らしいです」という断定を避けた言い回しが、外部の視線によって形成された曖昧なイメージであることを強調している)。

左:《OKINAWA 墓庭クラブ》 2004、ヴィデオ、6'00"
© Chikako Yamashiro, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
右:《I Like Okinawa Sweet (オキナワTOURISTより)》 2004、ヴィデオ、7'30"
© Chikako Yamashiro, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
《OKINAWA 墓庭クラブ》において、伝統墓のある空間があたかもクラブに変貌したかのように腰をくねらせて踊り続ける孤独な姿は、古い琉球文化/アメリカが戦後もたらしたカルチャーという対比やねじれを示唆する。また、基地のフェンスの前で差し出されたアイスクリームに笑顔を向け、汗やアイスの滴がしたたった肌を見せつけながら、過剰な性的アピールとともに「なめる」姿は、沖縄の置かれた現状を自己批判的に演じている。《I Like Okinawa Sweet》は、《OKINAWA 墓庭クラブ》と同様、受動的な女性性を付与され、快楽に没入する「沖縄」を演じてみせているのだ。一方、《日本への旅》では、能動的に声をあげる女性が登場するが、「観光PR」を絶叫する音声が入るのは「静止画面」だけであり、音声カットされて無音で流される動画部分の山城が本当は何を叫んでいるのかは分からない。「沖縄が本当の声を主体的に話すことは許されない」のであり、その声はたとえあげられたとしても、私たちには届かず「聞こえない」のだ。

《日本への旅 (オキナワTOURISTより)》2004、ヴィデオ、6'00"
© Chikako Yamashiro, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
このように初期の3作品では、琉球(とその変容)/米軍基地/日本国家という存在が背後から規定する文脈として屹立するが、それは背景=スクリーンである以上、山城の肉体はそこに介入できない。一方、《沈む声、紅い息》では、より抽象的でメタフォリカルな表現に移行するとともに、沈む/上昇するという運動のベクトルが際立ってくる。ボソボソと聞き取りにくいつぶやき(家族の記憶?)や歌を口ずさむ老婆、彼女が海中に投げる花束のようなマイクの束、海中で不思議な生き物のように揺れるマイク。海に沈んだマイクを追いかけるように、若い女性ダイバーが海中へ潜行する。荒い呼吸音、ボコボコという泡の音、キスする映像のオーバーラップ。そして最後には、海底に沈んだマイクから空気の泡が立ちのぼっていく。それは、マイクに吹き込まれていた(死者たちの、あるいは語ることを抑圧された)無数の声の解放だろうか。この「下に潜る/浮かび上がる」という上下感覚の運動は、沖縄がはらむ記憶、その深い胎内の中への潜行でもある。
そしてこの潜行とそこからの再浮上の運動は、《アーサ女》(2008)でも波間を漂う不安定な視線の揺動として見られたが、以降の《肉屋の女》(2012)、最新作の《土の人》(2016)において、より強烈なイメージの強度と深度をもって遂行されていくことになる。(《肉屋の女》では、米軍基地敷地内の闇市で肉屋を営む女性が、「肉」を求めて群がる肉体労働者たちに襲われた後、胎内を思わせる鍾乳洞の奥深くを潜り抜け、海中を泳ぎながら上昇していく。自由に泳ぐその姿は「解放」を感じさせる一方で、冒頭に登場する、海中を漂って浜辺へ流れ着く肉塊とのつながりも思わせ、転生や「消費」のループを暗示する。また、《土の人》では、大地と同化したかのような長き眠りから人々が目覚め、穴の中へ転がり落ちる。
洞窟を這い進み、異次元につながるトンネルの出口のような別の穴から人々が顔を出すと、その空間には沖縄戦の映像が映し出されており、彼らは映像の光を顔に浴びながら驚異の眼差しで見つめる。続くクライマックスでは、一面に広がる百合の花畑の中から人々の両腕が天へ差し伸べられ、祈りか祝福のような手拍子のリズムが青空へ高らかに響きわたっていく)。
本展は、展示の機会が少ない初期作品をまとめて見られる貴重な機会であったとともに、山城作品を構造的な移行という視点から捉える契機をもたらすものであった。

《沈む声、紅い息》2010、ヴィデオ、5'55"
© Chikako Yamashiro, Courtesy of Yumiko Chiba Associates
2016/11/05(土)(高嶋慈)
フェスティバル/トーキョー16 「x / groove space」
会期:2016/11/03~2016/11/06
東京芸術劇場 シアターイースト[東京都]
客席と舞台の区別がまったくなく、観衆巻き込まれ型のパフォーマンスである。観衆の隙間を狙って動くダンサーは、都市の雑踏で普段われわれがやっていることの誇張のようにも思われた。後半は紙吹雪の乱舞から、みんなの掃除まで自ずと参加する流れになる。蛍光灯でノイズを出す伊東篤宏の音や、独特な舞台美術もよかった。
2016/11/05(土)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)