artscapeレビュー
2022年09月15日号のレビュー/プレビュー
Transfield Studio『Lines and Around Lines』
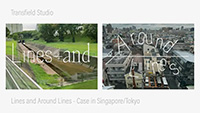
会期:2022/09/01~2022/09/04
元映画館[東京都]
私の足下にあるこの土地を規定しているものは何か。建築家の山川陸とパフォーミングアーツマネージャーの武田侑子によるユニットTransfield Studioの『Lines and Around Lines』(企画・構成:Transfield Studio[山川陸+武田侑子])は、「水の流れ」をキーワードに観客の土地への視線と想像力を更新する試みだ。パフォーマンスはレクチャーパフォーマンスとツアーパフォーマンスの二部構成。観客は会場となった元映画館でシンガポールの水の流れに取材したレクチャーパフォーマンスを鑑賞した後、簡易な地図とそこに付されたQRコードからアクセスできるオーディオガイドを頼りに隅田川へと向かうツアーパフォーマンスに旅立つことになる。
 [写真:金田幸三]
[写真:金田幸三]
 [写真:金田幸三]
[写真:金田幸三]
ところで、なぜシンガポールなのだろうか。実はTransfield Studioはシンガポールの劇場Esplanadeが主催するレジデンスプログラムContemporary Performing Arts Research Residencyの参加アーティストとして2022年の4月から6月までシンガポールに滞在しており、『Lines and Around Lines』はそのときのリサーチをもとにした作品となっている。公演期間中には関連イベントとしてシンガポールでの滞在制作の報告会も実施され、滞在制作の様子とシンガポールのパフォーミング・アーツ事情を知ることのできる貴重な機会となった。なぜシンガポールなのか、という問いに対するひとまずの答えは、たまたまTransfield Studioがそこに滞在する機会があったから、という身も蓋もないものになるだろう。
Transfield Studioはこれまでもフェスティバル/トーキョー19公式プログラムの『Sand (a)isles(サンド・アイル)』では池袋を、豊岡演劇祭2020フリンジに参加した『三度、参る』では豊岡を舞台に、その場所に関するリサーチからツアーパフォーマンスを立ち上げることを試みてきた(いずれも発表時は別名義)。そもそも特定の場所を歩くことが作品の根幹をなすツアーパフォーマンスにおいて、その場所に関するリサーチから創作が出発することはあまりにも当然のことであるようにも思えるが、しかしここにはある種の二重性がある。ツアーパフォーマンスはまず創り手がそこを歩き、次に観客が歩くことで成立するものだからだ。ならばそこにはズレを導入することもできるはずだ。未知の土地を訪れた者は、無意識のうちに自分の知る土地とその場所とを比較し、そこにある共通点と差異からその土地のありようを測るだろう。『Lines and Around Lines』は日暮里/荒川エリアを歩く観客に、シンガポールを歩いたTransfield Studioの視点をインストールする。
 [写真:金田幸三]
[写真:金田幸三]
 [写真:金田幸三]
[写真:金田幸三]
前半のレクチャーパフォーマンスではスクリーンに映し出される画像や映像に山川の声が重なり、シンガポールにおける水の流れを追っていく。やがて明らかになってくるのは、水資源の貴重なシンガポールにおいては、その流れのあり方こそがある面において国を「定義」しているということだ。山川の語りのなかに繰り返し登場する「定義」という言葉。シンガポールでは湾の出口は水門で塞がれ、そこはreservoir=貯水池として定義される。湾を堰き止めた水門はそのまま、国の輪郭を定める線の一部となるだろう。山川はスクリーンの手前に置かれたポールにロープを巻きつけていくことでその輪郭線を示す。線の内側、国土の9割はcatchment、雨水を集める場所と定義されているのだという。そして水が流れるための傾きの存在。 レクチャーパフォーマンスを聴き終えた観客は会場を出て、方位磁針を手に隅田川を目指す。地図には目的地である隅田川へと真っ直ぐに伸びるラインと、それと交差するJR常磐線、明治通り、都電荒川線、そして隅田川の4つのライン。その交差地点につく度に再生を促されるオーディオガイドは、ときおりシンガポールについての語りとも響き合いながら、東京という土地の来し方とそこに流れる水へと観客の意識を向かわせる。
 [写真:金田幸三]
[写真:金田幸三]
ところで、今回のツアーパフォーマンスに詳細なルートの設定はない。あるのは隅田川という目的地と北北東という大まかな方向だけ。レクチャーパフォーマンスを終え、おおよそ同時に街へと出た観客は、最初のうちこそ同じようなルートを辿るものの、住宅地の入り組んだ路地を進むうち、徐々に異なるルートへとバラけていく。それでも時おり、曲がり角を曲がった先にほかの観客の背中が見え、同じ方向へと向かっていることが確認されるのだった。複数の流れはときに合流し、ときに分かれ、そしていずれにせよ川へと至る。観客の歩みは水の流れと重なり合う。自らの身体をもって、目には見えぬ東京の水の流れを体感すること──。
 [写真:金田幸三]
[写真:金田幸三]
Transfield Studio:https://www.transfieldstudio.com/
関連レビュー
JK・アニコチェ×山川 陸『Sand (a)isles(サンド・アイル)』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年03月15日号)
2022/09/02(金)(山﨑健太)
北島敬三「UNTITLED RECORDS」

会期:2022/08/26~2022/09/25
BankART Station[神奈川県]
北島敬三は2011年の東日本大震災をひとつの契機として、北海道から沖縄まで、日本各地の風景を一貫した視点で撮影するシリーズの制作を開始した。「UNTITLED RECORDS」と名付けられたそれらの写真群は、『日本カメラ』(2012-2013)での連載を経て、2014年から2021年にかけて、東京・新宿のphotographers’ galleryの個展で20回にわたって発表された。同作品で第41回土門拳賞を受賞。今回のBankART Stationでの展覧会では、そのなかから選んだ48点を、大判プリントで展示している。ほかに北島が1970年代以降に撮影してきたストリートスナップ写真の大型スライドショーも併催されており、圧巻というべき充実した内容の展示だった。
展覧会に合わせてBankART 1929から刊行された172点を収録した同名の写真集を含めて、北島のこのシリーズをあらためて概観して感じるのは、彼が日本の風景のあり方を主に建造物を通じて見つめ直そうとしていることである。当然ながら、風景は自然と人間の営みとが融合して形をとってくる。時間というファクターで見れば、自然の方が厚みと永続性を備えており、人間の営為は仮設的で移ろいやすい。特にそれが露呈してくるのは、東日本大震災のような災害後の風景で、2011年に集中して撮影された東北地方の太平洋沿岸部の写真に、そのことがくっきりとあらわれていた。だがそれだけではなく、北海道から沖縄までの「見過ごされがちな場所」「意味がくじけてしまうような場所」を丁寧かつ執拗に追い続けた本作には、まさに大規模な変動に直面している日本の風景のあり方を、「いま」というスパンで切り出しておくべきだという北島の強い意志が刻みつけられていると感じた。
なお本展は、今年3月に急逝したBankART 1929の元代表、池田修が最後に企画した3つの展覧会のうちのひとつだという。池田の遺志をしっかりと受け継いでいこうとするスタッフの意欲が、展示の隅々にまでみなぎっていた。
2022/09/04(日)(飯沢耕太郎)
中野成樹+フランケンズ『EP1(ゆめみたい)』

会期:2022/09/11, 23
個人的なことは政治的なことである。演劇の実践もまたその渦中にある。中野成樹+フランケンズ(以下ナカフラ)が「20年かけて『ハムレット』を最初から最後までゆっくりたどっていく企画」の第一弾『EP1(ゆめみたい)』(原作:シェイクスピア『ハムレット』より、作・演出:中野成樹)はそのことを正面から引き受けようとする試みだ。
前作『Part of it all』でナカフラは「現状のメンバー全員が、 ①日常生活を維持しながら無理なく参加できる ②あるいは、積極的に不参加できる」という二つの指針に基づき準備を行ない、結果として上演の場にメンバーの子供たちの姿があるような公演が実現することになった。20年かけて『ハムレット』を上演するという今回の企画はその延長線上にあり、より長いスパンで生活と演劇とを撚り合わせる試みだと言えるだろう。中野は今回の試みをEP=extended play(ing)と呼んでいる。演劇の時間が限りなく、とまでは言わずとも20年という長さにまで拡張されたとき、それと生活の時間との、あるいは人生との関係はどのようなものになるだろうか。
『EP1(ゆめみたい)』として上演されるのは原作『ハムレット』の1幕5場にあたるシーンまで。以下では各シーンの内容に触れていくが、今作は9月23日(金・祝)に2回目の上演が、10・11月にも同内容での上演が予定されているので注意されたい。気になる方はホームページで作品の冒頭部にあたるシーン1「今 半透明」の戯曲も公開されているのでそちらをチェックするのもいいだろう。今作では原作において重要なモチーフとなる亡霊を軸に、見えない(ことにされてきた)ものの存在や陰謀論など、『ハムレット』の今日性が引き出されていくことになる。

会場に入ると舞台(となるであろう空間)では公演関係者とその子供たち(と思われる人々)がおもちゃを広げて遊んでいる(ということは拡張されるのは演劇ではなく子供の遊びの方なのかもしれない)。やがておもちゃが一旦片づけられると前説(斎藤淳子、出演者と配役は回によって異なりここでは9月11日の回の配役を記す、以下同様)がはじまり、今回の公演では子供たちがいてその行動は予測不能であること、諸々の事情で公演に参加していないメンバーがいることなどが告げられる。「いなくてもいい人の出席」と「いなくちゃいけない人の欠席」という表現からしてすでにすこぶるハムレット的である。なにせ、いるかいないか(To be, or not to be)、それが問題(?)なのだから。

シーン1および1.5「だから半透明」は原作の1幕1場を踏襲し見張り同士の会話の場面。「例の亡霊」が出たか否かという会話も交わされるものの、バナードー(野島真里)はいまいち要領を得ない様子でフランシスコー(佐々木愛)との会話も噛み合わない。「オカルトは、政治と連んでろって」と言うホレイショー(石橋志保)に対し、マーセラス(森唯人)は陰謀論は「それほど嘘じゃない気がする」と亡霊=陰謀論説を持ち出したりもする。しかしようやく亡霊が登場するに至り、世界は反転する。亡霊と思われた人物が、あたかもバナードーたちこそが亡霊であるかのように「誰だ! 何のため、姿を見せた?」と誰何するのだ。「俺たちが、亡霊にされている……?」「不具合の原因にされている……!」と彼(女)たちは言うが、さて、見えていないものは、不具合の原因は真実のところ果たしてどちらにあるのだろうか。ここには再び生活と演劇の関係も重ねて見ておくべきだろう。そこでは何が見えておらず、不具合の原因は果たしてどちらにあるのか(それは本当に不具合か)。「見え(てい)ないもの」は『Part of it all』から引き継がれたテーマでもある。

シーン2はクローディアス(洪雄大)とガートルード(小泉まき)による記者会見の設え。官僚の不倫騒動など現実の出来事を下敷きにしたと思しき場面はコミカルにアイロニカルだが、ここは「個人的なことは政治的なことである」という言葉がその本来意味するところとは異なる、悪しきかたちで体現された場面でもある。かつて物語の主人公は王侯貴族であり、そこでは個人的なことはつねにすでに政治的なことであった。だが、現代の権力者たちは政治を私物化することによって「個人的なことは政治的なことである」を実現してしまっている。

続くシーン3「お正月」で描かれるボローニアス(中野)、レアティーズ(新藤みなみ)、オフィーリア(端田新菜)のやりとりもまた、家族の会話でありながら政治的なものであることからは逃れられない。そしてこの場面では子供たちが舞台に戻り、正月の親戚の集まりさながら舞台上でわいわいと遊んでもいる。切っても切れない政治と家との、そして演劇と生活との関係がそこで絡まり合っている。
再び見張りの場面を挟んで先代ハムレット王の亡霊(福田毅)とハムレット(竹田英司)の対話(だがそこに滲むのはごくごく個人的な感情のようだ)で『EP1(ゆめみたい)』は一旦終わる。しかし物語は閉じず、生活も続く。決してオールオッケーではない、ひとまずのplayの区切り。
中野成樹+フランケンズ:http://frankens.net/
関連レビュー
中野成樹+フランケンズ『Part of it all』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年09月15日号)
2022/09/11(日)(山﨑健太)
カタログ&ブックス | 2022年9月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
性と芸術

著:会田誠
発行:幻冬舎
発行日:2022年7月21日
サイズ:20cm、212ページ
日本を代表する現代美術家会田誠の23歳の作品「犬」は、2012年の森美術館展覧会での撤去抗議はじめ、これまでさまざまに波紋を呼んできた。その存在の理由を自らの言葉で率直に綴る。人間と表現をめぐる真摯な問い。
ゲルハルト・リヒター 絵画の未来へ (現代美術スタディーズ)

著:池田修
発行:水声社
発行日:2022年8月10日
サイズ:A5判、164ページ
「絵画の終焉」がささやかれて久しい現代においてなお、絵画を描きつづけること。写真を描きうつす〈フォト・ペインティング〉から、デジタルイメージをもちいた近作〈ストリップ〉まで、多岐にわたる作品を横断し、リヒターの制作理念を明らかにする。
石が書く

著:ロジェ・カイヨワ
訳:菅谷暁
発行:創元社
発行日:2022年8月24日
サイズ:B5判変型、136ページ
風景石、瑪瑙、セプタリア(亀甲石)など、特異な模様をもつ石。それらは人の想像力にどう働きかけてきたのか。石の断面の模様と、抽象芸術作品が交わる地点はあるのか。聖なるもの、遊び、神話、詩学、夢といったテーマを縦横に論じてきたカイヨワが、自らの石コレクションをもとに、「石の美は、普遍的な美の存在を示している」と論じた、他に例を見ない論考。1975年に新潮社から翻訳が刊行されながら、長らく日本語では入手困難であった美しい名著を、新たな翻訳で刊行。
ドイツ演劇パースペクティヴ

著:寺尾格
発行:彩流社
発行日:2022年9月9日
サイズ:四六判、415ページ
「現代」とは、近代との区別における「いま・ここ」の視点の強調である。1945年、1968年、1989年の区切りを経て、ニューヨークで起きた9.11に3.11の東日本大震災。収束をみないコロナパンデミック。相互に関連する「ポスト(~以後)」を第二次世界大戦からフクシマを視野に、ドイツ語圏の現代演劇が日本において持つ「意味」を考える。
日本の中のマネ 出会い、120年のイメージ

企画・監修:小野寛子
発行:平凡社
発行日:2022年9月12日
サイズ:B5判、216ページ
19世紀フランスを代表する画家エドゥアール・マネの日本における受容について、洋画黎明期から現代の美術家たちが手掛けた作品や美術批評を通して考察する。
ル・コルビュジエ (講談社学術文庫)

編:八束はじめ
発行:講談社
発行日:2022年9月12日
サイズ:A6判、224ページ
20世紀を代表する、最も有名な前衛建築家、ル・コルビュジエ(1887-1965)。 「全ての建築家にとっての強迫観念(オブセッション)」「近代建築の言語そのもの」……。 スイスの若き時計工芸家は、なぜこれほどまでの世界的名声を勝ち得たのか。 師との出会いと決別、数多のコンペティション落選や学界との論争、生涯転身し続けた作風の背景――。 建築界の巨匠を“人文主義者”という視点で捉え直し、豊富な図版と共に、その全体像をクリアに描き出す!
クィア・アートの世界 自由な性で描く美術史

著:海野弘
発行:パイインターナショナル
発行日:2022年9月14日
サイズ:B5判変型、480ページ
すべてのアートは自由でクィア(ちょっと変わった、不思議)だ!これまで語られてこなかった、新しく〈クィア〉な美術の世界。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
2022/09/14(水)(artscape編集部)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)