artscapeレビュー
2020年12月15日号のレビュー/プレビュー
ときたま写真展「たね」

会期:2020/11/19~2020/11/29
コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]
ときたま(1954年、東京生まれ)は、これまで葉書に「コトバ」を印刷して不特定多数に送る「ときのコトバ」、ドローイングした「プラ板」で立体作品を作る「ぷらたま」、トートバッグに「コトバ」の1文字をドローイングした「ことバッグ」といった、日常の事物を介したコミュニケーションをテーマとするアート活動を展開してきた。2016年に携帯電話をiPhoneに変えたことをきっかけとして、日々写真を撮影し始める。それら数万点に及ぶスナップ写真から約5000枚をポストカード大にプリントし、そこから391点を選んで写真集『たね』(トキヲ)を刊行した。今回のコミュニケーションギャラリーふげん社での展覧会は、そのお披露目を兼ねた企画である。
「ときのコトバ」や「ぷらたま」と同様に、写真でも彼女の基本的な姿勢に変わりはない。日々の出来事を、全方位型のアンテナで捕捉して定着させ、短い断片を撒き散らすように提示していく。「日々は、いつもと面白いとたまたまの「たね」でできている」という認識、それらを再編集し、新たな世界を構築していく歓びが、写真集からも写真展示からもいきいきと伝わってきた。「たね」の写真群には「コロナの日々」に撮影されたものも含まれている。本来は今年6月頃に写真集を出版する予定で、写真選びやレイアウトも終わっていたが、「そのままだとコロナ以前の写真集になってしまう」ということで、急遽予定を変え、自粛期間中に撮影した写真も加えた。そのことで、日常と非日常とが交錯した2020年現在の東京のあり方が、よりヴィヴィッドに浮かび上がってきた。
ときたまの写真行為は、「スマホとSNSの時代」における写真表現のひとつの方向性を示しているのではないかと思う。インスタグラムやフェイスブックでは、垂れ流されるだけで拡散してしまいがちな写真群を、写真集や写真展のような長年の蓄積のある媒体を使って再組織化し、ソリッドな形式に落とし込んで観客に伝達していく。そこに思いがけない新たな可能性が生まれてきそうだ。
2020/11/20(金)(飯沢耕太郎)
小平雅尋『同じ時間に同じ場所で度々彼を見かけた/I OFTEN SAW HIM AT THE SAME TIME IN THE SAME PLACE』
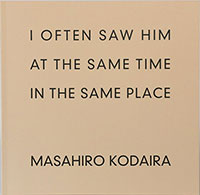
発行所:シンメトリー
発行日:2020/10/19
とても奇妙な、複雑かつ微妙な味わいを残す写真集である。場所はどうやら東京・六本木のようだ。いつもきっかり同時刻に、交差点を小走りに渡っていく若者がいる。やや小太りの体型、大抵チェック柄のシャツを身につけ、チノパンを穿いている。小平雅尋は彼の姿を目に止め、おそらく何気なくシャッターを切った。そのうちに、彼が必ず同時刻に現われることに気がつき、意識的にその後ろ姿を撮影するようになった。写真集にはそうやって撮り溜められた、2019年2月23日から2020年3月5日までの約1年間の写真、56枚が淡々とレイアウトされて並んでいる。
小平は、彼が何者であり、何を目的として、どこに行こうとしているのか、という謎解きをしようとしているわけではない。そのことは、やや距離を置いて後ろ姿だけを写した写真を選んで、顔のような彼の特定に繋がる部位を注意深く避けていることからもわかる。とはいえ、56枚の写真を見ているうちに、この男が写真家にとって、また写真を見るわれわれにとっても、何かしら特別な意味を持つ存在として、じわじわと浮上してくるように感じる。どこかしら、フランツ・カフカの短編小説を読む時のような、細部は明晰であるにもかかわらず、全体としてみるとあやふやで不条理な世界に誘い込まれるような気分になってくるのだ。
小平雅尋はこれまで、写真集『ローレンツ氏の蝶』(シンメトリー、2011)や写真展「他なるもの」(タカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルム、2015)などで、写真表現の本質的な要素を、抽象度の高いモノクローム写真で追求していくような作品を発表してきた。一転して本作では、曖昧な日常に潜む陥穽を明るみに出すような作品にシフトしている。とても興味深い作風が生まれつつある。
2020/11/21(土)(飯沢耕太郎)
石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか

会期:2020/11/14~2021/02/14
東京都現代美術館[東京都]
1966年に発表された資生堂ビューティケイクのサマーキャンペーン・ポスターは、広告業界で長く語り継がれている名作である。「太陽に愛されよう」というキャッチコピーと、ハワイの海辺で撮影された澄んだ青空ときらめく砂浜、そして強い日差しを全身に浴びた健康的な女性が、しっかりとした目力で前を見据える姿は、いつ見ても強いインパクトを残す。これこそ石岡瑛子が世に注目されるきっかけとなった作品であり、また彼女のクリエーティブを物語るうえでの原点とも言える。この健康的で強い女性像は、きっと彼女自身でもあるのだ。そもそも資生堂は、創業者の福原信三が化粧品にも美的価値の必要性を感じて意匠部を設立し、欧州を中心に流行していたアール・ヌーヴォーとアール・デコ様式を積極的に取り入れ、独自の「美」のスタイルを築いてきた企業である。石岡にとって、その伝統さえも時代遅れに感じたのだろう。伝統は革新の連続であるように、以後、資生堂は時代の空気を積極的に取り込んでいくことで、業界ナンバーワンに躍り出る。
 「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020[Photo: Kenji Morita]
「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020[Photo: Kenji Morita]
 「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020[Photo: Kenji Morita]
「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020[Photo: Kenji Morita]
本展を観て、とにかく石岡のパワーに圧倒された。エントランスに使われたキーカラー、赤のせいもあるかもしれない。資生堂のような大手企業のインハウスデザイナーからスタートし、独立してアートディレクターとして活躍するというのは、言わばグラフィックデザイナーのキャリアの王道であるが、石岡はそこに留まらず、さらに活躍の場を海外に広げた点が圧巻である。しかも演劇、オペラ、映画、コンサート、サーカスなど、エンターテインメント分野までも活動の舞台にしていった点が破格だ。そんなデザイナーは後にも先にも石岡をおいてほかにいないのではないか。なぜならグラフィックと、衣装や舞台はあまりにも違うからだ。彼女の頭のなかはいったいどうなっているんだろう。そんな私の狭い了見に対して軽やかに答えるように、本展のボードには「私は衣装をやっているのではなく、視覚言語をつくっているのだ。」と掲げられていた。なるほど、石岡にすれば、どれもデザインという共通言語でつながっているのか。ところで、観覧中、石岡がデザインについて語るインタビュー音声が会場中に響き渡っており、なんだか彼女に説教を受けているような気分にもなった。
 「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020[Photo: Kenji Morita]
「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020[Photo: Kenji Morita]
公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/eiko-ishioka/
2020/11/21(土)(杉江あこ)
私の選んだ一品[暮らしのピント]2020年度グッドデザイン賞審査委員セレクション

会期:2020/11/02~2020/11/30
日本で規模がもっとも大きいデザイン賞と言えば、グッドデザイン賞である。毎年、国内外から来るその応募数は数千件に及び、募集、一次審査、二次審査、受賞発表といった運営が1年にわたって行なわれる。当然、審査委員の数も相当数必要で、現在、94人が務めているという。しかもその顔ぶれは、研究者やジャーナリスト、企業経営者が一部いるが、第一線で活躍する中堅の種々デザイナーや建築家が多くを占める。見方を変えれば、グッドデザイン賞の審査委員になったことで、彼らは若手から中堅への仲間入りを果たしたとも言える。そんな風に思えるのは、本展を観て、審査委員のなかによく見知ったデザイナーがずいぶん増えたと感じたからだった。
さて、本展は審査委員が主人公の展覧会である。彼らのうち日本在住の84人に、二次審査の会場で個人的に気になった、もしくは気に入ったデザインをひとつずつ選んでもらうという企画だ。そこで選ばれた全69点が彼ら一人ひとりのコメント付きで展示されていた。コメントを読むと、何というか審査委員のキャラクターや人間臭さがにじみ出ていて、予想以上に面白かった。なぜなら彼らは審査委員という立場ではなく、このときばかりは生活者の立場でコメントしていたからだ。もちろんデザインの知見を入れながらのコメントも多いのだが。幼い頃の思い出がよみがえったもの、自分が率直に欲しいと思ったもの、実際に家で使っているもの、ありそうでなかった視点、趣味のものなど、いずれのコメントにも実感がこもっていた。
 展示風景 GOOD DESIGN Marunouchi
展示風景 GOOD DESIGN Marunouchi
デザイナーも建築家も、専門家である前に、まず生活者であることを忘れてはならないと思う。デザインとは社会や人の営みを良くするものであるため、実は自身の経験が大いに物を言う世界でもある。生活のなかでの気づきが新たなデザインを生むきっかけになることも多い。ちなみに展示品のなかで私が欲しいと思ったものは、「猫様専用首輪型デバイス&アプリ」である。我が飼い猫にこれを試してみたい。いま、本気で買うか買わないかを悩んでいる。
 展示風景 GOOD DESIGN Marunouchi
展示風景 GOOD DESIGN Marunouchi
公式サイト:https://www.jidp.or.jp/ja/2020/10/25/202010014
2020/11/21(土)(杉江あこ)
DEPTH DESIGN 1st EXHIBITION

会期:2020/11/19~2020/11/26
TIERS GALLERY[東京都]
印刷物をルーペで初めて覗き見たときの驚きをいまでも忘れられない。すべてが小さなドットで構成された世界がそこにはあった。特色を除く、通常のカラーはCMYKの4色で印刷されることを頭ではわかっていたにもかかわらず、実際に見る網点には何とも言えない迫力があった。本展を観て、そんな出来事をふと思い出した。本展を企画したDEPTH DESIGN(デプスデザイン)は、親会社のトヨコーと組み、壁面塗装によるパブリックアートの表現方法を研究している会社である。その代表取締役社長兼アートディレクターを務めるのが、デザイナーの清水慶太だ。設立されて間もない同社が、世間へのお披露目と同時に、パブリックアートの可能性を問うため展覧会を開いた。最初に観た作品「GRAY」はまさにCMYKの4色の原理を用いた実験作で、紙にインクではなく、壁にペンキで施されていた。実際に親会社の東京オフィスの内壁に用いられたそうで、遠目で見ると、4色のドットはグレーに映る。
 展示風景 TIERS GALLERY
展示風景 TIERS GALLERY
一般的にパブリックアートというと、巨匠アーティストによる、大衆の目を引く奇抜な作品というイメージが強い。それはそれで街や公園などにパワーをもたらし、また観光名物となることも多い。しかしDEPTH DESIGNの考えはむしろランドスケープデザインの延長上にあるようだ。公共空間を主に壁面塗装を用いていかに良いものへと変えられるかを模索する。「壁と景色」と題した作品では、街の景色は壁面の群によって印象づけられることを実証するため、立体模型を使い、街並みの一部を再現。これらの壁面に物語性のある色やパターン(濃霧や波、木々、アーチ)をプロジェクションマッピングで施し、街の景色がどのように変化するのかを実験していた。こうして見ると、壁面が街に与える影響の大きさに改めて気づく。
 展示風景 TIERS GALLERY
展示風景 TIERS GALLERY
一方で街の景観を損ね、治安悪化のイメージを与えるとされる壁面の落書き(グラフィティー)にも注目。主に文字表現が多いグラフィティーは、描き手からの何らかのメッセージではないかと肯定的に受け止め、グラフィティーを立体作品に転化する試みを行なった。これがベンチとして使用可能な立体作品に生まれ変わると、不思議と印象が変わる。たとえ街に置かれても、治安悪化のイメージにはあまりつながらないだろう。公共空間のあり方を考えるには、ミクロとマクロの両方の視点が大事になる。本展ではこの視点を生かした、柔軟な発想に基づく作品が観られた。
 展示風景 TIERS GALLERY
展示風景 TIERS GALLERY
公式サイト:https://depthdesign.co.jp/
2020/11/21(土)(杉江あこ)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)