artscapeレビュー
2020年12月15日号のレビュー/プレビュー
許紀霖『普遍的価値を求める──中国現代思想の新潮流』

監訳:中島隆博、 王前
翻訳:及川淳子、徐行、藤井嘉章
発行所:法政大学出版局
発行日:2020/08/20
中国における「現代思想」について、日本語で知りうることはいまだ多いとは言えない。思想史的なアプローチをとったものとしては、本書の監訳者である王前の『中国が読んだ現代思想──サルトルからデリダ、シュミット、ロールズまで』(講談社、2011)という好著があるが、その地理的な範囲の広さも災いしてか、今日の中国における現代思想の勘どころを伝えてくれる学術書が、日本であまり見られないのは残念なことである。
本書は、現代中国を代表する知識人のひとりである許紀霖(1957-)がみずから選定した論文をもとに編まれた、日本語では初の単著である。巻末の出典を見てもわかるように、本書所収の論文が発表されたのはおおむねここ10年ほどのことであり、なおかつ論争的な性格をもつものが多くを占める。現代中国における思想状況を概観するための足がかりとして──とりわけ、評者のような門外漢にとっては──格好の一書である。
著者の中心的な関心事は政治思想にある。より具体的には、今日の世界的な状況のなかで、東アジアの新たな国際秩序をいかに構想するかということに、著者の関心は注がれている。東西のさまざまな思想を理論的フレームとして用いつつ、中国および東アジアの現状を見つめる著者の視線は、日本にいるわれわれのそれとも大いに重なり合うものであろう。
本書の中核をなすのは「新天下主義」という思想である。これは、古代中国における「天下」の概念をもとに、東アジアにおける「新しい普遍」を構想すべく生み出されたものである。著者によれば、この言葉にはさまざまな批判が寄せられており、「歴史上の中華を中心とするヒエラルキーの帝国が捲土重来してくる」のではないか、と懸念を抱く人もいるという(v頁)。ある意味ではそれも当然だろう。しかし、著者があえて「天下主義」という中華的な概念を持ち出してくるのは、西洋由来の「普遍主義」とは異なる、もうひとつの普遍主義を構想するためにほかならない。ここでいう「新」天下主義という表現にはむしろ、かつての天下主義の「脱中心化と脱ヒエラルキー化」を目指すという意味が賭けられているのであり、それをもとに著者は、ヨーロッパにおけるEUに相当するような共同体を東アジアにおいて構想することは可能だろうか、とわれわれに問いかける。
いわゆる普遍主義は、多元主義(多文化主義、文化相対主義)の尊重へとむかった20世紀後半の思潮のなかで、長らく旗色の悪い思想であった。しかし今日ではむしろ、狭隘なナショナリズムに対するカウンターとして機能しうるような、新たな普遍主義が必要とされている。許紀霖の議論が興味深いのは、「普遍」という概念にそもそも複数のかたちがありうるということを、ウィトゲンシュタインの「家族的類似」などに依拠しながら論じるところにある。おそらく本欄の読者にとっても、東アジアの「隣人」たる同時代の知識人が、いま何を考えているのかということは大きな関心事であるだろう。柄谷行人、汪暉、白永瑞らとの思想的対話のなかで練り上げられた本書の議論は、国家や言語の枠組みを越えた、東アジアの現代思想の一面を照らし出すものである。
2020/12/03(木)(星野太)
小林康夫『《人間》への過激な問いかけ──煉獄のフランス現代哲学(上)』

発行所:水声社
発行日:2020/09/30
長年にわたり、フランスの思想や文化と密接な関わりを持ちつづけてきた著者が、20世紀後半のフランス哲学を「人間」へのラディカルな問いとして総括した書物。その上巻にあたる本書では、おもにバルト、フーコー、リオタールの三者について過去に発表された時評的な文章が集められている。
本書は三部からなるが、第I部「フランス現代哲学の星雲」が、本書全体の導入にあたる。そこには、著者が80年代以降に著した数本の概説的なテクストが配されているのだが、それら「《人間》の哲学」や「《ポスト・モダン》の選択」──ともに初出は1987年──こそが、本書のトーンを決定していると言っても過言ではない。本書の表題に含まれる「人間」という言葉が重要な意味を担うのも、まずはそこにおいてである。
著者によれば、20世紀後半のフランス哲学をあえてひとつの言葉によって特徴づけるなら、それは最終的に「人間」という言葉へと帰着する。これは、いささか驚くべきテーゼだろう。というのも、ひじょうに大まかに言って、実存主義のあとに台頭した構造主義──およびポスト構造主義──には、むしろ既成の意味での「人間」を後景に追いやることによって展開してきたというイメージがあるからだ。「構造」にせよ「記号」にせよ「テクスト」にせよ、そこで探求されていたのは個々の主体に回収されることのない非人称的な次元であり、その意味で「人間」は世界の中心からの退位を余儀なくされていたとも言える。
しかし著者は、グザヴィエ・ティリエット(1921-2018)がメルロ=ポンティに捧げた「人間の尺度(la mesure de l’homme)」という表現に合図を送りつつ、そこで問われていたのは、あくまで「人間」をめぐる問いにほかならなかったと指摘する。なるほど、かつて「構造」や「記号」や「テクスト」といった合言葉のもとでなされてきた探求は、「人間」からその明証性を剥奪する営みと地続きであったと言ってよい。しかし同時にそれは、「現に生き呼吸している具体的な人間の尺度」をけっして忘れることがなかったし、超越的なものの探求においてなお「具体的な人間に注がれる眼差し」を手放すことがなかった(29頁)。本書のひとつの読みどころは、いまだフランス現代哲学が導入・紹介される途上にあった1980年代に、すでにそうしたことを指摘している著者の慧眼にある。
第I部と同じく、第II部(バルト、フーコー)、第III部(リオタール)も、著者の旧稿を新たに構成しなおしたものが大部分を占める。そのため著者の世代の仕事を追ってきた者にとって、そこにさほどの新しさは感じられないかもしれない。だが、70、78年の二度のフーコー来日に立ち会った著者の回想、さらにフランスおよび日本で行なわれたリオタールとの濃密な対話をはじめとして、ここには彼らのいまだ知られざる表情がある。そして、これまで単行本に未収録であったこれら数々のテクストから見えてくるのは、半世紀にわたりフランス哲学の「隣人」でありつづけてきた著者の「冒険」の軌跡である。あるいは本書の表現に拠るなら(8頁)、ここに読まれるのは、フランス現代哲学という星雲の「客観的なマップ」などではなく、むしろひとつの「内部観測」にほかならない。その意味で本書は、著者が言うところの「パッションに貫かれた《人間》」(29頁)が示しうる、ひとつのモデルでもあろう。
2020/12/03(木)(星野太)
カタログ&ブックス | 2020年12月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をartscape編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
キュレーターズノート 二〇〇七ー二〇二〇

著者:鷲田めるろ
発行:美学出版
発行日:2020年12月10日
定価:1,800円(税抜)
サイズ:190×130mm、230ページ
※artscapeでの連載「キュレーターズノート」の鷲田めるろさんの原稿が一冊になった書籍です。
美術、美術館、展覧会、プロジェクト、ワークショップ、地域、美術教育、まちづくり、芸術祭、アイデンティティ、町家、NPO、都市とアート……さまざまな可能性を持つ人や場と共創し、新たなアートの生成に立ち会う、キュレーターの実践と思考のノート。著者初の単著。
TIMELESS 石岡瑛子とその時代

著者:河尻亨一
発行:朝日新聞出版
発行日:2020年11月20日
定価:2,800円(税抜)
サイズ:20cm、541+32ページ
伝説のデザイナーがいた。前田美波里をスターにした資生堂のポスター、大ブームになったパルコの広告。それらを手がけた後に渡米し、アカデミー賞に輝いた彼女は、変化の時代をいかにサバイブしたのか。スティーブ・ジョブズも崇拝したエイコの「私」に迫る評伝。
国際文化交流を実践する

編集:国際交流基金
発行:白水社
発行日:2020年11月27日
定価:2,100円(税抜)
サイズ:19cm、262ページ
コロナ禍や一国主義の台頭で揺らぐ国際協調をいかに守るか? 心と心の触れ合いに懸けたJF職員たちの渾身のルポルタージュ!
美術/中間子 小池一子の現場
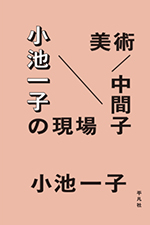
著者:小池一子
発行:平凡社
発行日:2020年12月11日
定価:3,000円(税抜)
サイズ:21cm、255ページ
日本のクリエイティブを草創期からつくり続けてきた小池一子。その多彩な仕事と歩みを豊富なビジュアルとともに通覧する一冊。
「宮島達男 クロニクル 1995-2020」展覧会図録

編集:千葉市美術館
翻訳:パメラ・ミキ
デザイン:近藤一弥
発行:千葉市美術館
発行日:2020年12月4日
定価:2,500円(税抜)
サイズ:B5判、216ページ
2020年9月19日〜12月13日まで開催されている「宮島達男 クロニクル 1995-2020」展の公式図録。
宮島達男は、LED(発光ダイオード)のデジタル・カウンターを使用した作品で高く評価され、世界で活躍する現代美術作家です。1980年代より宮島は、「それは変化し続ける」「それはあらゆるものと関係を結ぶ」「それは永遠に続く」という3つのコンセプトに基づき、これまで30ヵ国250ヶ所以上で作品を発表してきました。作品のモチーフであるデジタル数字は命の輝きをあらわし、0が表示されず1から9の変化を永遠に繰り返すことで、人間にとって普遍的な問題である「生」と「死」の循環を、見る者に想像させます。
本展は千葉市美術館の開館25周年記念として、首都圏の美術館では12年ぶりに開催される大規模な個展です。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
2020/12/15(火)(artscape編集部)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)