artscapeレビュー
2022年07月15日号のレビュー/プレビュー
ゲルハルト・リヒター展

会期:2022/06/07~2022/10/02
東京国立近代美術館[東京都]
ゲルハルト・リヒターの日本における最初の本格的な回顧展というべき本展を見て、あらためて彼の作品における写真の役割について考えさせられた。いうまでもなく、リヒターはその画家としての経歴の始まりの時期から、写真を単なる素材としてではなく、作品制作のプロセスにおける最も重要な媒体のひとつとして扱ってきた。ごく早い時期の作品である《机》(1962)が、雑誌『DOMUS』に掲載された写真図版を油彩で描き写した「フォト・ペインティング」であったことは示唆的といえる。
「フォト・ペインティング」だけではない。「アトラス」シリーズは彼が蒐集した新聞・雑誌の切り抜き、自らの家族写真など、膨大な量の写真画像を複数のパネルに貼り付けた大作だし、自作のカラー写真の上に油彩で抽象的なパターンを描いた「オイル・オン・フォト」シリーズもある。本展の白眉といえる《ビルケナウ》(2014)の連作のように、写真を元にして描いた絵を塗り潰して抽象化し、さらに写真で撮影するという、写真→絵画→写真というプロセスを取り入れることもある。今回は出品されていなかったが、2009年に刊行された『Wald(森)』は純粋な写真作品といえるだろう。
こうしてみると、リヒターは写真と絵画とを、その表現媒体としての違いを意図的に無視して使っているように思えてくる。そのあからさまな「混同」によって、写真、あるいは絵画の領域を踏み越え、逸脱するようなフィールドが姿を現わす。というよりも、彼の作品世界においては、写真も、絵画も、鏡やガラスのような媒体も、あるいは彫刻やパフォーマンスも、すべては視覚的世界の総体的な探求という目的に向けて再組織されているというべきだろう。あらゆる分類を無化してしまうような、未知(未完)のアーティストとしてのゲルハルト・リヒターの凄みが、今回展示された110点余りの作品からも充分に伝わってきた。
2022/07/01(金)(飯沢耕太郎)
撮影された岡山の人と風景──県内作家の近作とともに

会期:2022/06/03~2022/07/10
岡山県立美術館[岡山県]
仕事で出かけていた岡山の岡山県立美術館で、興味深い展示を見ることができた。EU・ジャパンフェスト日本委員会が1999年から実施している写真プロジェクト「日本に向けられたヨーロッパ人の眼/ジャパン トゥデイ」の一環として、2001年にオランダのハンス・ファン・デル・メールとベルギーのアン・ダームスの二人が招聘され、岡山県内を撮影した。今回は、同美術館主催の「岡山の美術 特別展示」の枠で、その二人の作品の20年ぶりの展示が実現した。あわせて、同県在住の写真家たち、柴田れいこ、小林正秀、杉浦慶侘、下道基行の写真作品も展示されている。そのうち、小林、杉浦、下道は、県内の若手写真家に授与されるI氏賞の受賞作家である。
ファン・デル・メールは都市や農村の環境に対応した1人の人物を選び出し、建造物の中央部に立たせて撮影する。ダームスは日常の断片を思いがけない角度から切りとったスナップ写真を制作した。これらオランダとベルギーの写真家たちの、いわば異文化に向けられた眼差しのあり方に対置するように、日本人写真家たちはそれぞれゆかりのある人、場所にカメラを向けている。柴田は戦没者の妻と日本人と結婚した外国人の女性のポートレートを、彼らへの聞き書きの一部とともに展示した。小林は在住する美作地方の風物を、端正な黒白写真にまとめあげる。杉浦は深みのある森の写真とオブジェによるインスタレーション、下道は東日本大震災以後に撮影した、小さな仮設の橋の写真を集成したポートフォリオ・ブックを出品していた。
彼らの写真の方向性はバラバラだが、逆に多元的な視線の絡み合いによって、岡山という土地のあり方が複層的に浮かび上がってくる。ほかの県でも、「日本に向けられたヨーロッパ人の眼/ジャパン トゥデイ」の作品を活用して、同じような企画が考えられるのではないだろうか。
2022/07/03(日)(飯沢耕太郎)
範宙遊泳『ディグ・ディグ・フレイミング!〜私はロボットではありません〜』

会期:2022/06/25~2022/07/03
東京芸術劇場シアターイースト[東京都]
『バナナの花は食べられる』で第66回岸田國士戯曲賞を受賞した範宙遊泳/山本卓卓の新作『ディグ・ディグ・フレイミング!〜私はロボットではありません〜』が7月15日(金)18:00から8月14日(日)23:59までオンデマンド配信されている。
炎上を意味する「フレイミング」をタイトルに掲げた本作は、インフルエンサー集団「MenBose−男坊主−」のメンバーである藤壺インセクト(埜本幸良)、キング塚村(小濱昭博)、根津バッハロー根津(福原冠)、そしてエキセントリック与太郎(百瀬朔)が謝罪の準備をしているところからはじまる。いや、正確には、謝罪の準備をしていてふと、何を謝らなければならないのかがわからないということに気づくところからはじまる。謝らなければならないのは与太郎が飼っていたスズメが死んでしまい、それを焼き鳥にして食べてしまったことか。動画のネタで「商店街の看板いくつ蹴って倒せるか大会」を開催したことか。あるいはホームレス美大生のアラレ・ビヨンド(李そじん)をゲストに迎えた企画をバラエティ調に撮ってしまったことか。過去の出来事を舞台上に召喚しながら検証は進むが、どれもこれも違っているようで謝らなければならない理由はなかなか見つからない。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
すると突然「オデのせいだ」と言い出す与太郎。どうやら与太郎には「文字が聞こえる」らしく、その文字は与太郎を責め立て「命をもって謝れ」とまで言っているらしい。「心ない声なんて全部ゴミ」と言い放つアラレに対しディスプレイに映し出される文字は「文字の奥に心がある!」と反論し、二人は「心があるならこんなにひとりの人間を追い詰めない。あなたは人間じゃない」「私は人間だ!!!!!」と激しくやり合う。そしてMenBoseのメンバーは炎上する画面の向こう側から文字の本体を引きずり出すが、そこにあったのはかつて企画でコラボしたインフルエンサー・ロクちゃん(亀上空花)のママ(村岡希美)の姿だった。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
さて、この物語は一体どこに向かうのだろうか。謝らなければならない理由、つまりは「罪」を探し求めることがこの物語を推進するが、ようやく辿り着いたかのように思われた罪もまた、探していたそれではない。ママはMenBoseとの収録の際に起きた出来事がきっかけでロクちゃんが部屋から出てこなくなってしまったと思っているが、そもそもママとMenBoseとでは「起きた出来事」に対する認識が大幅に食い違っている。部屋を訪れ、引きこもりの理由を直接ロクちゃんに尋ねたママとMenBoseは結局、MenBoseには非がなかったことを知るのであった。だがそれでも文字による糾弾は止まらない。それどころかその苛烈さは増し、やがて画面の向こうから「死」が現われ、オレンジ色の浮き輪のようなオブジェとして登場するその巨大な文字にメンバーは捕らわれていく。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
ある時期以降の範宙遊泳は、プロジェクターで舞台上に文字を投影する演出を取り入れ、その文字をときに登場人物のようにも扱ってきた。『ディグ・ディグ・フレイミング!』もその延長線上にあることは確かだが、決定的に異なっているのは、この作品においては文字が単にディスプレイに映し出される文字として扱われているということだろう。範宙遊泳/山本の視線は文字の向こうにいる人間に向けられている。MenBoseはしょうもなくモラルも低い集団かもしれないが、ディスプレイに映る文字の向こうにいる人間を相手にしようとする点においては誠実だ。与太郎が看板を蹴ってしまったスナックで一日バーテンをやってみたらそこのママに気に入られてしまったように、顔を突き合わせることでよい方向に向かうこともあるだろう。匿名の文字を相手にした格闘はほとんど何も生み出さない。そういえば、『バナナの花は食べられる』もまた、マッチングアプリの客とサクラとして画面越しに出会った二人の男がリアルで顔を合わせるところから物語が動き出すのだった。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
スタート地点が間違っているのだから「罪」の追及がどこにも行きつかないのは必然だ。物語はほとんど消化不良のまま唐突な幕切れを迎える。文字によって犯罪歴を含む秘密を暴露され力尽き倒れる登場人物たち。その様子は生配信されていて、舞台上にもその映像が映し出されている。やがて聞こえてくるサイレンの音。どうやら視聴者が通報したらしい。逮捕されると怯える彼らだったがそれはパトカーではなく救急車のサイレンで──。
劇中の言葉の繰り返しにはなるが、最後の最後で罪の追及は傷ついたもののケアへと転じる。そこにあるのは劇作家・山本卓卓が物語に込めたあるべき世界への願いであり、同時に、「そこにいるあなたは物語の結末と世界の行方を委ねるに足る人物のはずだ」という、配信の視聴者=客席の観客に向けられたほとんど攻撃的と言っていいほどの信頼でもあるだろう。世界を、人間を変えるには、まずはそれらを信じるところからはじめなければならない。範宙遊泳はそれを実践してみせたのだ。
範宙遊泳:https://www.hanchuyuei2017.com/
関連レビュー
範宙遊泳『バナナの花』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年09月15日号)
2022/07/03(日)(山﨑健太)
青年団リンク やしゃご『きゃんと、すたんどみー、なう。』

会期:2022/07/07~2022/07/17
東京芸術劇場シアターイースト[東京都]
東京芸術劇場が若手劇団に上演の機会を提供する提携公演「芸劇eyes」の1本として青年団リンク やしゃご『きゃんと、すたんどみー、なう。』(作・演出:伊藤毅)が7月17日(日)まで東京芸術劇場シアターイーストで上演されている。2017年にやしゃごの前身である青年団若手自主企画 伊藤企画の名義で初演された戯曲を加筆修正しての上演となった本作で描かれるのは、伊藤が「目に見えないマイノリティ」と呼ぶ「きょうだい児」(=病気や障害を抱える兄弟姉妹を持つ人)の姿だ。
舞台は関東郊外の日本家屋。母亡きあとの高木家には、軽度の知的障がいを持つ長女・雪乃(豊田可奈子)、次女・月遥(とみやまあゆみ)と助教として大学で生物学の研究をする夫の大越(辻響平)、そして三女の花澄(緑川史絵)が暮らしていた。次女夫妻の結婚に伴う引っ越しの日、知らない男性が苦手な雪乃は引っ越し業者の綿引(海老根理)に驚いてパニックを起こしてしまう。なんとか雪乃を落ち着かせ、引っ越しの作業を進めようとする面々だったが、電話の子機が行方不明になったり綿引が腰をやってしまったりとトラブルが続く。そこに雪乃と同じ授産施設に通う正志(岡野康弘)がやってくると、雪乃と二人で「お世話になりました」と家から出て行こうとする。どうやら二人は結婚するつもりらしく──。
 [撮影:石澤知絵子]
[撮影:石澤知絵子]
思いとどまらせようとする妹たちに対する二人の反応は痛切だ。「大人になったら何になりたい? ユキは聞かれませんでした」という雪乃。「お母さんはダメって言います。女の子のこと好きになっちゃダメって」「付き合っちゃダメって」「セックスしちゃダメって」「結婚しちゃダメって言います」という正志。二人を見た引っ越し業者の由香里(清水緑)の「純粋だなあ」という言葉は素朴に過ぎるが、「この二人、普通じゃないから」と言い放つ月遥に大越が返す「なに、普通って」という問いはあまりに重い。
だが、未来の可能性を閉ざされたと感じているのは雪乃だけではない。花澄は母亡きあとの高木家を切り盛りし、そのためにかつて描いていた漫画も描かなくなってしまったのだった。「自分のこと考えていいんだよ」という母(の幻覚)(藤谷みき)に対しても花澄は「もう遅い。見て、私、歳取っちゃった」と答えることしかできない。
本作に限らず、伊藤の戯曲にはそれなりの数の人物が登場し(本作では12人)、濃淡こそあれどほとんどその一人ひとりが抱える「事情」が作中でそれぞれきっちりと描かれる。それらは作品の中心的なテーマに関わり、あるいはそこから派生したものであることもあれば、まったくそれとは関係のない(ように思える)こともある。例えば高木家に頼りにされている授産施設職員の小篠(井上みなみ)は実は雪乃に嫌われていて、給料が安いこの仕事を辞めようかと思っている。花澄の友人で漫画家の幸子(赤刎千久子)は花澄にすべてを任せ家を出ようとする月遥に思うところがある様子。自分の連載もなかなか決まらないらしい。由香里の義理の兄で引っ越し業者の社長でもある康介(佐藤滋)はどうやら由香里に思いを寄せているようだ。大越の助手の笠島(藤尾勘太郎)が生物学の道に進んだのは父親が若年性認知症になったからだという。伊藤の筆は少々律儀に過ぎるようにも思えるが、そのような姿勢自体、かつて自らも「目に見えないマイノリティ」であったという伊藤の倫理を示しているようにも思える。全員の「事情」を詳細に描くことは不可能だが、それでも、それぞれが「事情」を抱えた、つまりは生きた人間であることを示すこと。人はそれぞれに異なる事情を抱え、その事情を抱えたまま、ほかの人の事情に関わることしかできない。
 [撮影:石澤知絵子]
[撮影:石澤知絵子]
上演の終わり近く、花澄が卵を机に落とそうとし、寸前でそれを月遥が止める場面がある。卵が今年で20歳になる年経たニワトリ・ピー助が産んだものだということを考えれば、卵は花澄の未来を象徴するもののように思える。あるいはピー助が大越の手によって恐竜の尻尾を取りつけられた「普通じゃない」ニワトリだということを考えれば、それは雪乃の未来だっただろうか。尻尾という「重荷」が取れた直後にピー助が卵を産んだことを考えれば、それは高木家を去り新しい生活をはじめようとしていた月遥の未来を示すものだったかもしれない。雪乃の結婚はもちろん、大越との関係に問題を抱える月遥の未来も、花澄のこれからの生活も先は見えない。花澄が捨てようとして考え直し、月遥が救おうとしたものはなんだったのか。二人はそこに何を見ていたのか。観客は何を見るのか。彼女たちの人生がこれからも続くことを強く示すかのように、終演のアナウンスの後も舞台の上の芝居は続いていた。
青年団リンク やしゃご:https://itokikaku.jimdofree.com/
関連レビュー
青年団リンク やしゃご『てくてくと』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年06月01日号)
青年団リンク やしゃご『上空に光る』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年10月15日号)
2022/07/10(日)(山﨑健太)
カタログ&ブックス | 2022年7月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
トーキョーアーツアンドスペース アニュアル2021

編集:杉本勝彦
発行:公益財団法人東京都歴史文化財団東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース事業課
発行日:2022年6月1日
サイズ:A5判、176ページ
2021年度二国間交流事業プログラム<ヘルシンキ>派遣クリエーターの上村洋一、「ACT Vol. 4」の出展作家ユアサエボシへのインタビューのほか、TOKASの活動20年を記念し、これまでの事業の歩みを年表形式で振り返る特集やかつてプログラムに参加した田村友一郎、三田村光土里へのインタビューも収録しています。
クリスチャンにささやく 現代アート論集 (水声文庫)

著者:小林康夫
発行:水声社
発行日:2022年6月3日
サイズ:四六判、200ページ
ささやくように、語りかけるように……「2人称のクリティーク」というスタイルによって〈美〉と〈倫理〉を激しく問い、現代アートを縦横無尽に論じた、破格の美術批評。
ポストモダニティの条件 (ちくま学芸文庫)

著者:デヴィッド・ハーヴェイ
監訳:吉原直樹/翻訳:和泉浩/大塚彩美
発行:筑摩書房
発行日:2022年6月9日
サイズ:文庫判、640ページ
モダンとポストモダンを分かつものは何か。近代世界の諸事象を探査し、その核心を「時間と空間の圧縮」に見いだしたハーヴェイの主著。改訳決定版。
美術作品の修復保存入門 古美術から現代アートまで

著者:宮津大輔
発行:青幻舎
発行日:2022年6月10日
サイズ:A5判、184ページ
美術作品や文化財の「修復保存」について、絵画作品、紙作品、立体作品、そしてタイムベースド・メディア(≒映像)作品に分け、技法や材料並びに保存・保管といった基礎を、豊富な事例や興味深いエピソードと共にわかりやすく紹介。楽しみながら学べるコラムも多数収録した、専門家に限らず、誰もが手元に置いて参考にできる入門書。
アヴァンガルド勃興 近代日本の前衛写真

編集:東京都写真美術館
発行:国書刊行会
発行日:2022年6月14日
サイズ:A4変型判、208ページ
海外のシュルレアリスムや抽象美術の影響を受け、1930年代から1940年代に全国各地に花開いた写真の潮流──前衛写真。写真家、画家だけではなく、詩人やデザイナーをも巻き込み、新しい表現を追求する大きな磁場となりつつも、やがて時代の波にのみ込まれていった前衛写真の相貌と本質に迫る!
2022年5月20日(金)より東京都写真美術館で開催される展覧会「アヴァンガルド勃興 近代日本の前衛写真」公式カタログ。
関連レビュー
アヴァンガルド勃興 近代日本の前衛写真|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年06月15日号)
池田修の夢十夜
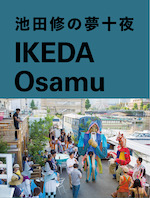
著者:池田修
発行:BankART1929
発行日:2022年6月14日
サイズ:182x240mm、351ページ
2022年3月16日に急逝したBankART1929代表・池田修が生前から企画していた、池田修のこれまでの文章をまとめた本。当初の予定通り65歳の誕生日にあわせて刊行。
関連レビュー
池田修を偲ぶ6日間「都市に棲む―池田修の夢と仕事」|村田真:artscapeレビュー(2022年07月01日号)
房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス2020+

監修:北川フラム/いちはらアートxミックス実行委員会
発行:現代企画室
発行日:2022年6月15日
サイズ:B5判、160ページ
2021年11月19日〜12月26日に開催された「いちはらアート×ミックス2020+」の全作品・イベントを収録した公式記録集。
TOP コレクション メメント・モリと写真
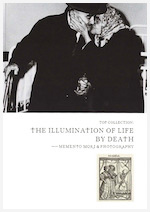
著者:浜崎加織、藤原信也、山野井千晶
発行:東京都写真美術館
発行日:2022年6月17日
サイズ:A5判変型、187ページ
2022年6月17日~9月25日まで東京都写真美術館にて開催されている展覧会「TOP コレクション メメント・モリと写真」のカタログ。
よむかたち デジタルとフィジカルをつなぐメディアデザインの実践
2022年06月21日

著者:永原康史
発行:誠文堂新光社
発行日:2022年6月21日
サイズ:B5変形判、256ページ
活動初期よりデジタルとフィジカルの表現を往復し、デジタルメディアとデザインをつなぐ制作を継続してきた著者の仕事を振り返る初の作品集。
社会化するアート/アート化する社会 社会と文化芸術の共進化 (文化とまちづくり叢書)

著者:小松田儀貞
発行:水曜社
発行日:2022年6月25日
サイズ:A5判、312ページ
「芸術」「美術」から、よりカジュアルに「アート」という言葉を用い始めて久しい。アートと社会は、それぞれが他方の一部となり「アートの社会化」「社会のアート化」が進む。本書はこうした状況を「社会とアートの共進化的動態」として捉えた。そこには地域、参加、多様性などの関連、さらに地域経済、市民社会論にまでかかわる「問題群」が浮上する。
AGI 2 / ENO

監修:中村泰之
著:藤本由紀夫、東瀬戸悟、嘉ノ海幹彦、平山悠、よろすず
発行:きょうレコーズ
発行日:2022年6月30日
サイズ:B5判、304ページ
「AGI 2 / ENO」1976年から1979年にかけて、日本でブライアン・イーノについて最も多くのことばを費やしてきたのは間違いなく阿木譲だ。本書では当時の『ロックマガジン』誌に掲載された阿木によるイーノに関する文章、レコード・レビュー、ライナー・ノーツなどを抜き出し、アーカイブすることを通して、阿木譲とイーノ、さらに音楽シーンの変遷にスポットを当ててみた。
ときめきのミュージアムグッズ

著者:大澤夏美
発行:玄光社
発行日:2022年7月4日
サイズ:A5判、144ページ
美術館や博物館での、ときめきの思い出を形にしたミュージアムグッズ。 本書では、ひと目見て欲しくなるような特別な輝きを持つ「きらめきのミュージアムグッズ」、ギミックの素晴らしさに感動したり、使ってその良さがさらにわかる「躍動するミュージアムグッズ」、アイテムが生まれたストーリーなど背景を知るとより愛着がわく「物語を紡ぐミュージアムグッズ」の3部構成で展開します。
YCAM BOOK 2022-2023

編:渡邉朋也(YCAM)、蛭間友里恵(YCAM)、岡崎里美、松冨淑香
発行:山口情報芸術センター[YCAM
]
発行日:2022年
サイズ:B5判、79ページ
山口情報芸術センター[YCAM]の2022〜2023年の活動リポート。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
2022/07/14(木)(artscape編集部)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)