artscapeレビュー
2019年04月15日号のレビュー/プレビュー
ダムタイプ 新作ワークインプログレス 2019

会期:2019/03/24
ロームシアター京都 サウスホール[京都府]
2002年発表の『Voyage』以来、18年ぶりに予定されているダムタイプの新作公演(2020年春)に向けての公開リハーサル。10~15分ほどの3つのシーンが公開された後、メンバーによるトークが行なわれた(今回のメンバーは、大鹿展明、尾﨑聡、白木良、砂山典子、高谷史郎、高谷桜子、田中真由美、泊博雅、濱哲史、原摩利彦、平井優子、藤本隆行、藤原マンナ、古舘健、薮内美佐子、吉本有輝子)。
ひとつめは「まばたきによるコミュニケーション」のシーン。冒頭、暗がりに、ダウンコートを着た女性パフォーマー2人が現われる。コートを脱いで水着姿になった彼女たちが横たわると、ライブカメラで捉えた顔のアップが頭上のスクリーンに投影される。無表情な彼女たちのまばたきに合わせ、機械音声のようなブツ切りの声による会話が流れ、スクリーンには無数の単語が星空のように浮遊する。全身不随の障害者がまばたきだけで行なう意思疎通を思わせるこのシーンは、コミュニケーションすなわち他者とつながりたいという欲望や、機械による身体機能の拡張を提示する。

[撮影:井上嘉和]
一方、2つめのシーンは、ボイスパフォーマーとして活動する田中真由美が登場。ホーミーのように高音と低音を自在に操り、声以前の欲動を表出し、吹き渡る風のうねりや動物の咆哮へと擬態する声は、機械的に増幅されるエコーと次第に境目が無くなり、人間の有機的な声と機械の領域の境界が融解していく。この2つのシーンは、「身体パフォーマンスとテクノロジーの拮抗」という、いわゆるダムタイプらしさへの期待に応えるものだった。
3つめは、ダンサーの砂山典子と薮内美佐子による、スウィングジャズのダンスシーン。陽気な音楽にノったショー的な要素の強いダンスだが、しばしばスローで引き伸ばされ、ノイズが混入し、頭上から段ボールが落下するなど、多幸症的な夢が反復によって不穏さへと反転していく。突き飛ばされ、倒れ、狂ったような笑い声を上げながらもがくシーンもあり、明るく乾いた嵐に晒されているような印象を受けた。

[撮影:井上嘉和]
上記三つのシーンは断片的で、シーンどうしの直接的な繋がりはない。そのことを示すのが、シーンの合間に客電が点き、「転換入りまーす」「暗転しまーす」「リハ再開しまーす」というスタッフの声が意図的に発せられることだ。「これは完成形態ではない」というメタメッセージを発する効果とともに、「観客の集中力を削ぐ」という両面があったことは否めない。また、トークでは個別シーンの説明にとどまり、特に全体的なテーマやコンセプトについては触れられていなかった(新作のタイトルも未発表)。
なお、18年ぶりの新作公演の背後には、2020年春に開催が予定されている大型フェスティバル「KYOTO STEAM─世界文化交流祭─2020」の存在があり、今回の公開リハはそのプロローグ事業の一環として行なわれた。杞憂かもしれないが、新作の制作の動機には、プロデューサー主導の流れが背後にある危うさも透けて見える。「京都のレジェンドの復活」として、「新フェスの目玉」として期待/消費されることにはならないか。フェスティバルのための単発の打ち上げ花火ではなく、その後の持続的な活動につながるかどうか。11月には東京都現代美術館での大規模な個展も控えており、回顧と再始動の年と言える。来年の本公演を楽しみに待ちたい。
2019/03/24(日)(高嶋慈)
とある窓

会期:2019/03/15~2019/03/31
浄土複合 スクール[京都府]
「浄土複合」は、2019年3月、京都市左京区の浄土寺エリアにオープンした複合アートスペース。ギャラリーと共同スタジオの運営とともに、ライティング・スクールも開催され、「展示」「制作」「批評」が交差する場の創出を目指すという。ディレクションは美術家の池田剛介、ギャラリー「FINCH ARTS」は櫻岡聡、ウィンドーギャラリー「Stand-Alone」は沢田朔、ライティング・スクールは編集者の櫻井拓が担当。元店舗の二軒並びの建物を改装し、それぞれ1階がホワイトキューブの展示空間に生まれ変わった。銀閣寺や哲学の道に近い浄土寺エリアは、観光客が多く訪れるとともに、劇団・地点が主催するアトリエ兼劇場「アンダースロー」や実験的なスリーピース・バンドの空間現代が運営するライブハウス「外」があるなど、近年、インディペンデントな文化エリアとなりつつある。
本展「とある窓」は、東日本大震災から7年あまりの経過後、岩手・宮城・福島の沿岸にある「窓」から見た光景を、地域と協働して記録をつくる組織NOOKによる聞き書きのテクストと、同行した写真家の森田具海が撮影した写真によって構成されている。昨年末に仙台で発表され、今春、京都に巡回した。展示は、壁に1点ずつ掛けられた「窓」の写真の下に、対応する聞き書きを収めた本が置かれ、鑑賞者は、方言で語りかける匿名の語り手の声に耳を傾けながら、室内から「窓」を通して見える/かつて見えていた風景を眼差すように誘われる。生々しい爪痕の残る窓や壊れた室内はなく、ごく平凡な窓を通して四角く切り取られた風景が、ほぼ無人の室内とともに淡々と写し取られている。だが窓外の風景は、クレーン車が作業中のかさ上げ工事、草の生い茂った空き地、更地に突然そびえる真新しい団地が多く、「震災後」の風景の変容を伝える。また、海や漁船、堤防の一部が見える窓も多い。

[撮影:前谷開]
震災後、自宅の庭で唯一残った石を運び、新しい庭に花や株を分けてくれた人々や前の庭の思い出を語る住人。松林が流され、海が見えるようになった海辺の公園のスタッフは、「子どもの頃の記憶と合致する場所として残ったのはここだけ」という安堵感と申し訳なさの感情を複雑に抱きつつ、再び子どもの遊び声が響く地域の拠点にできないかと展望を語る。公営住宅に住む老人は、「海は身体の一部。海の見えない暮らしは苦痛」と語りつつ、出征時にも披露していた民謡と、70代になって始めた民話が生きがいだと語る。かつて船で渡って田んぼを耕していた島は防潮堤で囲まれ、風景は一変したが、今も海に向かって民謡の練習をするのだと。一方、60年以上も同じ風景を見ているという老婦人は、「白い防潮堤が建つと、海が見えなくなる。でも、もう何十年も見せられたんだから、いいんだ」と呟く。福祉作業所のメンバーは、震災を契機に地域外の支援団体と交流ができ、「障害をひとつの価値と捉えて、カフェやギャラリーなど交流の場をつくり、仲間と自立する道を考え始めた」と語る。NPO法人の理事長は、「被災した障害者の支援のため、仮設住宅を回りたいがなかなか会いに行けない。ここに来てきてくれないかと待っている」と語る。その時、室内から入り口のガラス戸越しに外の風景を捉えたショットは、語り手の視線を擬似的にトレースしたものとして経験される。

[撮影:森田具海]
本展が秀逸なのは、複数の意味やメタファーを内包する「窓」という装置に着目した点だ。それは、室内と外、人の生活と自然、「今」の暮らし/震災の記憶/震災以前の過去/未来の展望といったさまざまな境界を隔てつつ結びつける媒介であり、語り手の心の内をのぞき込む装置であり、室内=箱のなかから明るい外界に開いた「窓」が切り取るフレーミングは、「視線」の謂い、とりわけ「カメラ」それ自体への自己言及性もはらむ。また、あえて室内には語り手が登場せず、方言とともに語りのリズムを伝える文章が匿名のまま添えられることで、想像の余白を生む。鑑賞者は、「生活の場から外界へ」「現在から過去・未来へ」眼差しを向ける語り手の視線を個人史に寄り添いながらトレースし、「もはや見えなくなった風景/これから見える風景」を共に想起するのだ。

[撮影:森田具海]
関連記事
「立ち上がりの技術vol.3 とある窓」|五十嵐太郎:artscapeレビュー
2019/03/24(日)(高嶋慈)
宮本隆司『首くくり栲象』出版記念展覧会

会期:2019/03/18~2019/03/31
BankART SILK[神奈川県]
2018年3月から活動を休止していた横浜市の現代美術スペース、BankART Studio NYKが、同市内の3カ所で活動を再開した。BankART Home、BankART Stationに続いて、坂倉準三設計の歴史的建造物《シルクセンター》の1階にオープンしたのがBankART SILKである。そのオープニング第2弾として、宮本隆司の「首くくり栲象」展が開催された。
宮本は10年ほど前から、庭先に吊り下げた縄に首を入れてぶら下がる「首くくり栲象(たくぞう)」(本名:古澤守)のパフォーマンスを写真と映像で記録してきた。いまにも崩れ落ちそうな木造平屋の「庭劇場」でほぼ毎日、首をくくってきた1947年生まれのパフォーマーは、2018年3月に亡くなり、いまはもうその「死に触れず、死を作品化する」伝説的なパフォーマンスを見ることはできない。その意味では貴重な記録といえるのだが、それ以上に、その普通ではない行為をあえて普通に撮影している宮本の撮影の仕方に共感を覚える。宮本が「庭劇場」を撮影し始めた理由のひとつは「家が近かったこと」だったようだが、自然体の撮り方にもかかわらず、そこには建築写真で鍛え上げた細やかな観察力と、精確な画面構成の能力が充分に発揮されていた。
会場では写真作品のほかに、パフォーマンスの一部始終を記録した映像作品も上映していたのだが、こちらも興味深い内容だった。フレームを固定した画面に、「首くくり栲象」のパフォーマンスが淡々と記録されているだけなのだが、途中でその傍に、巨大な猫が絶妙な間合いで出現して消えていく。むろん仕組んだものではないだろうが、その展開には意表をつかれた。なお、宮本隆司の写真と演劇評論家の長井和博のエッセイ「午後八時発動」を掲載した作品集『首くくり栲象』(BankART1929)も刊行されている。
2019/03/26(火)(飯沢耕太郎)
菊池聡太朗「ウィスマ・クエラ」
会期:2019/03/26~2019/04/03
ギャラリーターンアラウンド[宮城県]
東北大の五十嵐研の大学院を修了した菊池聡太朗の個展が、仙台の現代美術のギャラリーターンアラウンドで開催された。インドネシアのカリスマ的な建築家マングンウィジャヤによるジョグジャカルタの自邸《ウィスマ・クエラ》をタイトルに掲げているように、彼が図面なき増殖建築に魅せられ、その記録写真や記憶を独自のインスタレーションとして表現したのである。おそらくマングンウィジャヤは日本で無名と思われるが、カンポンのプロジェクトによって、イスラム世界の建築を顕彰するアガ・カーン賞を受賞している。独自の建築哲学をもち、職人集団と活動しながら、きわめて異形のデザインを行なっていた。彼のデザインは、広義には装飾性がポストモダンと呼べるのかもしれないが、ある種のヘタウマ的なテイストで、既存のカテゴリーに括ることが難しい。特に自邸は、彼の死後も日常的に小さな増改築が繰り返され、建築や家具などの境目も曖昧になっている。
菊池はインドネシアに留学中、この建築にしばらく滞在し、目の前で起きる変化も記録しながら、その空間体験をどのように視覚化するかを修士設計のテーマに取り組んでいた。そして彼が現場で撮影した時空間が錯綜した写真群を展示する空間を独自のルールによって構築し、学内外の講評会で高い評価を得た。彼は東京都写真美術館で開催中の「ヒューマン・スプリング」展を含め、写真家の志賀理江子の制作を長い期間にわたってサポートしたことで、観念的なデザインに陥らず、スケール感をリアルに理解した設計に到達したことも、修士設計の最終成果物に説得力を与えている。ただし、ギャラリー・ターンアラウンドでは、その展示空間を1/1で再現するには十分な広さがないこともあり、ドローイングと小さくプリントした写真群のインスタレーションで、別の空間を創造した。志賀はもちろん、リー・キットの影響なども見受けられるが、短い期間で、新しい独自の世界を高い密度で出現させた力量は高く評価できるだろう。
 マングンウィジャヤの自邸《ウィスマ・クエラ》
マングンウィジャヤの自邸《ウィスマ・クエラ》
 「ウィスマ・クエラ」展、会場の様子
「ウィスマ・クエラ」展、会場の様子
 「ウィスマ・クエラ」展、会場の様子
「ウィスマ・クエラ」展、会場の様子
 「ウィスマ・クエラ」展、会場の様子
「ウィスマ・クエラ」展、会場の様子
 「ウィスマ・クエラ」展、会場の様子
「ウィスマ・クエラ」展、会場の様子
 「ウィスマ・クエラ」展、会場の様子
「ウィスマ・クエラ」展、会場の様子
2019/03/26(金)(五十嵐太郎)
野村恵子「山霊の庭 Otari-Pristine Peaks」
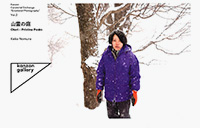
会期:2019/03/16~2019/04/13
Kanzan Gallery[東京都]
このところ、女性写真家たちの質の高い仕事が目につくが、野村恵子もそのひとりである。1990年代にデビューした彼女と同世代の写真家たちが、それぞれ力をつけ、しっかりとした作品を発表しているのはとても嬉しいことだ。野村は昨年刊行した写真集、『Otari-Pristine Peaks 山霊の庭』(スーパーラボ)で第28回林忠彦賞を受賞した。今回の展示はそれを受けてのことだが、菊田樹子がキュレーションするKanzan Galleryでの連続展「Emotional Photography」の一環でもある。
雪深い長野県小谷村の人々の暮らし、祭礼、狩猟の様子などを「湧き上がる感覚や感情を静かに受け入れながら」撮影した本シリーズは、たしかに「感情」、「情動」をキーワードとする「Emotional Photography」のコンセプトにふさわしい。特に、妊娠し、子どもを産む若い女性の姿が、大きくフィーチャーされることで、ほかの山村の暮らしをテーマとするドキュメンタリーとは一線を画するものとなった。
野村と菊田による会場構成も、とてもよく練り上げられていた。壁には直貼りされた大判プリントとフレーム入りの写真が掲げられ、写真とテキストを上面に置いた白い柱状の什器が床に並ぶ。ほかに、3カ所のスクリーンで映像をプロジェクションしているのだが、その位置、内容、上映のタイミングもきちんと計算されている。写真集とはまた違った角度から、「山に生かされて」暮らしを営む人々の姿が重層的に浮かび上がってきていた。近年、ドキュメンタリー写真における展示の重要度はさらに上がってきているが、それによく応えたインスタレーションだった。
2019/03/27(水)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)