artscapeレビュー
2018年04月15日号のレビュー/プレビュー
渡邊耕一「Moving Plants」
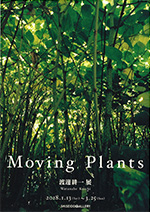
会期:2018/01/13~2018/03/25
資生堂ギャラリー[東京都]
スケールの大きな思考と実践の成果である。渡邊耕一は「15、6年前」に北海道を撮影している時に目にした、巨大なオオイタドリの群生に興味を惹かれ、その来歴をリサーチし始める。その結果、驚くべきことがわかってきた。イタドリ種の植物は日本では普通に見られるが、ヨーロッパやアメリカでは外来種であり、江戸時代に来日したフォン・シーボルトによって種子が持ち込まれ、「侵略性植物種」として各地にはびこることになったのだ。渡邊はこの「名も無き雑草」の200年以上にわたる遥かな旅の足跡を辿り、イギリス、オランダ、ポーランド、アメリカなどで、イタドリが生えている風景を撮影し続けた。本展はその成果をまとめて大阪のThe Third Gallery Ayaで2015年に開催された同名の個展の拡大版である。
渡邊の撮影のやり方は、正統なドキュメンタリー写真のそれだが、写真だけではなく、標本や古文書などの原資料、テキスト、スライド・プロジェクションなども加えたインスタレーションはとても現代的に洗練されている。発想の鮮やかさはもちろんだが、それを粘り強い調査を積み重ねて丹念に編み上げていくことで、展覧会としてもよくまとまったものになっていた。イタドリのある見慣れた眺めが、この写真展を見たあとでは、まったく違ったふうに目に映るのではないだろうか。写真による新たな世界認識のあり方を提示しようとする意欲的な試みといえる。なお、2015年の展覧会に合わせて、青幻社から同名の写真集も刊行されている。
2018/03/06(火)(飯沢耕太郎)
今道子「Recent Works 2018」

会期:2018/03/07~2018/04/28
PGI[東京都]
今道子は2016年に初めてメキシコを訪れ、すっかり気に入ってしまった。それはそうだろう。彼女の魚や野菜や果物を使ってあり得ないオブジェをつくり上げて撮影する作品は、元々ラテン・アメリカの「魔術的リアリズム」の風土ととても相性がいいからだ。その後の2回の滞在を経て、メキシコで受けたインスピレーションを形にした作品が、今回の展示の中核部分を占めている。実際に「死者の日」に撮影したという「Self portrait in Mexico」(2016)は、顔の半分にドクロのメーキャップを施し、メキシコの人形、聖母像、布などを配した作品だが、あまりの違和感のなさに思わず笑いがこみ上げてきた。
今回、もうひとつ気になったのは、昆虫を被写体にした作品が目につくことである。特に蚕蛾の生育キットをモチーフにした「蚕観察」(2018)のシリーズが興味深い。《目の見えない蚕》、《飛べない蚕蛾》、《口がない蚕蛾》、《蚕蛾と生きているアワビ》とそれぞれ題された作品には、今道子にはやや珍しく、苦いアイロニーが感じられる。ほかの作品も、それぞれ思考の深まりと技術的な洗練とが見事に合体しており、見応えのあるものが多かった。メキシコ滞在をひとつのきっかけとして、また別の世界が拓けてきつつあるのではないかと思う。今回で、PGI(フォト・ギャラリー・インターナショナル)では6回目の個展になるそうだが、さらなる飛躍が期待できそうだ。
2018/03/07(水)(飯沢耕太郎)
第11回JIA東北住宅大賞2017 現地審査ツアー
会期:2018/03/06〜2018/03/08
[宮城県、青森県、岩手県、福島県]
せんだいデザインリーグが終わると、東北住宅大賞の現地審査のツアーに出かけるのが恒例となった。今年からは、これまで10回の審査を一緒に担当した古谷誠章に代わり、飯田善彦とともに行脚し、3日間で10作品を訪れた。初日は仙台市内で3つ、宮城県内でもう2つをまわる。2日目は青森で1つ、岩手で1つ、郡山で1つ、そして最終日は福島で2作品という強行軍だ。第11回の東北住宅大賞に選ばれたのは、松下慎太郎によるいわき市の《IENOWA》である。住宅地に重なりあう複数のフレームを設定し、さまざまな領域をつくるものだが、竣工写真よりも施主の私物が入った状態のほうが、場の差異が強調され、さらに魅力的だった。折半天井の大屋根の下に、リノベーションによってポストモダン的な家型を挿入したようにも見えるのも興味深い。以前、東北住宅大賞の審査で見学した同じ設計者の住宅《RICO》とも雰囲気が似ているが、もっと開放的なデザインに進化している。
優秀賞は4作品が選ばれ、残りの5作品は佳作となった。以下に優勝賞の作品に触れておく。洞口苗子による岩沼の《複合古民家実験住宅》は、築60年の古民家を購入して救い、カラフルな二世帯住宅+(二階の秘密基地的)設計事務所に改造し、緑道に接する母の美容室を増築したもの。20代だから東北住宅大賞では最年少であり、これまでにないセンスのリノベーションだった。齋藤和哉による《八木山のハウス》は、中央のホールから四方向に傾斜屋根をもつが、それらの中心をテラスとして掻き取り、ホール上部の四方向に開口を設けることで、内部と外部が絡む、興味深い空間の形式を実現する。佐藤充が設計した《北山の家》は、線路沿いの敷地ゆえに、箱型の住宅で防御しつつも、室内に入ると、二層吹き抜けを外周にめぐらせ、開放的な空間だった。そして岩堀未来+長尾亜子による《矢吹町中町第二災害公営住宅》は、ダブルスキンの「縁にわ」をもち、大開口により南北に視線が貫く。ほかの被災地とは違い、雁行する二階建ての長屋になっており、街並み、植栽、ランドスケープ、環境を意識し、将来の町営住宅への転換も射程に入れたデザインだった。
松下慎太郎《IENOWA》
左=齋藤和哉《八木山のハウス》 右=洞口苗子《複合古民家実験住宅》
左=佐藤充《北山の家》 右=岩堀未来+長尾亜子《矢吹町中町第二災害公営住宅》
2018/03/08(木)(五十嵐太郎)
Tokyo Rumando(東京るまん℃)「S」

会期:2018/03/02~2018/03/31
ZEN FOTO GALLERY[東京都]
Tokyo Rumandoの「S」は意欲的な新作である。「S」という謎めいた文字が何を意味するかについては、いろいろな解釈が可能だろう。一番わかりやすいのは、「ストリップティーズ」の「S」ということだ。展示されている作品には、ストリップ劇場の看板や楽屋を撮影したものが多い。実際にその舞台で作者本人がストリップティーズを演じている場面もある。もうひとつ、「ストーリーズ」の「S」という解釈も成り立つ。これまでも、Tokyo Rumandoの作品には物語性が組み込まれていることが多かったのだが、今回はそれがより強く打ち出されてきている。一枚一枚の写真に、いわくありげなバックグラウンドがあるように見えるし、セーター服、網タイツ、能面のような仮面など小道具もそれぞれが自己主張しているのだ。さらに、ワックスペーパーに焼き付けた写真に、透過光を当てて再複写したという、ざらついた、白黒のコントラストの強いプリントも、ミステリアスな雰囲気を醸し出すために効果的に使われていた。
だからこそ、その物語性をもっとくっきりと浮かび上がらせる仕掛けが必要だったではないかとも思ってしまう。写真の並びだけでそれを実現するのはやや難しいので、テキスト(言葉)もあったほうがよかった。《DISCO Red Dress》(2017)と題する映像作品も、静止画像の作品ともっとうまく組み合わせれば、面白いインスタレーションとして成立しそうだ。全体的にまだ未完成な印象だが、ブラッシュアップしていくと、さらにインパクトが強まるのではないだろうか。
なお展覧会に合わせて、ZEN FOTO GALLERYから、同名のスタイリッシュな造本の写真集が刊行されている。
2018/03/08(木)(飯沢耕太郎)
平田オリザ『働く私』/『さようなら』

会期:2018/03/09〜2018/03/10
浜離宮朝日ホール[東京都]
『働く私』は男女の俳優とプログラムによって舞台で動く2体のロボット(かわいらしい造形であり、デジタル的な音声から推定すると、男女のジェンダー分けがなされている)による演劇。『さようなら』は不治の病の女性と、椅子に座って詩を読むアンドロイド(女性の形象だが、かなりリアルなため、やや不気味)による会話劇だった。なお、後者は3.11を受けての改訂版になっており、その後、原発事故が起きた福島に移送されるという設定が加えられている。技術的にロボットに何が可能かというスペックにあわせて、当て書きのように脚本が執筆されていること、また試行錯誤を繰り返しながら、もうすでに何度も国内外で上演されていたからだと思われるが、俳優と自動人形の息はぴったりと合っている。ロボットが途中でフリーズした場合、再起動する時間を稼ぐために、どのように対応するかもあらかじめ想定されているという。
これらの作品が興味深いのは、改めて人(俳優)とは何か、そして演劇とは何かを考えさせられることだろう。そもそも演劇とは、あらかじめ決められた演出に従い、俳優が身体を動かし、しゃべる表現の形式である。とすれば、究極的に俳優は、一定の振り付けを完全に再現できるロボットになることが求められている。アフタートークでは、ロボット演劇が誕生した契機となった、大阪大学における科学とアートの融合プロジェクトの経緯が紹介されたが、やはり平田のデジタルな演出法はもともと相性がよかったのだろう。彼は抽象的な言葉ではなく、無駄な動きも含めて、1秒以下の細かい単位で、俳優に指示をだしているからだ。ならば、将来、すべての俳優はロボットに置き換え可能なのか?(すでにハリウッド映画では、俳優のCG化が進行しているが)ただ、両者が接近するほど、おそらく人間の特性も明らかになるだろう。少なくとも、現時点で平田は、ロボットだけが登場する作品はまだ発表していない。また筆者が鑑賞したとき、人間とロボットのあいだの微妙な(ディス?)コミュニケーションが想像しうることの重要性を痛感した。
2018/03/09(金)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)