artscapeレビュー
2020年04月15日号のレビュー/プレビュー
ネオ・ダダの痕跡

会期:2020/03/18~2020/04/04
ギャラリー58[東京都]
1960年に結成され、わずか半年ほどで解体した前衛芸術集団ネオ・ダダの、結成および解散60年を記念した展覧会。出品は元メンバーの赤瀬川原平、風倉匠、篠原有司男、田中信太郎、吉野辰海の5人。昨年田中が亡くなったので、現役はギューちゃんこと篠原と吉野の2人となった(その数日後、メンバーではないが彼らと親交の深かった秋山祐徳太子の訃報が届いた)。
出品作品はネオ・ダダ時代のものではなく、1970年に出たウィルヘルム・ライヒの『きけ 小人物よ!』(太平出版社)の挿絵として描いた赤瀬川のペン画から、ニューヨーク在住のギューちゃんがこの春に制作した最新作まで、素材もサイズも制作年もバラバラ。そこがネオ・ダダらしいけど。なかでも目立つのが、パリ旅行の思い出を描いたギューちゃんの大作ペインティング《パリだぜ! 牛ちゃん─親友、木下新に捧げる》だ。パリへはこの1月、ルーヴル美術館の「レオナルド・ダ・ヴィンチ展」を見るために訪れたそうで、巨大画面にはルーヴルのピラミッドやサンジェルマンで食事する夫妻などが描かれているらしいが、なにがなんだかさっぱりわからない。画廊の人がギューちゃんに図解してもらったそうだが、そのスケッチを見ても、ピラミッドらしきものは認められたものの、後はさっぱり。でも色彩とタッチは以前にも増して激しい。
今年米寿を迎えるギューちゃんは、メンバーのなかでも最年長だが、元気いっぱいで毎日ニューヨークから電話をかけてくる、という話を画廊の人がしていたら、本当にかかってきた。なりゆきでぼくもお話しさせてもらったが、声に張りがあってトシを感じさせず、驚いた。いま新型コロナウイルスでニューヨークもパリも大変な騒ぎで、ルーヴルも閉鎖され、飛行機にも乗れないから、1月に行っといてよかったという話だった。ギューちゃん、コロナに気をつければ100歳までいけそう。
2020/03/28(土)(村田真)
芳木麻里絵「fond de robe ─内にある装飾─」

会期:2020/02/07~2020/03/28
ワコールスタディホール京都 ギャラリー[京都府]
「光の繊細な陰影」や「触覚性を喚起する質感をもつ表層」に着目し、モチーフの表面をスキャンまたは接写して得た画像を元に、アクリル板の上にシルクスクリーンの技法を用いてインクの層を数百回刷り重ねることで、イメージを「インクの積層」として再物質化する芳木麻里絵。その作品は、2次元と3次元、イメージと物質、表面と奥行きといった二項対立を攪乱的に往還しながら、「版」と複製・再現、3Dプリンターによる造形、そしてデジタル化された画像データに日常的に取り囲まれた私たちの知覚環境について問いかける。
芳木はこれまで、光の陰影や透過性、襞がもたらす2次元性と3次元性の共存といった点から、「レース」を主要なモチーフのひとつとして制作してきた。下着メーカーのワコールが運営するギャラリーで開催された本展では、1920年代と現代の「女性の下着」に使用されたレースをモチーフとすることで、これまでの関心を引き継ぎつつ、ジェンダーや社会史との接続によって作品の枠組みがより広がった。

[撮影:表恒匡]
参照されたのは、公益財団法人 京都服飾文化研究財団(KCI)が所蔵する、現代の下着の原型とも言われる1920年代のフランスのブラジャーやスリップと、ワコールの2020年春夏の最新の下着である。第一次世界大戦期に労働力として女性の社会進出が進み、身体を締め付ける窮屈なコルセットに代わってブラジャーやスリップが生み出され、戦後、機械織りによるレースの製造普及や女性の社会的地位の変遷とともに普及していった。100年前の下着も現代の下着も、華やかで繊細なレースの装飾が付されている点では変わらない。一方、100年前の下着は、(財団の所蔵資料ということもあり)表面に直接接触して文字どおり引き剥がすようなスキャニングではなく、接写による浅い被写界深度によってピントのボケを伴った画像に置換されている。そこに、現代の下着の源流という「近くて遠い」対象にどう接近するのかという眼差しを重ね合わせることもできる。

[photo: YOSHIKI Marie]
「外からは見えない」存在であるのに「装飾」が付されている下着の両義性はまた、「ファッションの一部として楽しむ」という女性自身の歓びの能動的側面と、「なぜ美や装飾性が求められているのか」という問いの双方と関連する。下着は、「服の土台(fond de robe)」として身体を支えつつ、「第二の皮膚」としての衣服とさらに皮膚の表面とのあいだの親密な領域で、自他の欲望が入り混じった複雑な領域を形成している。
(ヘテロセクシュアルの)男性作家が「女性の下着」をモチーフや被写体に取り上げた場合、「性的に眺める視線」を完全に排除することは難しいだろう。(ヘテロ)男性にとって「女性の下着」は、オブジェとして客体化された性的な視線の対象だが、日常的に身につける女性にとっては(上述のような複雑な欲望の領域を形成しながら)皮膚の表面に触れる、触覚性を伴ったものだ。ここで、2次元化された画像をインクの層の物理的堆積として3次元化して再出力する芳木の制作プロセスにおける問題意識を、よりジェンダー的な解釈へと開くことも可能だろう。「(性的な)眼差しの対象」として皮膚から引き剥がされたものを、触覚性を帯びたものとして取り戻す。そこで、インクの層が帯びる歪みや不連続な断層は、「自然」で「完全」な物質としての回復ではなく、他者によって一度異物化されたことの痕跡を宿すものとして立ち上がるのだ。

[photo: YOSHIKI Marie]
本展では、「1920年代のフランスの女性下着」が参照されていたが、日本の場合、「コルセット=規範的な美と身体の矯正からの解放」ではなく、「和装から洋装へ」という別の文脈が関わってくる。デジタル画像、イメージと知覚、シルクスクリーンという版画メディアへの自己言及性をキーワードに制作してきた芳木にとって、本展は、転機と新たな展開の第一歩となるだろう。
関連レビュー
芳木麻里絵「触知の重さ Living room 」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年02月15日号)
2020/03/28(土)(高嶋慈)
山下残『インヴィテーション』

会期:2020/03/27~2020/03/29
THEATRE E9 KYOTO[京都府]
飄々としたユーモアとクリティカルな視線で「ダンス」「舞台芸術」を照射してきた山下残。本作では、パフォーマー同士の「~してもいいですか」「どうぞ/ダメです」「~してください」というやり取りによって、許可/禁止/指示される行為が積み重ねられていく。舞台芸術の制作現場やワークショップにおけるコミュニケーションへの自己言及に始まり、パワハラ、セクハラなどさまざまな関係性におけるヒエラルキーや不均衡な権力構造をあぶり出し、「舞台芸術」を成立させている制度内の/外側の社会構造を解体し、再提示してみせた。その先に浮かび上がるのは、コロナ禍における「自粛」の要請と、(あいトリでの文化庁の補助金不交付問題やオリンピック関連の文化事業においてとりわけ顕在化した)「事前に許可と承認を求める」「忖度」という日本の文化芸術を取り巻く現状だ。またここで、「許可/禁止」の判断の根拠の曖昧さや、判断を下す役を絶えず入れ替える流動性は、その判断の咨意性や責任主体の不透明な曖昧さについても鋭く問うていた。
上演会場はオールスタンディングで、舞台の壇も客席のひな壇も取り払われたフラットな空間を40-50人ほどの観客が取り巻く。虫の触覚のような装置を頭につけたパフォーマー(音響担当のおおしまたくろう)が登場し、「ご来場ありがとうございます。只今より山下残振付・演出作品『インヴィテーション』を始めます」とどもりながら告げる。彼が身体を動かすと、触覚状のセンサーが振動を拾い、不穏な音響が響く。だがその「前説」は、「トイレ行っていいですか」という唐突な声によって遮られ、作品の「開始」「輪郭」もまた曖昧にぼかされていく。あるいは、おおしまが何度も登場するたびに繰り返す「前説」によって、「開始」はずるずると遅延させられていく。
「トイレ行っていいですか」「タバコ吸っていいですか」と許可を求める声の積み重なりは、その日常的な行為のたわいのなさゆえに、「わざわざ許可が必要か」という不穏さを次第にまとっていく。許可と指示の言葉は、「左腕を上げてください」「耳を触ってください」「腰を回してください」といった具体的な動作と、「海をつくってください」「橋を架けてください」「入道雲になっていいですか」といった抽象的・詩的な言葉によって、「舞台芸術の制作現場やワークショップにおけるコミュニケーション」の様相を呈し始める。だが、「海をつくる」ために床に唾を垂らし続けるパフォーマーや、「その海に橋を架ける」ためにブリッジの姿勢を取り続けるパフォーマーの姿、そして強い調子で度々発せられる「もっとイマジネーションを使え」という(演出家の? ワークショップ講師の?)声や禁止の命令は、時に理不尽な要求や身体的な過酷さを強いる振付や演出がはらむ権力性や暴力性を浮上させ、舞台芸術の制度への自己批判とともにパワハラへの危うい接近を見せる。また、男性パフォーマーが女性パフォーマーに「身体の部位を触ってもいいですか」と低い声で言うシーンはセクハラを匂わせ、ジェンダーの不均衡に基づく権力関係が追記される。一方的で理不尽な要求のエスカレート、こなしきれない多重のタスクを課された身体は、次第に暴走的な様相を呈していく。

[撮影:中谷利明]
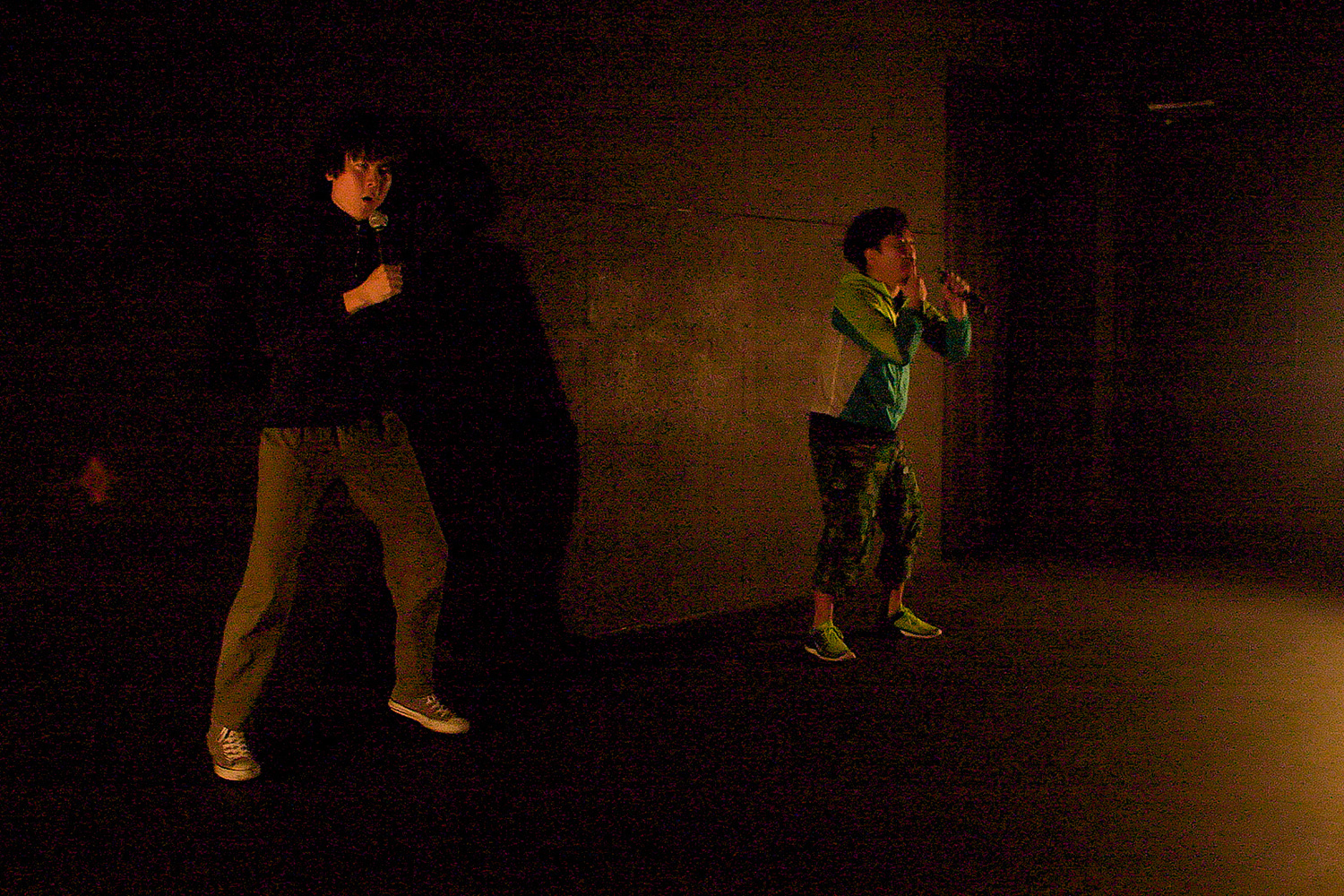
[撮影:中谷利明]
このように本作は、行為遂行的な言葉のやり取りがはらむ、(微温的な/だからこそ不穏な)権力の在りかをさまざまに浮上させつつ、「許可/禁止/要請」を発話する役割はパフォーマー間で絶えず交換される。その流動性は、ヒエラルキーの固定化に抗う一方で、誰が「許可を与える権力の主体」なのか? を曖昧に拡散させ、責任主体の見えにくさについても問いかける。また、反復される「前説」は、劇場に集った観客を迎える「インヴィテーション」の言葉であると同時に、「ここは舞台である」というメタ的な言及の繰り返しは、「人が集まること」という舞台の成立基盤と、それが「禁止」「自粛要請」されていく現状を照射する。「換気」のためと称して何度も解放される「扉」からは新鮮な外気が流れ込み、パフォーマーたちはラストで、開け放たれた扉から「劇場の外」へと歩み去っていく。

[撮影:中谷利明]
「入場料無料」という点も戦略的だ。それは一方では、「舞台作品にお金を払う価値とは」「観客は何を見たいと思って劇場に来るのか」という問いを投げかけ、「見たい」欲望と金銭的価値の交換、劇場・上演批判を繰り出す。だが他方では、スタッフワークの比重を下げ、照明や音響を出演者自身が操作することで、「低資金でも公演が実現可能」「無料で見られる」という、劇場利用者と観客の増加を共に目指す試みの希望的提示でもある。
山下によるこのポジティブな提示は、2019年6月に新しくオープンしたTHEATRE E9 KYOTOという劇場に対する強いメッセージでもある。同劇場は、関西圏のほかの多くの劇場が公演中止や延期を決定するなか、換気やアルコール消毒、客席の間引きなどコロナ対策を講じながら、3月末の本作まで初年度のプログラムをやり切った。もちろんここには、劇場スタッフや各公演団体の尽力があったことは言うまでもない。日々厳しさを増す状況のなか、1年目を最後までやりとげ、そしてこの作品で締めくくったことは、大きな意義があったといえよう。
2020/03/28(土)(高嶋慈)
東海道 西野壮平 展

会期:2020/04/01~2020/04/07
日本橋三越本店 本館6階 コンテンポラリーギャラリー[東京都]
西野壮平は、さまざまな場所に足を運んで撮影した大量の写真を、切り貼りしてモザイク状にコラージュし、風景を再構築する作品を制作し続けている。その彼の新作は、2017年の冬に、東京から京都までの「東海道」約492キロを、1カ月かけて徒歩で旅して撮影した写真で構成されていた。西野は写真家として本格的にデビューする前の2004年に、故郷の兵庫県から東京まで歩いたことがある。今回の「東海道」はそのルートを逆に辿るもので、彼にとっては写真家としての原点を確認するという意味を持つものだったのではないだろうか。
彼が最終的に発表の形態として選んだのは、約4万カットからセレクトしてコラージュしたというオリジナル写真作品を、カラー・コロタイプ(制作:便利堂)で印刷・複製し、全長34メートルという巻物状にして見せることだった。そのほかに、壁面には部分的に切り取った19点のフレーム入り作品も展示されていた。
これは、西野の作品を見るときにいつも感じることだが、細部に目を凝らせば凝らすほど、さまざまな場面がひしめくように錯綜し、迷宮を彷徨っているような気分になってくる。そこに写っているのは、たしかにリアルで日常的な光景の集積なのだが、全体として見ると、魔術的としか言いようのない非現実感が生じてくるのだ。特に今回は、歌川広重の「東海道五十三次」以来、日本人のイメージ回路に刷り込まれている「東海道」がテーマなので、よりその現実感と非現実感の落差が大きいように思えた。カラー・コロタイプの、水彩画のような色味、画質も、うまくはまっていた。これまでの彼の作品は、囲い込まれた都市空間を被写体とすることが多かったのだが、今後はある地点からある地点までの移動のプロセスが、より重要な意味を持ってくるのではないだろうか。
関連レビュー
西野壮平「Action Drawing: Diorama Maps and New Work」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年01月15日号)
西野壮平「Action Drawing: Diorama Maps and New Work」|村田真:artscapeレビュー(2016年01月15日号)
2020/04/02(木)(飯沢耕太郎)
王子直紀「吐噶喇・川崎」

会期:2020/03/29~2020/04/03
東京・新宿のphotographers’ galleryは、2001年に創設された。その立ち上げのメンバーのひとりである王子直紀は、同ギャラリーで「川崎」シリーズを発表し続けてきた。だが、このところ個展の開催が途絶えていて、本展は約6年ぶりの開催になるという。彼はその中断のあいだに、もうひとつのシリーズ「吐噶喇」を撮りためていた。今回は、この二つのシリーズを同時に見せることによって、写真家として次のステップに踏み込んだのではないかと思う。
「川崎」はモノクローム、「吐噶喇」はカラーで撮影されていることもあり、すべて縦位置という共通性はあるものの、両シリーズの印象はかなり違う。「川崎」のほうが風景を断片として切り取る意識が強く、被写体を突き放し、弾き出していくような視線の運動を感じる。それに対して「吐噶喇」はより求心的で、被写体との親和性が感じられ、南島の熱、匂い、湿り気などが伝わってくる。このような二つの対照的な場所を選び、微妙に撮り方を変えることで、明らかに王子の視点に厚みと奥行きが加わった。次は、両シリーズを単純に並置するのではなく、そのあいだをつなぐ構造を設定していくことが必要になるのではないだろうか。それがきちんとかたちをとっていけば、独自の「日本列島」の像が見えてくるのではないかという予感がある。
なお、展示に合わせて、それぞれ32ページのA5判変形の小冊子『吐噶喇1』(KULA)、『川崎1』(同)が刊行された。
関連レビュー
王子直紀「KAWASAKI」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2011年03月15日号)
王子直紀「牛島」/「外房」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2009年08月15日号)
2020/04/02(木)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)