artscapeレビュー
2024年02月15日号のレビュー/プレビュー
ホンマタカシ「東京郊外→オリンピア」
会期:2024/01/13~2024/02/10
TARO NASU[東京都]
ホンマタカシは1998年に写真集『東京郊外』(光琳社出版)を刊行した。バブル経済が破綻し、阪神・淡路大震災やオウム真理教事件の余波はあったが、どちらかといえばぬるめの希薄な空気感に包み込まれた1990年代後半の東京郊外の光景を、大判カメラで淡々と写しとったこの写真集は、翌年、第24回木村伊兵衛写真賞を受賞する。そのことで、現代写真の旗手としてのホンマの存在がクローズアップされていった。
それから四半世紀を経て、ホンマは再び東京にカメラを向けた。『Casa BRUTUS』誌の連載企画として、2015年から16年にわたって、東京オリンピックに向けて動いていく東京を主題として撮影を続けたのだ。今回のTARO NASUでの展示では、新たにほぼ同じ体裁の写真集として刊行された『Tokyo Olympia』(Nieves、2023)の収録作に加えて、旧作の『東京郊外』の写真も出品されていた。その二作を比較すると、1990〜2020年代にかけての東京がどう変わっていったのか、あるいは変わらなかったのかがくっきりと見えてくる。
ホンマの東京に対するアプローチの仕方は基本的には同じである。まさに「東京郊外」と言える田無市(現・西東京市)の出身である彼にとって、東京は特別な意味を備えた場所といえる。おそらく共感と違和感とを併せもって、少年期から青年期を過ごしていったのではないだろうか。その微妙なポジションが、醒めているようで、どこか安らぎや懐かしさも感じてしまう「東京郊外」の写真群に投影されているように見える。
「Tokyo Olympia」でも、見た目の印象はほとんど変わらない。だが、どちらかといえば違和の感情のほうが強まっているようだ。ここはもはや自分の居場所ではないという寂しさすら感じられる写真もある。それとともに、かつてはピカピカに光り輝いていた都市の表層に、緩みや綻びが目立ち始めている。いやあらためて見直すと「東京郊外」の写真にも、緩慢な滅びの気配のようなものがすでに漂っていた。ホンマは1990年代の時点で、現在の東京を包み込む空気感を先取りしていたということだろう。
©︎Takashi Homma Courtesy of TARO NASU[Photo: Keizo Kioku]
©︎Takashi Homma Courtesy of TARO NASU[Photo: Keizo Kioku]
©︎Takashi Homma Courtesy of TARO NASU[Photo: Keizo Kioku]
ホンマタカシ「東京郊外→オリンピア」:https://www.taronasugallery.com/exhibitions/ホンマタカシ「東京郊外→オリンピア」-2/
2024/01/13(土)(飯沢耕太郎)
梁丞佑「荷物」

会期:2024/01/12~2024/02/03
ZEN FOTO GALLERY[東京都]
韓国出身の梁丞佑(ヤン・スンウー)は。新宿・歌舞伎町や横浜・寿町などを根城とする人たちを、長期にわたって粘り強く撮影した写真群を発表してきた。今回の「荷物」もその延長上にある作品だが、偶発性を身上とするスナップ写真ではなく、明確に狙いを定めて撮影を続けてきた。
路上で生活するホームレスの人たち(そうでない人もいる)に声をかけ、彼らが所持している「荷物」をバッグなどから出してもらい、それらとともに彼らのポートレートを撮影するというのが、本シリーズのコンセプトである。この人が、こんなものを持っているという驚きを誘う「荷物」もあれば、なるほどと納得してしまうものもある。どちらにしても、そこに「人生が詰まっている」ことは間違いない。被写体となる人物たちに対する、梁の丁寧なコミュニケーションの取り方もあって、それほど数は多くないが、見応えのあるドキュメンタリーのシリーズとして成立していた。
2017年に第36回土門拳賞を受賞した『新宿迷子』(Zen Foto Gallery、2016)もそうなのだが、一見シビアな状況を撮影しているようで、梁の写真には不思議な明るさとユーモアがある。今回のシリーズでは、それがより強く発揮されているように感じた。梁自身が、鉢巻姿の「やん太郎」として自分の持ち物を路上に広げている写真もあり、遊び心のあるシリーズとして楽しむことができた。
梁丞佑「荷物」:https://zen-foto.jp/jp/exhibition/baggage
関連レビュー
梁丞佑「新宿迷子」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年03月15日号)
2024/01/13(土)(飯沢耕太郎)
オル太『ニッポン・イデオロギー』

会期:2024/01/13~2024/01/14
ロームシアター京都 ノースホール[京都府]
終わりのない肉体労働の搾取、共同体を形成する祝祭、歴史の反復構造といった観点から、日本の近現代を象徴する舞台装置のなかで、歴史/日常の遠近感を身体的に問うパフォーマンス作品を展開してきたアーティスト集団、オル太(井上徹、斉藤隆文、長谷川義朗、メグ忍者、Jang-Chi)。『超衆芸術 スタンドプレー』(2020)では東京オリンピックの新国立競技場の陸上トラックを、『生者のくに』(2021)では炭鉱の坑道を模した舞台空間のなか、パフォーマーたちは肉体労働に従事し、現代日本の日常的な光景の点描が連なっていく。
本作は、こうしたオル太の関心を、戦前から現在、そしてAIやロボットが労働を代替するようになる近未来までを射程に収め、全6章で描く大作である。上演時間は約6時間。
前半の1、2、3章では、会社員、女子高生、夫と妻、販売員、老婆、アナウンサーといった現代日本の匿名的なキャラクターたちの日常会話の点描のなかに、昭和天皇とマッカーサーが迷い込み、歴史の遠近を欠いた平坦な空間が展開していく。街頭の選挙演説カーも風俗求人広告カーも終戦詔書も「どこからか聞こえてくる機械越しの音声」であり、あらゆるものを等価に陳列し、脱政治化していく作用こそ政治的であることを突きつける。ミッキーマウスのカチューシャを付けたマッカーサーがセグウェイに乗って徘徊し、日本の民主化に関するGHQの指令文書を読み上げるが、彼が手にしているのは漫画本だ。「大人になれない日本人」にとって「アメリカ」とは「ディズニーランド」である。そして、(実際に1975年に訪米した)「夢の国」をひとり彷徨う昭和天皇の架空のモノローグにより、「排除」に支えられた巨大な消費のテーマパーク化に日本が覆われていく。あるいは、コロナ下の「自粛太り」解消のため、コンニャクダイエットが流行し、不足するコンニャクの増産が急がれているというニュースは、戦時下の工場で「風船爆弾」の制作に従事する若い女性たちや、無茶な増産を上官に命じられる軍人にスライドしていく。

[撮影:松見拓也]
パフォーマーたちの衣装には「菊の紋」「制服(軍隊/女子高生)」「高級ブランドロゴ」といった記号が張り付いているが、シーンの交替とともに次々と複数の役を担当することで、むしろ記号の表層性が強調される。発声の抑揚や身ぶり、表情は単調に抑えられ、出番外の者たちの身体はだらしなく寝そべり、モノのようにただ転がる。「ニッポンの空虚な退屈さ」を退屈な手法でひたすら並列化していく──ここには、いかにスペクタクルを回避するかという戦略が掛けられている。
一方、4、5、6章では、ロボットの労働や外国人が増加する「未来」への投射が「過去」へと接続され、沖縄と韓国に焦点が当てられる。そこに「フクシマ」「靖国」が絡み合う。排外意識や偏見は空気のように舞台空間に浸透している。親しみを込めたつもりで老婆に「ヨボさん」と呼びかけられた韓国人女性が示す拒絶(韓国語で「ヨボセヨ」は「もしもし」を意味する)。「外国人観光客があんまり増えてほしくない」という「本音」。平和教育とは戦時中に殺処分された『かわいそうなぞう』であると答える加害の忘却。福島に来たけど、刺身は食べないようにしようと言う夫婦の会話。「女はナメられるから田舎に住みたくない」と言う妻に対して、「そんなことないよ」と否定する夫には見えていない性差別。そうした無意識の断片に散りばめられているからこそ見えにくい、「コミュニケーション」に埋め込まれた権力構造や日常のなかの微妙な政治性をオル太は丁寧に拾い集めていく。一方、「大文字の政治」は徹底して戯画化される。「原発処理水の放出」はピノキオの人形の「放尿」として表現され、戦前のアジアの地図に向けて日の丸と菊のダーツが投げられる。

[撮影:松見拓也]

[撮影:松見拓也]
過去作品でもパフォーマーたちは、競技場のレールの上でトレーニングマシンを押して周回させ続けるといった労働に従事していたが、本作でも、パフォーマーを乗せた座席や段ボール箱を人力で押して運ぶ労働が基底をなす。そこには、戦前に結婚して朝鮮半島に渡った日本人女性が、終戦後に日本国籍が剥奪されたため、「荷物」の扱いで返還されたというエピソードが重なり、モノとして扱う人権意識が示される。自動開閉する透明なドアは、満員電車のドアであり、出入国管理のゲートであり、偏在する透明な境界線となる。
アーティストが「自主規制」してしまう、いや私たちが普段「政治的な話題だから」と口に出すのをはばかるトピックを、オル太は躊躇うことなく、これでもかと舞台にのせていく。「内面化された検閲」もまた、ニッポンを構成する見えにくいイデオロギーだからだ。

[撮影:松見拓也]
6時間という長さの必要性が伝わってくる舞台。同時に上演時間の長さは、身体のモードが「本気でやっているわけではないメタ演技」に常に拘束・回収されてしまうというジレンマやアポリアを感じさせた。過去作品と同様、本作にもオル太メンバーに加え、俳優やダンサーが出演する。ただ、右翼やレイシストの発言は「本気で言っているわけではない」という体栽が必要であり、無邪気に踊られるダンスは、(例えば「建国体操」のように)「素人の身体」が国家によって集団的に規律化されていく事態を示す必要がある。あるいは、「覇気のないシュプレヒコール」は、主体的な意志を欠いた集団感染的な不気味さとして示される。そのため、舞台上には、「〜を演じているモード」か、ゾンビのように不活性で弛緩した身体が提示される。
このことがアポリアを超えて両義性を感じさせたのが、終盤で流れる「君が代」のシーンである。だらりと頭を垂れた無言の身体が柱のように突っ立つ。そこではもはや、意志を奪われ絶望的に下を向いているのか、敬虔に頭を垂れているのか、区別不可能だからだ。

[撮影:松見拓也]
オル太『ニッポン・イデオロギー』:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/108622/
関連レビュー
オル太『生者のくに』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)
2024/01/14(日)(高嶋慈)
長船恒利「在るもの」
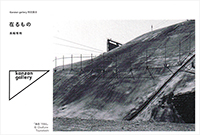
会期:2023/12/23~2024/01/28
Kanzan Gallery[東京都]
北海道小樽市出身の長船恒利(1943-2009)は、1970年代後半以降の自主運営ギャラリーを舞台とした作家活動において重要な役割を果たした写真家である。静岡県藤枝市を拠点に、仲間たちと「写真集団GIG」を立ち上げ、東京のギャラリーPUTでの個展や「今日の写真・展 77」(1977)、「視覚の現在」(1979)などの企画展にも積極的に参加した。今回展示された「在るもの」は、1977~79年にかけて発表された、長船の代表作といってよい作品である。
大判カメラによって撮影された都市の日常の光景は、画面の細部まで緊密に描写・構成され、完璧な諧調のモノクローム・プリントとして提示されている。それらは、当時の若い写真家たちによって展開された、現実世界の単なる写しではない、それ自体が独自の質感と構造を備えた「写真」の追求の極限というべきシリーズである。「写真による写真論」あるいは「写真論写真」とも称された「コンセプト・フォト」のスタイルを、最も純粋に探求していったひとりが長船であったことを、今回の展示であらためて確認することができた。
だが長船は1980年代以降になると、写真家という枠組みを超えた、より多面的なアーティスト活動を展開していくようになる。「在るもの」の続編というべき、クオリティの高い写真作品の制作はもちろんだが、パフォーマンス、プリペアド・ピアノの演奏、石彫なども試みた。後期の、写真以外の仕事も含めた彼の全体像を浮かび上がらせる展覧会をぜひ見てみたい。
長船恒利「在るもの」:https://sites.google.com/kanzan-g.jp/home/exhibitions/長船恒利-osafune-tsunetoshi
2024/01/18(木)(飯沢耕太郎)
シルエットファミリー展

会期:2024/01/18~2024/01/21
大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco][大阪府]
日本で出産・子育てを行なっている性的マイノリティを「家族写真」として可視化する写真展。性的マイノリティの出産や子育てを支援している一般社団法人こどまっぷが企画し、アーティストの澄毅が撮影と作品制作を行なった。写真展は、大阪公立大学による「EJ(Equity&Justice)芸術祭」の一部として開催された。「こどまっぷ」代表理事の長村さと子自身が女性パートナーと育てている子どもをはじめ、10組の家族写真と親から子へ宛てた手紙の文章、映像作品が展示された。

シルエットファミリー展 会場風景
澄毅は、主にポートレート写真に無数の穴や波打つ線のようなスリット(切れ込み)を開け、光を透した写真作品を手がけてきた。プリントアウトした写真に穴を開け、裏側から光を当てて再撮影する手法は、写真が物質的な媒体に依存することと同時に、「光の痕跡」を見ていることにほかならぬことを示す。それは、ロラン・バルトが『明るい部屋』で述べた写真論──「それはかつてあった」という写真の本質は、ほかの表象=再現の体系とは異なり、対象から発せられた光が感光性物質によって直接固定されることで保証される──と接続される。

《hikari》[© Takeshi Sumi]
同時に澄の作品は、写真と「光」をめぐるさまざまな両義性をはらむ。写真すなわち光学的装置によるイメージの複製であると同時に、「光を透す」ことで唯一性が刻印されること。被写体から放射され、発光しているかのような「光」は、「光によって像が焼き付けられた」という実在性の保証であると同時に、強い逆光を浴びたかのように顔が隠され、イメージは光の中に溶解していく。それは、「写真を見ること」が、「あたかもある星から遅れてやって来る光のように、私に触れにやって来る」★という被写体との紐帯の回復作業であると同時に、記憶の空白や欠落、忘却をも示唆する。
こうした「光」の両義性を、写真論の範疇を越えて改めて意識させたのが、李琴峰の小説『ポラリスが降り注ぐ夜』(筑摩書房、2020)の表紙に澄の作品が使用されたことだった。李の小説は、新宿二丁目にあるレズビアンバー「ポラリス」に集う客や店主を7つの連作短編の主人公に据え、レズビアン、バイセクシュアル、トランス女性のレズビアン、アセクシュアルなどさまざまなセクシュアリティや国籍をもつ女性たちを描く群像劇である。連作短編の巧みな構造を通して、各編の主人公たちの語りが星座のように連なり、その光がポラリス(北極星)のようにいまだ暗い闇夜を照らす指針となる──そのような読後感を抱く小説だ。そして、暗い影になった女性の頭部から、光の粒がこぼれ落ちる澄の写真はこう語りかける──これは光であり、同時に傷である。内側に抱えた傷だが、そこから光がこぼれ出し、照らすのだ、と。
一方、近年の澄は、写真に光の軌跡のような刺繍を施す作品も発表している。本展では、写真に光を透す手法は映像作品として実験的に発表され、プリントに糸で刺繍を施した写真作品10点がメインの展示となった。子どもを抱いて桜を見上げる男性カップルや、子どもと並ぶ女性カップルなど、ありふれた記念撮影的な構図だが、(数人の親を除き)顔や表情は光や星をかたどった刺繍で覆われ、見えない。だが、それぞれの親による文章が添えられ、子どもをもつことを決めた経緯や心境、パートナーと子どもへの愛情が綴られている。

《空にいる君と一緒にみている》[© Takeshi Sumi]

《小さかった君におんぶされた日》[© Takeshi Sumi]
刺繍が選択された最大の理由には、プライバシーの問題がある。「顔を出せない」という社会からの抑圧を、モザイクをかけるのではなく、被写体自身が不快に感じないようなやり方で、どう可視化し、表現として昇華できるか。写真の刺繍は、子どもから光が発したり、親と子を包み込むように施され、視覚的にポジティブなメッセージを放つ。同時にそこには、「いつか糸をほどくことができる未来になってほしい」という願いも込められている。
性的マイノリティのポートレートのなかでも、「子どもも含めて家族を撮影したもの」は少ない。日本は同性婚が法的に認められていない国であり、出産・子育てしている性的マイノリティの存在はほぼ不可視化されている。本展で取り上げられたのは10組だが、「性的マイノリティの家族」と一言で言っても、多様なあり方が示されている。レズビアンカップル、ゲイカップル、トランス男性とその女性パートナー、Xジェンダー(男女のいずれにも属さない、もしくは流動的な性自認)の親と子ども、片方が外国籍のカップル……。海外の精子バンクを利用して出産した女性は、子どもが「ハーフ?」とよく聞かれることを綴り、複合的な差別構造を示す。
光や星をかたどった刺繍は、一見ポジティブに見えるが、画面に近づくと、(光を透して再撮影した写真作品が「一枚の滑らかな表面」であることとは対照的に)、「糸」のもつ触覚性や物質的な抵抗感を感じる。それは社会的な抑圧の物質化でもある。従って、問われるべきは、「なぜ、
★──ロラン・バルト『明るい部屋―写真についての覚書』花輪光訳、みすず書房、1985、p.100。
公式サイト:https://eandjart.jp/program/107
2024/01/20(土)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)