artscapeレビュー
2012年03月01日号のレビュー/プレビュー
riya個展「11」eleven
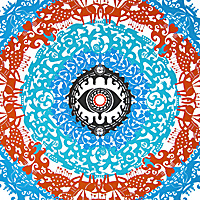
会期:2012/02/01~2012/02/21
DMO ARTS[大阪府]
着色した紙を即興的な感覚で切り抜き、人間、動物、星、雲、炎、波、眼などのモチーフを組み合わせたグラフィカルな平面作品。洗練された現代性とスピリチュアルな世界観をナチュラルに融合させているのが興味深い。DMO ARTSでは、オリジナル作品を15部限定のジークレー版画にして9,800円で販売する初心者向きカテゴリー「MY FIRST ART」を展開しているが、そこでも彼女の作品は好調なようだ。本展で初めてオリジナル作品を見て、なるほどこれは売れるはずだと納得した。
2012/02/01(水)(小吹隆文)
預言者

会期:2012/01/21
ヒューマントラストシネマ渋谷[東京都]
近年稀に見るフィルム・ノワールである。ジャック・オーディアール監督が描き出したのは、入獄した若い受刑者の男が刑務所内の社会でなんとか生き延びていくプリズン・ドラマ。孤独から出発しながら組織の底辺に組み込まれ、知恵を働かせながら対立する組織とうまく折衝していき、やがて組織の上へのし上がってゆく。アラブ系主人公のいかにもチンピラ風の顔と身ぶりが断然よいし、人道的な老人に扮した『サラの鍵』から一転して冷酷なコルシカ・マフィアを演じたニエル・アリストリュプの佇まいも味わい深い。閉ざされた刑務所社会の暗鬱とした空気感と、陰惨な暴力描写には言いようのないほどの恐怖を覚えるが、その一方で不可能にしか思えない困難な局面を切り抜けていく鋭い知性とたくましい根性のありようが、とてつもなくすばらしい。人間が生きる技術、すなわちアートが、すべて描き出されているといってもいい。たとえば権力を握るにつれて、主人公は刑務所の内外を往来するようになるが、日本とフランスの制度上のちがいに驚かされることに加えて、ここには人間社会の境界線を超えていく想像力が表現されているように考えられるからだ。刑務所社会に育てられたともいえる主人公にとって、一時的に出向くことができる刑務所の外のシャバは刑務所社会の延長でしかなかったし、そのことは完全に出獄したとしてもおそらく変わらないことは、ラストシーンで象徴的に描かれている。あの名作『ビューティフル』と同じように、画面に特定の死者がはっきりと映り込む設定にしても、この世の人間とあの世の人間の境界を軽やかに乗り越えていく想像力の表われにほかならないし、異民族のあいだを行き来する主人公も、その想像力を身をもって体現していると言えるだろう。そもそも「預言」という才覚ですら、現在と未来の境界線を部分的に溶解する技能として考えられる。この映画から得られるのは、人為的に構成されたありとあらゆる境界線を超越する根源的な想像力のありようである。社会の制度疲労がもはや隠しようがないほど明らかになっているいま、もっとも必要されているのは、このイマジネーションだ。
2012/02/01(水)(福住廉)
宮永亮 "scales"

会期:2012/01/14~2012/02/11
児玉画廊[京都府]
昨年秋に東京のgallery αMで発表した映像インスタレーション《arc》から、映像だけを抜き出したものと、新作《scales》を出品。宮永は国内外各地を訪れては映像を撮影し、そのストックを組み合わせて作品を制作している。《arc》は震災前と後の東北の情景と大阪のビル街や高速道路などが混然一体となったもので、《scales》はスウェーデンを訪れた際に撮った映像を巻物のような横長の画面に縦横に展開していた。どちらも夢幻的な作風で、人間の記憶はこういう形で保存されているのかな、と思ったりもした。
2012/02/02(木)(小吹隆文)
解剖と変容:プルニー&ゼマーンコヴァー チェコ、アール・ブリュットの巨匠

会期:2012/02/04~2012/03/25
兵庫県立美術館[兵庫県]
フランス・パリの、非営利団体abcdが所蔵する世界有数のアール・ブリュット・コレクションから、チェコ人のアンナ・ゼマーンコヴァーとルボシュ・プルニーの作品を展覧。併せて、アール・ブリュットの歴史や作家を紹介する長編ドキュメンタリー映画『天空の赤』の上映と同作品に登場する作家の作品展示を行なっている。ゼマーンコヴァーは普通の主婦だったが、子育てを終えた後の虚無感を埋めるかのように絵画制作を始め、独自の花や植物を描いた。プルニーは、内臓や骨格などへの関心を表現した平面作品を制作し、尋常ならざるテンションと反復に満ちた世界を構築している。2人の質の高い作品と映画を組み合わせることで、アール・ブリュットの魅力と本質をわかりやすく伝えているのが本展の見どころだ。記者発表時にabcdのブリュノ・ドゥシャルムは「作品の選択はあくまでコレクター目線で審美的に行なっている」と明言した。その意味で本展は、美術と教育と福祉の価値観が混在している日本のアール・ブリュットに対するひとつのメッセージとも言えるだろう。
2012/02/03(金)(小吹隆文)
金魚(鈴木ユキオ)『揮発性身体論「EVANESCERE」/「密かな儀式の目撃者」』

会期:2012/02/03~2012/02/05
シアタートラム[東京都]
鈴木ユキオは真面目な作家だ。真面目すぎるのではと疑問を抱くこともこれまであった。しかし、杞憂だったのかもしれないと本作を見て思った。彼の真面目さの向かう先が本作で明らかになった。
本作のタイトルに用いられている「揮発性身体論」とは、筆者が聞き手となったアフタートークでの鈴木の発言によれば、ものが常温で蒸発するイメージを指しているという。2007年の『沈黙とはかりあえるほどに』の時点でつくりだそうとしていた〈強い身体〉〈過剰な身体〉は、見る者に過度にエモーショナルな(言い換えれば「熱い」)印象を与えるところがあった。その点を反省して鈴木が発案したのは「常温」で「蒸発」する「揮発性」の身体というコンセプトだった。「常温」と聞くと、熱すぎず冷たすぎず、ゆえになにも起きない、なんでもない、だからつまらないのでは、といったネガティヴな連想が起こるかもしれない。なるほど本作においても記号として掴みにくいダンサーたちの動きが「アンビエント・ミュージック」に似た「眠さ」を感じさせたことは事実だ。けれども集中して見れば、ダンサーたちの「常温」(いわばゼロ)の身体が、プラス極の力(ある力)とマイナス極の力(ある力に拮抗する別の力)の合計によって成り立っていることに、観客は気づいたはず。常に身体に諸力の拮抗が起きていて、そこにズレが生まれると、そのズレが運動=ダンスとなる。スリルをはらんだ緊張をエモーショナルな外見抜きで呈示すること。「揮発性身体論」とはさしあたり、そうした純粋に運動であることを目指すダンス論と言えるだろう。
そう、鈴木が求めるのは純粋にダンス的なものである。排除すべきは非ダンス的なもの、例えばそれはエモーショナルな、あるいは芝居がかった、あるいは単に記号的な動作だろう。ダンスをダンスに返す、一種の還元主義的なモダニズムが鈴木の真面目さの真髄なのだ。
とはいえ、鈴木を単なるモダニストとカテゴライズするのは危険だ。鈴木が志向するのはモダニズムというより純粋にダンス的なもののはずだから。身体の拮抗を持続すること、言い換えれば、身体が狂気の状態であり続けること。前半のソロ作品(「「EVANESCERE」」)で強く感じられたその方向が、後半の女性たちによる作品(「密かな儀式の目撃者」)になるとまだ曖昧になるところがあり、もっと完成度をあげるべきではと思わされた。しかし、壺中天とも大橋可也&ダンサーズとも異質な、グループでありながらダンサー各自の存在感の強さを求める意図はよく伝わったし、すぐエモーショナルなものを表わそうとしてしまうモダンダンスのダンサーではなく、また舞踏の踊り手でもなく、バレエのスキルが浸透している(ゆえに垂直性がしっかりある)ダンサーの身体で自分の理想を実現したいという独自の狙いや、そこで生み出そうとする質の高さも感じられた。鈴木のソロで堪能できるズレのダイナミズムが「振り付け」というレディ・メイド(理念的には誰もがやってみることのできる動作)においても温存されていること、それが鈴木の出演しないグループ作品での目標であるならば、険しいかもしれないが登ってみて欲しい山だと強く思わされた。
鈴木ユキオ新作「揮発性身体論」 Yukio Suzuki "Volatile body"
2012/02/04(土)(木村覚)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)