artscapeレビュー
2016年03月15日号のレビュー/プレビュー
本城直季「東京」

会期:2016/02/12~2016/03/28
キヤノンギャラリーS[東京都]
本城直季は2006年頃からヘリコプターからの空撮で東京を撮影しはじめる。主に「空気が澄んで遠くまで見通せる」正月の3カ日を選んで撮影を続けたという。それら、使い慣れた4×5インチサイズの大判カメラで撮影された写真群に、高画素のCanon EOS5Dsを使った近作を加えたのが、今回のキヤノンギャラリーSでの展示である。
デジタル一眼レフカメラでの撮影は、本城に大きな解放感をもたらしたようだ。フィルムホルダーを取り替えてセットし直さなければならない大判カメラでは、1回の飛行で撮影できるのは、せいぜい30~40カットほどだ。デジタルカメラなら撮影枚数の制限はなくなる。さらに、ちゃんと写っているのかと心配することなく、安心してのびのびとシャッターを切ることができる。そのことによって、「東京をスナップする」という感覚が強まってきた。
さらに、今回の展示で本城は大きな決断をした。画面の一部にのみピントを合わせて、あとはぼかすことで、ミニチュアのジオラマのような視覚的効果を生じさせる従来の手法の作品と、画面全体にピントが合っている作品とを並置しているのだ。結果的に、つねにうごめきつつ増殖していく巨大都市「東京」の変貌のプロセスを、多面的に定着することができたのではないかと思う。また今回の展示は、あえて東京タワーのようなランドマーク的な建造物を外した作品で構成している。「どこまでも果てしなく続く密集した建造物の景色」に限定することで、「東京」という都市の基本的なエレメントが、くっきりとあぶり出されてきた。120×150センチという大判プリントによる細密描写も含めて、「デジタル化」が彼の作品世界をどう変えていくかが楽しみになってきた。
2016/02/13(土)(飯沢耕太郎)
藤本由紀夫 Broom(Coal)/Tokyo
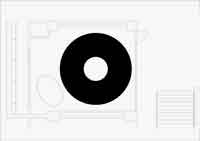
会期:2016/02/06~2016/03/06
シュウゴアーツ ウィークエンドギャラリー[東京都]
ギャラリーいっぱいに黒い石が円環状に敷かれている。石は黒光りしているので石炭とわかる。一瞬リチャード・ロングを想起したが、上を歩いてもいいというのでジャリジャリいわせながら歩いてみる。円環に沿って歩いているうちに、あ、これはレコード盤だと気がつき、自分がレコード針になった気分。「Broom(ほうき)」と題されたこの作品、最初は床に枯れ葉を敷きつめるインスタレーションから始まり(最初に発表した会場が「room B」だったので「Broom」になったとか)、次第に素材や形態を変えながら石炭のレコード盤になったという。考えてみれば石炭はレコード針に使われるダイヤモンドと同じ元素だ。横のテーブル上にはオルゴールを使った小品がいくつかあって、歯が全部そろってる手巻きオルゴールがひとつ、あとは歯が1本しかないもの、ぜんぜんないものなど。さすがに歯が1本だけではなんの音楽かわからない。また、箱のなかにオルゴールが二つ入っていて、ひとつは右から1、3、5……という奇数番目の歯、もうひとつは2、4、6……という偶数番目の歯しかない。同時に鳴らしても同調しないが、なんの曲かはなんとなくわかる。オルゴールひとつでこれだけ遊べるとは。
2016/02/13(土)(村田真)
京都市立芸術大学芸術資源研究センターワークショップ「メディアアートの生と転生──保存修復とアーカイブの諸問題を中心に」

会期:2016/02/14
元・崇仁小学校[京都府]
アーティスト・グループ、「Dumb Type」の中心的メンバーだった古橋悌二が1994年に制作した《LOVERS─永遠の恋人たち─》(以下《LOVERS》と略記)。水平回転する7台のプロジェクターによって4つの壁に映像が投影される本作は、コンピューター・プログラムによる制御や、観客の動きをセンサーが感知するインタラクティビティが組み込まれ、男女のパフォーマーによる映像と音響の作用に全身が包まれる。この作品を、「トレース・エレメンツ」展(東京オペラシティアートギャラリー、2008年)で見た時の静かな衝撃をよく覚えている。
京都市立芸術大学芸術資源研究センターでは、文化庁平成27年度メディア芸術連携促進事業「タイムベースト・メディアを用いた美術作品の修復/保存に関するモデル事業」として、《LOVERS》の修復を行なった。修復を手がけたのは、アーティストでDumb Typeメンバーの高谷史郎。修復された《LOVERS》の公開とともに、メディアアートの保存修復やアーカイブ事業に取り組むアーティスト、学芸員、研究者による発表とディスカッションが開催された。
修復を手がけた高谷からは、今回の修復の概要と、メディアアート作品に不可避的に伴うテクノロジーの劣化や機材の故障といった問題にどう対応するかが話された。メディアアートの修復作業とは、あくまでも「その時点での技術的ベスト」の状態であり、オリジナルの状態の復元ではなく、どの要素をキープしてどこを変更するかが問われる。さらに、現時点での「修復」の将来的な劣化を想定する必要がある。今回の修復では、主にプロジェクターを最新機器に交換するとともに、「古橋がこう想像していただろう」と考えられるアイデアルの状態を想定し、デジタル化した元のアナログヴィデオの映像をもとに「次の修復」に備えたシミュレーターの作成が行なわれた。つまり、映像をデータとして解析・数値化することで、今回の修復に関わったスタッフがいなくても、プログラマーが読み込んで再現・検証が可能になるという。
このシミュレーターの役割について、同研究センター所長でアーティストの石原友明は、音楽やダンスにおける「記譜」との共通性を指摘した。また、メディアアーティストの久保田晃弘は、メディアアート作品には、技術の更新とともにアップデート・変容していく新陳代謝的な性質が内在しているという見方を提示した。こうした視点によって、メディアアートの保存修復について、時間芸術や無形文化財の保存・継承のあり方と関連づけて考えることが可能になるとともに、現物保存の原則や「オリジナル」作品概念の見直し、技術や情報をオープンにすることの必要性などが求められる。また、ディスカッションでは、これからの課題として、美術館における作品収集の姿勢の柔軟性、メディアアートの修復技術者の養成、「作品の保存修復」を大学教育で取り組むこと、展示状態の記録や関係者のインタビュー(オーラルヒストリー)を集めることの重要性、といったさまざまな指摘がなされた。
タイムベースト・メディアを用いた美術作品の収集・保存に対して美術館が躊躇していれば、数十年前の作品が見られなくなってしまいかねない。これは、将来の観客の鑑賞機会を奪うだけでなく、検証可能性がなくなることで、批評や研究にとっても大きな損失となる。《LOVERS》の場合、エイズの危機、セクシュアリティ、情報化と身体、個人の身体と政治性といった90年代のアートの重要な主題を担っている。歴史的空白を残さないためにも、アーティスト、技術者、美術館、大学、研究者が連携して保存修復に取り組むことが求められる。
暗闇に浮かび上がる、裸体の男女のパフォーマー。水平のライン上を歩き、走ってきてはターンし、歩みよったふたりの像が重なりあい、あるいは出会うことなく反対方向へ歩き去っていく。両腕を広げ、自分自身の身体を抱きしめるように、あるいは不在の恋人と抱擁するように虚空を抱きしめ、孤独と尊厳を抱えて背後の暗闇に落ちていく。歩行と出会い、すれ違いと抱擁を繰り返す生身の肉体を、2本の垂直線がスキャンするように追いかける。線に添えられた、「fear」と「limit」の文字。生きている身体、その究極の証としての愛が、相手に死をもたらすかもしれないという恐怖。情報と愛という二極に引き裂かれながらも、パフォーマーたちの身体は軽やかな疾走を続けていく。今回の《LOVERS》の公開は、修復作業の設置状態での鑑賞だったため、本来は等身大で投影される映像が約半分のサイズであり、床面へのテクスト投影もなかった。今回の修復を契機に、完全な状態での公開が実現することを願う。
2016/02/14(日)(高嶋慈)
イシャイ・ガルバシュ「The long story of the contacts of “the other side”」

会期:2016/01/15~2016/02/28
Baexong Arts Kyoto[京都府]
2016年1月に京都市南区にオープンしたBaexong Arts Kyotoで、イスラエル出身の写真家、イシャイ・ガルバシュの「壁」シリーズが展示された。北アイルランドのピースウォール、韓国の38度線の壁、パレスチナウォール。大判カメラで細部まで捉えられた写真では、ごく普通の住宅街の中に異物のように立つ壁が、鉄条網や「地雷注意」の看板とともに威圧感を与える壁が、写し取られている。北アイルランドのベルファストで撮影された写真では、レンガ作りの住宅のすぐ隣に壁が立ち、その上にフェンスが空高くそびえている。これらの写真は、無人の住宅街や幾何学的な配置が冷たく硬質な印象を与えるが、一方、韓国で撮影された写真では、風景の中に人の気配や痕跡が入り混じり、そのゆるく笑いを誘うような脱力感が、場所の政治性や緊張感を和らげ、あるいは逆説的に増幅させる。軍事境界線の南北に設定されたDMZ(非武装中立地帯)のさらに南側に設定された民間人統制区域内では、防空壕の側に、観光客向けの「撮影スポット」が用意されている。つくりものの鶴とキムチを漬ける壺の背後に描かれた、ペンキの青空。ひなびたハリボテ感と遊園地のような空虚な明るさが、「観光客」向けに用意されたイメージの背後にある政治性を露出させる。一方、北朝鮮との軍事境界線に近い島では、畑の中に場違いな事務イスで「休憩所」がつくられている光景や、過疎化のため打ち捨てられた車の教習所の敷地が唐辛子を干すために無断借用されている光景など、政治的緊張と隣接した中に、日常生活が営まれる場でもあることが示される。そして、道路沿いの草取りしか仕事がない、低所得者の老婦人たちが笑顔で並ぶ写真。国境に近い周縁は、経済的な周縁地域でもある。
境界線を示す「壁」は、物理的な分断、隔離、権力の誇示、攻撃を受けることへの恐怖を体現する。現在の日本には、こうした物理的な「壁」はないが、心理的な境界線はないと言えるだろうか。ここで、展示場所となったBaexong Arts Kyotoの位置する地域が、歴史的にさまざまな差別や抑圧を押し付けられてきたことを考えるならば、本展は、物理的に可視化された「壁」の提示を通して、私たちに内在する見えない「壁」の存在をあぶり出すものであったと言えるだろう。
2016/02/14(日)(高嶋慈)
気仙沼と、東日本大震災の記憶

会期:2016/02/13~2016/03/21
目黒区美術館[東京都]
震災から5年、宮城県気仙沼市のリアス・アーク美術館が調査・記録した被災現場写真を中心に、家電やパソコンなどの被災物、過去の震災や津波の資料など約400点を借りてきて展示している。なぜ目黒区美術館でやるのかというと、1996年から続く「目黒のさんま祭」に気仙沼市がサンマを提供してきたからだそうだ。こうした食文化のつながりというのは意外と堅固で納得できる。さて、展示のほうは200点を超す写真が圧巻。といっても写真自体は大きくないし、驚くような光景が写されてるわけでもなく、こういってはなんだがもはや見慣れた被災地の風景ばかり。なのに目を釘づけにしてしまうのは、1点1点に150-200字程度のコメントがつけられ、言葉とイメージのダブルパンチで揺さぶりをかけてくるからだ。撮影者が地元の人であることも説得力があるし、また彼が美術館学芸員であるせいか、被災地や被災物にある種の美しさやおもしろさを見出そうとしているようにも感じられるのだ。例えばJR気仙沼線のレールがめくれ上がり、まるでジェットコースターみたいに裏返っていたり、津波で建物2階に運ばれて息絶えた魚の軌跡が乾いた泥に印されていたり、冠水した路地に建物が映る様子がヴェネツィアの運河を連想させたり。「破壊は美を奪い『醜さ』を生み出す」とコメントにあるが、そこにまた別の「美」を見出してるようにも見える。もちろん言葉とイメージだけですべて伝わるわけでもないだろう。おそらくここに決定的に欠けているのは「匂い」ではないか。大量のサンマが腐ってどす黒い塊と化した写真のコメントには「匂いのレベルが違う」「体が震えだし、身の危険を感じた」と書かれている。そして匂いは記憶のもっとも古層に沈潜し、ふとしたはずみに蘇る。これは美術館では伝わらない。
2016/02/14(日)(村田真)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)