artscapeレビュー
2016年03月15日号のレビュー/プレビュー
村上隆のスーパーフラット・コレクション──蕭白、魯山人からキーファーまで

会期:2016/01/30~2016/04/03
横浜美術館[神奈川県]
陶芸から現代美術まで、村上隆が個人的にコレクションしてきたものが、圧倒的な量で大空間を埋めつくす。いつもは吹抜けがデカ過ぎて、欠如を感じる横浜美術館が充満している雰囲気が素晴らしい。また彼の好みを読み解いたり、作品そのものを鑑賞したりするなど、楽しみ方もさまざまに開かれている。これは、どこかで常設の展示か、美術館になってほしい。
2016/02/14(日)(五十嵐太郎)
オペラ「夕鶴」
会期:2016/02/14
神奈川県民ホール[神奈川県]
戦後間もなく團伊玖磨が挑戦した日本語のオペラの実験である。メロディはちょっと地味だったが、山田耕筰が確立したものとは違う方法で、日本語をメロディにのせる試みを行なっており、おそらく方言が使われているのもそれと関係していると思われた。主役のつうは、佐藤しのぶ。縦長のスクリーンの移動と、傾いた廻り舞台だけでさまざまな場面を演出する。雪景色の美術は千住博、多色を用いた衣装デザインはカーテンコールで登壇した森英恵が担当した。
2016/02/14(日)(五十嵐太郎)
What Price Your Dance ダンスと仕事とお金についてのおもろい話とパフォーマンス

会期:2016/02/14~2016/02/15
Art Theater dB Kobe[兵庫県]
川口隆夫、砂連尾理、カンボジアの古典舞踊手のポン・ソップヒープ、マレーシアの古典舞踊手のナイム・シャラザード。国籍、年齢、セクシャリティ、ダンスの経歴、受けた教育、文化的背景もそれぞれ異なる4人のダンサーが、「アジアにおけるアートのための労働とダンスの経済」について言葉と身体による対話を行なう、レクチャー・パフォーマンスである。
冒頭ではまず、「あなたの生計を教えてください」という質問が英語でなされる。非常勤講師とダンス公演とワークショップと答える砂連尾、古典舞踊の教師と音楽のバイトだと言うソップヒープ、翻訳業と舞台公演が半々を占めると言う川口、舞踊団からのギャラで生計を立てていると言うシャラザード。4人の答えはバラバラだ。続けて、「あなたの手、足、胴体で何か見せてください」という質問と、それぞれの身体部位の「値段」が質問される。「値段は付けられない」と言う者、手羽先やスペアリブと比較して冗談交じりに答える者。だが、上半身をはだけた年若いシャラザードが、傍らの川口に「How much?」と問いかけるとき、臓器売買や売買春とのきわどい交差の中に、観客=ダンサーの身体を「見る権利」を買っている存在であることが仄めかされる。
続くシーンでは、「これまでのダンスで得た総額」「月収と支出の内訳」「公演制作費、ギャラの時給換算」「ダンス教育にかかった時間の総計」といった経済、労働に関する質問がなされる。それは、ダンサーの置かれた経済的状況について、「表現、身体、文化的支援、資本主義」に関する問いを投げかける。しかし、「お金」と「時間」と「(身体)資本」という資本主義経済の単位に還元してダンスの価値を測ろうとすればするほど、そこからはみ出さざるをえない豊かな剰余の部分が際立ってくる。それは、ダンス/ダンス以外でのさまざまな差異をもった出演者どうしが、身体的な交流のなかから動きを即興的に立ち上げていくシーンである。砂連尾とソップヒープは、合気道と古典舞踊を互いに教え合う。コンテンポラリー・ダンスに関心をもつシャラザードは、川口に「最初の振付作品を見せて」と頼み、振り写しのなかから即興的な動きが触発されていく。相手の動きを受け取って、どんどん次の動きを生み出していく、緩やかな連鎖反応。一方、砂連尾とソップヒープは、「2人の掌の間に見えないボールがある。その感覚をキープしたまま、空間をゆっくり広げていく」というワークを始め、見えない糸の繋がりが、空間的に隔たった2人の身体を動かしていく。
一方で、ソップヒープが見せるソロは、「ダンスとグローバリゼ─ション」という問題を提起する。彼は、持ち役の「猿の踊り」を力強く披露するが、この役には肉体の俊敏さや若さが求められるため、舞踊団では年齢的にもう踊れないと言う。「カンボジアにコンテンポラリー・ダンスが入ってきたのは2005年頃とまだ新しいが、自分にとってコンテンポラリー・ダンスは貴重な収入源だ」と話す。そして、古典舞踊のテクニックや培われた身体の強靭さをベースに、「砂連尾と一緒に作っている」と言う新しい作品の一部を披露する。それは、古典舞踊の動きや身体観と融合した「新しいダンス」を生み出すのだろうか。それともグローバルな市場においては、古典舞踊のエッセンスは商品価値を高める差異に過ぎず、「新たな商品」として消費の対象になるのだろうか。
2016/02/15(月)(高嶋慈)
映画『もしも建物が話せたら』先行上映イベント 第2回:建築系ラジオ公開収録! シネマアーキテクチャー番外編「建築を声で届ける意義」
会期:2016/02/15
渋谷アップリンクFACTORY[東京都]
アップリンクにおいて、映画『もしも建物が話せたら』のトークイベントを行なう。これは30分弱×6作品のオムニバスである。制作総指揮のヴェンダースによる《ベルリン・フィルハーモニー》に始まり、《ロシア国立図書館》、《ソーク研究所》、《ハルデン刑務所》、《オスロ・オペラハウス》、《ポンピドゥー・センター》を異なる監督が撮影したものだ。いずれも手法が異なり、それらを比較すると興味深い。カリム・アイノズ監督による《ポンピドゥー・センター》は、建築がわれわれを冷徹に見つめ、ボヤく感じだし、俳優のロバート・レッドフォードが監督したソークは社会派ドキュメンタリー風、そしてヴェンダースによるフィルハーモニーは人を追いかけながらカメラが動く。映画を見ながら、建物が話すような感じの建物解説の音声サービスがつくれるのではないかと思う。
2016/02/15(月)(五十嵐太郎)
森永純「WAVE」
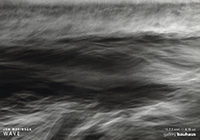
会期:2016/02/03~2016/04/16
gallery bauhaus[東京都]
寄せては返す波をずっと見ていると、次第にトリップ状態に入っていくことがある。単調なように見えて、一つひとつの波の形や変化の仕方には微妙な違いがあり、その表面で起きる出来事はひとつとして同じものはない。波の繰り返しに身を任せていると、自分がどこにいて何をしているのか、目眩とともに足下から揺らいでくるような気分になるのだ。
森永純も「ある年の5月」に、千葉の海岸に撮影行って防波堤に打ち寄せる波を見ているうちに、そんな状態に陥っていったようだ。「太陽熱と心地よい波の揺れのせいで軽い幻覚が起こり、波面が凍結したように見えた」という。この体験をきっかけとして、彼は30年以上にわたって波を撮り続けることになる。それらは2014年に写真集『WAVE~All things change~』(かぜたび舎)にまとめられ、今回はその中から44点(ほかに「河─累影」シリーズから2点)が展示された。
それら、撮影当時にプリントされたというヴィンテージ・プリントを見ると、波という現象が実に魅力的な被写体であることがわかる。撮影の条件によって千変万化するその様相は、それぞれが驚きをともなう奇跡的な瞬間として凝結しており、見飽きるということがないのだ。さらにそれらが繊細で深みのあるモノクロームの印画に置き換えられることで、視覚的な歓びはさらに強まってくる。森永が『WAVE~All things change~』に「「海の波」ほど、私たちの脳でおこる夢に似て、リアリティと幻想の交錯が激しい世界はない」と書いているのは本当だと思う。印画紙に定着された波は、われわれを夢想へと誘う強い力を秘めているのだろう。
2016/02/16(火)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)