artscapeレビュー
2013年05月01日号のレビュー/プレビュー
KYOTO STUDIO 17のスタジオと88人のアーティスト

会期:2013/04/13~2013/05/19
京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]
美大の集積率が高い京都では、複数の若手作家たちがスペースを共有して作品制作を行なう共同スタジオ(アトリエ)が30軒以上あると言われている。本展ではそれらのうち17軒が現場の再現あるいはインスタレーションを行ない、88作家による100点以上の作品が展示された。京都では近年、共同スタジオによるオープンスタジオが活発化し、話題を集めるようになっていた。本展はその動向を踏まえたものであり、時機を逃さず開催したことは評価されるべきである。また、会期中に共同スタジオを巡るツアーが4種類も企画され、展覧会場と現場を結ぶ導線を確保したのも優れたアイデアだった。
2013/04/16(火)(小吹隆文)
プレビュー:リサーチ☆パラダイス 潜水と浮上
会期:2013/05/18~2013/06/09
ARTZONE[京都府]
ブブ・ド・ラ・マドレーヌと山田創平が、2010年から大分・別府で地域住民へのインタビューや地域の歴史・文学などをリサーチして制作したインスタレーションを、ARTZONEバージョンとして展示する。ほかには、京都という地域をカメラで調査する「キョート・サーヴェイ・プロジェクト」に参加した、穐山史佳、金田奈津美、早瀬道生らの写真作品、ファッション業界のルールを越えて服づくりを楽しむ市井の人々をリサーチした、中川めぐみの「野生のデザイナー」などを展示。社会に沈潜している諸々をリサーチすことで、無限に広がる創造の原野を開拓する。
2013/04/20(土)(小吹隆文)
Chim↑Pom「PAVILION」展

会期:2013/03/30~2013/07/28
岡本太郎記念館[東京都]
死を扱うと、Chim↑Pomは生き生きする。そして、彼らが死を観念としてばかりではなく、ひとつの現実として扱うとき、彼らの躍動は何かある真実に触れてしまう。そんなことが希に起こる。そのとき、出来事は事件となる。「事件」といっても、法に触れるかどうかといった話ではない。「PAVILION」展で決定的に重要な作品は、岡本太郎の遺骨を展示した《PAVILION》だろう。真っ白い光を放つディスプレイのなかに、掌に載るくらいの小さな骨が、まるで宝飾でも展示しているかのように、飾られている。岡本を骨として見るという、なんともあっけらかんとしたあけすけな仕掛けは、世界を理想化されたものあるいは美化されたものとしてではなく、ひとつの生命の運動として見るよううながしてくる。この作品を含めた展示全体にそうしたベクトルが感じられた。とくに再制作された《BLACK OF DEATH》は、自然のエネルギーに満ち満ちていると感じさせられ、強いインパクトを受けた。最初につくられた際には濃厚だったいたずら的雰囲気が希薄だったことも功を奏していた。それによって、Chim↑Pomたちの誘導で空を黒くしてしまうカラスの群れは最初のものより迫力が増しているように見えた。そこに、人間の生活の背後で普段は隠れているはずの非人間的な自然界の相貌が立ち現われた。それは恐ろしく、美しかった。岡本一人の死は自然の運動のなかのひとつのモメントであり、しかしその死も包み込んで、運動は休まず続いてゆく。Chim↑Pomが岡本太郎の死に触れて、新しい渦巻きをつくって見せた。これもまたひとつの自然の運動である。とすれば、その運動を観客の前に開示して見せたということこそ彼らが起こしている本当の事件なのである。
2013/04/21(日)(木村覚)
ミュシャ財団秘蔵 ミュシャ展──パリの夢 モラヴィアの祈り

会期:2013/03/09~2013/05/19
森アーツセンターギャラリー[東京都]
日本でミュシャの回顧展が最初に開催されたのは1978年だという。それ以来、数多くのミュシャ展が開かれてきた。今年は森アーツセンターギャラリーから始まるこの巡回展のほか、美術館「えき」KYOTOからは、チェコのチマル・コレクションの巡回展が始まっている。また堺市立文化館アルフォンス・ミュシャ館ではミュシャのデザイン集である『装飾資料集』の全図版が公開されている。
サラ・ベルナールの公演のためのポスター《ジスモンダ》(1895)以来描かれたアール・ヌーボー様式のポスター、グラフィックを欠かしてはミュシャの人気はあり得ないだろう。しかし、近年は彼が描き続けていた油彩画や、祖国チェコに帰国してからの作品を紹介し、その祖国愛に満ちた人間像を描き出す試みが行なわれるようになってきた。チマル・コレクションの展覧会タイトル「知られざるミュシャ展」にも、本展のキャッチコピー「あなたが知らない本当のミュシャ」にも、そのような背景が現われている。展示は六つの章に分かれている。第1章は、ミュシャのチェコ人としてのアイデンティティを自画像や家族の肖像画から探る。第2章は、良く知られたサラ・ベルナールのポスターを中心とした仕事。第3章は、アール・ヌーボー様式の広告など。第4章は装飾パネル画。第5章は、1900年のパリ万博前後の作品。オーストリア政府の依頼でボスニア=ヘルツェゴヴィナ館の内装を担当したことによってスラブ民族のおかれた複雑な政治状況を再認識した時代にあたる。そして第6章は、《スラブ叙事詩》への道。ここでは、パリを離れて祖国に戻ったミュシャの思想をたどる。
良く知られたポスターはもちろん、ポスターや装飾画の下絵、《スラブ叙事詩》の習作、そして30点にのぼる油彩画が出品されている。また、友人たちや作品のためにポーズをとるモデルを写した写真もあり、思想から制作のプロセスまで、ミュシャの作品と人間を包括的に知ることができる展覧会である。[新川徳彦]
関連レビュー
知られざるミュシャ展──故国モラヴィアと栄光のパリ|SYNK・金相美
2013/04/23(火)(SYNK)
熊谷晋一郎『リハビリの夜』
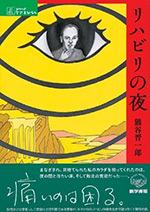
著者:熊谷晋一郎
出版社:医学書院
発行日:2009年12月
価格:2,100円(税込)
判型:A5判、264頁
例えばこんな文章が出てくる。
──「これがあるべき動きである」という強固な命令とまなざしをひりひりと感じながら、焦れば焦るほど、その命令から脱線する私の身体の運動がますます露わになっていく。
脳性まひの体とともに生活してきた、小児科医で研究者でもある熊谷晋一郎。少年期に通ったリハビリ施設でのトレイナーとの時間を振り返って綴った一文がこれなのだが、まるでダンスをめぐる文章のように読めてしまう。トレイナーが思い描く理想像を実現しようと努力しながら、それが叶わず、自分の体がバラバラになったかのように感じる。その切なさ、情けなさがとても丁寧な筆致で描かれる。この本の読みごたえがそこにあるのは間違いない。けれど、本書の白眉は、熊谷がトレイナーとトレイニーの関係性を、《まなざし/まなざされる関係》であるとき、《ほどきつつ拾い合う関係》であるとき、《加害/被害関係》であるときとに分けて論じる、その考察の確かさにある。
「自らすすんで私に従え」と告げているかのように、運動目標を押しつけるトレイナーの態度はトレイニーに対して監視的で、トレイナーにまなざされるトレイニーの体はこわばり、自壊する。こうした空しい《まなざし/まなざされる関係》やさらに強引に体の現状を見捨て体を矯正しようとする《加害/被害関係》を回避し、相互的に情報を拾い合うようにトレイナーがトレイニーに介入する状態、つまり《ほどきつつ拾い合う関係》こそ両者の望ましい関係なのではないか、と熊谷は説く。
熊谷の考察は豊かな発見に満ちている。介護という場の問題にとどまらず、ぼくが専門にしているダンスの現場にとっても充分刺激的だ。ナタリー・ポートマンが主演したバレエ映画『ブラック・スワン』に描かれたような、まなざし/まなざされる関係の苛烈さは、ダンスにおけるダンサーと見る者とのあいだに潜む基本的な状態であろう。それはそうとしてそこからさらに、ほどきつつ拾い合う関係というものへと意識を向けるのは、ダンスという枠のなかではなかなか難しい。ダンサーが目指すエリート的な身体ではなく「脳性まひの体」にフォーカスしたがゆえに、熊谷は「ほどきつつ拾い合う」などという関係を解きほぐしえたのではないか。そう思うと、ダンスという場の硬直性に気づかされる。しかし、それ以上に大事なのは、こうした視点の移動が体へ新鮮な向き合い方をうながしてくれる点に気づくことだ。他者にもわかるように自分の体験を内側から語る「当事者研究」という方法を推進してもいる熊谷の狙いは、まさにそうした新鮮な気づきを与えることにあるのだろう。
この本にはもうひとつの大きな魅力がある。「敗北の官能」「退廃的な官能」と熊谷が名づける、不可能性に直面したときに生じる独特の快楽に言及しているところだ。これをマゾヒズムに還元してしまうのは容易いが、トレイナーやボランティアと接して感じさせられる切なさや苦しさが、ある種の官能を喚起させもするということについての具体的で繊細な記述には、文学的な感動さえ受ける。授けられたこの体で生まれて死ぬほかないということは万人に共通の運命なのだ。この運命とどうきちんと向き合って自分の体ととともに生きていくか、その問いに熊谷はひとつの解答を与えてくれている。綾屋紗月との共著『つながりの作法──同じでもなく違うでもなく』もあわせて読むと、熊谷の考えをより深く知ることになるだろう。
2013/04/27(土)(木村覚)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)