artscapeレビュー
2015年11月15日号のレビュー/プレビュー
美術の中のかたち─手で見る造形 手塚愛子展「Stardust Letters─星々の文(ふみ)」

会期:2015/07/18~2015/11/08
兵庫県立美術館[兵庫県]
既成品の織物から糸をほどく、ほどいた糸で刺繍を施す、といった解体と再構築の作業を通して、絵画と表象、絵画を構成する多層構造の可視化、絵画と手工芸の境界、装飾や図案をめぐる東西の文化的記憶、といったさまざまな問題を提起してきた手塚愛子。本個展は、兵庫県立美術館のアニュアル企画である「美術の中のかたち──手で見る造形」展として開催された。この企画は、視覚障碍者にも美術鑑賞の機会を提供することを目的として、作品に触ることができる展覧会で、1989年度より始められ、今年で26回目になる。
今回の手塚の試みが秀逸だったのは、「点字」を作品に導入することで、「見る」行為における、視覚障碍者とそれ以外の鑑賞者との非対称性を解消したことだ。展示室に足を踏み入れると、天井近くから無数の白い糸が柱のように垂れ下がった光景が広がっている。鑑賞者はこの「糸の森」の中に入って、散策するように歩き回り、糸に触ることができる。さらに、インスタレーションの反対側に回ると、糸の柱は手前にいくほど低くなっており、白い柱の天辺が散らばった星のように見える。だがその配置は、実は点字の形を表わしており、手塚がベルリンから送った手紙が点字に訳されているという。この点字の文章は壁にも貼られており、視覚障碍者は手で触ってその内容を「読む」ことができるが、散りばめられた星屑のようなインスタレーションの光景を「見る」ことはできない。一方、点字を習得していない鑑賞者の眼には、糸の柱の無数の林立は、神秘的な光景として映るのみで、言語記号へと置換されず、手紙の内容を知ることはできない。手塚の作品は、両者にともに「想像すること」の余地と必要性を与えることで、他者のあずかり知らぬ知覚や思考が同居する空間へと想いを至らせる回路を開いていた。
2015/10/30(金)(高嶋慈)
チャンネル6 国谷隆志「Deep Projection」

会期:2015/10/29~2015/11/29
兵庫県立美術館[兵庫県]
正三角形に配置された数十本のネオン管が吊り下げられ、空間を赤い光で瞑想的に満たしている。近寄って見ると、ネオン管は丸い球が連なったようないびつな形をしており、鍾乳石や氷柱(つらら)といった自然の造形物を思わせる。そのなかを、炎のように、脈打つように揺らめく光。ネオン管の持つ都会的で人工的なクールなイメージは、柔らかで有機的なフォルムによって溶解していく。このいびつなフォルムは、熱したガラスに息を吹き込むことで成形されている。丸い球のような連なりは、作家の呼吸という身体的痕跡でもあるのだ。国谷の作品はライトアートの系譜に属するものだが、既製品ではなく、自らの息を吹き込んでつくったガラス管を用いることで、彫刻的要素とともに、生の痕跡をガラスという儚くも美しい素材で提示する装置ともなっている。
2015/10/30(金)(高嶋慈)
松谷武判の流れ MATSUTANI CURRENTS

会期:2015/10/10~2015/12/06
西宮市大谷記念美術館[兵庫県]
具体美術協会のメンバーであった松谷武判の、新作を加えた回顧展。初期の日本画、ボンドをレリーフ状に盛り上げた具体時代の絵画作品、版画、巨大なロール紙に鉛筆の線を描き重ねた黒一色の平面作品、ボンドの膨らみを鉛筆で黒く塗りつぶした作品、新作のインスタレーションに至るまで、約60年の軌跡を辿ることができる。
初期の幾何学的な造形構成の日本画においてすでに、「生命」というタイトルで染色体のような形が描かれていたが、松谷の関心は一貫して、細胞の分裂や増殖、生命の有機的エネルギーの表出にあることが窺える。具体時代のボンド絵画は、盛り上げたボンドの塊にできた裂け目が目や口、細胞分裂の過程、卵からの孵化、胎盤といった有機的なイメージを連想させる。さらに、一枚の紙を鉛筆の線で黒く塗りつぶした作品群を経て、近作では、ボンドの膨らみが鉛筆で黒く塗りつぶされている。そこでは、内部からの強い圧力で膨張し、表面張力ギリギリに膨らんだ緊張感や破裂の凄まじいエネルギーが、黒という色彩によって相乗効果を生んでいる。被膜を突き破って、どろりとした物質があふれ出す。あるいは、さざ波のように波打つ表面の起伏。光の当たる角度によって、光沢感と暗く沈む部分が交替する、豊穣な黒。それは、画家の身体的運動の痕跡でもある。ボンドと黒鉛という、無機的な素材、メタリックな質感、モノクロームの色彩にもかかわらず、硬質なエロスとでも言うべきものを開示していた。
2015/10/30(金)(高嶋慈)
小野耕石展「版表現を切り開く者」
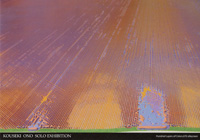
会期:2015/10/17~2015/11/15
ギャラリーあしやシューレ[兵庫県]
一見すると、モアレに覆われたような抽象的な色面が広がっているが、その前を横切ると、見えなかった色彩が次々と現われ、視点の移動とともに刻一刻と表情が変化する。オパールや玉虫色のように、光の反射や屈折によって複雑に千変万化する表面は、きらめく海面や暮れてゆく夕暮れ空、蝶の翅へと変貌していく。小野耕石の《Hundred Layers of Colors》は、その名の通り、100層以上もシルクスクリーンを刷り重ねることでつくられている。近寄って見ると、1cmほどの極小の突起が画面に規則正しく並んでいることがわかる。一つひとつの突起を横から見ると、インクの層を無数に刷り重ねた色の柱になっている。したがって、視点を移動させながら見ることで、真正面からは見えなかったさまざまな色が、角度によって現われては消え、幻惑的に色彩が移り変わる表面を生み出しているのだ。
「版画は、インクの物質的な層の堆積である」ことに自覚的に取り組みつつ、2次元と3次元の往還、視点の移動による表面の複数性に言及する小野の試みが、今後どう発展していくのか期待したい。
2015/10/30(金)(高嶋慈)
浮世絵から写真へ ─ 視覚の文明開化─

会期:2015/10/10~2015/12/06
江戸東京博物館[東京都]
浮世絵の専門家である我妻直美と、幕末~明治期の写真師・画家、横山松三郎の研究で知られる岡塚章子、この二人の東京都江戸東京博物館の学芸員が共同でキュレーションした「浮世絵から写真へ」は、とても面白い展覧会だった。
写真術が幕末に日本に渡来した時、それがリアルな遠近法や陰影法を備えた西洋画の一種と見なされたことはよく知られている。油絵、銅版画、石版画、そして写真などの写実的な表現は、伝統的な浮世絵(錦絵)の描法にも大きな影響を及ぼすとともに、主題的にも「黒船」や「文明開化」のようなより時事的な要素が取り入れられていく。一方、写真の側も「名所絵」、「役者絵」、「美人画」などの浮世絵のテーマを巧みに取り込んでいくようになる。本展は、その二つの媒体の交流の様相を、近年発見された新資料を駆使して、ダイナミックに浮かび上がらせていた。
たとえば、明治中期の写真師、小川一真が1890(明治23)年に竣工した浅草・凌雲閣(通称、浅草十二階)のために企画した「凌雲閣百美人」の写真帖、それは歌川国貞らが安政4~5(1857~58)年に売り出した「江戸名所百人美女」のシリーズに通じるものがある。また横山松三郎と鈴木真一が考案し、小豆沢亮一が1885(明治18)年に特許を得た「写真油絵」(鶏卵紙印画の感光面だけを剥離し、裏から油絵具で彩色する技法)は、まさに写真と絵画の合体というべきものだった。江戸東京博物館だけでなく、日本カメラ博物館、横浜開港資料館などから出展された多数の作品・資料から浮かび上がってくるのは、少なくとも明治中期までは写真も浮世絵も西洋画も渾然一体となった、奇妙に活気あふれるイメージ空間が成立していたということである。それらがどのように結びつきつつ発展し、やがて解体していったのか、さらにさまざまな角度から検証していってほしい。
2015/10/30(金)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)