artscapeレビュー
2016年07月15日号のレビュー/プレビュー
笹岡啓子「SHORELINE」
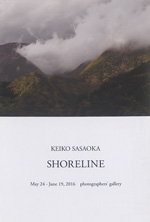
会期:2016/05/24~2016/06/19
photographers’ gallery[東京都]
笹岡啓子が2015年から東京・新宿のphotographers’ galleryで開催している「SHORELINE」展も今回で3回目になる。展覧会にあわせて刊行される同名の小冊子も、もう24号になった。主に川筋を辿りながら、「時制を超えた「地続きの海」を現在の地形から辿り、連ねていく」というシリーズだが、今回は静岡県の大井川沿いの山間部(「奥大井」)と沿岸部(「遠州灘」)を撮影している。
会場に並ぶ13点を見ると、風景の細部に向かう笹岡の眼差しが、少しずつ練り上げられ、厚みを帯びてきているように感じる。かつてルイス・ボルツ、ロバート・アダムズ、ジョー・ディールらが1970年代に試みた、地勢学的な風景の描写(「ニュー・トポグラフィックス」)の現代版といえなくもないが、笹岡のアプローチはそれとも違っている。「ニュー・トポグラフィックス」の厳密で冷ややかなモノクロームの描写と比較すれば、笹岡のカラー写真はもっと柔らかなふくらみがあり、風水的な気の流れが写り込んでいるようでもあるからだ。独特の感触を備えた、日本の風土に即した風景写真が、かたちをとりはじめているのではないだろうか。
なお、隣接する展示スペース、KULA PHOTO GALLERYでは、「飯舘」のシリーズ8点を展示していた。いうまでもなく、福島第一原発の事故による放射能汚染で、いまだに居住制限地域、帰還困難地域が大きな面積を占める土地だ。2014年4月、8月、2016年3月に撮影された笹岡の写真にも、除染された汚染土を袋詰めして、あちこちに放置してある光景が写り込んでいる。数千万年、数億年という単位で「地続きの海」が見えてくる「奥大井」、「遠州灘」と、5年前の震災の記憶がまざまざと甦えってくる「飯舘」を対比的に展示したところに、笹岡の批評的な企みがあるのだろう。
2016/06/07(火)(飯沢耕太郎)
アート・アーカイヴ資料展XIV「鎌鼬美術館設立記念 KAMAITACHIとTASHIRO」

会期:2016/06/01~2016/07/15
慶應義塾大学アート・スペース[東京都]
細江英公は1965年9月、舞踏家、土方巽をモデルとして秋田県羽後町田代で「鎌鼬」を撮影した。このシリーズは、1968年3月の銀座ニコンサロンでの個展「とてつもなく悲劇的な喜劇」に出品され、69年には田中一光のデザインで現代思潮社から写真集『鎌鼬』として刊行されて、細江の代表作のひとつとなった。それから50年あまりが過ぎたが、撮影の舞台となった田代の住人たちのなかには、わずか2日間あまりの土方との邂逅の記憶が深く刻みつけられているという。東北の農村に、土方はまさに折口信夫のいう「マレビト」として出現したのではないだろうか。
本展は、田代の旧長谷山邸が「里のミュージアム 鎌鼬美術館」として生まれ変わるのを期して、東京・三田の慶應義塾大学アート・スペースで開催された。細江撮影の「鎌鼬」のオリジナルプリントとコンタクトプリントに加えて、桜庭文男が現代の田代を撮影した「稲架(はさ)のある里/四季」、藤原峰のドローン空撮による映像作品、ポスターなどの関連資料が出品され、会場の一角には、細江の写真に印象深く写り込んでいる「稲架」も再現されていた。展示スペースがやや小さいのが残念だが、ひとつの写真シリーズが呼び起こした反響を、時代を超えて検証しようとする興味深い企画である。今後「鎌鼬美術館」の活動が展開していくなかで、さらに多様なコラボレーションが期待できるのではないだろうか。
なお、展覧会を主催した慶應義塾大学アート・センターは、土方巽のほかに、瀧口修造や西脇順三郎の関連資料も多数所蔵している。その一部を見せていただいたのだが、展示企画に結びつきそうな写真資料もかなりたくさんあった。ぜひ展覧会や出版物のかたちで、積極的に公開していってほしいものだ。
2016/06/08(水)(飯沢耕太郎)
ポンピドゥー・センター傑作展 ─ピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで─

会期:2016/06/11~2016/09/22
東京都美術館[東京都]
ルーヴル展が2、3年に一度、オルセー展が4、5年に一度くらいの割合で開かれてるとすれば、ポンピドゥー展は10年に一度くらいだろうか。それでもルーヴルとオルセーに比べれば有名作品の絶対数が少ないので、展覧会のテーマや展示構成に工夫を凝らさなければ人は入らない。そこで今回考えられたのが「1年1作家1作品」という方式。フォーヴィスムやキュビスムの前衛芸術が立ち上がる1906年から、ポンピドゥー・センターの開館する1977年まで約70年を、各年ひとりの作品でたどるというもの。トップの1906年を飾るのはラウル・デュフィの《旗で飾られた通り》。いささか地味かなと思ったが、よく見るとフランス国旗のトリコロールが林立している風景ではないか。そうやって見渡してみると、赤、白、青を使った作品が多い気がする。あとで気づくのだが、展示は3フロアに分かれ、地下1階の壁が赤、1階が青、2階が白を基調にしており、会場もトリコロールになっているのだ。少し進んで、1913年にはデュシャンの初のレディメイド作品《自転車の車輪》があるが、じつはこれ1964年の再制作。次の1914年はデュシャンの兄のレイモン・デュシャン=ヴィヨンの彫刻が来て、続く15、16年は第1次大戦のため、アルベール・グレーズの《戦争の歌》とピエール・アルベール=ビロの《戦争》が飾られるといったように、何年にだれの作品を持ってくるか、けっこう考えられている。ちなみに第2次大戦中の1944年は、ジャン・ゼーベルガーとアルベール・ゼーベルガーの写真《ドイツ軍が撤退するオペラ座広場》で、45年は壁が空白のまま、エディット・ピアフの歌が聞こえてくるという趣向。45年にだって作品はたくさんつくられてるはずなのに、あえて外すという選択だ。この年になんでこの画家が? と首を傾げる選択もある。フォーヴィスムの創始者マティスはトップに来てもいいはずだが、晩年の1948年の作品《大きな赤い室内》が来ている。いい作品だけどね。逆に、ピカソとともにキュビスムで知られるようになるジョルジュ・ブラックは、キュビスム以前の1907年、まだフォーヴィスムの時代の絵が出ている。これもまたいい作品だが。そして最後の1977年は、レンゾ・ピアノとリチャード・ロジャースによるポンピドゥー・センターの模型だが、その前年は「Georges Pompidou」の文字をアレンジしたレイモン・アンスの平面作品、さらに前年の1975年は、ポンピドゥー・センター建設のために取り壊される建物に介入したゴードン・マッタ=クラークの映像が出品され、なんだか自画自賛で終わってるぞ。
2016/06/10(金)(村田真)
海と住む──台湾東部の海岸線にデザインされた住宅建築をめぐって
会期:2016/06/10
台北駐日経済文化代表処台湾文化センター[東京都]
陳冠華「海と住む──台湾東部の海岸線にデザインされた住宅建築をめぐって」@台湾文化センター。レクチャーでは、時間を刻み込むブルータルなコンクリートによる一連の住宅が紹介された。なるほど、彼の作品集も、通常の建築家とは違い、竣工写真ではなく、すでにツタに覆われ、廃墟にも見えるような状態の写真ばかりを掲載している。非都市の風景を強烈に際立たせる批判的地域主義的なデザインである。が、室内から大きな窓で海を望む操作は意外になく、屋外に出て、海を見る感じだ。
2016/06/10(金)(五十嵐太郎)
キリコ「2回目の愛」
会期:2016/06/01~2016/06/12
galleryMain[京都府]
写真家のキリコはこれまで、会社を辞めてニートになった元夫との関係を綴った《旦那 is ニート》や、かつて売れっ子の舞妓だった祖母の思い出の写真の再構成/現在の日常生活のスナップなどによって、家族という親密な関係性のただ中に身を置きながら、写真という装置の介在によって距離を測るような試みを発表してきた。「私性」をテーマにした、ヨシダミナコとのダブル個展では、「2回目の愛」というタイトルの下、自身と祖母との関係に再び向き合っている。
キリコによれば、88歳になった祖母は、食事、着替え、排泄などの世話をキリコの母親(祖母にとっては娘)に依存しないと生きられない状態になっており、娘を「おかあさん」と呼ぶようになった。逆転した母娘関係。そこに、孫である自分が入り込めない拒絶感を感じるとともに、「肉親であるから故に、愛も憎しみも表裏一体となるなか「愛」という言葉で片付けられる程簡単なものではないことは重々承知しているが、2回目の関係にも 1 回目の時と同様に、母娘の「愛」があればと願ってしまう」(個展ステートメントより)。
わが子へ愛情を向けるように、祖母の食事や移動の介助をする母親。無防備な祖母の姿。しかしその親密な光景は、キリコ自身がその場にいてカメラで撮影したものではなく、「介護用モニター」の画面を静止画として再撮影したものだ。撮影行為の二重の介在。その二重化された隔たりは、「そこに入れない」「疎外されている」というキリコ自身の意識をむしろ如実に映し出す。また、「静止画」として切り取ることで、2人の間で交わされた会話内容や声のトーンなど、聴覚的なディティールが抜け落ちていることも、疎外感を増幅させる。黒い箱状のフレームに静止画を収め、連続したシークエンスとして繋げて見せる展示方法は、時間の流れを可視化するとともに、フレーム=枠の存在を強調し、閉じ込める檻のようにも見えてくる。
解像度の粗さ、画面に写る電波の受信サインや温度の表示は、これが「介護用の監視モニター」の画面であることを告げ、その間接性は他人のプライベートに向き合う生々しさを緩和するとともに、「カメラの機械の眼」が本質的に持つ非人称的な暴力性を露わにする。撮影主体としての人間を介さない非人称的なカメラの眼に、最も親密な関係性が映り込んでしまうということ。その無慈悲なまでの残酷さの露呈こそが、
「他人のプライベートを覗いてしまった」という後ろめたさよりも、私たちをいっそう居心地悪くさせる。
通常のドキュメンタリー写真の場合、写真家の身体は、「その場にいないもの」として予め消去され、透明な媒体として、いかに「自然なあるがまま」の被写体の姿を捉え、本質に肉薄するかが賭けられている。一方、キリコの本作においては、「写真家」である以前に、一人の個人としてその場にいることが初めから拒絶されている。キリコは、自らが撮影主体となることを手放しながら、カメラの機械の眼の暴力性やそれとの(擬似的な)同化という欺瞞に向き合っている。
逆転した母娘関係が育む「2回目の愛」は、葛藤の果てに同様の境地に至った佐野洋子の小説『シズコさん』からの引用によっても補強されている。実際に、そうした美しい瞬間は訪れたのだろう。だが、それを「母性愛」という側面から強調することは、別の問題をはらんでいる。介護を「自然な母性」として女性の労働として押し付ける圧力が浮上するからだ。
介護という問題と、(特に家庭内で行なわれる場合の)密室性、逆転した親子関係。それは親密で美しいものであると同時に、「母性愛」という言葉で語られるとき、介護労働を女性に負担させる構造の危うさが透けて見える。さらに、写真(静止画)と映像(動画)、個人の生の生々しさ/モニターを介して見るという間接性、親密な関係性と非人称的なカメラの暴力性など、重層的な問題をはらんだ展示だった。

会場風景 撮影:キリコ
2016/06/11(土)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)