artscapeレビュー
2022年08月01日号のレビュー/プレビュー
アビシニア高原、1936年のあなたへ─イタリア軍古写真との遭遇─

会期:2022/07/07~2022/08/09
PURPLE[京都府]
映像人類学者の川瀬慈が知人を介して偶然譲り受けたイタリア軍古写真を、自身のエッセイとともに展示する企画。古写真は、イタリアによるエチオピア帝国侵略時代(1935–1941)にイタリア軍の兵士が撮影したと思われるものを中心に、200枚余りに及ぶ。撮影されたエチオピア北部と近隣エリア(現在のエリトリア)は、川瀬が長年フィールドワークを行なってきた土地である。トランプ大の古写真が展示台に並べられ、そのうち6点がパネルに引き伸ばされ、川瀬の言葉を添えて展示された。
これらは、イタリアの蚤の市で、ただ同然の値段で売られていたものだという。所有者の手を離れ、出自も撮影者も不明だが、被写体の性格や撮影手法の点でいくつかのまとまりが見えてくる。イタリア軍の活動には、戦車や行軍、兵士たちの日常生活のスナップに加え、凄惨な死体や兵士の墓もある。一方、典型的な植民地写真の群れは、侵略した土地とその住民や動物を「イメージ」として二重に所有しようとする欲望を表わす。現地住民を従えた記念撮影。裸の上半身に首飾りを何重にも巻いて着飾った少女たち。ワニやダチョウなどの野生動物。古代遺跡や雄大な風景。イタリア兵はカメラを意識せずラフに写るのに対し、現地住民は正面向きや直立不動の姿勢であり、眼差しの前に物体化した身体を晒している。

[撮影:守屋友樹]
本展のポイントは、さまざまな被写体に「あなた」と呼びかける川瀬の言葉にある。「あなた(タバコの火を分け合うイタリア兵たち)」は、加害者であり、帝国の野望の犠牲となった被害者でもあった。「あなた(戦車の隊列)」は、19世紀後半に「文明国」がエチオピアに敗けた屈辱を晴らすため、近代兵器の強大な力を示しながら再びこの地にやってきた。王侯貴族のお抱え楽師/道化/庶民の代弁者/社会批評家とさまざまな顔を持つ「あなた(吟遊詩人)」は侵略者を賛辞する歌を歌ったが、抵抗を歌って処刑された者もいた。「あなた(巨大なムッソリーニの彫像)」は、かつてイタリア軍が敗れた街に征服の証として建てられ、兵士たちは「あなた」の前に現地住民を「陳列」して記念撮影した。「あなた」の帽子のかぶり方は、侵略者側に付いた現地住民の傭兵であることを示す。住民の憩いの場であり、争いごとを木の下で話し合って調停する場でもある「あなた(イチジクの巨木)」は、人間の叡智も繰り返される愚かさも見守ってきた。

[撮影:守屋友樹]
川瀬はまた、「イメージはこうやって、おのずからひょっこり私たちのまえに現れるので、おもしろくもあり、やっかいでもある」と書きつける。これは、2度目の「遭遇」である。1度目は、異民族の前に侵略者・征服者として相対し、イメージとして他者を所有しようとする眼差し。そして、そうした欲望の眼差しが焼き付いた写真を、時間的・空間的距離を隔てて再び見つめる眼差し。この2度目の「遭遇」のもとで、第一次エチオピア戦争での敗北(1896)からエチオピア併合(1936)の40年に及ぶイタリア史というナラティブの流れが発生する。写真は常に、遅れてきた眼差しの下でナラティブを生み出す。写真とは、眼差しを何度でも受け止める物質的な層である。それは、イメージとして印画紙の上に固定されつつ、決して固定された時間を生きてはいないのだ。
また、現地住民もイタリア兵も巨大な彫像も古木も「あなた」と等しく呼びかける川瀬の語りは、さまざまな示唆を含む。どんなものでも代入可能な「あなた」は、固有名が失われ、回復不可能な忘却という空白を示す。同時に、いま私とともに私の目の前にある「あなた」という存在を承認し、唯一の固有性を回復しようとする呼びかけは、弔いにも似た行為である。
客観性を装った通常の「歴史資料の解説文」であれば、「私」「あなた」といった人称を欠き、「私とあなた」という親密な関係性も想像的な対話もない。そうした形式をあえて逸脱した川瀬の語りは、再び「征服者」「所有者」としてイメージを奪取するのではなく、被害者として一方的に糾弾する(立場を偽装する)のでもない、「あなた」として向き合う倫理的な態度を示していた。

[撮影:守屋友樹]
2022/07/07(木)(高嶋慈)
川田喜久治「ロス・カプリチョス 遠近」

会期:2022/06/29~2022/08/10
PGI[東京都]
毎回同じことを書いているようだが、1933年生まれ、90歳近い川田喜久治の近年の活動ぶりには、驚きを通り越して凄みすら感じてしまう。今回のPGIでの個展(全48点)も、意欲的なコンセプト、内容の展示だった。
ゴヤの版画集のタイトルを引用した「ロス・カプリチョス(気まぐれ)」は、川田が1970年代初頭に『カメラ毎日』『写真批評』などに発表した写真シリーズである。日常の事物にカメラを向けたスナップ写真の集積なのだが、被写体の捉え方に独特の角度があり、悪意すら感じさせる諧謔味が全編に漂っている。今回の展示では、その旧作の「ロス・カプリチョス」シリーズだけでなく、ヨーロッパのバロック美術を中心に撮影した写真群を集成して、1971年に写真集として刊行された『聖なる世界』からも何点か加えている。それらをいわばマトリックス(母体)にして、ここ数年に撮影した「ロス・カプリチョス」の現代編というべき写真群を混在させていった。
注目すべきなのは、旧作と新作との間の落差がほとんど感じられないということだ。発想、被写体の切り取り方、提示の仕方に共通性があり、指摘されなければどれが旧作で、どれが新作なのかを判断するのはむずかしいだろう。ゴヤが版画で辛辣に描き出した人間社会の「気まぐれ」、愚行は、1970年代でも2020年代でも変わりなく続いているということであり、それらをつかみ取る川田の視線も、まったく錆びついていないことがよくわかった。和紙にプリントしたという印画のトーン・コントロールも興味深い。彩度がやや落ち、インクが紙に滲むように染み込むことで、カラー写真と黒白写真とが、違和感なく溶け込んで見えてくるように感じた。
なお、展覧会と同時期に赤々舎から写真集『Vortex』(2022)が刊行されている。川田がInstagramにアップし続けている写真群を中心に、250点以上を掲載した544ページの大作である。そこにおさめられている写真を見ても、『地図』『聖なる世界』『ラスト・コスモロジー』などの旧作と、分かち難く結びついているように見えるものが含まれている。川田喜久治というフィルターを通過することで、新たなイメージの時空間が形成されつつあるのではないだろうか。
2022/07/08(金)(飯沢耕太郎)
記者発表会「岡本太郎、新発見!」
渋谷ヒカリエ 8/COURT[東京都]
「このたび、従来の岡本太郎史を塗りかえる可能性が高い重要な発見がありました。つきましては、その詳細について、新たに発見された作品を会場でお見せして ご説明する記者発表会を開催いたします」とのメールが届いた。「岡本太郎史を塗りかえる」「重要な発見」というから、東京美術学校の入試デッサンか、戦時中に描かされた戦争画でも見つかったのか? いやいや、どうせ1カ月後に迫った「展覧会 岡本太郎」の煽り、大した作品じゃないんじゃないかなどと思いつつ、会場へ。
まず、岡本太郎記念館館長で同展のスーパーバイザーを務める平野暁臣氏が概要を説明。発見されたのは3点で、いずれもパリ時代(1930-40)に描かれた初期の抽象画。太郎のパリ時代の作品は帰国時に持ち帰ったが、すべて戦災で焼失したため、現在残っている《空間》《傷ましき腕》など数点はいずれも戦後に再制作されたもの。1934年制作とされるオリジナルの《空間》以前の3、4年間の作品は現物はおろか印刷物でも確認されておらず、空白の期間となっていた。今回見つかったのは、岡本太郎芸術の原点ともいうべきその時代に描かれたとおぼしき最初期の抽象画なのだ。この発見は、岡本太郎独特のスタイルがいかに確立されたか、パリの一青年がいかに芸術家になったかを解き明かしてくれるミッシングリンクといってもいい。
3作品の発見の経緯はこうだ。1993年、パリのシテ・デ・フュザンというアトリエ村のゴミ集積場に捨てられていた1点をデザイナーが拾い、翌年そのデザイナーが同じアトリエから出た2点をオークションで落札。そのうちの1点に「岡本太郎」の署名を見つけ、戦前に出たカタログも参照して3点とも岡本作品と確信したという。今回、展覧会開催を契機に3作品を日本に持ち込んで鑑定を行ない、ほぼ岡本太郎の作品に間違いないという結論に達した。
てなわけで、いよいよカーテンの裏に隠された3作品をご開帳。

記者発表会の様子。右から、吉村絵美留、平野暁臣、山下裕二の各氏[筆者撮影]
現われた作品は、いずれもモノクロームの背景にどこか《空間》(1934/54)を思わせる有機的形態が浮かび上がる構成だが、なんとも無骨でお世辞にもうまいとはいえない。「岡本太郎史を塗りかえる」「重要な発見」というにはいささか頼りないが、しかし見方を変えると、《空間》以前の暗中模索期の習作ということであれば納得できるし、岡本が日本に持ち帰らなかった理由もうなずける。つまり半端であるがゆえに真実味も高いのだ。
平野氏はこれらが岡本作品である可能性は95パーセントとしたが、続いて登壇した美術史家の山下裕二氏は99パーセント、絵画修復家の吉村絵美留氏は100パーセント近いと証言。絶対100パーセントとは断言できないものの、ほぼ間違いなく岡本作品であるということだ。だいたい日本ならともかく、フランスで贋作がつくられるほど岡本太郎は有名じゃないし。平野氏は、逆に贋作だとしたらものすごく手の込んだ詐欺で、拍手したいくらいだと述べていた。現物を見て確かめたいという人は、大阪中之島美術館(7/23-10/2)、東京都美術館(10/18-12/28)、愛知県美術館(2023/1/14-3/14)の「展覧会 岡本太郎」へ。
2022/07/08(金)(村田真)
李晶玉展「SIMULATED WINDOW」
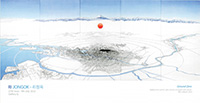
会期:2022/06/27~2022/07/09
ギャラリーQ[東京都]
この春、原爆の図丸木美術館で作品を発表したばかりの李による同題の個展。ギャラリーからいただいた丸木美術館のカタログを見ると、どうやら同じ作品が出ているようだ。丸木美術館は足の便が悪くなかなか行きづらいので、見逃した者にとってはありがたい★。
まず目に入るのが、180×450センチの大作《Ground Zero》。東京のパノラマ俯瞰図の上に赤い球体が浮き、その上(奥)に富士山が遠景として描かれている。球体の下には同心円が幾重にも広がり、赤球が核爆発であることを示唆する。つまりこれは東京上空で核爆発が起きる瞬間を描いたもの。赤球の下(グランド・ゼロ)には黒く塗り潰された領域があるが、これは皇居か。なるほど、グランドゼロとはあらゆる情報が発信されないブラックホールというわけだ。だがよく見ると、赤球の真下は皇居ではなく、やや南西方向にずれている。かつて参謀本部があった三宅坂あたりであり、近くには国会議事堂を有する日本の中枢部がグランド・ゼロに想定されているのだ。赤球の背景は白く抜かれているので日の丸に見え、その真上に富士山がそびえるというまるで日本な構図。ちなみにこの作品は、紙に鉛筆で描いた原画を2倍に拡大したデジタルプリントに着彩したもの。
ほかに《Enora Gay》と《Dome》という対作品もある。前者は広島に「リトルボーイ」を投下したB-29のコックピットを描いたもので、後者は広島の原爆ドームを内部から見上げたところ。どちらも鉄骨に覆われた半球状の形態をしているが、一方は落とした側(加害)、もう一方は落とされた側(被害)という真逆の視点から捉えているのだ。この両者が「重なったように見えた時に視点を得たような感覚があった」と作者は述べている。こうしたある意味恐るべき視点の発見を、緻密でクールな描写によって表わしているところが気持ちいい。
★──原爆の図丸木美術館「李晶玉 SIMULATED WINDOW」動画公開 https://marukigallery.jp/news/rijongok_movie/
2022/07/08(金)(村田真)
ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ:どこにもない場所のこと

会期:2022/05/03~2022/09/04
金沢21世紀美術館[石川県]
2009年に結成され、ドクメンタやヴェネツィア・ビエンナーレへの参加など韓国を代表するアーティストデュオ、ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホの日本初の大規模な個展。金沢21世紀美術館での滞在制作を含め、映像インスタレーション6点を展示する。現在/SF的な未来、韓国/北朝鮮、現実/夢や虚構といった二項対立の構造、「過去」「異質な外部」との接触、監視された閉鎖空間、植物の収集や育成といった要素が、商業映画なみのクオリティの映像どうしをつないでいく(実際に有名な俳優が出演している)。
特に、構造の類似性を感じさせるのが、《世界の終わり》(2012)と《どこにもない場所のこと:フリーダム・ヴィレッジ(News from Nowhere: Freedom Village)》(2021)。《世界の終わり》では、2面スクリーンの左右にそれぞれ、終末を迎えつつある世界で男性アーティストが孤独にスタジオで制作する「現在」と、終末後の世界に生きる女性が「旧世界の遺物」を調査する「未来」が投影される。「未来」の調査ラボは無機質でクリーンな「白」に覆われ、調査サンプルの持ち出し禁止や滞在時間の制限など厳重な規則が課せられている。だが、「現在」で男性アーティストが手にしていた電飾コードの残骸が、再び息をするように明滅し始めるのを見た「未来」の女性は、その「光」を自らの身にまとい(田中敦子の《電気服》のようだ)、トランクに詰め、「外」の世界へ出る決意をする。

「ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ:どこにもない場所のこと」展示風景、金沢21世紀美術館、2022年
《世界の終わり》(2012)
金沢21世紀美術館蔵[© MOON Kyungwon and JEON Joonho 撮影:木奥惠三 画像提供:金沢21世紀美術館]

《世界の終わり》(2012)
2 channel HD video installation with sound., 13 min. 35 sec.
金沢21世紀美術館蔵[© MOON Kyungwon and JEON Joonho]
一方、《どこにもない場所のこと:フリーダム・ヴィレッジ》では、「現在」と「SF的な未来」の映像が表/裏に背中合わせで投影される。「フリーダム・ヴィレッジ」とは、韓国と北朝鮮のあいだの非武装地帯(DMZ)に実在する、韓国唯一の民間人居住区の通称である。正式名称は大成洞(テソンドン)。1953年の朝鮮戦争の休戦協定後、国連の管理下に置かれ、休戦当時の住人とその直系子孫のみが居住を許されている。GPSには表示されず、住民の生活はさまざまな制約を受け、部外者の立ち入りはほぼ不可能だ。表側の映像では、この「村」で生活する青年の日常──農作物の加工工場での労働、森での植物採集と標本制作──が描かれる。裏側では、SF的なカプセル型居住空間で暮らす「未来」の男性が、「過去の遺物」である「植物標本」をデータ解析する姿が描かれる。だが彼は、宇宙食のような食糧をこっそり「標本」に与え、干からびた命を復活させて育てている。監視カメラが異常を検知し、警報が鳴り響くなか、「植物の苗」を手にカプセルの「外」へ脱出を企てる男性。特殊なマスクを付けた姿は、「外の世界」がなんらかの「汚染」状態にあることを示唆する。

「ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ:どこにもない場所のこと」展示風景、金沢21世紀美術館、2022年
《どこにもない場所のこと:フリーダム・ヴィレッジ》(2021)
[撮影:木奥惠三 画像提供:金沢21世紀美術館]
このように、「過去の世界」との接触が鍵となり、遺物が再び「生命」を宿し、禁忌を犯して閉鎖空間の「外部」へ出ようとする姿が「SF」というフィクションを借りて反復される。ここでは、「現在/SF的未来」という時空的隔たりを装って、朝鮮戦争がもたらした分断が扱われている。ある時点で切り離され、「凍結された過去」をパラレルに生きる者の存在。だが、「過去」からのシグナルが、時空の壁を超え、「未来」を生きる者に意志と「脱出」への希求を与える。「どこにもない場所」というタイトルは、ウィリアム・モリスの小説『News from Nowhere(ユートピアだより)』に由来するが、モリスが「夢の中で訪れた未来のイギリス」の姿を借りて当時の社会批判を行なったように、ユートピア小説とは現実を反映する批評的鏡像である。「過去」がパラレルに存在し、「未来」の時制に干渉し、あるいは「未来」が「現在」の鏡像でもある時制のねじれ。従って、無菌室のように管理と監視が行き渡る閉鎖空間からの「脱出」の企ては、出口のないトラウマ的な時間からの「脱出」でもあるのだ。
「フィクションという装置を借りなければ語れないこと」はまた、並置された写真とテキスト、絵画からもうかがえる。「フリーダム・ヴィレッジ」についての資料然としたモノクロ写真といかにも古そうなタイプ打ちのテキストが並ぶが、「村の標識」の写真に添えられた「大洪水で押し流された砂がつくった」という村の起源の語りや、プロレスのマスクをかぶった2人の男の写真に幽霊の目撃譚が添えられるなど、違和感が混ざる(実は写真もテキストも「捏造」である)。「捏造されたアーカイブ」は、「歴史資料の欠落状態」と「村自体の人工性」の双方を指し示し、両義的だ。
さらに、展示室の最奥では、謎めいた巨大な絵画が出迎える。「フリーダム・ヴィレッジ」に暮らす青年が植物採集をしていた冬の森を思わせる絵だ。葉が一枚もない枯れ枝が、神経網や毛細血管のようにうねりながら絡み合い、空虚な空間を満たす。リアリズムなのに非現実感に満ちている、イリュージョンなのに確固たる強度で存在する、枯死しているが旺盛な生命力に満ちてもいる──これらの矛盾が破綻なく存在する場所。それは、どこにもないがゆえにどこにでも偏在する「フリーダム・ヴィレッジ」の似姿を象ったイコンである。

「ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ:どこにもない場所のこと」展示風景、金沢21世紀美術館、2022年
《どこにもない場所のこと:フリーダム・ヴィレッジ》(2021)
[撮影:木奥惠三 画像提供:金沢21世紀美術館]
2022/07/09(土)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)